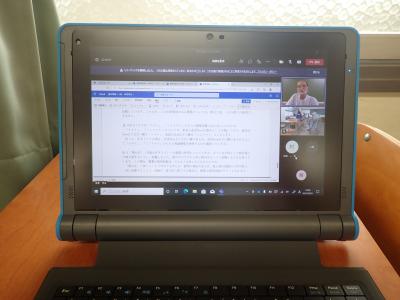本文
令和3年度の様子
農大の近況をお知らせします。
→全般へ
→園芸学科(野菜・果樹)へ
→畜産学科(肉用牛・酪農)へ
全般
先進農家等派遣学習報告会を開催しました(令和3年11月11日~12日)

11月11、12日に2学年生が1カ月間行った派遣学習の成果を報告する「先進農家等派遣学習報告会」を開催しました。
今回は、ウェブ会議システムも活用して行い、受入農家ほか89名に出席していただきました。
学生らはプレゼンテーションソフトを用いて、学習の様子や感じたことを発表し、最後は受け入れ農家への感謝の気持ちで締めくくっていました。
受入農家から「よく頑張った」「今後に期待します」などのねぎらいの言葉や今後の活躍を応援する言葉をいただきました。
「緑の学園」を開催しました(令和3年10月30日)
10月30日(土曜日)に、県内で農業を学んでいる高校2年生に対して、「緑の学園」を開催し、高校生20名が参加してくれました。
午前は、実習体験。午後は、「若手農業者と語る会」を行い、卒業生で就農している3人から、農業を目指したきっかけなどを語っていただき、その後の分科会では「私がやってみたい農業」について、話し合いを行いました。
「農業について聞きたいことが、たくさん聞けて良かった」「とても充実した時間だった」などの感想が聞かれました
プロジェクト学習計画検討会(果樹・畜産)を行いました(令和3年10月4日)

10月4日に、計画検討会をハイブリッド方式で開催しました。
1学年の果樹専攻と畜産学科の学生11名が、自分が取り組む計画を発表し、学生や職員から指摘や助言を受けていました。
今回の発表会で1学年生全員のプロジェクト学習の計画が決定しました。
通常授業を開始!


農大では、新型コロナ緊急事態措置(第5波)の解除を受けて、通常授業を再開しました。
最初の授業は、1学年生は、10月4日のプロジェクト学習計画検討会(果樹・畜産分)です。
学生達は、在宅学習中にリモートで担当職員と打ち合わせして作成した計画を発表し、職員や学生から助言を受けていました。
なお、コロナ対策として二教室を活用して実施しました。
2学年生は、先進農家派遣学習です。
10月1日から受入れ農家さん宅に伺い、派遣学習を開始しました。
約1か月間、お世話になります。
「プロジェクト学習中間検討会」を開催しました(令和3年9月21-22日)
9月21・22日に、2学年生が1学年の時から取り組んできたプロジェクト学習の途中経過を発表する中間検討会を開催しました。
学生達は在宅学習中に成果をまとめ、当番を除きオンラインで発表し、学生や職員から質問や助言を受けていました。
2学年生は、今回の検討内容を受けて卒論を取りまとめます。
ハイブリッド授業を実施中(令和3年9月2日)
新学期になりましたが、新型コロナ感染症対応で全学生が登校して、実習や座学を行うことができなくなってしまっています。
そこで、座学については、8月30日(月曜日)からオンライン授業を開始し、大部分の学生は農大から配布されたタブレットPCを用いて自宅で受講しています。なお、当番で登校している学生については、教室で直接受講するという「ハイブリッド授業」方式で行っています。
学生全員が揃って、実習や座学ができる日が来るのを心待ちにしています。
1日体験入学(第2回)を開催しました
8月19日(木曜日)に今年度2回目の一日体験入学を行ました。
今回は県内のみからの参加で、学生8名 保護者3名の11名を受け入れました。
体験実習の内容は、
野菜は、トマトの出荷調製とパプリカの栽培管理
果樹は、梨の選別
畜産は、本日生まれた子牛への授乳
で、参加者の感想は「楽しかった~」でした。
夏季集中「資格試験講座」を開催中
農大では、夏休みを利用して資格試験の取得に向けた集中講座を開催しています。
畜産学科の学生は「家畜人工授精師」、野菜・果樹学科の学生は「毒物劇物取扱者」です。
学生達は夏休みを返上して勉強に励んでいます。
全員合格すると良いですね。
自動操舵システムのバージョンアップを行いました(令和3年8月6日)

令和2年度に導入した自動操舵トラクタ2台の自動操舵システムのバージョンアップを、メーカに来ていただいて行いました。
システムの熟成度が上がって来ているようです。
1日体験入学(第1回)を開催しました(令和3年7月27日)
7月27日(火曜日)に一日体験入学を行い、学生25名、保護者12名の参加がありました。
本行事は、今年度のオープンキャンパスの一環で開催するものです。
午前中に学校紹介、午後からは希望する専攻の体験実習を行いました。
参加者は、職員や学生に教わりながら、真剣に実習に取り組んでいました。
オープンキャンパスは8月にも開催します。詳細は農大HPで確認してください。
プロジェクト学習計画検討会(野菜)を行いました(令和3年7月15日)


農大では、学生全員が1課題を設け、2年間をかけて課題解決に取り組むプロジェクト学習を行っています。
7月15日に、1学年の野菜専攻の学生14名が、自分が取り組む計画を発表し、学生や職員から指摘や助言を受けていました。
10月には、果樹専攻と畜産学科の学生も計画を発表し、プロジェクト学習に取り組みます。
小型車両系建設機械運転特別教育の講習を実施しました(令和3年6月5日から12日)

6月5日(土曜日)、6日(日曜日)、12日(土曜日)に小型車両系建設機械運転特別教育の講習を行いました。
今年度の受講生は20名で、5日に全員で学科を受講し、その後2班に分かれ実技講習を行いました。
初めての機械操作に、最初は苦労しましたが、何度か繰り返すうちにスムーズに操作することができるようになり、全員合格しました。
ラジコン草刈り機の講習を行いました。(令和3年6月24日)

果樹専攻の学生に対してラジコン草刈機の講習を行いました。
学生達は、ゲーム感覚ですぐに操作に慣れ、使いこなすことができましたが、防鳥ネットに近づきすぎたため、マフラーの熱で穴をあけてしまいました。やらかした学生はガッカリしてましたが、次回からは気をつけて作業を行ってくれると思います(失敗から学べ!!)。
令和3年度 岐阜県農業大学校入学式を開催しました。(令和3年4月13日)
令和3年4月13日(火曜日)に入学式を行い、26名の新入生が本校での新たな一歩を踏み出しました。
山田校長からは、「国内の農業で勝ち残っていくためには知恵と創意と工夫が必要。友と切磋琢磨しつつ2年間を有意義に過ごし、自身の基礎を作ってほしい。」と激励の言葉がありました。
新入生を代表して、平澤万絢さんが「農業大学校では仲間とともに学び、経験と多角的に物事を見、考える力を養い、これからの農業を支える農業者、農業経営者になるために精進する。」と誓いの言葉を述べました。
園芸学科(野菜・果樹)
チェーンソー講習を受講しました(令和3年12月3日~5日)



1学年の果樹専攻学生6名が12月3日~5日の3日間、大垣市のコベルコ教習センターで伐木作業の特別教育を受講しました。
学生達は、初めてチェーンソーを使用した作業だったため緊張していましたが、上手に使いこなし、修了証をいただくことができました。
使用するチェーンソーは、自分たちで目立てなどの整備を行い、整備の仕方で作業効率の向上や事故防止につながることなども教えていただきました。
梨の出荷最盛期です(令和3年9月10日)


農大では、梨(幸水と豊水)10aを栽培しています。
今年の生育は平年並みで、色つやがよく、おいしい梨が獲れています。
出荷は、「幸水」が8月9日から始まり、9月3日からは「豊水」に切り替わり、現在は、「豊水」の出荷最盛期。
学生は収穫、選別等の作業に大わらわです。
出荷は9月下旬まで続きます。
今年度のトマト独立ポット耕栽培を開始(令和3年9月7日)
昨年導入したトマト独立ポット耕システムに苗を定植しました。
昨年は工事の関係で、栽培開始が9月下旬からになってしまいましたが、今年度からは通常栽培の開始です。
ところが、新型コロナ感染症の影響で学生が登校できず、ようやく植え付け完了です。
苗は徒長気味ですが、プロジェクトに影響がないようこれから挽回開始です。
いちご栽培システムを刷新しました(令和3年9月6日)
いちご栽培ハウスに7月から導入を進めていた最新の高設栽培システムと環境制御システムが、このほど完成しました。
9月7日からは、定植を開始し、新たなシステムでの栽培が始まります。
緊急事態宣言下では、いちごを栽培する学生達全員が集まって苗植え付けの実習を行うことができないため、当番の学生と職員が植え付けをするなど、しばらくの間少人数で管理を進めていきます。
きゅうりのほ場準備実施中(令和3年9月3日)

在宅学習中ですが、当番の学生を中心にきゅうりのほ場準備を進めています。
1学年にとってははじめての畦たて作業です。慣れない機械作業に四苦八苦でしたが、何とか完成しました。
袋掛けの真っ最中(令和3年6月24日)


農大の果樹は、どの品目も順調に生育し、現在は1学年生の果樹専攻の学生も加わり、袋掛け作業を行っています。
袋掛けは、1学年生にとっては初めての作業。先輩に教わりながら丁寧に進めています。
袋掛けは大変な作業ですが、これにより病害虫の発生を減らし、肌のきれいな果実に仕上がります。
収穫物が楽しみです。
梨の摘花作業を進めています(令和3年4月19日)


農大では、柿、梨、桃の3品目の果樹を栽培しています。今年は、冬場の低温と春先の高温の影響で、サクラとほぼ同時に桃、続いて梨と一気に開花が進みました。
現在、学生たちは梨の摘花に大わらわです。
次は桃の摘果、柿の摘蕾へと作業が続きます。今年もおいしい果実が穫れますように
畜産学科(肉牛・酪農)
乳牛の手術を行いました。(令和3年9月24日)


当番の学生が助手を務めて、職員(獣医師)が執刀しました。
在宅学習中なので、全学生が現場で執刀の様子を見ることはできませんでしたが、助手をした学生達は、牛の体内に手を入れて内蔵の確認も行うことができ、大変良い経験ができました。
デントコーンの収穫を行いました(9月7日~)

農場で栽培していたデントコーンの収穫を行いました。
今年は、学校行事や降雨等により追肥ができず、中盤以降の生育が悪くなったり、やや刈り遅れとなってしまいましたが、昨年より多く収量を確保することができました。
今後、サイロで醗酵させた後に12月頃から乳牛に給餌を始めていきます。
牛の去勢手術を行いました。
実習の時間を利用して、子牛の去勢手術を行いました。
まず始めに、農大職員(獣医師)からプレゼンソフトを用いて手術方法の説明を受けてからの施術開始です。
職員に教わりながら真剣に取り組んでいました。
種牛審査の講義を開催しました。
6月29日(火曜日)に畜産学科1・2学年生を対象に、飛騨牧場の高原伸一場長を招き、肉用牛審査の講義・実践を行いました。
まず、和牛の登録制度、黒毛和種種牛審査標準について講義を受けた後、農場の「こうめ号・きなこ号」を用いて牛体測定、鼻紋採取、そして審査を行いました。鼻紋採取では鼻の汗、ヨダレなどの水分を取り除き、素早く実施しないと上手くいかないため、学生は皆、とても苦労していました。
審査は5グループに分かれて実施し、グループ内で話し合って点数をつけました。答え合わせの結果、なんと高原講師の評価に近い1位のグループにはご褒美がありました…。
削蹄講習会を開催しました(令和3年6月7日)
6月7日(月曜日)に畜産学科2学年生を対象に、削蹄師の松本大輝講師を招き、削蹄講習会を行いました。
始めに削蹄の基本となる牛の単独保定について学びました。枠場やロープを使わず、牛のバランスをとって前肢を上げるため、簡単にはいきませんでしたが、かろうじて学生全員できるようになりました。
その後、削蹄方法を学び、蹄の部位の名称、切る位置の決め方、どの程度切るかの見極め方を教えていただきました。
最後に削蹄道具の手入れの仕方を学び、「道具の大切さ」を教えていただきました。
自動操舵トラクタを用いて飼料畑の圃場準備を始めました(令和3年4月16日)

令和2年度に導入した自動操舵トラクタと従来型のトラクタの2台を協調させて、飼料用トウモロコシの播種準備を始めました。
以前に比べ、ロータリーの反転性能も向上し、作業精度と能率が向上しています。