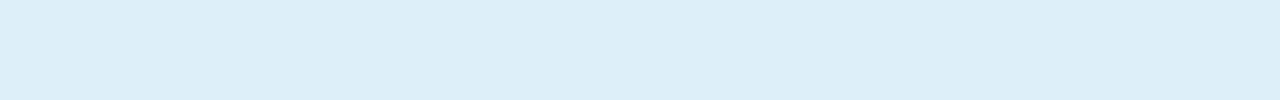本文
知事記者会見録(令和7年10月22日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年10月22日(水曜日)15時00分
司会
それでは、知事定例記者会見を始めさせていただきます。
知事お願いいたします。
知事
発表事項の前に、まずは皆さんにお礼を申し上げなければいけないのですが、昨日までのねんりんピック、おかげさまで大成功だったと思いますし、素敵な報道をたくさんしていただきまして、本当にありがとうございました。県内だけではなく、全国的にも知っていただけるということで、本当にありがとうございました。
冒頭、少しだけお時間をいただいて、改めてねんりんピック2025岐阜を振り返りまして、いくつかポイントだけ申し上げたいと思います。
10月18日から4日間、彬子女王殿下をお迎えしてスタートしたところでございます。いろんな関係者のおかげで本当にいい流れができたかなと。そして昨日、次の開催県に旗を渡したのですが、今回のねんりんピックは、次の埼玉県知事さんとも話をしながら、3つ特徴があるんじゃないかと思います。
まずは、若い世代の方が盛り上げていただいたと。ねんりんピックというと、どうしても60歳以上のシニアのものというイメージがあるのですが、開会式から始まり、昨日の閉会式もそうですが、本当に若い人たち、武将隊、濃姫隊をはじめ、県立岐阜商業高校の生徒たち、岐阜総合学園高校、加納高校の国歌斉唱、ボランティアの大学生の皆さんは、いろいろアトラクションを考えて大いに盛り上げていただいたと。
会場に来ていただいた方も、高校生が出てくるのは初めてだという声が非常に多く、やはりどうしてもシニアのものから全体のものになったかなと。そして、昨日の閉会式で島保育園やながら児童合唱団に出ていただいて、会場の皆さんがもう涙が出そうというか、子ども達の声で感動していただいたかなという感じがありました。アシスタントは、岐阜女子高校の生徒さんたちがしていただいて。そういう意味では、本当に全世代でできたなというのが1つです。
2つ目は、お弁当が大好評で、普通は9マス弁当といって、ちょっとずつ県内のいいものがありますよ(と紹介するお弁当)が普通なのですが、今回はスタッフの皆さんが考えていただいて、メインを決めようと。今日は飛騨牛、今日は鮎、今日はボーノポーク、最後は黒唐揚げということで、相当インパクトがありました。初日に、「飛騨牛味わい弁当はどこで買えますか」、「すみません。売っていません」というやりとりがありました。また、「飛騨牛ってこんなに美味しいんだ」というのと、昨日の共同記者会見でも言いましたが、「飛騨牛を食べられるお店を紹介してください」という声も結構ありまして、よかったなと。ちょっと小ぶりだったこともあって、食べた後、残す方ほとんどいらっしゃらなくて、更に色々な売店で色々と買っていただいて、特に岐阜らしいものが売れました。鮎の塩焼きには列ができ、逆に一般的な焼きそばが売れないということがありました。ねんりんピックの(参加者の)方々が、全国から岐阜らしいものを求めてこれほどいらっしゃるのかというのが驚きました。なんと開会式の前に、宅急便でお土産を送るところに列ができていて、「もうすぐ開会式が始まるのですが、大丈夫ですか。」というぐらいで、皆さん、せっかく岐阜に来たのでとなっていらっしゃいました。食はすごく大事だなと思いました。
その流れで、3つ目のポイントは、今回、岐阜の特徴ですけど、モーニング文化。これを全国に発信できたなと思っています。当初は、100いくつかなと思ったのですが、県内410を超えるお店が協力していただきました。また、岐阜メモリアルセンターなど、県内3カ所で実際にモーニングが食べられる場所を設えました。県外の方から、「これがこの値段でいけるんですか」という驚きの声がありました。特に、私も出させてもらった講演で、鎌田實先生、お医者さんであり、有名な作家でもある方ですが、やはり朝食の大切さと外出することの大切さを本当に強調していただいて、今後、岐阜の名前をモーニングとともに発信してくださるそうでありますので、岐阜と言えばモーニングというそんな流れができたかなと思っています。
こうした特徴も踏まえて、今大会を契機に、健康長寿といえば岐阜県、とりあえず岐阜県に行ってみようということを、全国の皆さんが感じていただいて、いつも言っています、「美味しい・楽しい・ワクワク」で、頑張って健康になるのではなく、意識しなくても健康になる環境が岐阜にありますよと、それがモーニングであり、自然もあり、そうしたものだということをわかっていただきますと、まさに大会のレガシーであります、人生百年時代の健康づくり、まさに大成功だったかなとありがたく思っております。
こうした盛り上げと同時に競技もありましたので、お手元に配らせていただきましたが、本当に頑張っていただいて、総合優勝を競うものではありませんが、水泳、テニス、剣道。剣道は、決勝戦が両方とも岐阜県の選手で、素晴らしいものでありました。最後の最後、閉会式の後にソフトボール優勝というのもありました。これも取り上げていただきましたが、本当に皆さん一生懸命やっていただきましたし、個人も12種目で優勝と、お年を取られても、そうしたところに挑戦し、また賞を得ていただけるというねんりんピックの大事な一面だと思いますが、非常に良かったんじゃないかなと思っている次第です。これが冒頭、触れさせていただきましたねんりんピックの総括です。
それでは、お手元にお配りしております発表項目について説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず最初に、この週末にあります岐阜県農業フェスティバルについてです。地域の方にも人気の一大祭典になります。週末の25日、26日にこの県庁周辺で行われますので、ぜひご参加ください。もうすでに、県庁前の広場にはテントが立っておりますし、隣のアリーナのステージなどでフェスティバルを行います。結構長い歴史になりますが、今回のフェスティバルの特徴は、やはり「農業は楽しいんだ」ということをしっかり発信したいということです。ただ野菜を買って、安くて良いよね、美味しいよねということだけではなく、農業そのものに触れていただき、植物を育てる楽しみを体験したり、釣りの疑似体験をしたり、コクチバスといった問題があるということをしっかり理解していただきたいなと思っております。その上で、マルシェ。やはり、有機農業などを目指している沢山の方がいらっしゃるので、こちらの販売をします。そして、薬草フェスティバルですが、県内の薬草を利用し、新たな商品を開発して、それを発信するという大切な機会です。また、ジビエですが、鳥獣害対策ではあるのですが、流れが変われば1つの産品ということになります。そして、次のページにありますように、農福連携の商品の発信であるとか、お花の寄せ植え体験もしていただけるということで、ただの購買だけではないということです。さらには、県庁の20階で、能登地域の応援ということで、石川県の特産品の販売をしたり、福島県の水産物・特産品の販売も考えています。今回も、250団体の参加を得まして、非常に大きな取り組みにしたいと思います。
その上で、1つの目玉としまして、楽しく儲かる農業フォーラムということで、「岐阜から発信!楽しく儲かる農業フォーラム」を開催します。ここで、先ほど申し上げました、「農業は楽しいんだ」ということをしっかり発信をしていきたいと思っております。県庁1階のミナモホールで行いますが、最初に事例発表ということで、たわらファームさん、そして、UmaiJapan株式会社さん、さらには、福井農園さん。こちらは、よく私も色々なところで紹介させていただいていますが、元々岐阜大学の農学部の先生で、農業のあり方を自分がやってみせるということで、一反の畑で、土作りから始めて、56畝全て違う野菜を植えることによって連作障害を乗り越えて、一反で数百万円儲けておられます。多分、今までの農業の常識をある意味根底から覆す取組を実際にやっておられて、これをJA岐阜さんとも連携しながら広げていこうと。今までの農業の当たり前を見直していくきっかけになるのかなということでございます。その後、パネルディスカッションがありまして、あろうことか私がファシリテーターをやらせていただくということで、農業をやってきた人間でもありますので、色々盛り上げていければ良いなと思っております。後ろにチラシが入っておりますが、農業の楽しさについて、ほとんど今は草刈りしかしていませんが、私も畑仕事をやりながら土地を維持していく者として、やっぱり農業は土づくりだということの意味で、種をまけばいいのではないかと思われるかもしれませんが、そうではないということ。逆に、それがいかに楽しいことだということもお伝え出来たら良いなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
次に、今度は森です。なぜドイツなのと思うかもしれませんが、「日独連携シンポジウム2025」と本県初となる「ぎふ森の機械展」について発表します。このタイトルだけで見ますと何だろうとお思いになるかもしれませんが、実は世界的に見ると、ドイツが最高峰と言われています。最高峰という意味は、ドイツは「黒い森」と呼ばれるシュヴァルツヴァルトで、林業の技術が一番発達している。特に、発達という意味は安全であるということ、非常に効率的なやり方をしているということです。日本は急斜の山が多いので、なかなか単純にはいかないのですが、その中で安全に効率的に林業経営をするのが世界一と言われているドイツにある大学と森林文化アカデミーが連携しているので、もう一度改めて発信しようというシンポジウムです。期間は、10月28日から30日までということです。それから、「ぎふ森の機械展」について、資料の後ろの方にシンポジウムについてのチラシがあり、ドイツの先生が来て、同時通訳をするのですが、ドイツの取組、いろんな課題に対する対応、そうしたことをご説明いただくのですが、その中で「ぎふ森の機械展」について、木で機械を作るとお思いになる方がいるかもしれませんが、そうではなくて、林業、日本の場合は自分の足で山に入って、いろんな江戸時代からの技術も含めて、これはこれで伝統技術なのですが、やはり若い人達がこれから山に親しむ、そして安全に(山の中に)入ることを考えると、ヨーロッパで培われたロボット技術、こういったものを使うことによって、本当に多くの人が山に入る可能性を広げていくということでございます。(資料を)1枚開いていただくと、国内のメーカーさんにも協力していただいて、丸太を掴んで倒すと。枝は機械でビーッと切って、バーッと落としてくれる。テレビか何かでご覧いただいたことがあるかもしれませんが、日本の場合は方向を定めて下刈りをして、まさに「倒れるぞ。気を付けろ。」と言ってバタンという感じなのですが、世界ではそんなことはしないです。先に掴んでいますから、下を切っても倒れないと。そのまま持ってきて、安全な所で降ろすということがある意味一般的に行われていると。全部が全部そのままいけるわけではないのですが、そういったノウハウを日本の林業に入れることによって、例えば、力仕事じゃないですよ林業と言うのは。まさに機械を扱うということ、そして女性であってもこうした分野にも入れますよということをご理解いただくために、どんな機械があり、こういうやり方があるのかということを見て感じていただくことによって、木の国山の国で、森林面積が81%を占めているこの岐阜県としては、こうした技術をしっかり普及させることによって山を生かしていくと。もちろん同時にそうした所有権の問題、これはこれで進めていくのですが、そこが解決したとしても、どうやって(山に)入るのということになってしまっては意味がありませんので、そうしたことを広く進めるように、こうしたシンポジウムでご理解いただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それと、一度取り上げていただきましたが、やはり若い人達にどうやって情報を届けるか、これは皆さんの悩みでもあると思うのですが、インスタグラムというのが特に若い人達に伝わる重要な手段ということで、今日からはこの会見を、会見のワンポイント(解説)みたいな、まとめて即、特に若い人向けに発信をすると。やはり難しいとか、探しにくいとかではなくて、それをSNSで解消するということをやりたいと思っております。県職員で特別チームを作りまして、本当に新しい働き方を自ら実現するとともに、自由な発想でやってみてくださいということで、(資料を)開けてびっくり江崎くんが出てきました。これは職員のデザインで、プロは使っていないと思いますが、「え、これかっ。」と思いながらで、昔、私の(商工労働)部長時代にこういう絵を描いている人がいたなと思うのですが、やはりこういったものを使って、分かりやすく親しみやすく、県の情報をお伝えするようにしたいなと思っています。それで、県民の皆さん、特に若い方は県との関わりはなかなかちょっと遠いかなと感じておりますので、そうしたものを分かりやすくお伝えすることで(メディアの)皆さんと共に重層的に情報発信することによって、県民の皆さんが今何が起きている、これから何をどちらに進もうとしているのかということをしっかり伝えていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。私の方から以上です。
記者
NHKさんとの面会の件は何か進展ありましたでしょうか。
知事
今、まさに鋭意調整中でございますので、日程が取れたらお邪魔させていただこうと思っています。
記者
NHKに申し入れたのは、いつ頃になりますでしょうか。
知事
結構前だったと思います。
記者
全国知事会議の直後なのか、(9月議会)開会のタイミングぐらいだったのか。
知事
そんな先ではないです。
記者
議会で発表された前後ですか。
知事
(議会で発表した)前後だったと思います。ただ、こちらの行ける日の選択肢が無さすぎて、そこの調整をしているところです。向こうの事情というよりは、こちらの事情かもしれないですね。
記者
ご承知のとおり、高市政権が新たに誕生しました。日本維新の会との連立政権を組む中で、ガソリン税の暫定税率の廃止であるなど、地方にもかなり大きな影響を及ぼすような政策も掲げられている中で、これから新しい政権とどのように向き合っていかれるのか。あるいは、どんなことを課題として考えていらっしゃるのかお聞かせください。
知事
報道されていますように、この国の憲政史上初めての女性の総理大臣の誕生ということで、ある意味、多くの方がここで何か新しい視点が入り、変わるんじゃないかなという期待があろうと思います。それは、我々にとっても同じでありますし、もっと国際的に見れば、高市さん自身がおっしゃっておられるように、世界の政治の中で中心的な役割という中で、日本も女性が総理大臣になれる国になるんだということを発信できたということだけでも、非常に(意義が)あると思います。そして今回、日本維新の会との連携ということなので、今までとは違ったいろんな政策の判断を、まずは我々というよりも、与党の中で調整されると思うのですが、その中でいろんな発信、特にあのガソリン税ですね。これはもうすぐやるということなのですが、そうすると当然財源が無くなってくるわけで、無くなって終わりということは多分ないでしょうから、それに対する対応策をしっかり求めていきたい。これは、前の全国知事会議でも、決議として出していますので、これは引き続き変わらないと思っています。
その一方で、物価対策をしっかりやるということでもありますし、そういった意味では、私も国にいたのでわかるんですが、物価対策を進めると言って各省に号令がかかるんです。さて、何しましょうかっていうのはそこから始まるんですが、そういう時に、例えば、地方ではこういうことをやってもらうとありがたいというようなことも含めてこれから打ち込んでいきたいなと思っていますし、そして、頭の体操も、我々もしっかりやっていきたいと思っています。いずれにしましても、誰がやっても今大変な時期だと思いますが、そんな中で、世界の情勢、それから、特にトランプさんとの関係で経済に影響は少なからずあると思うのですが、それをどういうふうに前向きに捉えて、そして、業態転換とかですね。それから私ども進めている働いてもらい方改革。こうしたものを、効果的につないでいくのかと。これをしっかり、この政権ともつないでやっていきたいなと思っています。
記者
事務事業の見直しのことで伺います。議会答弁の中で、職員から168件提案があったと(思います)。昨日、知事も本部員会議に出席されたかと思いますが、例えば、いくらぐらい減らしたいという目標値であるとか、その辺の進み具合を教えてください。
知事
昨日の本部員会議でまさに指示したのは、そういう額ではなく、県民サービスは減らさないと。むしろ高めると。ただ、そのやり方を根本的に見直してくれと。特に、今日の幹部会議でも少し言いましたが、今までの当たり前ではなくて、もしそれが自分のお金だったら本当にそんなことをしますかと、逆に言うと、お金を使うのだったら、一過性で終わるような事業にはしないでくれと。使ったものを次に生かせるように、そんな発想も含めてやってくださいっていうのは1つ。逆に本部員の方からは、それを1年で(行うの)はやはり無理があると。当然のことながら、プログラムでやってほしいという議論が出ました。それはもちろん、まず大きな方向性を示しつつ、ただ1つ、各幹部の方に申し上げたのは、今大変だから我慢してくださいという政策をやろうとしているのではありません。まさにこの県が、50年後、100後、どういうまちになっていくのか。我々の子や孫、その先も含めて、どういう岐阜県であってほしいかということを、県職員として一番考えることのできる何十年に一度のチャンスなので、そんな発想で政策を見直してくださいと。
その結果として、どこにお金を使うべきなのか、使ったお金がどう生かされるのか、そこをしっかり検証していきましょうというのと、次長を中心とする一種のドリームチームという言葉を昨日言われていましたが、財政経験者が大半だという中で、やはり県全体を見てどうあるべきかと。頑張ったとこだけが予算が減らされるということではなく、そうしたこともしっかりやっていきましょうと、それが昨日の本部員会議の議論でした。
記者
ねんりんピックに関連することになりますが、改めてこうした大型のイベントに対する考え方というものをお伺いしたいです。いろんなまあ効果ももちろんあると思うんですが、一方で、市町村への負担や、時間自体も、知事も多分この2、3日ずっとねんりんピックの方に行かれていたと思いますし、いろんなところもあると思うんですが、その辺も踏まえて、今後、大型イベントに対する考え方というところをお伺いできればと思います。
知事
私も国にいる時は、前任から引き継いだ仕事を、「えっ」と思いながら(やっていて)、むしろ変えることによって、当初思っていたよりもいい政策にするということは、割と経験させていただきました。今回、ねんりんピックが良かったのは、もちろん、5年越しということで、何度も中止がありながら、準備期間を含めれば7年という期間だったのですが、そうしたものを引き継いで、私の県政になってから実際に実行するということですが、この間にも、おかげさまで、スタッフの皆さんが、さっきの方針通り考えてくださって、かなり大きなプロジェクトをやめています。やめていますが、多分それをやらなかったから下火になったかという感じはむしろなくて、かえって盛り上がったかなというのはあります。特に、工夫をすることによって、同じお金の使い方でも変わったなというのと、今までは、どちらかというとイベントというと有名なタレントを呼んできたりとか、外国の方に来ていただいて、その旅費から何から全部持つとか、デコレーションもみんなプロに任せるということで、ものすごいお金を使ってきたかなと。
そこで、そういうのをやめようよということで、まずは自分たちでできるところは自分たちでやる、有名なタレントではなく、地元出身の方を中心というのと、やはり先ほど申し上げた高校生、若い人たちが参加していただいたことによって、各県の参加者も、ねんりんピックで高校生が出るというのを初めて見たというのと、特に県立岐阜商業高校の応援団の子たちですね。オープニングだけでなくて、サイドイベントでも応援していただきましたが、本当に立ち見が出るぐらい大人気ということで、そういったやり方によって、お金は節約した上で、会として盛り上げることができるということで、そのやり方を経験するには、ねんりんピックはすごく良かったと思います。ただ、今後、そうしたイベントをガンガンやっていくかというと、今回の農業フェスティバルもこの一種のイベントなのですが、その中では政策のメッセージをしっかり付けていくということ。やるからには、しっかりその後に残るようなもの。今回は、アグリパークにつなげていくという政策目的のもとに、農業は楽しいということを大々的に発信して、イベントが終わったら忘れるのではなくて、イベントがあったから、こうした政策がやりやすい環境ができたと、そんな方向で使っていくものについては、しっかりイベントをやりますが、とにかくイベントをたくさん取りに行こうとか、そういうことではないということです。
記者
差し支えなければ、ねんりんピックはだいたいもともと予定されていた事業費をどれぐらい節約されて開催されたのでしょうか。
知事
億単位では節約しています。
記者
それこそ主にタレントを呼ぶのではなくて、ある程度地元の方々で構成していくというか、その辺の人件費って言っていいのですかね、その辺を削られたってことですか。
知事
イベント費だとか、人件費なのかな。イベント費の中に人件費も入っていると思いますけど。
観光文化スポーツ部
いろんな形で削減を進めておりまして、特にこれがごそっと落ちたとか、そういうことではなくて、知事が話した通り、とにかくいろんなところで節約をしていると捉えていただければありがたいです。
記者
それは数億円単位でだいたい削ったということですか。
観光文化スポーツ部
今まさに決算をしようとしておりますので、もう少しお待ちください。
知事
大きく辞めたのは、もう1つ別のイベントでした。そちらもおかげさまで大成功だったんですが、大きく減らしています。
記者
LRTに関してですが、この前の議会で(補正予算が)無事可決されまして、その調査の進捗、外部の専門家の方は決まったのか、もう調査は始まっているのか、いつ頃始まるのかなど、そういった進捗を伺えると幸いです。
知事
まさに、今、オンザウェイでやっております。その中で、何を調査してもらうのかというのは結構大事なポイントになってくるかなと思っておりますが、特に今の現状の交通の状態、これと、新しいルートを取った時にどんな交通影響があるかなど、プロのシミュレーションができるところにお願いをするという、そんなことで考えておるところでございます。特に今契約がどこまでいっているかっていうのは答えて良いものなのか。
都市建築部
補正予算におきましては、事業スキームの検討業務と既存バス路線の再編、パークアンドライド等の導入の検討の方を行うということで、予算計上しております。こちらにつきましては、予算の成立に伴いまして入札を行いまして、それぞれ契約を締結したところでございます。こちら3月下旬の工期までということで検討を進めていくということにしております。
記者
3月までというのは、なんでしたでしょうか。もう1回よろしいでしょうか。
都市建築部
契約工期です。契約の工期を、そういう形で設定して検討を進めているという事です。
記者
要は、3月までの期間で調査をしてもらうということでしょうか。
都市建築部
その通りです。
知事
補正予算なので、そこで終わらなきゃいけないので、できるものをやっていただくという形になります。
記者
どこと契約したかというのは、今のところ明らかにしているのでしょうか。
都市建築部
入札の情報で公表はしております。事業スキームの検討につきましては、日本工営株式会社さん。路線網の再編やパークアンドライドの検討については、株式会社オリエンタルコンサルタンツさんと契約をさせていただいております。
知事
そこまではいいですね。金額はその内容に応じてということで。
都市建築部
詳細は、県ホームページの入札情報の公表等で確認していただけると思いますので、よろしくお願いいたします。
記者
大きく3点質問させていただきます。まず、発表項目にありました、インスタグラムの件ですけれども、先ほど知事ご紹介いただいたキャラクターの「えさきくん」ですが。
知事
というものを私も先日聞いて、おお、と思って。
記者
非常に愛らしいキャラクターと言いますか。
知事
ちょっと額が広いなと思って。
記者
後ろにあります、今のキャラクターのミナモちゃんでありますとか、ちょっと知名度は劣るんですが、あすはちゃん、というのもいまして、この「えさきくん」ですが、そこと同じようにブランディング戦略において活躍の場を広げるお考えはありますでしょうか。
知事
ミナモはミナモでもう確立されていていいのではないかなと思っています。おそらく、若者たちが考えてくれたのは、知事という存在も遠いし、知事自らが発信するというのを、いちいち私が出てくるよりは似顔絵の方がわかりやすいんじゃないかということだと、私は勝手に解釈しています。昨日、たまたま来られたお客さんが、これを絶賛してくれて。あんまり絶賛されるので「似てるか」と思ったのですが、やっぱりウケはいいみたいです。おかげさまで。だから、別にミナモにとって代わろうというつもりは全くありません。あくまで、県庁から発信した時に、「あ、知事ってこんな人なのね」と、皆さんのおかげで写真が出るので、なんとなく似てると、皆思ってるのかな。昔、やななと一緒に絵を描いてもらった時に、確かやっぱりあの時も「額広くないか」と聞いたことあるのですが、それが復活したようでございます。
記者
先ほども少しお話がありました高市新政権について、石破前総理が肝いり政策として掲げられた防災庁についてですが、高市新総理も引き続き継続していくというお話がありました。ただ、江崎知事に関しては石破前総理とのパイプが1つ、岐阜県の誘致に関しては強みだったと思うのですが、政権が変わったことによって、その影響というのをどのように江崎知事はお考えでしょうか。
知事
石破総理は、実はまだ総理になるずっと前というか、私が書いた本「社会は変えられる」を結構愛読していただいて、特に地方創生という観点で一緒に仕事をしたことがあったのと、特に彼は高齢社会の医療問題はすごく関心があるということで、そこのパイプは非常に強かったのはあります。なので、就任早々、官邸に来てくれないかということで1時間ほど話したという関係ではありました。高市さんはどうか言うと、それなりに親しいです。なので、見れば「江崎さんどうも」という感じの関係ではありますし、今回、政務の秘書官になられた飯田(祐二 前経済産業事務次官)さんは、私が(経済産業省の)1年生の時の2年生です。なので、この間まで経産省の事務次官をやっていた方でありますし、そういう点では、この政権、特に高市総理とは役人時代もいろいろと政策でも話をしたこともありますし、そういう点では、これ(政権)が変わったから、特に不利になるということはないかなと思っています。むしろ、高市新総理の視点に、しっかり我々としても政策を打ち込めればいいかなと思っています。
記者
先日、県議会の常任委員会の教育警察委員会の方で、小中学校の異学年教育の話題が出まして、そこを踏まえて質問させていただきます。知事は、小中学校の5教科での導入を前向きに考えるということで、市町村教育委員会に対して、来年度から財政支援をいわゆる手上げ方式で(行う)というところだと思うのですが、先日の総合教育会議の中でも、知事自らお話しされていたと思います。ただ、先日の県議会の常任委員会の方では、議員の先生から、小中学校はほとんどが市町村立であって、県教育委員会主導で、半ば強制的にやられるということに不安もあるというご指摘もありました。そういう意味で、県教育委員会の所管でありますとか、市町村教育委員会の所管というところを考えると、今の県の案というのは少し行き過ぎもあるのかなという指摘だと思うのですが、その辺り知事としてはどのようにお考えでしょうか。
知事
強制されるのであれば、多分フィールド外だと思いますが、私、元々国にいる時に「未来の教室」ということで、教育改革を担当しておりました。その時に、どうやってこの国の教育の在り方を考える、それはまさにいじめの問題だとか、不登校の問題、もうその頃からそういう議論になっていました。その中で1つの解としてあるのは、昔から、明治時代からやってきた一斉教育、同じ学年で同じペースで同じことを決めて学ぶというのは、当時の議論でしたが、先進国でこれをやっているのはもう日本と韓国だけで、韓国ですらも変えようとしている中で、やはり一律型というのは、読み書きそろばんをより多くの人に揃えるのは良いのだが、やはり自分の発想で自分の能力を生かすには合わないのではないか、当時そんな議論をしていました。ただ、その中で、それをどこの段階でやるのが一番効果的かということを、実はこの4年間も見ている中で、やはり小学校というのは一番良いのではないかということを経験的に感じております。当時、「未来の教室」をやっている時も、やはり小学生、ギリギリ中学生は少し遅いかもしれませんが、小学生が一番良いだろうなと。だから1年生から3年生までで1つの学年、4年生から6年生まで1つの学年、中学を1つにするかどうかというのはまた議論があると思うのですが、そんな中で、やはり自分の良さを見つける。今までは、この国はとにかく分ける方向に分ける方向に教育を進めていってしまったので、それを、例えば、3年生の中では目立たない子でも同じ教室の中に2年生、1年生がいれば、その子たちに対してはリーダーになれるし、思いやりの形もできると。実際、岐阜県で実践していただいた学校に私も行きましたが、やはりその結果として、いじめが減ったというか、人は自分より明らかに弱い人に対しては優しくなるという、当たり前のことなのですが、これは教育長と話をしても、我々とあえて言いますが、昔は学校が終わればお宮に行って1年生から6年生までが一緒に遊んでいた。その社会構造が今の社会になくなってしまったので、これをどうやって教育のところに戻すかという中では、やはり小学校、中学校ぐらいが良いのではないかと。なのでおっしゃる通り、それを県がなかなかやるわけにはいかないので、市町村の教育委員会の中でそうした関心があるところに呼び掛けて、だから手上げ方式になったのですが、実際に事前アンケートで、おかげさまで約3割の小学校から(5教科の学習に限らず、学校生活の中で異学年集団による活動の機会を拡充することに)関心ありという反応を頂いておりますので、ただ、もちろん不安もありますし、特に先生方の不安が一番大きいです。全国でもいくつかやっていまして、すでに回ってきましたが、やはり導入のタイミングが一番難しいですし、やりたいという学校はたくさんあるのですが、やはりスタッフが足りないということが多いので、今回そこについての手当てを県の方でしてみるので、教育委員会単位で手を挙げようと思っています。だからどの学校と指定するのではなくて、そういった教育委員会として関心あるところが手を挙げていただいて、さらにその教育委員会の中で学校としてやりたいというのがあれば応援しますよという、間接支援方式を取っておりまして、ただ、これを高校でいきなりやるかというと、多分高校だと、これまでの経験から言うと、タイミングとしては少し遅いのではないかということで、教育全体を考える意味でも、市町村に協力を呼び掛けたと、そんなスタイルになっています。
記者
関連で質問させていただきたいんですが、つまり、県立学校という所管、市町村立学校という所管というところを考えないと言いますか、そこを取っ払っていくというような思いでしょうか。
知事
取っ払うというか、やっぱり教育というのは1つ人生の中のどのステージで、そうしたことをやるのが一番効果的かという意味においては、私自身やっぱり小学校が大事かなと思っています。プラスアルファとして、中学でもそれが残ればいいかなと思っていますが、やっぱり小さい頃に勉強は楽しい、特にあの会議でも言いましたが、この国は遊びと学びを分けてしまった。
遊びは放課後とか休み時間で走り回って楽しいもので、学びというのは教室でじっと座って苦しいものみたいな、そうじゃないだろうと。
そうすると、これ逆転教室と言って、我々の頃がそうであるように、学校で習ったことを家で復習して、翌日小テスト、これは我々、多分ここにいらっしゃる皆さんが経験してきた教育ですが、この異年齢学級は多分、最終的に逆転教室と言って、家で勉強してきたことを学校で復習する。そうすると分かる人に聞いたり、友達に聞いたり、なので場合によっては同じクラスの中で違う科目やってることも、これは最終形なんですが、それに向かってどんなことができるのか、逆にできないのか、そのためにはどんなことが必要なのかということを、やってみる。
もうそのタイミングに来てるかなというふうに思っておりますので、それを県内でそういう関心を持って、意外に関心が高かったので、やれるといいかなとそんなステージになっております。
記者
最後にもう1点だけ、手上げ方式という支援、まだ検討段階だと思うんですが、ただ、どこかの市町村が手を挙げると、うちも支援してもらいたいっていう所、どんどんどんどん出てくると財政的にも結構負担っていうのも大きくなってくるのかなと思うんですが、そのあたりについてどのようにお考えでしょうか。
知事
文部科学省に持って行こうと思っています。全部県の予算でやるつもりはありません。これまさに国家百年の計ですから、私も実は内閣府の審議官の時に教育担当をしておりましたので、まさに文部科学省とやりあいながら、これからの教育のあり方、いじめの問題を担当しておりましたので、文部科学省さん自身がその答えがなくて非常に苦しんでいるというのを私はまさに担当してきましたので、だからこそ、ちょうど未来の教室をその前にやってたと思うので、できないかということも文部科学省と話をしてて、やはり実際にやっているところとその成功例がないとやはり難しくて、これまでの経験で一番難しいのは先生です。今までの教え方と違う教え方をするということに対する抵抗感はすごく大きいので、しかもこれは、ある校長先生が頑張って実現した学校っていうのは今国内にあるのほとんどなんですが、やっぱりその先生がいなくなるとやっぱり消えてしまう。だからこそ、今回、教育委員会として手を挙げてくださいと、それを全体として評価する中で、そのやりたいと思う学校を選んでくださいと、二段階方式ということで、それによって継続できる、それがある程度成功する形になったら、もう即これは文部科学省と話をしようと思っています。そんな流れにしたいと思っています。
記者
ちなみに、その文部科学省の話については、現状、支援する制度、支援メニューがあるのか、これから作っていくという流れなのか、どんなイメージですか。
知事
これからまさに我々はやっぱ加配というか、やっぱりスタッフが足りないのが一番だというふうに今そういう声が多いので、だからその人件費を見ると、あと勉強代とか、やっぱり成功している例が全国にあるんですが、そこに行く出張旅費がないとか、まさにそういうリアルな声があるので、そこを今回は県で応援しましょうと。やってみた結果として、たまたまこのクラスが良かったから成果が良かったではいけないので、3年間という時間をあげて、その間の中でやっぱりこれ良さそうだっていうのを持って、そのためには、例えばそういう専門の先生がいるのか、それとも先生の負担を変えるのか、ないしは生徒に特別な部屋がいるのかということはこれで見えてくると思いますから、それをもって文部科学省に支援のあり方を要請していこうと思っています。
記者
農業フェスティバルに関連して、その中で行われる農業フォーラムは県としては初めての試みなのでしょうか。
農政部
今回初めて行うものです。
記者
いろいろと現状や課題改善点もある中で、初めての開催ということだと思うのですが、そのあたりの経緯や、何か今後のビジョンや目指す方向性などを聞かせてください。
知事
実は今回、タイトルは楽しく儲かるが表題になっていますように、令和の米騒動を踏まえて農業のあり方が国を挙げて見直そうという流れの中で、我々として、もともとアグリーパークを推奨する立場から、農業というのは大変だとか、お金がかかるという発想を変えていけるようにしたいと。まずは楽しいし、ビジネスとしても儲かるんだということを見せていく。先ほど申し上げました、この福井先生、岐阜大学副学長までやられた方自身が実践して、すでに成果を上げているということを見るだけでも、「そんな農業があるんだ」というのとか、あとはこのたわらファームさんもそうですが、本当に若い人がやってる。若い人がやることによって、今までの農業とはこんな面白いのがあるんだと、若い人でもできるんだということや、結構儲かってますという話もあって、そういうことを実際に聞いていただくことによって、これまでも長い悩みがあったように、後継者不足だったり、いつも言っているように農家を継ぎたい人は少ないけど、農業をやってみたい人は多いということを、実際にこういったことでさらに加速をするということ。それを今度は、これから募集していきますが、アグリパークの中で実践していくようなそんな流れです。一過性のイベントではなくて、ここから県としてやりたい農業政策につなげていく、そのキックオフのそんなフォーラムにしたいと思っています。
農政部
補足ですが、現在、来年から始まる新しい農政の基本計画を策定しておりますが、まさに今、知事が申しましたようなことが内容になってくるということで、アグリパークはその肝というところになっていますので、そのキックオフイベントとしてこれを開催するというところです。
記者
弊社としても、今週の月曜日、清流の恵みの新米フェア初日、販売会と食堂での特別メニューを取材させていただいたのですが、こうやって儲かる農業というのと、育てやすい品種を育成していくという点も力を入れていこうと思っていらっしゃるということでしょうか。
知事
実際には、今までの当たり前だと、設備投資にすごくお金がかかるとか、農業は気候変動で大変だという話ばかり聞こえてくるのですが、別に個々人が買わなくても共同で機械を運用したり、場合によっては居抜きのような形でもいいですし、さらに気候変動=悪ではなくて、暑さに耐えられる品質で美味しいものができればいいですし、もともとは台風が多いので腰が強いものを作ろうというのがあったのですが、そんな中で今度は暑さ対策ができるものがあれば、本当にそうした農業の発展の可能性を広げていく、その両輪でやっていきたいと思っています。
記者
新首相誕生というところで、その中で日本維新の会と合意文書を交わしたということで、この中で2つ、地方に関わるものがありました。副首都構想が合意書に盛り込まれたということで、地方創生に大変影響があると思います。これについての所感をお聞かせください。
知事
日本維新の会は、もともと大阪維新の会から始まっているので、副首都ということがメインに出ていますが、ちょっと視点を変えると、いわゆる東京一極集中が変わるかもしれない大きなきっかけになると思います。逆に言うと首都が2つあれば、問題はすべて解決するかと言うと多分そうではなくて、なんで副首都がいるのかというその文脈の中に、地方創生はしっかり入ってくると思います。おそらく役割として、前も申し上げたように、東京と大阪だけが栄えればいいかというと、多分そうではなくて、特に岐阜の場合はその真ん中にありますから、特にリニアができることによって、東京のパートナーになれる。人生百年を都会か田舎かではなくて、都会も田舎もどちらも楽しむことができる。特にバリバリ働きたい人もすぐ行けるし、やはり子供は自然の中で育てたい。今の農業がそうであるように、東京の真ん中で農業はできませんので、そうした土に触れるということができるという意味においては、この国の持っている機能、役割、期待というものを全国に分散していく1つのきっかけになればいいかなと思っています。
記者
衆議院の定数の1割削減が盛り込まれているということで、地方の声が届きにくくなるのではないかという危惧もあろうかと思いますが、これについての所感を教えてください。
知事
定員削減の問題は昔からやって、なかなか実現しないと。その中でもおっしゃった(声が)通りにくくなるかもしれないという議論はもちろんないわけではないです。他方で、届け方がそれだけかというと、先ほど質問があったように、直接、政権に対して県として発信をしていくルートも結構大事です。私はたまたま霞ヶ関にいたので、霞ヶ関の局長クラスはほとんど知っているというのと、国会議員の先生方に伝えていただくルートもあれば、我々が直接伝えてくるルートもあると。あともう1つは県民の皆様の声をどれぐらいそれぞれが吸収できるか、むしろこちらの方が大事だと思っていて、それで今回、インスタグラムを作らせていただいているのは、特に若い人たちが何をやっているのか知らないまま意見を求められても言えないというのが1つと、それから特にXというのは、発信一方通行ではない。必ず返ってくるのに対して、キャッチャーのチームを作りましたので、それに対して答えていくという中で、県民の声がどういうところにあるのかと。いつも言う人の話ばっかり聞いていると、それは県民の声になってしまうように思われるので、そうではないところも広げて、いろんなルートを使いながらしっかり届けていく中で、あとは定員がどれぐらいがいいのかというのは、国会の方で議論した方がいいかなと思っています。