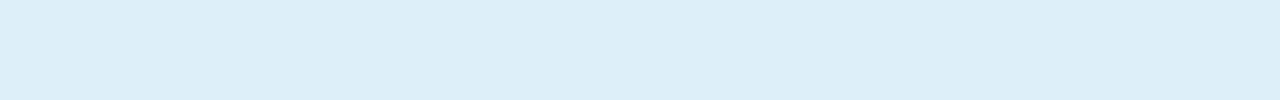本文
知事記者会見録(令和7年9月10日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年9月2日(火曜日)14時00分
司会
それでは、知事定例記者会見を始めさせていただきます。
知事お願いいたします。
知事
今日は、私の方から2つご報告させていただきます。
まず1つ目が、「働いてもらい方改革」の第二弾の発表になります。実は昨日、私は官邸で総理、官房長官含めて、県の取組み、特に地方創生についての報告をしてきたのですが、その中で働いてもらい方改革、これを1つの柱としてご説明させていただきました。非常に皆さん関心を持っておられて、今の特に人手不足という問題と、企業の生産性向上、これを同時に達成するということで、昨日は(事例集の)第一弾の方の、坂口捺染さん、こちらでも(以前の記者会見で)ご紹介しましたが、それを例に挙げながら、まさに分業化と、多能工化、そして他のところで、特にDX、ICTを使うことによって、本当に生産性が上がってると。今回は、後ほどご質問いただければと思いますが、今まではどちらかと言うと、ものづくりなどが多かったのですが、特に農業だとかサービス業の中で、今まで当たり前と言われていたような、動物を飼うと休みがないとか大変だということを見事に変えて、ちゃんと休みもしっかりと取れるし、その上で飼育量を2倍以上にするということで、本当に見事なこれからの時代を先取りするような企業さん10社、第1弾と合わせて20社を発表しております。
今日も、実は東京からお客様が来られて、これからの政策を考える中で、これをご紹介したら非常に関心を持っておられて、特に今、労働市場において賃上げということが議論されておりますが、大企業は内部留保を取り崩しながら何とか賃上げを達成していますが、特に中小企業の場合は、むしろ生産性が今低い状態の中で、賃上げということで大変苦しんでおられますが、むしろ働きたい方が働きやすい時間帯が一番生産性が高いと。坂口捺染さんの社長の言葉を借りて言うと、「企業にとって都合の良い人を探そうとするから人手不足がある。」と。働きたい人が働きやすいように企業が働き方を変えれば、人手不足はなくなるし、さらに坂口捺染さんも10年で売り上げ10倍になっているように、まさに業績も上がっています。今回、ご紹介する10社の例を見ていただければ、本当に生産効率がものすごく上がって、2倍だとかそういったことが普通に達成されていると。そうしたものが、特に岐阜県からではあるのですが、この国の未来を考えるに当たっての極めて有効というか、参考になる情報を発表させていただきます。
よく読んでいただくと、ほとんどの会社に共通点があります。業種ではなく、そうしたものの中に未来の姿があるなと読み取れるのではないかと思いますので、是非可能でしたら、各社さんそれぞれに取材をしていただくなり、取り上げていただくと、皆様が発信する中身も充実するのではないかと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。これがまず1点目です。
2つ目が、いよいよ議会に向けて、来年度当初予算編成ということで、もちろん今度の9月議会では9月補正(予算)もあるのですが、この段階から、国もそうですが、来年度当初予算が、いよいよ私の県政になって、本格的にゼロから作っていくという中での方針、残念ながら以前も申し上げましたが、非常に財政が厳しい状況の中で、それでも県民の皆さんの生活を守り、むしろ発展させていくために、どのような取組みをするのかということで、今日の午前中に事業見直しの推進本部が行われましたので、それを踏まえての発表ということになります。
先にお手元の資料で、現状をもう一度説明して、実は職員の中でも「なかなか今の現状は厳しいとは聞いているけど、何がどう厳しいのかがよく分からない。」と。多分皆さんもそうだと思いますので、もう一度簡単に、この場を借りてポイントだけご説明させていただきます。お手元の「参考資料」(1ページ)の円グラフ、これをご覧いただきエッセンスだけご説明しますと、今岐阜県の令和7年6月補正後でありますが、直近の予算で予算額9,244億円です。たくさんあるなと思うかもしれませんが、この中で職員給与だとか医療費、福祉だとか市町村に交付するお金とか、借金の返済だとか、元々政策的にいかんともし難いものが義務的経費と言うのですが、これが赤枠で示してある部分です。ほとんど7割以上ということですが、これが今後どうなるかというのは右側にありまして、これが残念ですがどんどん増えていきます。そうすると、この赤枠でないところ、とは言っても災害復旧だとか、消費してしまうわけではないのですが、投資的経費と言いながら、どちらかと言うと災害復旧系を中心に、それから施設の維持管理だとか、制度融資などのように、そんなに自由度が無く、政策として維持しなければいけないものが大半で、その他の287億円、これがある意味、いわゆるいろんな政策を打っていくところなのですが、これは全部県費ではなく、国のお金も入っているので、国のお金を使いながら、この部分がいわゆる政策と言われるもので、3.1%しかないと。この中でどう予算を組んでいくのかということなのですが、中でも実は、今回本格的に難しくなってくるのが2ページ目でありまして、今までも大変、大変と言っていたじゃないかと、特に何が大変かというのを端的に示したのがこの2ページ目であります。実は前の県政の古田知事の時も大変だったのですが、ある意味少し良かったのは、借金の返済を10年先延ばしすることができたということです。左のグラフで言うと、本来は青いグラフのように返済をしなければいけなかったのですが、10年見直しができたので、オレンジ色のグラフのように、ちょっと減らすことができたと。その結果何が起こるかというと、令和7年以降にその分を返さなければいけないということで、ここから先、先延ばしはできないのかと言うと、法律上できません。なので、それを端的に表したのが右側のグラフで、下に下がって上に上がってるというところです。つまり、前県政において、1,500億円の借金を何とかしなければいけない中で、10年先送りにできたので、平成30年をピークに負担がぐっと減りました。ここの部分がちょっと楽になったという言い方をしますが、当たり前ですが借金なので返さなければいけないと。それが、何とこの令和7年から本格的に返すことになると。これはもう先送りできないので、今までと違って、これを返しつつ、県政を運営しなければいけないと、そこが今回の一番難しいポイントになってきます。その影響を端的に言うと、(参考資料の)その次のページ(3ページ目)をご覧いただくと分かります。すごく分かりやすい説明をしてしまうと、破綻という概念はいろいろあると前回も言いましたが、特に県政運営の中で、いざという時に対応できるかどうか、これがすごく大事なポイントになってきます。そのために、財政調整基金、いわゆる基金というものがあります。何かあった時に当初の予算では対応できないもののために、こうした基金を積んであるのですが、昔2千何百億円とあったのですが、今はぎりぎりです。これまでと同じような予算を組んでいくと何が起こるかと言うと、この基金を取り崩しながら予算をやってきたと。いわゆる、だましだましという言い方を昔されたかもしれませんが、そういうことです。今回、令和8年度の予算を去年と同じように組んだとすると何が起こるかというと、当初の段階で、459億円の基金残高になっています。これの意味するところが何かというと、この基金がなくなると、令和14年には赤色(のグラフのよう)になります。そうすると、何かが起きた時に対応ができなくなります。かつて財政破綻をした時は、まさにこのように基金がゼロの時です。それこそ、いろんな給与カットをしたり、福祉の予算を切ったりとか、公用車のカーナビを外したりとか、およそできることは全部やって回しているのがこの令和14年ということになります。これはいわゆる一つの破綻の姿になります。もう1つは参考のところに、実は令和7年6月補正予算で414億円という、これは少し技術的な話になりますが、実は当初予算を組む時にこの基金が使えることを前提に予算を組みます。最終的には、いろんな事情の変更で国から後で予算が来たりして、最終的には少し基金が戻るというのを繰り返しながらこの基金がずっと減ってきているのですが、実は、鋭い方は分かるかもしれませんが、普通に今までどおりに予算を組もうと思うと、当初の段階で414億円ないと、予算が組めないということです。ということは、お分かりのとおり、もう今の状態で令和9年度の予算は組めません。ですから、ある意味、半強制的にこの事業を止めろということをやらない限り岐阜県は予算が組めないんだということです。多分、これが一番分かりやすい説明だと思いますが、まず緊急事態に対応できなくなる、いわゆる破綻が令和14年です。それに対して、当初予算がそもそも組めないというのが令和9年ということになりますので、そんな先どころか、2年後にも予算が組めなくなるというのが、残念ですが、今この岐阜県の現状です。
さあどうするかというのは、まさに我々が課された課題なのですが、今申し上げたように、今までどおりやるとすればなので、今までどおりやらない。一方で、県民の皆さんの生活に支障をきたさない、ないしはもっと前向きなこともやって、未来を作っていくために我々は県政運営をやっていくので、そのために何をしていくのかというのが、まさに今日の本部員会議で議論されたことです。ここで「資料1」に戻っていただくと、まずやれることはそうたくさんあるわけではないのですが、「事業見直しの方針」です。大きく分けて3つのことをやっていきます。何かと言うと、県のお金は残念ながら非常に少ない状態ですが、逆に県のお金でない形で必要な事業をやっていけば良いだろうということで、まずは何と言っても国費、これは前回の議会でもお示ししましたが、公共事業の見直し、特に災害その他いろんなことが進んでいくのですが、いろんな形で公共事業に使えるお金を最大限有効活用すると。実は、お昼に国の方に来ていただいて、今度新しく国でできる補助金についての説明を今担当部局が受けておりますが、あらゆる可能性を使って、国のお金を活用して、県を発展させるための取組みをしようということ。そして((1)の)②は、「第2世代交付金」といって、国の方でもいろいろと新しい事業を始めてくれています。これを、交付金が充当できるところに再構築してはめていく。①の亜流だと思いますが、全く新しいものから、順次国の方にシフトしていく。特に、子ども達に対する支援金などが国の方でどんどん充実されていきますので、こうしたものに差し替えて、実際にはご本人の負担が増えたりしないようにしていくというもの。それから③、これが腕の見せ所というものですが、むしろ国が作る制度に合わせていくのではなくて、国自体に制度を作ってもらいにいくと。今社会的にはこうした課題があるので、昨日総理に対して説明をしたのはまさにここなのですが、このように変えてくれれば地方はもっと活性化するということで、制度提案をするというものが(1)の柱です。まさに、国などのお金を最大限使うということです。そして(2)は、業務見直しの柱になってきますが、同じ政策を打つにも費用対効果というのはあるでしょうと。なので、実際に対象を絞る、何をするべき事業なのかと、同じことをやるのだったらもっと他にやり方はないのかということを洗う作業です。そして、他県と比べて過度になっている事業について、「そこまでやらなくても」ということで、お金を付ける優先順位をもう一回しっかり見直していくということ。そして③、これは国でも一緒ですが、一定の役割を終えた事業については見直していくということです。大体3年で「サンセットクローズ」というのは国でも決まっていますが、そういったタイミングで、やっている最中にいきなり切るというのは大変なので、事業を終えたところで、もう一度これを見直していくということをしっかりやっていくと。特にこれまで、イベントが割と多かったというご指摘がありますが、本当にそれの効果を見た上で、同じことをまた淡々とやるのか、そのお金を振り替えて、場合によっては、県ではなく他のお金を使いながらやっていったら良いのではないかなど、そんなことを考えたいと思っています。そして(3)が、今度は入りを増やすということで、そうは言っても、県の収入はそう簡単に増えるものではないのですが、いろんな状況を踏まえて、手数料を見直したりとか、税収を増やしたりとか、あとはもう一つ、お金というわけではありませんが、せっかくある県有財産、特にこの建物自体が非常に価値のあるものであるならば、この建物を使うことによって、普通だったらどこかの施設を借りてお金を払ってやるようなイベントもこの施設でやるとか、まさに様々な、今回(「県民文化の森」夏のわくわくプロジェクトを)やった図書館もそうです、美術館もそうです。そういった県有財産をしっかり使うことによって、地域の活性化、こうしたことをやることによって、所期の目的を達成しにいきたいということです。いずれにしても、県民生活をより豊かにするという目標、ここは一切揺るぐことはありません。そのやり方の中で、ありとあらゆる知恵を使って県政運営をしていくということです。ですから、何となく今までこうやってきたからいけるのではないのかということではないということも分かっていただいた上で、皆さんに知恵を出していただくということをお願いしたいと思っております。県はどうするんだというところが「資料2」でありまして、今日の本部で決定したところですが、こうした厳しい状況にあっても必要な政策は着実に進めると。基金枯渇は何としても回避すると。早くやることが大事なので、前回と言うか、財政破綻の時は、突然来年いきなり300億円切ろうというような話になり、「えっ」ということになるのですが、今お示ししたように、先が見えているわけですから、それに対して計画的にやっていくということをやろうと。先ほどの三本柱に合わせて、このために今度プロジェクトチームを立ち上げることが今日決まりました。その中で、業務の見直し、政策の見直し、特に私もいろいろとこれまで回っている中で、やっている本人自身が「本当はもっとやり方があるのではないか。」、ないしは自分がやってきた事業、今は異動しているが、「こうやったら良いのではないか。」ということを提案していただくような、そんな仕組みを作りたいなと思っております。もちろん、後任だとか、今までやってきたことの関係で、「言いにくいな」というのもあるかもしれませんので、ここは無記名で、いろんな提案、もちろん提案されたものを全て採択するわけではありませんが、いろんな見直しのヒントを広く募るということで、まずは県職員の中から、こうした取組みをすることによって、来年以降の県政運営をより円滑に行っていきたいと、そんな取組みをやっていきたいと思っております。おかげ様で、午前中の幹部会議もものすごい盛り上がりまして、もう時間切れというぐらい、各部の部長さん達からもいろんな提案、それから確認、やはり本当にどれぐらい厳しいのかということを、かなり厳しいやり取りの中で、こうした提案が良いのではないかということはやろうということでありましたので、私としても非常に嬉しかったと言うか、皆さんが我が事として県全体の財政を考えながら政策を作っていただけるという、そんな流れができたかなと思っておりますので、これからまさに来年度の本格的な予算編成に向けて、ありとあらゆる知恵を使って取り組んでいきますということを申し上げて、2つ目の報告とさせていただきます。私からは以上です。
記者
(来年度当初予算に向けた事務事業見直しに係る)職員提案のところで、担当している本人からの別のやり方の提案とか、以前の担当者が(提案する)という話がありました。普通に考えて、予算要望で上がってくるのは、部署の中では議論済みで上がってくるという前提なのではとは思うのですが、無記名としてあることで、途中で潰されてしまうような意見も上がってくることに期待しているのか、それとも、無記名であるから他の部署に関して、客観的な意見も出るというのを期待できるかと思うのですが、知事の狙いとしてはどういうところにあるのでしょうか。
知事
多分、皆さんの会社でもそうだと思うのですが、自分としてはどうかと思いながらも、前からやっているからだとか、いろいろ関係者が多いからだとか、これはこういうふうになっているからということの中で仕事をされる方も多いと思います。これまでの4年間というわけでありませんが、この半年間もいろんな方から、こういうことやったら良いんじゃないかと、だけど、部局の中で議論すると消えてしまうといった声もちらほら聞こえてきております。ですので、この人が言ったからどうのこうのということではなく、しっかり制度として位置付けていっても良いんだということ、それをオーソライズしてあげることによって、言いやすいと。今、申し上げたように、言ったからすぐどうなるわけではないのですが、いろんなことを考える中で、一番頼りになるのは、やっている本人の意見が大きいかなと。ないし、私もそうですが、この間までその部署にいた中で、本当は自分だったらこうしたかったのだけど、前任からの引継ぎでこれはできなかったとか。いろいろなしがらみでやることになっているのですが、本当にそうかという疑問。これは、ある意味一番大事な財産になると思いますので、ただ単に淡々と上がってきたものを聞くということだけではなく、そういうことをしっかりやっていきたいと、そんな趣旨です。
記者
やっている本人の意見というか、その裏打ちがあるということなのですが、無記名で集めると、やっている本人かどうかというのは分からないような気もします。無記名でそうやって上がってきた意見が多数あると思いますが、優先順位の際の材料として活用とありますが、どのような感じでフィードバックするリストを作ってやられるのでしょうか。
知事
今のプロジェクトチームと、私及び財政課のチームの中で、以前は、記名で書いて全部公表してとありますが、そうすると、多分、出てくる量が圧倒的に減ると言われていますので、しっかりまずは私が見るということ。それで、チームの中で揉んでみて、そして、大事なことは、これは良くないのではないかとか、別に犯人探しとか、そうなればなるほど、こうした取組みは失敗しますので、まずは自由に思うところを言ってくださいと。そこから始めませんかと。以前に、前の県政でやられていましたが、政策総点検といって、絨毯爆撃的にわーっと1年間かけてやるということはしません。その代わり、ここだけは伝えたいという声が実はちらほら上がってきていますので、そうしたものを、たまたま私に入れた人だけが動くということではなく、広く募ってみようと、そういうものです。
記者
事業見直しの件ですが、例えば、来年度当初予算では、県費の負担を計何万円、何億円減らしたりとか、そういう目標設定みたいなことはあるのでしょうか。
知事
まさにそれを、これからプロジェクトチームの中で揉んでみて、特に、今日の幹部会議の中でも、職員の中ですら大変だとは聞いていますが、何がどう大変で、何をどうしたら大変ではなくなるのかというところまで共有しないといけないし、県民の皆さんも同じだと思うので、何で私の関連しているこの事業が減らされるんだという時の納得感がなければいけないということで、そうしたものも含めて、これから検討していきたいと思っています。
記者
細かいことなのですが、事務事業見直し推進本部員会議の構成員は、基本的に県の部長の方々でしょうか。
知事
はい。
記者
プロジェクトチームは、部局横断で、若手も含めてやられるということでしょうか。
知事
若手と言いますか、課長クラスだとか現場でやっているリーダー、全部局になるか総務を中心に、そういったクラスで編成するのが大体プロジェクトチームの1つの形になると思いますので、それをまた本部員会議に上げていくと、そんな流れになると思います。
記者
大野泰正元参議院議員の初公判が今日あって、従前言われたとおり、無罪を主張されたところなのですが、その受け止めというか、今後の審議でどういったことが明らかにされることを期待されますでしょうか。
知事
今回の裏金未記載問題は、かなり大きな話題になりました。大野さん以外は、皆さん略式だとか何かで、結局何がどうだったのかということが、詳らかにならないまま終わっているので、今回初めて裁判という形の中で、何が起きていて、逆に無罪とおっしゃるわけなので、じゃあ何が問題だったのかということが明らかになるということが、大事なプロセスではないかなと思っています。
記者
大野さんと、起訴後に江崎さんが個人的に話をされたことはありましたでしょうか。
知事
実はないです。
記者
連絡が向こうから来るとかもなかったでしょうか。
知事
ないです。確か、聞くと、携帯が全部没収されて誰も連絡取れなかったという話なので。
記者
昨日石破さんとお会いされたということで、退陣を表明されて、10月4日に総裁選ということで、防災庁の設置や地方創生が看板政策であったと思いますが、そういった点が引き継がれるかどうかという点も踏まえて、今後国に期待したいことをお願いします。
知事
おそらくご存じの方も多いと思いますが、初代の地方創生担当大臣ということで、ご自身が鳥取の出身ということもあって、地方に対する理解が大きい方の一人でないかと思っておりました。そういう意味では、我々としては、後にみえる方が、そういった理解をしていただきたいということは是非お願いしたいと思っておりますし、石破総理ご自身からすると、前も申し上げたように、国の仕事というのは外交と防衛がまず大事だという中で、トランプ大統領との関係で一定の成果を得られたと。これは一つの区切りなのかなと。それはご自身の判断であると思いますが、やはり私どもとしてみれば、まさに地方創生は待ったなしの状況でありますので、次の方がどなたになったとしても、こうした問題は重要ですし、総理が変わったから災害がなくなるわけでありませんので、まさにその防災庁設置も含めて、引き続き、しっかり発信をしていきたいなと思っております。昨日は総理だけでなく、官房長官やその他、地方創生担当大臣もいらっしゃいましたので、その中で言うべきことは言っていきますし、これからもそれは続けていきたいと思っています。
記者
財政構造に関するグラフについて、お伺いします。人件費や社会保障関係経費や公債費は、いずれも増えていくという折れ線グラフがありますが、こちらに関してはこのとおりで、減らすことは難しく、このとおりに推移してしまうと、そういったものなのでしょうか。
知事
私が十数年前に県に出向させていただいた時には、総合企画部の次長で、まさに同じグラフを見せられて、「これは決まってるんです。」と言われて、「本当ですか。」と質問したことがあります。結論から言うと、このとおりなわけはないです。ただし、通常大体こういうようになります。なぜかというと、高齢者の方の受診率だとか、医療費自体の単価が上がっているのでもっと上がるかもしれません。そういう意味では、このとおりというよりは、上振れするかもしれないし下振れするかもしれない。通常、上に増えることが多いです。ただ、今日の発表テーマでありませんが、まさにねんりんピックとモーニングプロジェクトがそうであるように、例えば社会保障費であれば、高齢化すれば当たり前のように増えるのか、ここはしっかりチャレンジしていきたいと思っておりますし、人件費は人事院勧告に基づくものなので、人が減らない限りあまり変わらないですが、ただ財政破綻すると、ここに手を付けたこともありますので、もちろん全く変わらないものではないですが、モチベーションの問題、その他が出てきますから、単純ではありません。公債費に関しては、借金は返さないといけないので、ここは一番動かないと思いますし、制度上可能な限り先送りしてしまったので、法律が変われば別ですが、そうでない限り、ここは固い形になると思いますので、フィックスではありませんが、これをベースに、多少上振れ下振れがあるかなというのが実態だと思っています。
記者
政策的に使える経費は年々少なくなっていくとのご説明がありましたが、その辺についてお伺いします。10年後を目標としているLRTなど、前回の記者会見の場で、目下の財政の厳しさと、LRTが実際に建設されるような時期とのずれというか、そういったものもあってというようなご説明もあったかと思います。そういった面を可視化するために、例えば市町村では総合計画がございますし、県であれば長期構想であるとかそれに準じた計画もあるかと思いますが、そういったものもLRT等を入れた形で、近々に見直されるようなお考えはあるのかお聞かせください。
知事
実は十数年前に、私が(当時の総合企画部)次長を担当していた時に、まさに長期構想をやっていましたのでよく分かりますが、ただ長期構想と言ってしまうと、非常にふわっとした議論になります。もう少し、財政なら財政に特化した形できっちりやることが必要かなというように思っています。それから、LRTというちょっと特出しのご質問ではありますが、まさにまちづくりの中で、どういう取組みが良いのかということと、今議論されているように当たり前のようにお金がかかるかというと、やり方というように申し上げましたし、これは路線の決め方、その乗客の可能性によって、事業として行う場合に、初期にどれぐらい要るかというのはあるかもしれませんが、丸々県でやるかどうかは全く分かりませんので、財政的に響いてくるかどうかも分かりません。国の予算を使ったり、もし民営で回るのであれば、PFI等いろいろなやり方があります。そうなると県費は出てきませんので、いろいろな調査費、その他はもちろん出てくると思いますが、まさに財政全体を左右するかどうかは分かりません。唯々諾々とこのまま縮んでいくつもりはありませんので、いろいろな取組みをすることによって、新しい事業をやっていく中で、やはり財政的にもプラスの方向に持っていき、新しいこともやっていかないといけないと思っておりますので、10年後という1つの目標ではありますが、その過程において、いろいろな財政のやり方を考えていきたいなと思っています。ですので、長期構想を作るかという質問については、今のところ長期構想という議論にはなっていませんが、その中の一部で、財政の見通しの辺りは、適宜見直していくと言いますか、そこを切り出して、修正をしていくということは十分あると思っています。
記者
2点伺います。まず1点目、石破総理の退陣の件ですが、今週日曜日に、党内を分裂するわけにはいかないということで退陣表明されて、その退陣自体についての知事の受け止めと、総理が在任期間1年ほどになるかと思いますが、その仕事ぶりについてどのように評価されているか教えてください。
知事
まずは、本当にこれほど大変な状況で総理をやられたということに関して、本当にお疲れ様でしたということだと思います。あの状況でトランプ大統領とあの立ち回りができたという意味においては、本当に素晴らしかったと思います。一方で、1年という時間はやはり、彼自身も昨日おっしゃっていましたが、やはり十分ではなかったかもしれない、道半ばというのはあろうかと思います。まさに昨日が地方創生という、石破総理自身が一番やりたかった仕事を、もちろん昨日は終わること前提の議論はしませんので、こういうことをやっていきたいということで話をさせていただきました。まずは、先ほど申し上げたように、関税、特に外交において一定の成果を出されたというのが、今おっしゃった、やはり党を分裂させないという自民党総裁としての判断があったのかなということで、政策とは多分関係ないと思いますが、そこについては、そういうご本人のご判断を尊重したいと思っております。
あと、今後我々が、次の方というか、総理になられる方としっかりやっていくということもありますが、そんな中で、昨日の総理のお言葉を少し引用させていただくと、やはり我々自治体、知事というのは、県民から直接選ばれて、4年という時間を使うことができると。その中で、この国を本当に良い方向に導く役割として非常に大きいものがありますという言葉もありました。それは偽らざる彼の思いだと思います。ですから、我々としてはしっかり受け止めて、この国を強くする。3か月前にお目にかかった時も、外交と防衛はお願いしますと、この国を強くするのはこちらでやります、ということをしっかりこれからもやっていかなければいけないと改めて思ったところです。
記者
総裁選があるということで、新総裁に期待することとして、今までであれば、新総裁イコール新総理というところだったかと思いますが、今回は少し違うので難しいところでありますが、それでも比較第一党の党首となる新総裁について、知事の立場として期待されることを教えてください。
知事
どなたが総理になられるにせよ、今この国の状況は楽な状況ではありません。国際的にもそうですし、人口減少だとか、東京一極集中という問題を、いかにこの日本という国を安定的に発展させていくか、この課題に取り組んでいただく必要があります。併せて、もう1回トランプ大統領との関係をゼロから構築していくことになると思いますので、それはもうしっかり、国として仕事をしていただきたいと同時に、やはり今申し上げた人口減少、それから東京一極集中、ここのある意味、均衡ある発展をしっかり政策に位置付けていただきたい。今おっしゃったように、かつてのような総裁イコール総理ではないかもしれませんが、これは多分、他の野党であっても政策目標が変わるものではないと思いますので、より良い政策を打ち出していっていただけることを期待しています。
記者
2点目の質問として、事業見直しの件ですが、例年事業見直しというのは何かしらの形でやっているのかなと思いますが、それと今年との決定的な違いを改めてご説明お願いしたいのと、今までのやり方のどういったところに不足していた点があるとお考えですか。
知事
それぞれの時代時代に、事業見直しのやり方というのはあったかと思うのですが、それを梶原県政の時代も、前に向かって、前向きなことの見直しをやった時代もあり、古田県政においてはもう1回総点検ということで、全部見直すと、本当絨毯爆撃的に全部やっていくと。これはこれで一つのやり方だったと思います。他方で、今私が担当させていただく中では、やはり財政の見通しをしっかり見せる。今まではどちらかというと、是々非々で見直します、みたいなことが多かったですが、明確に2年後の予算が組めないということ、このままだと令和14年に基金が枯渇して、また破綻をするということが見えている中で、しっかりと、その両方を回避していくという目標があります。加えて守りだけで良いかというと、今この国の状況、先ほど申し上げました、総理からいただいたこの国を強くするという仕事をしないといけませんので、その中で、要するに見直しをして、よくあるのは削る方向の見直しをするのが多いが、そうではなくて、前向きに、特に今回一番大きな違いはやはり国のお金をしっかり使っていくということ。そして提案していくということと、これは直接ではないかもしれませんが、民間の力もしっかり使っていくということで、いろんな政策提案も含めて、未来に向かって見直しをしていきたいというのが特徴だと思っています。
記者
住宅街などにクマが出没した際に、首長の判断で銃猟の使用ができるという制度をめぐって、岐阜県内の自治体の9割以上が、その制度の運用を始められていないというのが、私達の取材で分かりました。実際は、42自治体中3つしか始められていないという状況についての知事の受け止めと、市町村向けに何か指導や通知を出したり、講習会を開いたりといった対策は検討していますでしょうか。
知事
端的にお答えすると、まず、3つもできているとは聞いていないのですが、今準備中と聞いているので、間もなくほぼできるというのが3つぐらいと言うことかもしれません。何が言いたいかというと、今、大車輪で準備中かなと思っています。特に、質問外ですが、今回、ツキノワグマですが、これは結構びっくりで、もともとクマの種類の中でもヒグマはどちらかというと獰猛で、やはり危ないというのがありましたが、ツキノワグマは元々割と臆病な動物です。我が故郷の美山でも、昔は(クマが)いて、私の息子はランドセルにクマ除けのベルを付けていました。だから、山に入るときはラジオを付けっ放しにするとか、我々の方で割と当たり前にやっていました。逆に言うと、それで避けられた。ところが、今回住宅街まで(クマが)来るし、人を襲うなんてことは余程のことがない限り今まで起きなかったことが起きてしまった。これはある意味、一つ大きく踏み出さないといけないということで、今回、制度も変わったと思います。ただ、今おっしゃったように、制度が変わったからすぐできるかというと、皆大慌てで、今準備されていると思っていますし、猟友会との連携の中で、被害が出たらすぐに飛んでいってくれというのは、居てもすぐにできるものではなかったり、では誰がどういうルートで、どのような連絡をするのかと、その時に費用はどうするのかというようなことを、今各自治体が一生懸命準備されていると思っています。県としては、もちろんこういった動きを全面バックアップしたいと思っていますので、いろんな指導だとか研修だとか、そうしたことについてはしっかりやっていく。岐阜県は木の国、山の国ですから、ある意味クマに市境、町境はありませんので、どこでも出てしまう可能性がありますので、そうした意味ではしっかり県としてはサポートしていきたいと思っています。
記者
具体的に講習会の日程とか、いつぐらいを目途にやりたいとかはありますか。
知事
今まさに詰めているところですので、またそれが決まったら発表したいと思います。
記者
「事業見直しの方針(資料1)」のところに書いてある、「多額の県費を要している事業」や「これまで当たり前に実施してきたイベント経費」とか、何となく日頃の業務のことは、職員から上がってくると思うのですが、知事としてある程度全体をご覧になっていると思うのですが、この辺りは非常に多いとお思いなのか、その辺りの所感を教えてください。
知事
これは2つあって、職員から上がってくることは、結構本当にそうなんだろうなと思います。一方で、これまでの4年間も含め、今でもそうですが、県庁の外からもいろんな声が聞こえてきますので、そうしたものもできるだけ大きな耳で聞いていきたいなと思っています。それはもちろん事実に基づかないとか、多分、正確にご存じないからおっしゃっている意見もあったりするので、そういうのはちゃんと精査したいと思いますが、とにかくできるだけ多くの声が耳に届くようにしておくということが基本だと思っています。先ほど申し上げたように、既に私の耳にいくつか届いているものもありますので、ただ、それがたまたま私が聞いたからというのは政策のやり方として良くないと思っていますので、しっかりこうした制度として位置付けたいというのが、今回の主旨です。
記者
働いてもらい方改革について、就任して半年が経ったのですが、助成金を出したり、こうしたいろんな取組みをされていると思うのですが、今後の課題というか、こうした取組みを全県的に広めていくための課題はどの辺りになるのでしょうか。
知事
課題と言うよりは手応えと言った方が良いかもしれませんが、私もこの4年間の中でいくつかの例を挙げてきたのは、いくつかの例でしかなかったのですが、今回で20社、ご覧いただくと見事なぐらい共通点があります。業種を問わず、やることは実は同じだなということを私も感じているのですが、そうすると横展開がしやすくなる。
他方で、やはり企業文化を変えることは簡単なことではありません。ただ、ありがたいことに、私は国で健康経営を主導してきましたので、当初、健康経営と言っても皆さんからほぼ総スカンでした。健康と経営は語義矛盾なので、何をやっているんだとさんざん非難を受ける中で、いろんな取組みをやっていく中で、「健康経営銘柄」から始まり、「ホワイト500」、今は「ブライト500」になり、今や知らない人はいない。当時は企業文化を変えようということを合言葉でやってきたのですが、10年ちょっとでやはり変わるんですよね。そうすると、今回、「働き方改革」ではなくて「働いてもらい方改革」ということで、総理の前でも大分連呼してきましたので、今日も、国から来た方に言葉をしっかり選んでくださいと(伝えました)。今働いている人の残業を減らしたりするのが「働き方改革」。「働いてもらい方改革」は今、働けていない方も働けるようにする、という違いがあるんですよと。これを繰り返す中で、今までの当たり前、若くて体力があって、文句を言わずに徹夜残業をしてくれる人しか働けないと思っている経営者の意識を変える、これは大事だと思っていますので、大きな障害というよりは、これから丁寧に、しっかりと普及していくというのが大きなテーマかなと思っています。
記者
いろんな企業があって、そうした固定概念を変えるということは結構難しいと思うのですが、そこをより浸透させていくために、こうしたことをした方が良いということはありますか。
知事
皆さんに期待したいところがありまして、私は昔、ベンチャーというのを政策にして、まだベンチャーということが有名ではなかった頃に、まさにマスコミの皆さんに、そういう、新進気鋭の企業というのを毎週取り上げてもらうことによって、要するに単なるエピソードではなくて、そういう企業は社会的に評価されるんだということが世の中に浸透してきて、今やベンチャーと言えば何かすごく良い感じがあるじゃないですか。当時は、ベンチャー企業の取材をさせてくださいと言ったら怒られまして、「うちはそんなにいかがわしいものじゃない。」と、そういう時代でした。ですから、やはり皆さんのお力はすごく重要で、社会にとってそうした働き方、働いてもらい方に価値があるということを、多くの人に知っていただくこと、これが一番の力かなと。あとは、健康経営の時がそうであったように、銘柄、その他いろんな形で、これからどんどん仕掛けをしていきたいと思っていますが、まずは知っていただくということ、これが重要かなと思っています。
記者
事業見直しの方針のところでお伺いします。最大の特徴として、国費の最大限の活用というところで、今までも、知事はずっと国費の活用をおっしゃられていたと思いますが、その一方で、国のお金に頼り過ぎることが続いてしまうと、依存体質が続いてしまって、国にコントロールされて、本来自分達がやりたい事業ができなくなってしまう側面もあると思いますが、その辺りを知事はどうお考えでしょうか。
知事
そのために、(「事業見直しの方針(資料1)」の(1)③に)あると言うか、私も霞が関で30年以上仕事をしてきた中で、霞が関は何をしたいか、実は今日も、霞が関から1人課長さんに来てもらったいましたが、彼らがやるべき政策のヒントは実は現場にしかないんですよね。私もそうでしたが、徹夜でふらふらの頭で明日までに政策を考えてこいというのが霞が関の一般的な状況なので、むしろできてしまった政策に合わせるのではなくて、彼らの政策を現場に合わせていきたいというのが一番大きなポイントです。それと、もう少しご質問にストレートにお答えすると、国にコントロールされるという意味では、いわゆる昔の「3割自治、4割自治」ということがあったと思います。実は今、県のほとんどが国からもらったお金なんですよね、元々が。法人税とか、県の中で収入として得られる金額は今どれくらいでしたっけ。
総務部
予算額9,244億円のうち、4,206億円が県税などの税収です。割合は45.5%です。
知事
逆に言うと、50数%は国の言いなりじゃないが、もらうお金なので、ある意味ではお金に色は付いてない。ただ、おっしゃるように、国の政策に合わせる形でやるとその枠内でしか仕事ができないですが、私がかつて財政破綻の時の商工労働部長の時は、厚生労働省まで行って制度を直してもらいました。これ使いにくいので直してくれと。ということで結構たくさんのお金をいただいたり、やり方はいろいろあるかなと。やはり国にいた事のアドバンテージはそこだろうと思いますので、国のお金だから国の言いなりになるつもりは全くありませんので、そこはしっかりうまく使っていきたいと思います。
記者
事業見直しの関連であえて聞きたいのですが、職員提案の部分で、今年度から始まった政策オリンピックやモーニングプロジェクトであるとか、独自制度で少なくない県費が使われていると思うのですが、見直しの対象に提案として挙げて良いものなのでしょうか。
知事
むしろ、政策オリンピックのオリンピックをやっているように、そういう中で、本当だったらやりたかった政策もあるだろうし、これまでの政策オリンピックは先にテーマを決めての募集だったが、やはり今やるべきことは提案でありますので、これもまさに見直しの一環かなと思っています。
記者
先ほど大野元参議院議員の話がありましたが、司法の方は、司法の話ですので、事実解明してほしいということだと思いますが、大野さんは今は引退した形になっていますが、代々、地域のための働きぶりをどう評価しているか、特に山県市民としてどのように捉えているのかお尋ねします。
知事
山県市民というより、同じ岐阜県人としてといった方が良いかもしれませんが、大野伴睦先生は美山の方でしたが、ご本人はあまり美山にいらっしゃったことがないので、地元でということはないのですが、県のためにいろんな道路だとかいろいろと活躍された話は伺っていますし、この間も橋ですか、ああいったことにご尽力いただいたということにおいては大事な方だと思っています。特に羽島の方々にとってみれば、本当にいろいろ期待されるものがあったと思います。であるからこそ、今回の問題をしっかり決着をつけていただいて、評価する人をしっかり評価する、見直すべきところは見直すと、そんな流れに繋がると、我々地元の人間としても安心できるかなと思っています。
記者
事業見直しの活用可能基金のところですが、このままいくと令和8年度にもだいぶ底をついてしまうということですが、知事として何かあった時の備えとして、これぐらいの額は残しておきたいという考えがあれば知りたいです。
知事
年によって結構ぶれて、特にこの件で言うとまさに雪ですね、除雪のときの緊急対応は大事です。ただ数年前のコロナみたいなものがあると、もうえらいこっちゃと。もちろん国から(手当が)来るが、その間のギャップを埋める方法がなかったりするので、国が手当してくれたら国から来るが、それまでの緊急対応だとか。あと豚熱、これが出るか出ないかによって結構大きくぶれるので、それで今、財政課の方も唸りながら、結局どれぐらいあったら良いのか、要するに今後、見直しをしていく中の1つのメルクマールになりますから、大車輪でやっているところです。英知を結集して、今やってもらっています。