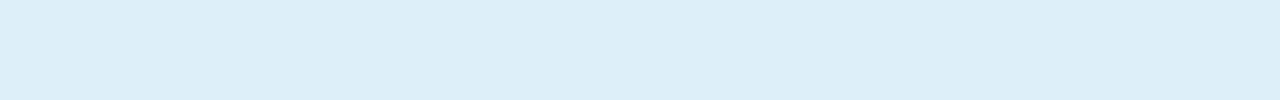本文
知事記者会見録(令和7年8月26日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年8月26日(火曜日)14時00分
司会
それでは、知事定例記者会見を始めさせていただきます。
まず、項目の1つ目として公益社団法人日本青年会議所東海地区協議会との災害時における相互協力に関する協定の締結式を行わせていただきます。
本日は、協議会の戸嶋一将会長ご出席のもと、協定締結の署名を行い、戸嶋会長からのご発言、知事からのご発言、そして質疑応答、最後に写真撮影の順で進めさせていただきます。
それでは、まずお手元の協定書にご署名をお願いいたします。
(協定書署名)
それでは、ここで戸嶋会長からご発言をお願いいたします。
戸嶋会長
まずは、本日お時間をいただきましてありがとうございます。
公益社団法人日本青年会議所東海地区協議会で、本年度会長をしております、戸嶋と申します。出身の愛知県の半田市から本日お伺いをしております。本日防災協定ということで、私ども日本青年会議所では、災害が起きた際、防災の初動マニュアルというものが既に存在をしております。県単位の場合、地区単位の場合、そして日本全体の場合で、それぞれの規模の災害によって動くべきところ、トップとなるところが変わりはするのですが、今回は東海地区協議会ということで、岐阜をハブとしました、三重、愛知、静岡の南海トラフ(地震)に対応するべく、物資のルート、そして拠点、人的リソースの流れ、あとは情報の収集、収集から分配、実際にどのように動かしていくのかを、細かく決めさせていただきました。昨年発生しました、能登半島(地震)では、日本青年会議所としてもできる限りのバックアップをさせていただいたのですが、基本的にはその時もし決まっていればというところを大幅に改善させていただきました。日本青年会議所としても、東海のような地区が10地区ございますが、これは東海地区が今年初めて行わせていただくこととなりますので、この先、願わくば全国的に同じようなスキームを、どんどん用意していきたいなと東海地区としては考えておりますので、これから先も、東海地区内での災害が起こった場合は、全力で取り組ませていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
司会
ありがとうございました。続いて知事からご発言をお願いいたします。
知事
まずは、戸嶋会長本当にありがとうございます。
ただいま締結をさせていただきましたのは、今お話がありましたように、東海地区ということで、実は岐阜県が初、最初になります。実際に能登半島地震もそうです。私も県の(商工労働)部長時代に東日本大震災を経験しましたが、やはり現地で動ける方というのはいかに重要かを非常に感じております。特に今回の協定の中では物資の調達、配送、場合によっては現地でのキャッチ、これは実際には私も商工労働部長の時に、5,000人分の衣類を確保して送る体制まで取ったのですが、受け取る側の体制がなく結局配れなかったという問題があります。特に、こうした混乱の時期において、自由に動ける、そして実際に(会員の方は)お仕事を持っておられるので、そのネットワークを活かしていただくというのは本当にありがたい状況でございます。特に岐阜県の場合は、青年会議所さんは歴史が長いというか、昭和28年の災害時に青年会議所さんが中心になって、関市を中心とする災害の復旧に力を入れられたと。それが元となって青協建設さんができたという、やはりまちづくりにおける青年会議所の役割が重要かというのは岐阜県が一番知っていると思っております。そして今、ありましたように、来たるべき南海トラフ地震の時に、岐阜県は被災県であると同時に愛知県、三重県、場合によっては静岡県の被災者の受け入れをする県になるという意味においては、こうして早い段階で協定を結ばせていただきまして、このネットワーク、特に情報の共有というのは非常に難しいところなのですが、こういう協定があれば本当に遅滞なく情報を共有する、それによって、現地でどう動くべきなのか、誰が動けるのか、そしてどんな物資が調達可能なのかということも、二重三重の構えで災害対策に当たれるのは本当に県としてもありがたい限りでございますので、これを皮切りに、これが全国に広がり、またいろんな災害がこれから想定される中で、こうした形で、県民の皆さん、国民の皆様の安心に繋がれば本当にありがたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
記者
確認となりますが、東海地区協議会というのはこの4県、静岡、愛知、三重、岐阜県が対象のエリアとなるのでしょうか。
戸嶋会長
はい。
記者
協定内容で、物資の調達とか仕分けでの協力とあるのですが、青年会議所さんがそこに貢献できるというのは、具体的に例えば参加者の企業でこういうところがあってできるとか、少し具体的なところをお話しいただければと思います。
戸嶋会長
青年会議所で最も強いのが、人材、人的なリソースの確保と、それに伴う物資の調達、あと資金の調達がとても早く、どこよりも早く動けるような仕組みで、既に作ってございます。ですので、例えばこの物資が必要であるという場合は、社協(社会福祉協議会)さんと連携をして、もちろん県とも調整をした上で、日本JC(青年会議所)の本部に情報を上げることで、今必要なのはこういうものと人ですということで、早急に準備をさせていただくという側面がございますので、県の仕組みと青年会議所の仕組みがお互いに邪魔をしないような、お互いがそれぞれ必要な分を必要なだけ行えるような仕組みとなっています。
記者
相互協力に関する協定ということで、青年会議所さんから協力していただくことの記載はあるのですが、県側としてはどのように協力していくことになるのでしょうか。
知事
大規模災害時における協力なので、場合によっては、そのメンバーの中にも被災者の方がいらっしゃいます。なので、個々のプレイヤーが思い思いにということがこういう災害時は一番危険なことになります。なので、まずは県からすると、県が持っている情報をいち早く青年会議所さんに提供させていただくことで、青年会議所さんの活動そのものが非常に有効になっていくということ。それから今、会長からありましたように、やはり連携するということは結構大事で、お互いに手が届かないところ、場合によっては県の場合だと、警察その他との連携も、国との連携も迅速にできますので、それで青年会議所さんが行われる活動をより価値のあるものにする、非常に有効なものにすることにおいての協力ができるかなと思っています。
記者
青年会議所さんが人的とか物的とかいうものを提供するというよりは、お互いにそういうところと連携して効率的にやっていくための協定というイメージでよろしいですか。
知事
そうですね。ただ実際、県そのものにものがあるわけではありませんので、実際、東日本大震災の時も、繊維組合とかにお願いをして、今出せる量を確認して、それと同時に現地の方にどれくらい必要なのかということを確認しながら、正確に言うと、少なくとも何人分集められるんだというところから始まります。実際には5,000人分(の衣類)、老若男女問わず集めたのですが、そこから先が繋がらなかったというのが実際の経験でありますので、青年会議所さんの場合は全国ネットワークですから、その被災地にもメンバーがいらっしゃいますから、そこからの情報も、我々にとってみると非常に貴重なものになりますので、そうした意味では、本当に実際にビジネスを行っておられることによるネットワークと、ものを持っておられるということ。それに対して我々は、行政の立場から、警察との連携も含めて、場合によっては自衛隊との連携も含めて、それが一体となるということがまさにみそになるかなと。
記者
元々連携はしているということで、ある種円滑に、そして強化していくみたいなイメージがあるということでしょうか。
知事
これは実は、想像に難くないと思いますが、災害時であってもいろんな情報というのは、流せば良いというものではありませんので、どのルートにしっかり流すかということ。場合によっては、プライバシーに関するような問題もあったりしますので、その中でやはりそういった信頼関係というか、何をしてくれるところなのか、ただ単に協力しますからというだけで情報を流すようにいかなかったりしますので、お互いに役割を決めておくことによって、その辺りが元々連携というか、協力したいというのは後からもたくさん来られるのですが、事前にこうした連携をしていくことによって、そこの確認を躊躇する時間を一切カットできますので非常に有効だと思います。
記者
資料の中で、他県の静岡、愛知、三重県とそれぞれ災害時応援協定の締結を調整中ということで、今回相互協力に関する協定と書いてあるのですが、内容について、他の3県は少し(岐阜県とは)別になるのか、それとも特にその言葉にそこまで深い意味はないのかお聞かせください。
戸嶋会長
いずれにしても、東海地区協議会としては、東海四県を対象として活動を行っておりますので、例えば海沿いで被災する想定の静岡、愛知、三重県に対して個別でサポートしていくよりも、その横の繋がりで情報を網羅的に把握することによって、より効率的に支援をしていくという意味合いも込めて、今調整中ではあるのですが、計画をしているところです。
記者
応援協定というのと、今回の岐阜県の相互協力に関する協定は、言葉遣いが違っているということで、内容が変わるということなのか、それとも大まかに同じようなものを結ぶと考えれば良いのか教えてください。
戸嶋会長
各県とはこの先もどんどん協定を結んでいく予定でいまして、包括的に取りまとめる仕組みがいるのではないかというところで、ニュアンス的には少し別の感じです。
記者
災害時に関する何らかの協定ですけど、今回の岐阜県のとは内容がちょっと変わるかもしれないという理解でよろしいですか。
戸嶋会長
はい。
記者
岐阜県の会員数を教えていただけますか。
戸嶋会長
500程度です。
記者
愛知県とか静岡県、三重県ともそれぞれ協定締結を調整していかれるとのことでしたが、これも時期としてはいつ頃までに結びたいとか、そういったようなご予定はありますでしょうか。
戸嶋会長
各県様とは既に日程調整を行っておりますので、可及的速やかに調整が完了しましたら、随時協定を結んでいく予定です。
記者
今年度中ということでしょうか。
戸嶋会長
もちろんです。今年度中です。
記者
何月頃までにというのはありますでしょうか。
戸嶋会長
9月、10月ぐらいまでには何とかしたいと思っています。
記者
東海地区協議会と同じように、複数の県をまとめている地区協議会というのが10ぐらいあるとおっしゃいました。このように、都道府県との協定を結んでいる他の地区というのはあるのでしょうか。これが第1号というか、全国的に見ても珍しいケースになるのでしょうか。
戸嶋会長
各地区協議会が、全国で東海含め10地区あるのですが、こういった地区協議会と、例えば絞られた県との協定というのは存在はしているのですが、エリアの内の全ての県と事前にこうしましょう、どうしましょうというルール付けをしているのは今回が初めてとなります。
記者
戸嶋会長に伺いたいのですが、物資だとか、資金の調達の仕組みがあるというようにおっしゃっていましたが、仕組みというのはどういうものになるでしょうか。
戸嶋会長
日本青年会議所自体に、冒頭に初動マニュアルというものが存在するというようにお話をさせていただいたのですが、まず少し細かいお話をさせていただくと、災害が発生した場合、例えば県単位なのか、県を跨いでいるのかによって異なるのですが、災害支援本部というのが設置されます。そこから実際に被災地からのニーズですとか要望を収集して、必要な支援内容を災害支援本部が計画立案します。その際に、例えば、お金がどれぐらい要るですとか、ものがどれぐらい要るというのを日本青年会議所自体が取りまとめをしますので、その時点で全国のメンバーに、今この物資がこれぐらい必要で、お金についてもこれぐらい必要ですという、その仕組み自体が既に存在をしておりますので、我々としては協議会から日本青年会議所本体にこういう内容でこういうようなニーズがございますというのと、あとは各地の、例えば岐阜青年会議所さんとか、私だったら半田青年会議所というところが、何かあった場合に、例えば募金活動ですとか、そういったものも随時大至急始まっていきますので、そういったところからの資金調達がございます。
記者
情報収集、ニーズの集約の話なのですが、これは被災された会員の方々から上がってくるような、そのようなイメージなのでしょうか。
戸嶋会長
こちらについては、実際には青年会議所の縦のルートで上がってくる情報と、あと市町村の社会福祉協議会さんから上がってくる情報が複数あると思います。それで、一番重要なのは、この情報がお互いに知らないことですとか、知らないこと、ないしは全く同じ情報が錯綜しながら上がっていくところが一番問題になりがちだというように、能登(半島地震)の時も全く同じ状況がありましたので、基本的には各市町村の社協さんと連携をしながら、加えて私どもは愛知ブロック、ブロック協議会もありますので、ブロック協議会と県社協で、そういった具合でどんどんレイヤーが上がっていって、相談内容、ニーズが取りまとめられてという仕組みでございます。
記者
知事に1点伺いますが、こういった協定を結ばれると、例えば災害対策本部だとかができた時に、避難所対応といったメンバーには、JCさんも入ってくるという、そういった想定なのでしょうか。
知事
実際、会長からおっしゃっていただいたように、実際被災をした時に情報というのは体系的に上がってきません。バラバラバラバラと上がってくるのと、今おっしゃったように、同じ情報が別ルートで上がってくる時に、それが全体像なのか、また別なのかは実は分からないです。東日本大震災の時もそうだったのですが、そういう時に、それぞれが思い思いに動くことによって、やはり現場が混乱するというのはこれまでの大災害の経験としてありましたので、まずは、「うちにはこういうものがあります。」、「それは多分一緒ですね。」ということが迅速にできることが、せっかく集めた物資が二重に行ってしまったりとか、本当に必要な人のところに届かないことが常に起きることですので、まさにこれからの災害の時に可能な限り来ていただいて、訓練の時もこのように情報が入ってくると。今、5階にある県内から集まってくる情報のシステム、これは県外とも繋いでいることになりますから、その時にどこにどういう情報が来るのかということを知っていただくというのは極めて重要なことになると思いますので、できる限りそうした情報が全体として集約できること、これが災害対応の要点になりますので、その重要なメンバーになっていただけると思います。
記者
実際に何かあった時は、委員というか、メンバーとして入るという認識で良いでしょうか。
知事
災害にもよりますので、まさに南海トラフ地震の場合については、より広いことになると思いますし、また違うところでの災害だと、豪雨で局地の場合についてはまた変わってきます。それはその状況に応じてということであります。
司会
ありがとうございました。
それでは、写真撮影に移ります。写真撮影には、日本青年会議所東海地区協議会副会長の高橋英夫様(※)、同協議会防災レジリエンス構築委員会委員長の森裕紀様のお二人にもご参加いただきます。
それでは、恐れ入りますが、中央の方へお進みください。
(写真撮影)
知事
2つ目の項目でありますが、お手元に「大関ケ原祭2025~東西対決、舞台は岐阜関ケ原~」の開催についてという資料があるかと思いますので、これについてお話をさせていただきます。
ご案内かと思いますが、10年前に「世界古戦場サミット」というのを行いました。その際に、ベルギーのワーテルロー、そしてアメリカのゲティスバーグに並ぶ世界三大古戦場ということで、関ケ原を上げてサミットを行いました。これを中心にいろんなイベントをやり、この地域の活性化に繋げていきたいと思っております。資料の方、パンフレットもありますが、まず文章の方からご覧いただくと、「世界三大古戦場サミット」ということで、アメリカと、そしてベルギーからお客さんをお招きして、いろんなイベント、まずは(関ケ原、ワーテルロー、ゲティスバーグの)お三方で、特に古戦場の使命や課題についてのいろんな意見交換やトーク、竹下景子さんに進行をお願いして、(岐阜関ケ原古戦場)記念館のアンバサダーでもあります竹下さんにお願いをしてやるという大きなイベントが一つです。それから次のページにありますが、「関ケ原スペシャルトーク」ということで、来年の大河ドラマが「豊臣兄弟!」ということで、これに所縁の、お出になられる松本怜生さんと井上和さんに来ていただいて、戦国武将にまつわるトークをしていただくということで、これは無料でございますが、登録は必要になります。そして、東西対決ということで「花いけバトル」です。これはいろんなイベントでお願いをしておりますが、ここで華道家が東西に分かれて即興による生け花を披露していただきますし、そしてその次、(岐阜関ケ原古戦場)記念館が(開館)5周年になりますので、これを記念してのパネルディスカッションというのも行います。これは特に歴史をしっかり踏まえた形で、小和田哲男さんをはじめ、こうした歴史のプロの方々に、特に関ケ原の合戦を題材に、武将たちの決断とその結末と、ある意味、幸運と不運ということも含めて、誤算と幸運ということなのですが、本当に歴史のいろんな巡り合わせその他についてしっかりとお話をいただくという、歴史家にはたまらないイベントだと思っております。そして、これもいつも行っていますが、東西の人間将棋、特に日本人だと当たり前なのですが、取った駒を自分の駒として使うというのは、世界的にはあまりないです。チェスなどでも取った駒は捨てるだけなのですが、そうしたものも含めて、海外からも非常に関心のある将棋というのを、人間将棋ですね、これも秀吉がよくやったということでありますが、こうしたものを再現すると(いうものです)。そして、戦と言えばお茶です。一期一会という戦国武将ゆかりの茶の湯を体験していただくと、そうしたイベント。そして、何と言っても武士と言えば日本刀ですから、その次のページにあります(日本刀の)鍛錬、これもご覧いただくというものもございます。あとは、いろんなライブということで、尺八の演奏。それから関ケ原絵巻と言えば、武者行列その他いろいろあります。お手元の方にパンフレットがありますので、本当に盛りだくさんのイベントで、世界三大古戦場という、天下分け目と言えば関ケ原ということでありますので、これでしっかり大いに盛り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に3つ目のテーマでありますが、「ねんりんピック」、バッジも付けてきましたが、いよいよ本番に向けての機運を盛り上げるということで、キックオフイベントを行います。これは9月14日日曜日、午前9時15分から始まりますが、この県庁、ぎふ結のもりということで、イベントを行うわけですが、以前ここでもご紹介しましたが、5地域からそれぞれ火を、「健康長寿の火」ということで採火式、私も参加させていただきますが、これが集まってくるということで、それを合火すると言うのですが、集めるのと同時に、まさに選手の結団式、これを行いたいと思っております。お手元の資料で言うと、真ん中下ぐらいから採火のイベント、そしてキックオフセレモニーということで、開催地域の首長さんたちも来ていただきますし、結団式、次のページにありますが、まず合火をするということ、そしてちょっと面白いイベントになりますが、この日に合わせましてもう一つ、ねんりんピックの「美味しい・楽しい・ワクワク」という中で、モーニングを使って健康になろうということで、コンテストの最終審査を行います。以前もご紹介しましたが、様々なモーニングがあるのですが、ワンコインでいける部門と、プレミアム、1,000円以下という2つの部門に分けて、一次審査が終わっていますので、それぞれ3つずつ選んだ中で、県民から100人くらい審査に来ていただくのと、(応援大使の)勅使川原郁恵さんと流れ星☆にも入っていただいて、試食の審査をします。もうびっくりしますが、少しつまみ食い的に紹介すると、「これ本当にワンコインなの。」と思うようなものもあるのですが、裏から2枚目の紙にありますが、ワンコインモーニング部門の3つ、どう見てもランチじゃないかというのはあるのですが、これの中からグランプリを選んでいただく。そしてその下のプレミアムモーニング部門、これは税抜き 1,000円以下というので、選んでいただくということで、これは実際に食べていただきます。食べて投票していただくという形を取りたいと思っています。間に合えば私も参加したいなと思っていますが、「審査員で応募した人しか食べられないのか。」というリクエストもあろうかと思いまして、この審査は別なのですが、同じ会場の20階に、やはりモーニングというのを体験したいという声があろうかと思いますので、資料の2枚目のところにありますが、これは喫茶組合に協力していただいて、今回図書館でモーニングをやっていただいたところのご協力をいただいて、「Café de Volta」さんと、「サンドイッチとカフェ PANDA」さんにそれぞれ、ワンコイン+αぐらいですが結構頑張っていただいたと思いますが、サンドイッチと焼きそばのセット、ないしはサンドイッチとサラダのセットというのをご提供いただきますので、せっかくですから、審査会を見に来た人も、これでモーニングを楽しんでいただけるような、そんな設えもしております。これも本当に面白いと思いますので、ここで選ばれたものをまたいろんな形で発表していきたいと思っております。それから、モーニングセットを販売するほか、スタンプラリーのキャンペーンもやったりとか、eスポーツ体験だとか、そんなことをしております。おかげ様で、企業さんからの協賛もいただけて、大塚製薬さん、やはり熱い中で水分補給ということでポカリスエットの提供をいただいたりとか、やはりスポーツのためのいろんなウェアその他のヒマラヤさんからの割引の協力、そして食べただけではいけないので、歯ブラシ・歯磨き粉ということで、口腔ケアということで、ライオンさんからもご協力をいただきながら、こうした取組みを盛り上げていきたいと思っております。これが3つ目でございます。
そして、最後4番目になりますが、ちょっと毛並みが変わりますが、訪問介護などのサービス提供体制の補助金を新設ということで、一言で言うと、「働いてもらい方改革」の介護バージョンだと思ってください。特にポイントは、最初の方に書いてある文章の最後の行ですが、超短時間勤務、マイクロワークをこの分野においても実現していこうということで、それに対する支援をしたいと思っております。特に介護、どこの地域でもそうですが、人材不足で大変ということなのですが、この分野にも、「ちょっとだけなら手伝えるよ。」とか、「昔やったことがあるから、若い人のアドバイスくらいならできるよ。」という人たちも参加していただけることによって、介護のニーズを満たしていくような仕組みに取り組んでいくと。そのために、事業所に支援をしたり、人件費を応援したりという形で、介護の体制を充実すると、そんな取組みの応援をしたいと思っておりますので、その募集を8月26日から9月30日、約1か月強でありますが、やはり各事業所さんで、人材確保で大分お困りなところがあるということを大変聞いておりますので、まずはできるところからということで、始めたいと思っております。補助率は10/10ですので、まずはいろんな可能性にトライしていただけるような、そんな環境に持っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。
記者
キックオフイベントでですが、モーニングセットの販売の料金の600円は、これは税抜きなのか、税込みなのか。また、この提供というのは、(9月)14日の午前9時15分からのイベントと同時に始まるのか、提供時間なども教えていただけたらと思います。
観光文化スポーツ部
料金は税込みです。それから、提供時間につきましては、セレモニー等を行った後になりますので、今、午前10時半からの予定をしております。
知事
モーニングと言うより、ランチに近いかもしれませんが。
記者
キックオフイベント一連が各地であって、この後はねんりんピックの開会式までに何かイベントがあるものなのか、次は公式には10月18日になるのか、その辺の見通しをお願いします。
知事
内部的にはリハーサルとか結構大々的にやるのですが、イベントとしてはこれで結団式をやりますので、あとは本番と、一般的にはなろうかと思います。
記者
5月から提案を募っておりました旧岐阜県庁舎の関係です。8月に提案内容を確認されて、9月に結果公表ということだと思うのですが、今のところ進捗状況はいかがでしょうか。
知事
現在、提出された提案書に基づき、担当課が、提案者に対してヒアリングを行っているところです。
記者
知事の目線から見て、良いなと思う提案はあったのでしょうか。
知事
実は私は見ていないです。すみません、4つと聞いているので。
記者
知事が就任されてから半年が過ぎまして、9月ということで、いよいよ来年度予算の編成作業も本格化してくるかと思うのですが、本当の意味での江崎カラーの出る予算にはなると思うのですが、意気込みみたいなところもいただけたらと思います。
知事
江崎カラーを出したいところなのですが、前回議会で申し上げたように、非常に財政的には厳しいので、江崎カラーというよりは、まさにこれから腕の見せどころかなと。私というよりは、県の職員の方が、いろいろ知恵を絞っていただいていて、まさにそのインフラに関するものについては、あらゆる手を尽くして国で使えるものを使っていくということ。それともう一つは、今回せっかくご質問をいただいたので、先取りして申し上げると、財政破綻をしないような運営をどうしたらできるかというところを今一生懸命みんなで議論しています。前に申し上げたように、昨年と同じようにやれば、あと3年ぐらいで基金が枯渇してしまうので、そうすると緊急事態についても対応できなければ、国の予算も使えないということになってしまうので、それを回避しつつ、そうは言ってもインフラその他の事業規模を維持するという、かなりの綱渡りというか、それをやっていくことになると思いますので、その仕組みをですね、ある意味、しっかり出していけると良いかなと思ってます。
記者
少し関連するのですが、先ほどインフラというところもあったと思うんですが、財政が厳しい中で、今までやってきたイベントだったりとか、補助金であったりとか、そこの打ち切りであるとか、規模の縮小みたいなところの可能性はあったりするのでしょうか。
知事
これは次回以降にまた公表することになると思いますが、これから業務見直しというか来年度予算編成に向けての、これは通常やっているところですが、これをかなりしっかりやっていこうと。特に(見直しの)視点を提供していますので、一旦決めた予算を打ち切るということは基本的にはしないのですが、実際にやろうとしている中身、今回の関ケ原もそうですが、その目的に対してここの部分はもうちょっと組み直した方が良いんじゃないかとか、その辺りは予算の範囲内でかなりできるものがありますし、その中で、例えばそこでこれはなくても良いんじゃないかと浮いてきたりしますので、それが翌年度の予算の発射台になってきますので、その辺りもしっかりやっていきたいと思ってます。
記者
県の農業政策に関してお尋ねします。県内の農業振興を図るべき農地のうち、10年後に耕作する後継者が決まっていない農地の割合が、43.5%に上るというような集計をしているという話を伺いました。今後の県の農業政策で、知事が特に力を入れていきたいとお考えになっていることを教えてください。
知事
すごくタイムリーなニュースになって良いなと思っているのですが、今多分、日本中共通の課題だと思うのですが、今はそういう調査をやると何が起こるかというと、自分の息子ないし娘、家族が後を継いでくれるかどうかという調査にほぼイコールになります。そうすると、半分ぐらいは「継がない」と言っているということだと思います。他方で、昨日、白川町に行ってまいりましたが、かつて消滅可能性ナンバーワンだったところに、今続々と移住者が来て、今(放置すると危険な)空き家(特定空家)もゼロだそうです。そして、そういう方々は、実は、ほとんど農業をやりに来ておられます。そうすると、おそらくこれからは、家族が継ぐかどうかという議論ではなく、外部から来た人、戻ってきた人たちが、どれくらい農業を継いでくれるかという議論に変わっていくのだろうと思っています。ただし、それが今までと同じことを同じようにやるのではなく、有機だとか、より付加価値が高いもの、そして、専業の農家ではない可能性も結構たくさんあるという中で、農地を維持し、農業として成立させるというような形に変わっていくだろうと。大変ありがたいことに、そのすごく良い例をたくさん昨日勉強させていただきました。そんな中で、以前から申し上げているように、農家を継ぎたい人は少ないかもしれませんが、農業をやりたい人はたくさんいると。それを円滑に、まさに農業分野に入っていただくため、アグリパークをまずは体験してみる。その中で、本格的にやりたい人のレベル分けをしながら導入、そして、いろんな機材の調達、この辺りも非常にしやすくすることによって、今まさにお示ししていただいた数字が大きく変わる未来は実現可能だと思っておりますので、今回いろんな意味で農業の見直しを行えるという中で、そのモデルをこの岐阜県からしっかり示していきたいと思っています。
記者
より農家に近いところで市町村が仕事をしているかと思うのですが、市町村と県の役割分担というか、そこはこの件に関してはどのように考えておられますか。
知事
特に、基礎自治体としての市町村の場合は、実際の土地を誰が所有していて、どのように移住者の方が生活しておられるのか。農業だけを見たのではいけなくて、やはり移住された方の教育の問題とか、生活の問題、住居の問題、その辺りが基礎自治体としては大事なことになっていきます。特に、町内会として成立するのかどうかという、広い意味で、そこは重要な役割になります。それに対して、県の場合は、農業政策として考えた時に、もっと効率的に、例えば一つの市町村だけではなく、より広域でやった方が良いような場合、例えば、同じ作物を作った場合に、勝った負けたではなくて、全体として、例えば、名古屋の市場にどう繋いでいくかというような問題だとか、特に国の補助金がどういう形で出た方が良いのかという辺りを、国との間の調整、場合によっては制度を作りにいくという意味でしっかり役割分担がありますし、逆に、昨日は非常に良い例を見たのですが、そこだけで閉じてしまったのではあまりにもったいないので、それを他の地域に展開すると、その辺りが県の役割だと思っています。
記者
クマに関する話題なのですが、9月1日からの法改正で生活圏内、市街地にクマが出た場合に、市町村の首長の判断で発砲が可能になりますというところで、知事に直接関係がある話ではないのですが、法改正に対する受け止めをお聞きしたいのと、岐阜県の方から市町村のトップに対して、通知や説明はこれまでに行ったのでしょうか。
知事
それは、クマに関してということで良いですか。
記者
クマ、イノシシについてお願いします。
知事
まず、今回の法改正というのは、実際に残念ながら人的被害がこれだけ出ている中においては、本当に現場においては死活問題でありますし、それは手続きにおいて時間をかけてはいけない。まさにそれこそ基礎自治体の大事な役割ということで、市町村の判断というのは、これは十分あり得ることだと思っています。その上で、今回は、特に人的な被害という点が中心なので、こうした判断もあろうかと思います。なので、県にお伺いを立ててということではないということは合理的だと思っています。他方で、今度はイノシシだとか、今度は広域の農業だとか、いろんな人命というよりは経済的被害ということを考えた時には、個別の市町村ではなくエリアになってくると県の役割は非常に大きいと思っておりますし、私が着任して一番の一丁目一番地に鳥獣害対策を上げているように、そこの役割分担と県のやり方、まずはサルから始めましたが、これからイノシシ、シカに展開していきたいと思っています。ただ、クマはちょっと毛並みが違うというか、農業被害も出ていますが、それよりも人的被害が非常に大きい。実際に亡くなられた方がこれだけ出ている中においては、一つの緊急避難的な対応としてはあるのかなと思っています。
記者
名鉄広見線の関係です。御嵩、可児、八百津の沿線三市町がみなし上下分離で運行継続を目指す方針を発表されました。これについて、財政的にはまだ結論づいているものではないのですが、以前何か月か前にお伺いさせていただきましたが、県としてここに財政支援をするお考えはあるのかお聞かせください。
知事
県のスタンスは変わっておらず、人口が減るから経営が成り立たなくなるというのは、日本中どこでも同じ話なので、まずは線路、そして鉄道を維持するためには、どうやって乗客を増やすのか。ここの議論がないままに、支援をするしないという議論はまずはしないということです。今、実際に関連する首長さんたちとも話をしておりますが、実際は誰が使っていて、誰がさらにこれを使う可能性があるのか、その時にどういうサービスがいるのかという話をしましょうということを、まさに繰り返しております。その上で、特にあの路線は、3つの高校の非常に重要な足になっています。もう一つは、なかなかその自治体によって温度差があるというものの、外国人労働者の方にとっても極めて重要な足になっていますので、それがバスで良いのかどうなのか。そして、直接質問にはありませんでしたが、実際に観光ということを考えたときに、電車であるのか、そうでないのかで結構大きな違いになってきます。なので、そうしたものも含めて、関連市町でどういう計画を立てるのか、それをまず決めた上で相談しましょうというスタンスをとっていますので、まずはそれを聞いてから判断したいと思います。
記者
ライトレールの計画について、特に財政負担への懸念が出ております。先日、県議選に出馬表明された(岐阜市議会の)和田議員の言葉を借りる形になるのですが、計画の詳細等が分からないと、とても良い計画なのに、打ち上げ方に少し不安が、混乱が巻き起こっていると。とても良い計画なのに、それでおじゃんになってしまっては意味がないということで、計画の進め方に対して、まだ候補者の段階ですが苦言が呈されておりました。その点について、江崎知事の受け止めをお願いします。
知事
先ほどの名鉄広見線と違うのは、今回のLRTが主目的ではなく、岐阜という、特に県都である岐阜駅前から始まるこのエリアの非常に良い観光資源をどう活かしていくのか、まちづくりをどうしていくのか、というそのアプローチが根本的に違っていまして、その一つの方式としてLRTがあるのではないかという問題提起をしているということです。ですから、決定してしまったのであれば、あとは財政云々かもしれませんが、その中でエリア、ルートについても、まさにこれから議論をしていくと。宇都宮のLRTにしても、そうした財政議論まで4年かかっておりますので、そういう点では今まさに問題提起をし、これから色々な方の意見を聞きたいと。ありがたいことに県庁にもたくさん応援のメッセージであったり、うちにも引いてほしいと言うところも続々と来ています。そんな中で、やはり大事なことは、市民、県民のみなさんがそれをどう必要とされておられるのか、これは打ち上げないことには分からない。よくあるのは、全部決まってから打ち上げたらどうかという考えもありますが、それでは打ち上げたことになりません。そして、その中でもう一つ大事なことは、今ある良いものを活かすために、今あるもののあり方そのものとも関連してくる話なので、先立っては岐阜市、そして羽島市とも議論を始めているように、これからまた関連市町から色々な意見が(あると思うし)、昨日は昨日で、その2つと関係のないところからも是非話を聞かせてほしいというラブコールがたくさん来ておりますので、そうしたものを議論していく中で、どういう事業形態が良いのか。その上で、誰がその財政負担をするのか、要するにダメになっていくところを、どのようにお金を支えるのかという議論ではなくて、むしろ良いものを活かした時に、それで採算性がどうなるのか、それによってはそのお金の出し方は必ずしも県や市町が出すだけに限らないやり方というのはいくらでもありますので、そうしたことを考えていくための、まさに土台を作っていると、そんな段階です。
記者
打ち上げて議論していくことに意味があるということはおっしゃるとおりだと思うのですが、一方で、打ち上げるにしても資料が少ないということで混乱が巻き起こっているということが今の現状だと思います。これについて、以前、他社さんからも提案のような形で質問があったと思いますが、もう少し公開の場での議論があってもよろしいのかなと思うのですが、今後そういった場を設けていくお考えはありますでしょうか。
知事
先ほど申し上げたように、他の例を見ていただければ、公開まで4年かかっているのが普通です。混乱をしているというように、皆さんが言えば言うほど混乱を作ってしまっているので、実際に県に来ている議論は、むしろもっと前向きな議論の方が多いです。ですから、本件に限らず、色々なプロジェクトを実施していく中で、たたき台としてこういうものがありますよと、ある程度煮詰まったところで、それはもちろん発信していきたいというように思っています。特に、皆さんが関心のあるルートだとか、経費に関しては、まさにこれから議論していくところなので、それこそゼロベースでの議論をすると、何も決まらないというのは、むしろかえって混乱してしまうので、まさに議会の質問にお答えしていくというのが一番ルートとしては正しいかなと思っておりますので、前回の議論から、関連のところと今議論を始めていると。6月からプロジェクトチームも始めておりますので、その中で揃ったところで発信していきたいと思っています。
記者
冒頭の旧県庁舎の件なのですが、スケジュール感でいうと、9月頃にどの提案の方向で進めたいとか、そういう発表があるようなイメージで良いのでしょうか。
知事
私も聞いてみたいなと思っていますが、4つというところまで聞いていますが、現在はサウンディング型市場調査により情報収集を行っており、調査の結果概要は9月に公表させていただく予定であります。
記者
LRTの関連で、同じ日の議会答弁で、財政運営の厳しさというものを語っていらっしゃっていて、その後に、LRTに民間の資金の活用も視野にという話がありましたが、どちらにしても、県としてもかなり事業費の負担はあるのではないかと思われるところです。財政の話は4年かかった例もあるという話ではありましたが、同じお金の話と捉えると、やや矛盾を感じる部分があるのかなという印象で、その辺の捉え方はどのようになっているのでしょうか。
知事
多分、時間感覚を入れると、見えてくると思います。今いきなり打ち上げたから明日作るぞ、さあお金どうするという議論に割と皆さんしたがるのですが、基本的には10年という時間があります。その中でまずは本当にたたき台として、ここまでいけるのではないかというのに、普通は数年かかっていくと。その上で、その事業規模に対して、どういう資金調達のあり方があるのか、それで今度作る時には国が半分(負担する)と言われていますが、もっといろんなやり方があると思います。その後で、運営の段階になって、どういう負担があるのかというのはその先の話になっています。その頃までにはやはり財政は立て直したいと思っています。ですから、今、作れるお金があるかないかで議論を皆さんしたがりますが、そういうことではないですよと。それともう一つは、割とこれまで県は県のお金で事業をやることが事業だということが多くて、あまり民間のお金を使ってプロジェクトをやってきたことはないので、ある意味、PFIも含めていろんなやり方は、今世の中にあります。あとは、先ほどの事業性です。事業性が高ければ、逆に民間出資を集めやすいものだったりするので、その計画を今まさにこれから作っていくと。なので、今、お金があるから何ができるというのは割と今までの議論だと思うのですが、おそらくそういう議論をすべき対象ではない。もっと大きな議論と言うか、逆に一部心配されているように、今お金がないからできませんと言うと、多分何もできなくなってしまうので、まさに事業の信頼性、それから事業性の中でどのお金を使っていくのか、それは段階を追って議論していきたいと思っています。その段階で県として必要なお金はいくらで、それをどういう計画で積み上げていくのかというのは、まさにこれから始めるところです。
記者
財政の立て直しについて、どういうやり方、事業の棚卸も含めて、どれぐらいのスパンで仕上げていきたいかというのを教えてください。
知事
今、まさにやっているところですが、9月議会に向けて、まず大事なことは財政破綻をさせないということです。そのためにやるべきことは、そうたくさんあるわけではなくて、まさに使えるものは徹底的に使うということです。特に国のお金その他ですね。そして今おっしゃったように、今ある事業の中で、実は例年どおりにやっていれば良かったのか、同じ効果を上げるのだったらもっとやり方があるんじゃないかという形ですね。そのやり方、あとは新しい事業は何もできないのかというと、そんなことはなくて、今のLRTがそうであるように、今までの財政としてできることの外数で事業をやるというのは結構あります。私が(商工労働)部長時代は、商工労働部はほぼ(裁量性のある)予算がゼロでしたから、基本的には、人のというか、よその金を使うことによって事業を成功させていくというのはあり得る話だと思っていますので、そうしたあらゆる可能性をやりつつ、財政再建だから何もできませんというのでは、今度、県民の皆さん、市民の皆さんが困ってしまいますので、その辺りを同時に見た時に、何とか基金がゼロにならないように。基金がゼロになってしまうと、いざという時の対応が取れませんので、国のお金すら使えなくなってしまうので、そこを避けつつ、あともう一つは、当然のことながら、いろんなインフラのところで、事業者の方々が、事業規模が縮んでしまうとインフラの維持とか重機の維持ができなくなりますから、そこはしっかり確保した上で、ある意味、針の穴を二つ通すということになると思うのですが、そうした財政運営をしていくことになると思っています。
記者
財政再建と言った時に、目標となる、何の数字がいくらぐらいになれば良いみたいなものがあるのでしょうか。
知事
基本的に、破綻しなければいいということではなくて、これから東海・東南海地震などいろんなことが起きていきます。もちろん大災害になれば国の資金があるかもしれませんが、やはり小回りが利く部分だとか、国のお金が出ないけれども、やらなくてはならない、特に除雪だとか、いろんな道路の周辺整備ということを最低限これぐらい(の予算を)持っていないと、やはりいざという時に動けないので、それが大体いくらぐらいなのかと。大体、基金としては数百億、昔は2,100億円あった時代もあったのですが、そこまでないにしても、本当に必要な額を今試算しています。なので、やはりいざという時に安心して県政が運営できるための基金の額というのを弾いて、それに近づけるべくどのように運用していったら良いのか。ただし、全体の需要規模を縮めないという、かなり難しい綱渡りでありますが、それをやることによって、まずは事業者の方、県民の皆さんに不安を与えないこと、これが重要です。逆に言うと、元気よくやって財政破綻してしまったら元も子もないので、そこの綱渡りをしていくということだと思っています。
記者
LRT議論の関係で、宇都宮でも公開まで4年かかっていて、議論というのは時間がかかるものであるという話ではあったと思うのですが、これまでの会見で、年度内というお話もあった中で、イメージとして年度内でどういうところまで示せればいいみたいなことがありますか。
知事
そういう意味では、別に4年かけようと思っているわけではないので、いつもLRTとして引き合いに出されるのが、成功例として宇都宮があります。宇都宮にも職員を派遣したりして、いろいろ勉強していますが、そうした住民の皆さんの意見を求めるには、やはり4年かかっているというのは伺っています。他の地域でも2、3年はかかるというのがある程度一般的なのですが、そうした先達の経験を踏まえて、我々としてはできるだけ早く、もっと早くやりたいなと思っています。ただし、先ほどからお話があるように、やはりLRTに関しては、皆さん興味も高いですし、思いもありますし、うちにも来てほしいという思いが、やはりしばらくはいろんな意見が出る時期があると思っています。そこはある程度集約した段階で、まずはこのルートではないのかと、こういう規模じゃないかというのを、一刻も早くやりたいと。それで、関係の岐阜市、それから羽島市にまずは説明をする。それから違うところからも話を聞きたいというのは、続々と来ていますので、その中である程度議論が落ち着いたところで、浮上していくと。そこから先ほどから話があるようなルートの確定と、事業規模、そして採算性、特にこれは大事だと思っていますが、それを見越した上で改めて公開をして、この形でいきたいと、そんな状況にしたいと思っています。年度内でできればそれはベストですが、今の状況を見ながらも、おかげ様でいろんな意見もありますし、それを踏まえた形で、これを大車輪で進めたいと思います。
記者
9月議会も始まりますが、9月補正(予算)で調査費であったり、LRTに関して(の予算)も計上していく予定はありますか。
知事
今のところ、これからなので、多少は調査費があっても良いかなと思いますが、そんなにお金をかけるつもりもないです。実際には調査費がなくてはできないというよりは、職員の方でもいろいろ調査をしてもらっていますので、各地域で成功したところ、困ったところももう全部調査を進んでいますので、どういう形でやるかはこれから相談しながら進めたいと思っています。
記者
財政に関してです。財政破綻という言葉に関して、定義上はいろいろとある言葉だと思います。古田前知事の場合では、実質公債費比率が18%のところが、よく基準として語られていたと思いますが、江崎知事が捉える財政破綻とは、どのような指標がどれくらいまでいったところをお考えでしょうか。
知事
一般的に言われる財政破綻には2種類ありまして、かつて岐阜県が陥った起債許可団体、要するに、自由に起債ができなくなってしまう、まさに自分たちでコントロールできなくなるというのが一つのパターンの定義であります。あともう一つは、先ほどから申し上げたように、基金がなくなってしまう、基金が枯渇するというのは補助が入る国の予算も使えない。それから、例えば除雪する時も使えない。そうなると何が起こるかというと、かつてあったように職員の給与を削ったり、福祉関係の予算を削ったり、教育関係の予算を削って対応しないといけなくなる。そんなことになった時には、まさに県民、市民の生活に直結しますので、それは一種の破綻というかは分かりませんが、本来手をつけてはならないところまで手をつけなければいけなくなるというのを一つのメルクマールにできればと思っています。
(※)高島屋の「高」ははしご高