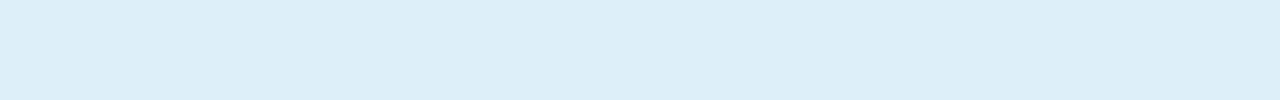本文
知事記者会見録(令和7年8月19日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年8月19日(火曜日)14時30分
司会
それでは、知事定例記者会見を始めさせていただきます。
知事お願いいたします。
知事
今日は4項目、私の方からご説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。まず最初に、バイオコークスについてご説明させていただきます。以前にも少しここでお話をさせていただいたと思うのですが、新しいエネルギー、特に岐阜県ならではの資源を活かした新しいエネルギーということで、バイオコークスを本格的に稼働させるために研究会を開催いたします。今月の終わり28日に研究会を行いますが、まずバイオコークスとは何かと言うと、木のくず、特におがくずですね、昔のオガライトというのを知っている方がいるかもしれませんが、ぎゅっと固めて燃料にすると、あれをはるかに固くして石炭と同じ強度まで持っていくことによって、はるかに用途が増えるものということで、これは近畿大学の特許なのですが、本当にこれから再生可能エネルギーの有力な候補として期待されるものなのですが、実はそれがこれです。すごいです、ほとんど石の状態になっています。これはよく見ていただくとおがくずです。固いです。写真ではこの音は伝わらないと思いますが。さらに驚いていただきたいのが、これは何かというと、やはり同じように固いです。これも同じように固いですが、何と牛の糞なんです。飛騨牛で有名な岐阜県なのですが、特に畜産農家にとって牛糞堆肥の利用先の確保が課題だという話がある。今、農業では、どうしても化学肥料が中心になっている関係で、今までは資源であったものが、廃棄物になりかねない状況にある。これをエネルギーとして活かしていくということで、臭くないのかというと、ほとんど臭いはしないです。最初、私も説明を受けた時に、横でコーヒーを飲みながら「臭くない。」と聞いたのですが、全く臭くないです。ついでに言うと、コーヒー殻も実はこの候補としては非常に有効だと聞いてます。エネルギーとして使う意味においては、この糞は結構貴重で、(木くずの方は)確か3時間ぐらい持つのですが、これは8時間持ちますし、あとガス化した時の割と使いやすさも、この堆肥を使ったものが素晴らしいという報告を受けていますが、そんなことを専門家の方も交えてしっかり研究会として産業化を進めるというのが、今回の岐阜県バイオコークス普及推進研究会なのですが、一応岐阜県とついておりますが、これはエネルギーの問題に関わってきますので、既に資源エネルギー庁に行って、長官、それから(経済産業)大臣とも話をしていて、非常に期待されるものということで、今回の研究会には、遠隔ではありますが、資源エネルギー庁新エネルギー課も参加をする、中部経済産業局とかそういったところも参加することによって、まさにこれからのエネルギー、特に地産地消ということで、今、地元にあって、これまではほとんど使われていなかったものをしっかり価値もあるものに変えていくということで、取組みを進めてまいります。今回は第1回でもありますので、私もご挨拶差し上げますが、その思いと概要についてのところは公開させていきますので、是非皆さん、大変これは勉強になると思いますし、これからいろんなところで皆さんも解説されたりとかあると思うので、是非お越しいただければと思います。後半は、かなりビジネスとか特許に関わる話もあるので、そこは非公開とさせていただきますが、概要のところまでは、皆さんのお手元の資料で言うと、(資料の)2ページ目の②のところまでは公開をさせていただきます。ここでかなり勉強になると思いますし、本当に見ていただいてお分かりのとおり、これがエネルギーになるのだったら日本は資源国になれるのじゃないかという、そんな思いもあって、少なくとも岐阜県においては、水力そしてこうしたバイオコークスを活かすことによって、いろんな今後の国際的な課題もある中で、しっかりとした対応ができるのではないかと、それに向けての発信をします。お手元の資料では、参加者の中の既にJFEさんとは、これまで石炭でなければ使えなかったような分野にもこうしたものが使えるということで、非常に期待をされているエネルギーでありますので、さらにこれをコアにして、国の政策として結びつけながら進めていきたいと思っております。これが1つ目です。あとでまたご質問いただければと思います。
2つ目のテーマですが、20階の展望ロビーについてです。これまで試行的に行ってまいりました土日祝日の開放ですが、試行期間が終わるのに伴いまして、本格スタートさせていただきます。本格と試行の違いは何だということで、試行期間中はとりあえずずっとこの期間やりましたが、本格的にやる時には、休館日というのを作りながらしっかりメンテナンスもできる体制を整えながら土日祝日も使っていただくということで進めていきたいと思っております。なので、利用していただいている皆さんにとっては、従来どおり引き続きやりますというイメージだと思いますが、一応日にち的には9月6日土曜日から、試行期間ではなくて、本格開放ということになります。土日祝日の開放時間は午前10時から午後8時まで、平日も従来通り午前7時半から午後5時45分までは変わりません。ただし、閉庁日というものが、全館停電させてチェックをしなければいけないというのがありますので、それはどうしても避けられないので、令和7年度中においては、少し変則的ではありますが、令和8年度以降は、原則毎月第3土曜日を閉庁日としてメンテナンスを行うということで、そこだけはすみませんが、来たけど空いてなかったということもありますが、第3土曜日というように決めれば、ご利用される方も分かりやすいかなと思っております。それから、開放場所は20階の展望ロビーと1階のギャラリー、これも従来どおり開放させていただきます。
そして今回、試行期間から本格実施に至るにあたって、やはり手探りではありましたので、どれくらいの方が来ていただけるのかと、それからたくさん来られた時にいろんなトラブルはないかということで、かなり慎重にやってきたのですが、おかげ様で、先立ての長良川花火大会の時で約2,000人の方にお越しいただきました。私は現場の方、長良川の花火大会の方におりましたが、職員の方が随時この県庁内から報告をくださいました。結果的に、ちょっと嬉しい報告としては2,000人近くの方が来られて、これは今まで本当にこれだけの方が来られたことはなかったのですが、皆さん非常に整然と対応していただいたのと、もちろん場所取りとかあったのですが、後から来られた人のために譲っていただいたり、特にやってみて本当に良かったなと思いましたのは、車椅子の方、そして赤ちゃんを連れて来られた方、本当は花火を見たいのだけれども現地に行くにはやはり渋滞も怖い、それから暗い所を歩かなければいけない、暑い、虫もいるということから、お声としては、駐車場がありますし、渋滞がなく涼しい所で、そんなに大きくはないのですが、私も報告を受けていて、それなりに楽しめるというか、Facebookにも出させていただきましたが、本当に(県庁舎20階展望ロビーの)中は中の喜びというか、皆の声がまたすごく良くて、「わぁ、すごい。」、「わぁ、きれい。」と最後に拍手が起きて、皆さん大変満足して帰っていただけたかなと。もちろん2,000人近くになりますので、帰りのエレベーターはもちろんかなり渋滞はするのですが、皆さん涼しいので夜景を見ながら、本当にトラブルなく、これは本当にありがたかったのですが、楽しんでいただきました。来庁者のアンケートでありますが、満足度においては98%の方が「非常に満足」、「満足」ということと、9割の方がまた来たいということをおっしゃっていただいておりました。今申し上げたように、そうした大きなトラブルもないということから、本当に県民の皆様のおかげで譲り合って使っていただけることがこんなに素敵なことなのかと。マイクでああしろ、こうしろという人が一切いなくて、皆さんに対応していただけたことが本当にありがたかったですし、空調について、もっと温度を下げてというのもありましたが、その辺りはまた声を伺いながら丁寧に対応していきたいと思っております。まさに県有施設を有効に使うと。
あと、今日の発表とは関係ないのですが、私も展望ロビーへ毎日行っていますが、その中で高校生の子から、「ここで勉強したい。」という声がありましたので、せっかくですから、お盆明けから、土日祝日のこの(試行の)開放期間においては、20階の会議室を勉強用に開放させていただきました。これもおかげ様で本当に喜んでいただいております。平日は、会議があっていっぱいなので、それは少し難しいのですが、空いている限りにおいては、対応できないかということも考えております。まだ夏休み期間中ですので、是非皆さんに使っていただいて、本当にせっかくの施設ですので、存分に使っていただければありがたいかなと思います。
次に、令和7年度の総合防災訓練を実施いたします。だいたい9月1日に一番近い土日に行われるのですが、今年は8月31日、日曜日に防災訓練を行います。テーマとしてはもちろんいろいろありますが、南海トラフ(地震)が割と注目されがちですが、今回は能登半島地震での検証結果を踏まえて、一つは濃尾地震、(発災から)100年経っておりますのと、もう一つは能登半島地震では大地震の後に大雨が降ったということで、複合災害も想定しながら、初日に地震、2日目に大雨という想定のもとで防災訓練を行うという、それを図上訓練も含めて対応することを考えております。この中では、まさに孤立地域対策訓練だとか、避難所支援広域物資輸送訓練、まさに自治体との連携をどのように取るのか、こういったことが本当に大事になってまいりますので、関係市町について、(資料の)裏面に記載がありますが、大垣市、関市、海津市、輪之内町、川辺町が、同一のシナリオで対策を行い、常に連携を取りながら対応するということであります。あとは実動訓練も現地で行いますし、資料の7にありますように、シェイクアウト訓練です。意外にその場になると動けないというのがあるので、まず何が大事かというと、私も聞いてなるほどと思ったのですが、「まず(姿勢を)低く、頭を守り、動かない。」というのが結構大事で、昔は机の下に入れというのがあったと思うのですが、私も国にいる時に、課の中でやったら、机の下は狭くて息ができませんという人が結構いたので、むしろ従来どおり、もちろん(机の下に)入れる人は入ったら良いと思うのですが、まず頭を守るということ、身を屈めるということが、意外にその場になるとできない人が多いので、こういったこともしっかりとやっていきたい。あとは、参加関係機関と連携しながら、いろんな訓練の中では、全てを県、自治体が賄うのではなく、民間と連携しながら、より効果的な対応をする。これは国全体もそうですが、そんな取組みを進めておりますので、今回においてもしっかりとそれを踏まえた訓練と、「事前の一策は事後の百策に勝る」と言われるように、訓練をして、特に情報交換のトレーニングが結構大事なことだと思っていますので、しっかりやりたいと思っております。
次は4つ目、「ぎふ森フェス」です。森林の中で心も体もリフレッシュということで、一言で言うと、森林のサービス産業化です。山と言えば、どうしても「木材、以上。」というイメージの方が大きかったりして、せいぜいバイオエネルギーぐらいだと思うのですが、そうではなくて、せっかく(県土の)82%が山というこの岐阜県でありますので、暮らしの中に森が生きるということで森林浴だとかキャンプ、トレッキング、E-BIKE、クラフトなど、気軽に森に親しむ。意外に岐阜県の子でも山に行かないということがあったりするので、もっと身近なものとして、体験していただくプログラムだと思ってください。これを10月1日から11月30日までと期間を決めて、(資料の)後ろにチラシが付いていますが、いろんなプログラムをやっていきます。もちろん観光に近いプログラムで、有料ではあるのですが、なかなか「おっ。」と思うものが結構あって、自分だけの何とかを作るというものもあるのですが、何と鹿肉ジビエの解体だとか、意外にマグロ(の解体)は見たことがあるのですが、むしろジビエの場合は防災の時でも、自分でスーパーに買いに行くわけにいかないので、自分で解体するとか、なかなか見ることもない、そういうものもあります。自分だけのルーペを作ったり、ウォーキングガイドツアーとか、まさに、地に眠る古木と浮かぶ根とか、いろんな見ているようで見ていないもの、価値のあるもの、こうしたものを是非体験していただこうということで、これは令和5年にできました森林サービス産業のための協議会(ぎふ森のある暮らし推進協議会)、こちらが主催となって、県も応援していますが、こんな取組みをしてまいります。まずは、県内、そして日本の皆さんが中心ですが、これはいずれ海外からもすごく人気がある話なので、体験型のツアーとして将来発展させていきたいと思っております。こうしたことを発信してまいりますので、是非よろしくお願いいたします。
記者
バイオコークスですが、近畿大学さんが特許を持っていて、それなりの歴史があるというか、企業さんと各地で実証実験もされているようですし、他のバイオ燃料でも、地域によっては実証実験とかこれまでもあるところだと思うのですが、今取り組む、そして岐阜で取り組む意義というのは、どういうところにあるのでしょうか。
知事
まさにおっしゃるとおりで、技術的には特許も取られて確立はしているのですが、エネルギーとして産業化するには、安定供給というのが絶対条件になります。使えますよというだけでは意味がなく、計画的に、安定的に使えるのかどうかということ。それから、今回JFEさんも入っていただくように、安定的に使ってもらえるのかどうか。要するに、消費先がなければ、いかに技術があってもしょうがないというところなので、今回、作る方、技術を持っておられる方、それから利用される方、そしてもう一つは、特に岐阜の場合は、牛糞というのが一つ大きな目玉になっていきますが、これをこのままの形で使うというのはあるのですが、ガス化することによって、気体エネルギーにするためのもの、実は、石炭もかなりの部分はガス化して、それから非常に使い勝手が良いものとして使ったりするものですから、これをベースに、そうした取組みも必要かなと。一部では、非常にガス化しやすいという話を聞いております。ただその時に、技術的にできるかどうかを超えて、産業として成り立つのか。それからコストです。企業秘密に入るところがありますが、どれくらいのコストなら石炭代替になるのか、ないしはどの閾値を超えれば普及できるのか。逆に、時々こちら、時々向こうというわけにいかないので、年間を通して安定供給できるのか。あとは、保存状態がこのままの形でどれくらい持つのか。そういった技術的な課題がたくさんありますので、それをしっかり考えて、国全体として、もう既に、隣県の長野県にも話をしていますが、山がある県にとってはみんな使えるものであるので、そうすると国全体のエネルギー供給の中にどれぐらいのウエイトを占めていくのか。今のところ、エネルギーミックスの中にほとんど入っていませんので、これが今までは木を燃やすという意味でのバイオ燃料の話がありましたが、コークスまで持っていくというのはこれからの話になりますので、したがって、始めから資源エネルギー庁を入れて議論する、そうした課題に取り組んでいきたいと思います。
記者
牛糞を使ったコークスだとガス化しやすいということですか。木くずと違って。
知事
これはたまたま聞いたのですが、おそらく中の成分の関係だと思います。その辺りも、こっちだったらしにくいのかということも、これからのテーマになると思います。
記者
岐阜だと飛騨牛はありますが、牛糞のコークスをたくさん供給できるとか、そういう背景はあるのでしょうか。
知事
というよりは、むしろ逆です。圃場の少ない中山間地では牛糞の行き場所がないんです。牛糞に関して、各農家は法律に基づいて適切に処理し、主に堆肥利用をしていますが、それをこういう形でエネルギーに変えれば、一石二鳥というか、まさに牛糞堆肥の利用促進にもなると同時にエネルギーに使えるという意味で、ある意味、むしろありがたいというか、そういう道があったのかということで、そちらも大きなテーマです。
記者
県庁舎(20階展望ロビーの土日祝日)の開放ですが、1日最大1,990人は、花火の時の1日の人数ということだと思うのですが、花火が上がっている時点で何人ぐらいの人が見ていたのでしょうか。
知事
花火が上がっている時は、だいたい1,500人です。朝からずっといらっしゃる方もあって、トータル1,990人ですが、花火が上がっている時間帯は約1,500人で、花火が上がっていない時間帯は、だいたい500人ぐらいです。
記者
花火がない日で、1日最大だとどれぐらい来られていたのでしょうか。
知事
大垣の花火を外すと、だいたい500人ぐらいですかね。
記者
自民党の総裁選挙管理委員会の関係で伺いたいのですが、今日、臨時の総裁選挙の是非を判断する手続きの議論を開始しています。これまでの経緯で言えば、石破首相の続投を支持する声がある一方で、退陣を求めて臨時の総裁選挙実施を求める声もあったという経緯があるわけですが、今回の総裁選挙管理委員会の手続き、議論が始まったことについての知事の所感をお願いします。
知事
元々参議院選挙で勝てなかったということの責任論というのは党の中ではあるのだろうと思いますが、日本国全体が今置かれている状況だとか、今変わったら何か好転するのかというような論点が、多分、皆さんも報道していただいているように、両面あるのかなと。けじめ論といわゆる政策論がまさに交錯している、そんな会議かなと。石破総理に関する動向を見るにしても、割と党の中の議論として、国民全体から上がっているかどうかというと、ちょっとそんな感じはしないなという感じがしていますので、おそらく、前回の会議でも出席者は結構少なかったというような意味においても、ある意味党の中身の議論として静観しているというそんな立場でいております。そういうものかなと思っています。
記者
重ねてその関連なのですが、知事ご自身としては、退陣を求める声もあり、一方で総理ご自身は続投を明言していらっしゃいますが、知事ご自身はどのようにご覧になっていますか。
知事
続投するのも退陣するのも大変だと思うのですが、今、国全体からするとやはり続投ということが自然な流れかなと思っております。特に今、ウクライナをめぐって、ロシアとトランプ大統領のあのような動き、ヨーロッパも動いている中で、やはり日本としてのスタンス、立場を継続させる意味でも、石破さんであることは大事かなと。特に、トランプ大統領との関係で、訪問された時に、非常に良い人間関係も作っておられて、彼独特なあの無表情で、かつウィットに富むということで、国際交渉上は非常に強い武器だと思っております。仮に、別の方がやられた時に、その関係をまた一から構築するというのは、特に今、世界情勢が非常に急速に動いている中では、続投というのも一つの選択肢かなと思っています。
記者
バイオコークスについて伺います。先ほども言及されましたが、特に牛糞等の処理コストがなかなかかかっているという状況で、タダでも良いから引き取ってほしいというような状況ではあると思いますが、そういう部分の連携も進めていくということなのでしょうか。畜産業界とも検討して、進めていくということでよろしいでしょうか。
知事
もちろんです。
記者
念のための確認ですが、(バイオコークスというのは)10の目指すべき目標ということで、知事発案のプロジェクトということでよろしいでしょうか。
知事
そうですね。エネルギー問題が重要となる中で、4年間回っている中で、この技術というのを教えていただいて、これはいけるなと。私も元資源エネルギー庁のエネルギー政策企画室長ですので、先ほど申した継続性と安定性がすごく大事なことなので、技術としてできることと供給できることは別問題だということは非常に感じておりますから、その点でもこれは期待できるかなと思っています。
記者
ライトレールの構想についてお伺いします。現状、国の補助においては、特に宇都宮市の例をみると、宇都宮市と芳賀町という立地自治体の方がメインになっていて、補助金の要件にも立地自治体の計画が必要になっていたと思います。この点について、現状、岐阜市が少し難色を示している部分もありますが、そこの理解をどう得ていくかお聞かせください。
知事
多分、岐阜市は難色を示しているのではなくて、市長さん自身がおっしゃるように、「こういった課題を解決する必要がありますよね。」ということなのですが、あの5つの項目は当然我々も検討しておりますし、採算性やコストに関しては、まさにこれからルート決定とともに出てくることかなと思っております。一方で、既に国土交通省等には話をしております。ありがたいことに、担当者の方も、非常にシンパシーを感じていただいており、やはり今のところの想定ではありますが、いろいろな交通システムを考える中で、1番乗降客が多いルートであるということ。特に学生さんですね、そしてお年の方の病院、その他のところを考えた時に、どういうあり方が一番望ましいのかと。もちろん必ずしもLRTでなければならないというわけではありませんが、定時性の確保であるとか、そしてまちづくりを考えたときに、国土交通省からも非常に高い評価をいただいておりますので、あとは自治体の中で、今いろいろな課題をそれぞれの自治体でお持ちでしょうから、丁寧に取り組んでいきたいと思います。宇都宮の構想から公開までは4年間かかっていますので、そういう意味では今まさに丁寧に作業を始めていると、そんな状況であります。
記者
関連して最後に一点お伺いします。県議の皆さん向けの説明会の際に、(東海環状自動車道の)岐阜インター(岐阜大学)の辺りに駐車場を作る、いわゆるパークアンドライド構想みたいなものがご説明の中にあったと思いますが、その点について改めて、歩く街へ生まれ変わらせるという構想の一環だと思いますが、その意図をお聞かせください。
知事
せっかく岐阜の中には良いものがあるのに、やはり車でないと行けない形であるが故に、活かせないものがあるという中で、歩く街ということが一つの哲学としてあります。それを実現するための方法として、このLRTは有力だということの中で、実は電車である限り操車場が必要になります。操車場をどこに置くのかという話と、あとは今回岐阜大学の前と言っていますが、もう一つは、岐阜市唯一の岐阜インターに繋げていくことによって、車で来られた方々がLRTに乗り換えることができると。岐阜の中心部に車で入ってしまうと、渋滞の原因になりますので、そうするとパークアンドライドをやりやすい場所としては、非常に期待が高い場所なので、その結果として、操車場とパークアンドライドの場所としては非常に有力な候補ではないかと、そんな議論をさせていただいたところです。
記者
20階の展望ロビーの土日祝日開放(本格実施)についてお教えください。これまでは試行ということでアンケートを取りながら、いろいろな改善点があるかどうか探ってこられたかと思います。今後もアンケートを継続されるのかどうかと、始められた時に、飲食に関するものもあったら良いかなと知事がおっしゃられたと思いますが、今後付加していくようなサービス等考えておられることがありましたらお教えください。
知事
まずはトライアルであるが故に、県民の皆さんのご意見をしっかり聞くというのは大事な取組みでしたので、アンケートを取りました。ただ、本格的に開けるにあたっては、今までのようなアンケートの取り方はしない予定です。ただ、県民の皆さんの要望は聞けるようにはしておきたいというように思っております。
2つ目のご質問の飲食については、結構大事でして、初めから喫茶店があると良いよねという希望もありましたが、やはり当たり前ですが、民間の方からすると店を開いてもお客さんが足りないといけないということで、今のところ1日約500名というのがほぼ安定した数字になってきました。さらには、飲食が人を呼ぶということもあると思いますので、その辺も含めて、可能であれば、喫茶店や、今のところは自動販売機でコーヒーが飲めるようにしていますが、サンドイッチ等があっても良いかなとは思いますね。そんな声もちらほらありますので。ありがたいことに少し出店しても良いかなというような喫茶店がないわけでもないので、そのあたりも含めて、いろいろな条件、それから水道等の設備を準備しなければいけませんので、ニーズと希望も含めながら今後も考えていきたいと思っています。
記者
LRTについてお教えください。議員への説明会ということで、岐阜県議会の一部の会派の方であるとか、岐阜市議会に関しても一部の党派への説明の機会は県として持たれているかと思います。今後、まだ説明されてない羽島市等の地域や会派の方々に対する今後の説明会の予定やお考えがありましたらお教えください。
知事
これは大事だと思っていて、結論から言うと、積極的にやりたいと思っています。まずは構想の段階ですので、聞きたいと仰っていただいたところから優先的に、そちらのご希望に合わせる形で進めさせていただいております。県議の先生からもありましたし、岐阜市議会にも話をした時に、関係する人にも話をしてもらえるとありがたいという話がありましたので、まずはご希望されるところに。今日も希望がありましたので、対応しております。ですから、羽島市さんはもちろん、両市さん同じように進めていきたいと思っています。さらには、周辺で今のところ計画はないがうちもという自治体は結構いらっしゃいますので、そういったところにも説明をしていきたいと思っています。
記者
バイオコークスの関係をお伺いします。このバイオコークスなのですが、岐阜県としてバイオコークスを製造する施設を作るのか、民間でも作るところがあって、そこを支援していくのか、どのようなイメージを持たれていますか。
知事
実はもう既に作っている会社があるので、今これを借りてきたのですが、規模的にはかなり小さいので、先ほど申し上げたように、エネルギーなので、安定供給ができないと、やはりできますということと供給は違うので、おそらくそうした設備そのものを改善していくという、砕く時に音が出るとか、あと臭いをどうするかというのと、そしてこの場合、乾燥させるというのが結構難しい技術になるので、そこについては研究開発要素があります。それで、それを今できているから良いというよりは、大量にあった場合にどんな技術が必要なのか、これは国の補助金も活用しながら研究テーマにしたいと思ってます。
あともう1つは、岐阜である強みというのは、実験室でできても、今度は一般のところについて、先ほどの臭いの問題とか音の問題だとか、稼働させる重機の音などもあるので、適地があるかどうかを考えた時に、多分一箇所あるから良いということではなく、あとは季節によってもどう稼働させるかという、その辺りを考えていくことになりますので、おそらく当たり前ですが、エネルギーなので、拡大することを前提に、ただ先行者利益というのは当然ありますし、拡大すると同時に必ず利用者が必要になりますから、それだけの需要と供給をバランスさせながらどう発展させていくか、これがこの研究会の一つの重要なテーマになると思っています。
記者
つまりは、企業さんを支援して、量産化に繋げていくようなイメージということで良いでしょうか。
知事
先行者にはやはりノウハウがありますので、特許としては近畿大学ですが、さらにそのまま、生産ノウハウとか、もっと言うと、山からどうやって下ろしてくるんだとか、その供給体制、山があれば良いわけではなくて、今日のテーマではありませんが、やはり安定的に山から下ろしてこなければいけない。牛糞は、おかげさまで安定的にあるので良いのですが、本格的に山の整備とセットにしていくというのはもう計画なので、一企業ができる話ではありませんので、県や国も含めて進めていくことがあると思います。
記者
需要の部分についてですが、このバイオコークスというのはどういったところが使うのでしょうか。
知事
なぜコークスなのかというと、先ほど申し上げたように、石炭でなければできなかったことの代わりができる、そうすると当たり前ですが、石炭火力発電所というところで使っているものもありますし、もっと分かりやすく言うと、製鉄所です。なぜJFEさんがいるかというと、鉄鉱石を精錬する時には、鉄鉱石、石炭とコークスという層状に並べて下から800度から1,000度で飛ばしていくんです。それで、その間に燃料として何時間か持たないと、ここに普通の木を入れてしまうと一瞬にして燃えてしまいますので、多分効率はめちゃくちゃ悪くなりますから、それはやはり石炭でなければできなかったところで、日本では供給が足りないので、オーストラリアとか外国から輸入したものでしかできなかったところに日本産のこれができるというのは革命的に大きいということと、あともう一つは先ほど言い忘れましたが、バイオコークスなので、CO2排出係数ゼロです。これはものすごいことで、石炭が一番のCO2排出の元凶と言われて。小泉元環境大臣が世界的に非難され、石炭火力発電所を止められないということを内外で言われた。そこで、これが使えてゼロになるということは、ある意味環境の世界においても、革命的なことが起きます。なので、そうしたことも踏まえながら、当然利用される方も、もちろんオーストラリアとの関係がありますが、全部止めてしまうわけにはいけませんので、一部、例えばCO2排出量を半減させるためにも、半分はバイオコークスを使う。そうすると、今までとルートが変わってくるのと、全く石炭と同じように使えるかどうかの研究も必要になります。一部使い始めていますが、量産にした時に今度はそれが安定供給できるかという辺りも含めて、ビジネス的なところと技術的なところの両方を踏まえた時に、相当大きく変わってくる。そうすると、今度はCO2排出係数がゼロになるということは、これまさに排出権との絡みでも出てきますから、その後のビジネスモデルも考えていくと、そんな流れになると思います。
記者
LRTの構想についてお伺いします。知事は、LRTを岐阜市街に敷くことによって、歩きたくなる街、歩く街にしていきたいというお話だったと思うのですが、今の柳ヶ瀬を中心とする中心市街地を見ていますと、イベントの時とかを除いて、どうしてもひいき目に見ても、閑散としているなという現状があると思うのですが、歩きたくなるような店なり、施設なりも必要だと思うのですが、その辺りの現状と言いますか、どのように見ていますでしょうか。
知事
実は私、合気道の関係で40年間宇都宮という街に通っていたのですが、やはり宇都宮に比べると、岐阜の中は街が閑散としているのですが、拠点拠点には良いものがあります。ですから、おそらく賑わいがあってから電車を作るのか、電車を作ることによって賑わいがあるのか、これはどちらか分かりません。ただ、仮にLRTとして作った時に、あそことこことここを繋ぐことができれば効果的だよねというものは、おそらく岐阜市の方があると思います。そうすると金華山もそうです。今回の岐阜城楽市もそうです。それから鵜飼、川原町もそうです。国際会議場もあります。その辺りを考えた時に、やはり逆に考えていただければ、岐阜城楽市に行っても、車で行く人がほとんどですから、じゃあ次にどこ行こうかと思うと、おそらく車に乗って次の場所に行ってしまうので、おそらくあそこから流れて、伊奈波神社を通ってという人があまりいないからこそ、たぶん街が閑散としてしまっていると。電車だと乗り降りが割としやすくなりますし、特に大事なのはお年寄りの方です。そして、若い子ども達、自分で車を運転できない人にとっては本当に大きく行動範囲が変わるかなということなので、そうすると、そういう人達が行ってちょっと休める場所で子ども達が買いたいおもちゃがある場所というのは、今度ニーズとして出てきた時に、今空いている店舗のところにどんなお店を置いておくとその人達が買ってくれるのかなと、おそらくその相乗効果になると思っていますので、繰り返しになりますが、岐阜市にはその拠点なるものは既にあるし、その間と間のところも、空き店舗というか、建物があるので、そこを新しく埋めていくことによって、岐阜市全体、まさに県都であるところは非常に賑やかになると良いかなと思ってます。
記者
関連で、岐阜市の柴橋市長が、まもなく市長として任期8年を迎えるところなのですが、柴橋市長も道路空間の利活用であったりとか、自動運転バスであったり、こういうのを活用して、歩きたくなる街、知事と目指すところは同じようなことで話されていると思うのですが、ただこの8年間で柳ヶ瀬がかつての賑わいを取り戻したかというとなかなか言いづらい部分があるのかなと思うのですが、その辺りについて、今までの岐阜市の街中の活性化策の評価というのをどのように見られていますか。
知事
私もかつて商工労働部長をやって、岐阜県で初の街コンをやった人間でありますので、あの時もそうだったのですが、最初は皆さんおっかなびっくりではありましたが、一度成功すると非常に空気が変わるというのがあります。そういう中では、今回の岐阜城楽市とか、自動運転バスも取組みとしてはあると思うのですが、そういう意味では、(バスの自動運転)6年間やっていましたっけ、その結果を聞きたいなと思っています。今度岐阜市にそれを教えてもらえると(と思います)。LRTがあるから他がいらないというわけではなくて、成果として良い面があり、課題があるでしょうから、そうするとあれをLRTに繋ぐことによって、LRTが行かないところに自動運転バスを使うとか、いろんなやり方があると思います。そうすると今おっしゃっていただいたように、高島屋(※)もいなくなり、どちらかと言うと発展してきたというよりは・・・という感じでおっしゃったのだと思いますが、ただ繰り返しになりますが、良いものはあるので、そこの活かし方の一つの方法として岐阜市が取り組まれたその結果をまず教えていただいて、その上でせっかく一緒に勉強会をやるので、LRTでなければいけないというつもりはありませんので、それを活かした時に、どんな答えがというそういった経験が結構大事だと思いますので、それを活かした上で、岐阜市を活性化するための方策を考えていきたいと思っています。
記者
自動運転バスが走っている街中の路線と言いますか、変更と言いますか、そういったところも検討の一つとなりますでしょうか。イメージですが。
知事
今(のイメージで)は被っていないと思いますが、ただ、自動運転バスでしか実現できないことが何かと。逆に自動運転バスだと何が課題として残ったのかっていうところがある意味次への大きなステップになると思っていますので、そこはまず教えてもらってから考えたいと思います。
記者
全国知事会の会長選があったかと思います。長野県知事の阿部知事が、無投票で当選を決めまして、江崎知事も推薦者の一人に名を連ねていらっしゃったかなと思うのですが、阿部新会長に対して期待するところを教えていただければと思います。
知事
先立ても阿部さんと知事懇談会をやったのですが、実は長野県の知事さんというのが会長になっていただけたのは、岐阜県としても非常に心強いところです。同じような環境というか、海なし県であり、非常に面積が広くて大半が山という、ほぼ同じ状況になっています。そして、人口減少の課題も抱えているということで、実は先ほどのバイオコークスも阿部知事とも盛り上がったのですが、やはり共通の課題、それから鳥獣害対策、こういった意味において、これから岐阜県がやろうとしていることの共通の問題意識を持っていただいている方が会長になっていただけるということによって、これを全国に発信できる、そうした立場の会長さんになられたというのは、非常に心強いと思っています。それから、お人柄も非常に気さくで、この間も非常にいろんな議論をさせていただきましたし、ありがたかったのは着任当初、万博に行った時に初めてお目にかかった時に、向こうから「是非懇談会をやりましょう。」と。14年間止まっていたそうなので、「是非やりましょう。」と、初めての日にそう言っていただいて、この間も本当に有意義な議論ができたかなと思っていますので、そういう点では非常に期待をしております。
記者
バイオコークスですが、設置の目的のところに、「バイオコークスの生産消費プロセスを通じた地域課題の解決・まちづくりの推進等」とあるのですが、地域課題は先ほどの牛糞の話もあるかなと思いますが、その辺りいかがでしょうか。
知事
それともう一つは、やはり山です。前も申し上げましたが、山がたくさんあるのに林道が作れない。それによって山から木が下ろせない。そして、間伐・枝打ち・下刈りができないというような、まさに山を持っていてもできない課題というのが一つと、やはり山間部はどうしても人が減るのは当たり前と言われているかもしれませんが、なかなか林業を継ぐ人は少ない中で、4番目に申し上げました、森林の三次産業化に対して、これは一次か二次かよく分かりませんが、エネルギーという新しい価値を踏まえることによって、その地域そのものの価値が高まると、そこで働いてみよう、生きていこう、住んでみようという、まさにまちづくりにも繋がる、非常に重要なテーマかなということで、このような目標を立てていただきました。
記者
県庁の20階展望ロビーの(土日祝日)開放について、来庁者アンケートだと、岐阜県内からの来場者が約8割と、そして県外(からの来場者)が16.5%となっています。この辺の割合はどう見ているかということなのですが、やはり県外の方をもっと増やしていきたいという考えなのか、その辺りいかがお考えでしょうか。
知事
まずは何と言っても、岐阜県の方には皆登ってもらいたいなと思っていますが、せっかく県民の皆さんの税金で作らせていただいた財産ですので、ある意味シンボルとしての岐阜県庁にできればなと。誇りを持って、ここが岐阜県の行政を司る場所なのかというのと同時に、展望ロビーからの眺めも、まさに岐阜県内一望とは言いませんが、非常に広く、北の山々から、まさに濃尾平野も一望できますので、それを知っていただくと同時に、県外の人にとっても非常に魅力的でしょうから、おそらく名古屋方面からだとは思いますが、ちょっと寄ってみようかなと(思ってもらいたい)。まだ構想ではありますが、LRTがもし近くを通れば、もっともっと人気のスポットになっていくかなと思っています。
記者
例えば、インバウンドの方を、(県庁は)岐阜羽島駅からそんなに遠くはないと思うのですが、呼び込むとか、そういったお考えもあったりするのでしょうか。
知事
十分あります。ある意味、岐阜県に来て、いきなりどこに行きますかというよりは、まずは岐阜県全体を眺めていただいて、おそらく多くの方は飛騨高山ということを名前のイメージだけで来ていると思いますが、例えば、展望台から北の方に向かっていただいて、一番端に見える山の辺りですよとか、ちょうど金華山のすぐ隣に御嶽山が冬の時は綺麗に見えます。位置的なイメージで、恵那山も見えます。そういったこともイメージしながら、これからどこへ行くんだとか、伊吹山の方を見ながらあそこに関ケ原があるんだという、要するに頭の中でマップを描いていただくには最高の場所だと思っていますので、まさに岐阜県の観光の玄関にできればと思っています。
記者
今ちょうど(高校野球の)試合をやっていますが、県岐阜商の試合も先日甲子園の方に行かれて観戦されたと思うのですが、その戦いぶりをどのように見て観戦されていらっしゃったかのでしょうか。
知事
素晴らしいですね。私も実際現場に行かせていただいてすごく良いなと思ったのは、我々はどうしても勝ったという情報しかないので、頑張ったんだねと思うかもしれませんが、途中途中の緊張感だとか、特に前の試合(明豊高校戦)の場合、エース温存だったものですから、なかなかコントロールが効かない、あのプレッシャーの中でストライクを投げなければいけないというあの怖さというのは、本当に高校生にとってもすごい大変なことだろうなというのを、やはり同じ空間で見させていただくというのは、本当に応援したくなるというか、結果勝ちましたが、「あわや」というところは何度もあったので、そこを見事に凌いでいくという、そういったものも試合全体としてやはり現場で見て、そして応援の方々の思いとか、やはりテレビで見るのも良いのですが、1回見ると次の再放送がないので、見逃したら終わってしまうというのはあるのですが、あの空気感というのもすごく大事かなと思いましたので、良かったと思います。特にそういう意味では、さらに言うと、横山(温大)君が、本当に見事にハンディを乗り越えてどころか、すごいなと思ったのは、期待の場所では必ず打つので、県岐商という、あれだけたくさん(硬式野球部員が)いる中でレギュラーを勝ち取るし、さらにその中でも一番期待の場所に置かれているということは、いろんな人の力になると思いますし、それから今日特集をしていただいていましたが、チーム作りの中で、主将を選ぶ中でも皆で一体となると、あれはすごいことだなと思いました。確かに見ていて非常に気持ちの良いプレーをしてくれたなというのがありましたので、そうしたものも本当に行かせていただいて、私も学ばせていただきましたし、是非皆さんそういうことをお伝えいただければありがたいなと思っていました。
(※)高島屋の「高」ははしご高