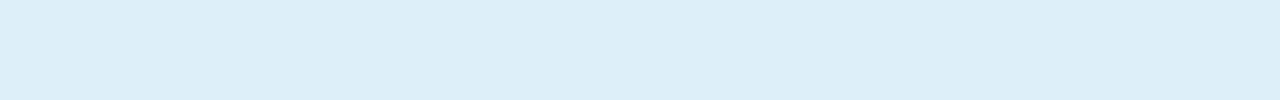本文
知事記者会見録(令和7年6月18日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年6月18日(水曜日)15時00分
司会
ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。
知事お願いいたします。
知事
今日は、4つ大きな項目がありますし、前回に引き続き、ゲストの方にお越しいただいています。まず1つ目ですが、政策オリンピックです。私も先立って最終審査会に行ってきましたが、素晴らしかったです。特に、季節に応じた住民参加型訓練ということで、まずこちらについてご報告いたします。
私の方から簡単に概要と趣旨を説明した後で、(ゲストの方に)それぞれ一言ずつお話いただければと思います。まず、4月1日からスタートした政策オリンピックの第1弾の2つ目ということで、まさに「安心とワクワク」ということで、安心を実現するともに、安心だけではダメで、ワクワクしながら皆さんに参加していただくということであります。災害発生時は自らの命は自ら守る「自助」と、そして、地域でともに助け合う「共助」が災害の初動においては非常に大事ということで、この力を強化するために、住民の皆さんに協力いただく形で、そして県民の皆さんからアイデアをいただくということで、政策オリンピックをスタートさせていただきました。そしてこれは、我々が選ぶのではなくて、県民の皆さんに選んでいただくということで、まさに子ども達、おかげ様でたくさん応募いただきましたので、第1次のスクリーニングとして、有識者、大学生、高校生、中学生に絞っていただいて、最終審査を小学生に行っていただきました。何でかと言うと、今回のオリンピックの一つの目的は、各地域で自治会が成立しなくなっていると。自治会の組織率、地域の力が弱くなっているので、今まで自治会には関心がなかったけれど、これを機におもしろいと思っていただくということ。その中で、子ども達に楽しいと思って参加いただく、これが地域力に繋がるということで、子ども達も積極的に参加したくなるようにということで、この間は輪之内町の小学校へ私も行きましたが、その時に皆さんにお願いしたのは、皆さんが未来を選ぶということでした。これまでは、皆さんよりお兄さんお姉さん、大人達が選んできたものを、最終的な金・銀・銅(賞)は皆さんが選びますということで、熱心に頑張っていただきました。そして、この度、金・銀・銅と入賞を、今回は入賞までが予算を予定し、(補助率)10/10で満額回答というところですし、特に金・銀・銅の団体の皆さんはこれからいろんな形でPRしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。せっかくですから、(受賞団体の方に)並んでいただきましょう。
まず、金賞の御嵩町は、「小中学生がプロデュース!!まるで縁日のような自治会防災フェスタ」ということで、取り組んでいただいております。この地域は、地域クラブと自治体の連携ということで、非常に珍しく、頑張っていただいていますし、特に小学生の意見の中に、煙の部屋から脱出するということが、いろんなグループから面白いと。なかなか自分達では経験できないところがあると言っていました。そして銀賞が2つなのですが、羽島市の「防災スポーツフェスティバル」については、レクリエーションや模擬テントの設置ということで、地域の防災力を、毎年やっておられるということで、ただの運動会ではなしに、防災に関連した形で、ブラッシュアップしたもので素晴らしい。もう一つの銀賞については、中津川市の「中山間地区のフィールドを活用した楽しい防災キャンプ事業(寒冷期編)」ということで、特にこれで面白いのは、山から取ってきた薪を使うと。買ってきたものではなくて、ジビエや防災農園で取れた食材で、自分達で火を起こすと。そして、銅賞として、高山市の「シナリオのない防災訓練+α」については、雪国ということで、年6回季節に応じて、そして雪だけでなく噴火ということもありますので、そういったことも含めて、非常に面白い取組みでした。それでは、金賞の方から、一言ずついただきます。
御嵩ぼうさい倶楽部
御嵩町の御嵩ぼうさい倶楽部代表の須美と申します。今回の政策オリンピックにおいては、私どもの防災イベントのアイデアを高く評価いただき、大変光栄に思っております。
地域クラブである御嵩ぼうさい倶楽部は、小、中学生自身が楽しく防災を学び、子ども達の目線で啓発することで、地域の防災力の向上に繋がっていけばと活動しています。子ども達が一生懸命知恵を出し合い、考えた自分達も、参加者も楽しめる、まるで縁日のようなアイデア満載の防災イベントに、子どもからお年寄りまで幅広いの方に参加していただきたいと考えています。引き続き自治会と連携して、防災力アップに貢献できるよう、メンバー全員で頑張ってまいります。本日は本当にありがとうございました。
竹鼻町自治会
この度は竹鼻町の防災フェスティバルに対し、銀賞という大きな評価をいただき、心から感謝申し上げます。私達の合言葉は、「地域の助け合いは心と心の結びつき」です。防災を自分事として感じてもらうために、笑顔で楽しめる運動会形式に防災訓練を組み合わせ、平成26年から取り組んできました。防災を身近に感じ、行動に移すきっかけになればと思い取り組んできましたが、この活動が他の地域でも心と心を結ぶ防災のモデルとして広がることを願っております。本日はどうもありがとうございました。
神坂まちづくり協議会
中津川市の神坂まちづくり協議会の会長をやっております島田と言います。神坂は、中津川市の中でも最東端にありまして。馬籠地区、あるいは島崎藤村の生誕地として、ご案内があることかと思います。神坂まちづくり協議会は、昨年できたばかりの組織でございまして、それまでは地区内に2つ組織がありましたので、私どもは始まったばかりなのですが、そういった中で地区の安全・安心を守るためにどうしたら良いのか、あるいは神坂地区は典型的な中山間地でございますので、耕作放棄地とかジビエ、有害鳥獣対策とか、いろんな問題があります。それを皆で話し合いを持ちまして、地域で困っていること、有害鳥獣、あるいは耕作放棄地、あるいは森林をどうするかということを、苦しいとかつまらないとか、困ってることを楽しみに替えようということも含めて、そしてまた今回は季節を意識したということですので、冬にあえて開催しようということを企画させていただきました。そこで、先ほど知事からお話がございましたように、火起こしとか、ジビエを使ったカレーとか、あるいは防災農園で育てた野菜を使ったカレーを作って、食していただこうということで、地域の猟友会の皆様との連合を保ちつつ、そういったことをやっていこうと思っております。最後になりますが、我々(県の)東の端におりますと、県の行政に遠いと常々思っていたのですが、今回のこの企画を通じて、とても身近に感じることできました。そしてまた、こういった銀賞ということで大変名誉に思っております。本日はどうもありがとうございました。
大八まちづくり協議会
高山市の大八まちづくり協議会の事務局長の山本と申します。今回は、大八まちづくり協議会の「シナリオのない防災訓練+α」ということで、出したプランを高く評価していただきありがとうございます。高山市は皆様ご存知の通り、日本で一番広い市です。それで火山でありますとか、豪雪地帯ということもあって雪もあります。そういったことで、地震だけではなく、雪とか火山とか、そういった災害の種類とか、規模や想定など、いろいろなパターンを行うために、一つのまちづくり協議会だけではなく、20個のまちづくり協議会があるのですが、その4つのまちづくり協議会と連携することによって、季節ごとに1年に6回の訓練を行います。それで6個に4つの団体で分けるということは、役員さんの負担が減るということと、いろんな体験とか経験スキルを共有することができるということで、そういったプランで組んでおります。ワクワクということを知事もおっしゃいましたが、大型カルタを東小学校の方に防災クラブというのがありまして、そちらの防災クラブの子ども達に公募をしまして、読み札を集めて、それでA3サイズの読み札と取り札を作って、スキーができるような原山公園というところで、そちらでかるた大会をするとか、あとはダンボール迷路ですとか、小学校のお子さん達が、地震が起きた時の被害の模型みたいなのを作って、お化け屋敷的にそういったものの中を地域の方が参加して、どういった被害になった時にどうしたら良いかというようなことを考える、そういったプランを考えております。このように、お子さんを巻き込んで、また自治体の高山市さんと協力しながらいろいろやっていきたいと思います。今回は評価していただき、この場に来れてとても光栄に思っております。ありがとうございました。
司会
それでは、この件に関しまして、ご質問をお受けいたします。
記者
知事はこの間、小学校での審査も視察されたということで、現場でも取材を受けていらっしゃいましたが、改めて実際に見て、若い人が審査に加わったことの感想と言いますか、評価をどのようにされていますでしょうか。
知事
今聞いていただくとお分かりのとおり、はるかに我々の期待を上回る提案をいただいて、ちょっと感動しておりました。どれくらいフェアにやっているかというと、私も(プレゼンテーション審査で)どの6つが選ばれたか、小学校に行って初めて見せてもらいましたので、一切事前にあれやこれはとはやっておりません。それでこれだけのレベルがあるというのが素晴らしかったですし、あと小学生の子達、3つの小学校で6人ぐらいずつのグループに分かれて、皆で議論をして、グループごとにどれが良いかというのを点数分けして貼ってもらうと。本当に、手続きも透明性を徹底的に追求している中でも、すごく皆さん盛り上がって、「これはここが良いんじゃないか。」、「自分はこう思う。私はこう思う。」というのを活発にやっておられました。先ほど申し上げたように、「煙の部屋からの脱出はすごいよね。」とか、あと、実際に火を起こすとか何とかということを子ども達も自分事として一生懸命考えてくれたのは本当に良かったなと思っています。
今のお話は少し続きがありまして、銀(賞の2つ)は実は全く同じ評価であり、2つになりました。これも子ども達の評価そのままです。一切我々は手を加えておりません。そしてお手元の資料の中にあと2つ、下呂市(地縁法人上村区)の、これ名前が良いなと、「知る(しる)区(く)ロード」と言うのですが、「区を知る」ということです。これは何かというと、過去の災害や防災体制を子ども達がお年寄りの方と一緒になって街中を歩くことによって、昔ここの崖が崩れたとか、昔ここで川が氾濫したとか、そういったことを一緒に学びながら、そして途中途中のお寺で休憩して、そこで歴史も一緒に学ぶという。これもなかなかすごいなと思いましたが、子ども達は「何だ勉強か。」と思ったかもしれませんが、これも面白いなと思いました。
その下の岐阜市(華陽自治会連合会)です。これも本当に、後ろの(ページに)にさらに追加の資料がありますので、ご覧いただければと思いますが、やはりお年寄りから小中学生まで一緒に防災を考えて、何度も訓練するということ。そして、学校に泊まって、停電になった時に何が起こるかとか、他もあったと思いますが、そういった訓練を実際にやってみるという。だから頭で分かっていることと実際やってみることは違うよねということをまさに体験していただくということです。
それから、実はこの6つ以外のものについても、その前(最終審査)の段階でスクリーニングされてしまったのですが、なかなか面白いものがたくさんありまして、例えば外国人の方、それから障がいがある方がどうやったら避難できるかを皆で考えようとか、本当にいろんな工夫、いろんな人が活躍できる場が結構大事かなということです。そして大学生の感想で、企画者がまずは楽しそうにやっていると。防災と言うと何か悲惨なイメージですが、あれこれ心配するというよりは楽しくやる、まさに「安心とワクワク」を審査員の方々も感じていていただいたので、すごく良かったかなと思います。特に防災の場合は、事前の一策は事後の百策に勝ると。いかに早く事前に考えておくかが大事でありますので、是非これを皆さんに取り上げていただいて、しっかり応援していただけるとありがたいと思っております。
これが1つ目なのですが、その次に、実は政策オリンピックは既に第2弾というか正確には第1.5弾という発想でやります。政策オリンピックとして、「ふたつのふるさと」を募集します。「海・山の防災交流」です。
実は、今申し上げたように、金・銀・銅の皆さんは、これからどんどんアピールしていきますが、そうでなかった方々の中にも非常に良いアイデアがあります。そして、審査の過程で出てきたなかなか良いアイデアもありますので、まとめて公表したいと思っております。
それを踏まえたうえで、愛知県とか三重県の県外の児童生徒の皆さんと岐阜県の子ども達で交流しようというプロジェクトをやります。何のためにやるかというと、まず、お互いの地域を知るということもあるのですが、例えば海の子達が山の方に来てもらった時に、一緒にいろんな活動する中に防災の活動も入れましょうということです。ですから、前から言ってますように、南海トラフ地震が起きた時に、岐阜県は被災県であると同時に、間違いなく三重県、愛知県の被災者を受け入れる県になりますから、今から直ちにその準備を始めませんかということで、(政策オリンピック第1弾の結果)発表と同時に次をやるのかと言われるかもしれませんが、まさに今日やることに意味があるかなと思っております。県内中でおかげ様で本当にいろんなアイデアを出していただきました。自分達を守ることがまず大事なのですが、他の人も守っていくことも大事になるということで今日発表させていただきました。
やり方は工夫してあります。例えば、もう既に三重県、愛知県と提携している、もうすぐにでもできるよというところに対しては、こんなことをやります、その中で要件として、まずは宿泊を伴う交流をするということ。地域の資源についてお互いに学ぶということ。そして防災に関する体験をするというセットのプログラムを考えてみてください。もう提携先がありますから、ある人はできるんだったら200万円の(補助率)10/10で良いアイデアについては採択をして、いろいろ計画があるでしょうから、すぐにはできないかもしれませんが、今年の夏以降、秋にかけてそうした取組みができるというところのグループが1つ。
そんなにすぐにできないよ。提携先が無いよという人達のために、例えば来年度、令和8年度において、こういう取組みをしたい、ないしは、まだ提携先はないのだけれど、今、自分の地域にこんな資源がある、空き家はこんなにある、いろんなところに防災訓練ができる場所がある、地域の魅力があるということを今勉強しておきたい。また、自治体がそういう方と一緒になって、市町村が対象なのですが、地域のことを知っておくための勉強、準備費用として20万円。これも(補助率)10/10です。ですから、いろんな人に集まっていただいたり、活動する、調べる費用として2段階の募集を今回してみたいと思っております。
災害は明日起こるかもしれませんので、せっかくこうした防災の意識が高まっている時に、今度は外の人も一緒に考えるような、そんな計画ができたらと。実はこの話は既に中部圏知事会議の方で話をしてあります。既に三重県、そして愛知県も含めてお話をしておりますので、まず岐阜県の方でこういう準備がありますよと言う上で、こうした取組みをしたいと思っております。
司会
それでは、この件に関しまして、ご質問をお受けいたします。
記者
今回は市町村が対象ですか。
知事
市町村が対象です。学校が対象になりますから、市町村の教育委員会でやっていただくのが良いかなと思っています。まずはですね。
記者
知事会でも話されたというのは、他県も巻き込んでやっていきたいということでしょうか。
知事
もちろん。相手があることなので、三重県は既に防災部局の方に話をしていただいていている。ただ、小中学校はほとんど市町村(所管)になるものですから。もう一段、クッションが入ると思いますので、まずは岐阜県の方でその準備をしていくと。その上で今度は自治体を通して、既に連携があったり、これから提携しようというとか探すということになると思いますので、あるところはもう既にいくつかやりたいところがありますので、そこは考えてくださいと。これからというところは県が応援して、間に入って提携もしたり、町ぐるみの提携でなくても、このプログラムだけの連携でも良いので、これから進めていきたいと思っています。
記者
子ども達に、ふるさとと感じてもらいたいということの狙いは何でしょうか。
知事
今、本当に人口減少の中で、子ども達も減るということで、いきなり子どもが増えるというよりは、いわゆる今回の骨太(の方針)にも出ているように、交流人口を増やしていく。ただ来てくださいという話だと、観光地だけの話になるのですが、そうではなくて、ふるさとを知ってもらう。それによって子ども達の交流の機会を増やしていくということ、そしてもう1つ、実は15年前の商工労働部長の時に東日本大震災を経験して、一番最初に福島県の被災者の受け入れをこの県でやりました。その時、驚いたことに、福島も含めて数百名の方に岐阜県に避難してもらったのですが、ほとんど飛騨高山でした。美濃地方は確か各務原かどこかの2件ぐらいしかなくて。「何で飛騨高山なのですか。」と聞いたら、「知っているから。」と。逆に美濃に来た2件は、「何でですか。」(と聞いたら)「親戚がいるから。」と。つまり、人は知らない土地には避難できないということをその時、非常に勉強させていただきました。なので、例えば南海トラフ(地震)が起きた時に、「岐阜県があるから行きましょう。」と言っても、「岐阜県のどこに行くんですか。」となる。要するに、災害が起きてから考えるのではなくて、今から自分達のふるさとを2つ持っておけば、何かあった時には、例えば「美濃市のあそこに行っていたよね。あそこに行けば助けてくれる。」「あそこに行けば知り合いがいる。」と。そして、「自分達で一緒に作った畑がある。」と。「あの時に宿泊させてもらった空き家がある。」と、知っているかどうかによって全く違う。迅速に対応できるし、不安なく、安心して避難してきてくださいと、受け入れる方も誰が来るか分からないのではなくて、実は毎年来ていたあの子達が来るんだよねと。その子達の、例えば食事は地域のおじいちゃん、おばあちゃん達が面倒見てくれるということで、彼らにとってはふるさとが2つ。逆に岐阜の子達にとってみると、海がない県ですから、海の近くにいて海の体験もする。まさに子ども達の出会いの場を増やすと同時に、交流人口を増やしていく。それが防災という形で、観光地でしかできないわけではなくて、どんな地域でもできるということで、こうした取組みを始めたということです。
記者
県として補助金を出すとなると、三重県、愛知県それぞれの県が補助金を出すことになると思いますが、そのあたりの調整はどうするのでしょうか。
知事
これからまさにやっていこうと思っていて、最初の案では全部丸ごとをやってしまうかというのもあったのですが、まずは岐阜県でできることを準備するということに集中しようと。当然三重県にしても愛知県にしても、うちはこういうことができるよと、こういうプログラムありますよというのを、岐阜県の提案を見ながら、考えてやることになると思いますので、そういう意味では、防災オンリーではなく、防災も含めて楽しく交流することが大事かなと。その中でいろんなプログラムもあると思いますので、そこはまた県が間に入って、調整していきたいと思っています。
記者
愛知県と三重県とでまずはやっていくということでしょうか。
知事
実は静岡県知事とも話をしていて、「浜松の方は来ますか。」と。長野県知事もいらっしゃったので、「そっちは長野県で面倒見ますか。」みたいな話もちょっとしていていました。ただ、そのモデルになるのを、まず岐阜県で始めてみますという話をしています。
記者
長野県の話も出ましたが、基本的には海に面している県との交流ということですか。山の方の県との交流もあるのでしょうか。
知事
(山の県との交流も)あっても良いと思ってます。南海トラフということを意識してスタートした方が、議論がしやすいかなと。三重県も始めから防災部局に話を持っていっていますので。ただ災害は南海トラフだけでありません。場合によっては山と山、長野県でもあるのですが、何を交流しているのか分からなくなってしまいますので、まずは分かりやすく、海と山ということで交流を始めたらどうかということです。まずはキックオフということです。
司会
他の2項目について、知事、お願いします。
知事
3番目ですが、今度はスタートアップについて発表させていただきます。「ぎふスタートアップ支援コンソーシアム『ぎふスタートアップカンファレンス2025』」を開催します。これは、いわゆるベンチャーというか、新しく起業されるという方々を応援する、産学金官と最近は言うそうですが、金融機関も一緒になってスタートアップの応援をしようというものです。日時は、7月18日金曜日午後3時から午後4時半で、商工会議所の大ホールで行います。ここは、コンソーシアムの会長で、商工会議所連合会の会長である村瀬さん、岐阜大学の吉田学長さんと私、そしてコンソーシアムの会員とか関心のある方々、約100名ということで考えております。ここで行われることは、スタートアップ企業の認定式、そして認定者のビジネスプレゼンテーションとパネルディスカッションで、お話をしていきたいと思っています。テーマは「岐阜発スタートアップが起こすイノベーション~経済を強くし、人やモノが集まる岐阜県を創るためには~」ということで、実際にスタートアップとして活躍しておられる方々とお話をして、そして私も議論に入ります。ご存知の方は少ないと思いますが、私は国のベンチャー政策を最初にやったメンバーの一人であります。ちょうど第3次ベンチャーブームの店頭市場改革だとか、マザーズを作ったメンバーであります。ちょうど(ソフトバンクグループ株式会社代表取締役会長兼社長)孫さんが、それほど有名でなくてと言っては怒られますが、そしてちょうどその頃、インターネットでビジネスをやりたいけど相談に乗ってくださいと言ってきたのがあの(楽天グループ株式会社代表取締役会長兼社長)三木谷さんです。まさにあの頃に、ベンチャーということをやっていた、その時の経験も踏まえて、何が今スタートアップに必要なのか、例えばお金だけではない、私自身もいろんなたくさんのベンチャーとお付き合いしてきましたし、それからコンテストもたくさんやってきました。そんな中で、この岐阜ならではの課題だとかそういったことを、ぜひ皆さんと議論する中で、これからチャレンジしようという方々へのヒント、それからもっと大事なのは、彼らを応援する人達の心構えです。何が当たるかどうか、よく目利きがいれば当たるみたいなことを言いますが、そんなことは絶対ないです。それをどうやって育っていくのかというノウハウが結構大事だと思いますので、そういったことについて、皆さんに発信できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
では、最後の項目も続けていきます。4つ目ですが、ねんりんピックでのモーニングプロジェクトをやりたいと思っています。モーニングというのは喫茶店のモーニングです。これは、スタンプラリー、結構面白いと言うか、実は健康長寿社会を考える上で、すごく大事な取組みになりますので、お手元にいっぱいパンフレットがあるので、何でこんなにたくさんあるんだと思われるかもしれないので、一つずつしっかり説明をしていきたいと思っています。
まずは、このきっかけとなりますねんりんピックが、今年、岐阜県で開催されます。1万人を超えるお年寄りの方々が、全国からこの岐阜県に来られて、基本的にはスポーツ、レクリエーションをされるのですが、それだけで終わってしまったのではもったいない。特に、元(経済産業省)ヘルスケア産業課長として、高齢者の方の健康づくりにはやはり美味しいものを食べて、ちゃんと運動して、そしてワクワクする、この3つです。栄養と運動とメンタル、これが揃うことによって免疫力が高まる。それこそが、これからの健康上、社会のキーであるということを、国の政策としてずっとやってきた人間なのですが、それを形にしたというのが、今回のねんりんピックにおけるモーニングプロジェクト、「栄養のワクワク版」になります。
まず1つ目がスタンプラリーです。何でモーニングかというと、もともと薬剤師会の方々が、お年寄りの方々を健康にするための取組みをしたいと。最初は薬局だとか、そういうところにお年寄りに来ていただいて、そこで健康アドバイスをしたいという相談を受けたのですが、なかなか薬局に通っていただくお年寄りは少ないということから、むしろお年寄りが集まっておられるところに行ってはどうかということで、そこで健康アドバイスをしたらどうかということで、昨年、そんなプロジェクトをやっていました。これは大当たりでありました。喫茶店に通っておられるお年寄りの方々、毎朝、家から出て、喫茶店でほとんどランチのようなモーニングを食べながら、1、2時間みんなで談笑する。これは健康づくりには完璧だということでありまして、一部の方から、せっかくねんりんピックがあるので、できるだけ大きく広げる、このモーニング文化を定着させることによって、健康づくりのキーステーションにできないかということで、まずは知ってもらうということでスタンプラリーをやります。7月1日から12月19日まで、結構長期間にわたります。ここで、2店舗以上を回っていただくということが原則なのですが、スタンプ5個で一口応募できます。2,000円分の商品券(の応募)ができます。10個貯まると、5,000円分の商品券の応募ができますよということで、毎月抽選をします。まずはモーニングを食べてもらおうというスタンプラリーがあります。
その次に、「あの店はどうだった。」、「この店は。」と、必ずそういう話になるので、モーニングコンテストをやろうじゃないかということです。これも喫茶組合の皆さんと色々相談させていただいて、もちろん「うちはオリジナルだよ。」とかあるのですが、あまりにもデコボコがあるともったいないので、まずワンコインで、500円以下のところで、「うちはこんなのがあるよ。」というところで、コンテストをやろうと。「いやいや、うちはもうちょっとちゃんとしたやつ出したいんで。」ということで、1,000円以下のところと2段階に分けてコンテストをやりたいということで、今、出店参加者の募集をしています。実は自然体でもすでに百何十店も集まっていますが、せっかくなので、いや知っていたら入りたかったという喫茶店さんもたくさんあるので、是非皆さんにこの宣伝をお願いしたいなと思っております。そうすると、岐阜の喫茶店はどこへ行っても美味しいものが食べられるということが定着するための応援として、これをやりたいと思っております。そうすると、誰が選ぶのという話になるので、審査員も募集します。これは実際に食べて、審査してもらう人を選びたいと思っておりますので、時間感覚的には、まずスタンプラリーで知ってもらおうと。それをやっている間にコンテストをやるので、まずお店を募集します。その次に審査員を募集しますということで、最終的には審査を9月14日に行って決めます。
何でこのタイミングなのかというと、この後に、いよいよねんりんピックで1万人の方々が岐阜県に集まって来られるので、その時にここで賞を取ったところを表彰すると同時に、岐阜駅だとか人が集まるところでこのモーニングを出すという、そんなキャンペーンもやりたいと思っております。ですから、全国から来たお年寄りの方々が、一応(期間が)4日間なものですから、何日か泊まられると。もちろんホテルで食事をされても結構ですし、そればかりではなく、近くの喫茶店に行ったら(モーニングが)食べられるねと。では、その人達に何かメリットがあるのかというと、岐阜を味わう「ワクワクパスポート」を配る予定です。これは500円分の、割引の店舗ごとの特典をまとめた冊子で、2万冊作ろうと思っております。これを岐阜県に来ていただいた方々にお配りをして、是非近くの喫茶店に行ってみて使ってみてくださいというクーポンを作りたいと思っております。そうすると、単に(岐阜県へ)来て、スポーツやって終わりということではなくて、食べるという文化、食べながらみんなと談笑すると、まさにこのモーニングを使って健康なまちづくり、病気になってから治すのではなくて、気づかないうちに健康になってしまうと、そういったものを実現していきたいと思っております。「何で喫茶店なの。」と思われる方があるかもしれませんが、将来的には喫茶店が地域のコミュニティステーションになってもらえるとありがたいと。これからどうしても一人暮らしの方が増えていきますから、一人暮らしの方は、家に閉じこもりがちになってしまいます。食事もちゃんと取らないまま、フレイルと言って、体が弱くなるということが知られています。なので、「かかりつけ喫茶店」という言い方をしておきますが、毎日朝、まずは起きて、家から出て、喫茶店で食事をして、皆と談笑するというのを日課にしてやるようになる。何のためかというと、安否確認ができるのです。今、いろいろ一人暮らしの方がどうなのかということを郵便局の方にご協力いただいていろいろやっていますが、逆にそういう方々が毎日来ていただける場所があれば、「最近あそこのおばあちゃん見ないよね、ちょっと心配だね。」ということが分かるわけです。まさに地域力、地域の方々は、意識した安否確認ではなく、普段の生活の中で安否確認ができる。特にお年寄りの場合、実は昨年やったプロジェクトでよくわかったのは、毎日喫茶店に来ていただいているお年寄りですら、栄養が全然足りていないということです。糖分もタンパク質も全然足りていませんでした。逆に、塩分と脂質が多く、あれあれというのがありましたし、実際に栄養素で見ても、カリウムもカルシウムもビタミンCも足りないです。そうしたことが明確に、昨年やったトライアルで分かっています。それもあって、メニューそのものを工夫していただきながら、楽しく健康になってしまう、そんな流れを、まさにねんりんピックという機会に、岐阜県から全国にこうした文化を発信できると良いかなということで、今回、発信をするということであります。是非報道の皆さんにも発信していただいて、この国を健康にしていくお手伝いをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
記者
県として、モーニングを盛り上げる施策を実施するのは初めてですか。
知事
そうですね。多分初めてでしょうね。岐阜市は(喫茶代支出額が)日本一だということで、いろいろモーニングを(PRする)ということだったのですが、モーニングを使って何かをするというのは多分初めてだと思います。
記者
ねんりんピックがきっかけということですが、スタンプラリーは年齢問わず誰でも参加できるものでしょうか。
知事
まずベースとなるのは、喫茶店のモーニング文化を広げようということですから、年齢問いません。
記者
県内外問わずということでしょうか。
知事
お店は県内であって欲しいですが、参加する人はどなたでも結構でございます。
記者
喫茶店については、今おっしゃったように、県内のお店を募集するということでしょうか。
知事
今募集しています。一宮から来たらどうかというと、今回はパス(対象外)ということです。県内の喫茶店ということです。
記者
現在、もう100以上の喫茶店から応募が来ているのですか。
知事
県の喫茶組合と話をして、やりたいなというところは、今自然体でそれぐらい(100以上)もう手が上がってきているので、ただ、それは我々とコミュニケーションを取っているところだけなので、全県的にこれから募集をかけるということです。
記者
県内にどれくらいお店があるのでしょうか。
知事
1,600店くらいです。もう調べはついております。
記者
スタートアップの件なのですが、先日(愛知県の)「STATION Ai」を視察されたかと思うのですが、やはり東海圏でスタートアップ、あるいはベンチャーというのは、岐阜県も含めて、今までそんなにそういった印象はない地域かなと思うのですが、その辺り今課題に感じておられることがあったら教えてください。
知事
先立って私も、中部圏知事会議で視察をさせていただきました。本当にさすが愛知県で、素晴らしい施設ですし、インキュベーションセンターもあります。ただ、実はこれ、先々代の知事の梶原さんが結構力を入れていたんです。ソフトピアができた時に、各務原の方にまたそういった施設を作ったのですが、その時、私は国のベンチャー担当として少し関わったことがありまして、その時の経験からすると、あのような施設は大事です。大事なのですが、逆にそこからビジネスに展開するには、もう一つハードルがあります。そこをしっかり応援していくということが大事で、何かと言うと、資金と居場所はあっても、やはり取引先に繋がっていくということは結構難しいということはもう経験しています。ですから、この間の愛知県の(STATION Ai)も素晴らしいのですが、中でも特に素晴らしいのは、トヨタさんをはじめとして既存企業も入っているということです。これがある意味、繋がると良いなと思っています。ただ、居るから成功するかというと別問題です。特に、中部地域と言った方が良いですが、ものづくりが盛んな県であるが故に、そうしたスタートアップは、むしろ企業の中で行われてくるというのが基本だったのですが、今大企業がどんどんどんどんイノベーションということがやりにくくなっている。これは、世界的に見てもそうなのですが、そんな中で新しいチャレンジは大企業がお金をかけて取り組むというよりは、やはり小回りの利くところが、いろんなアイデアを出すというところに世界全体がシフトしていますので、この中部地域においても、そういったものが大事ということになろうかなと思っています。
記者
その中でも、岐阜県として、既に住んでいる人にスタートアップの意欲を起こさせる、あるいは起業家を呼び込むところが課題になってくるかなと思うのですが、その辺りの見解はいかがですか。
知事
もう一つ今申し上げましたソフトピアというのが、まさに梶原さんの時に、繊維の次の産業を考えるということで、情報だということで始められたものです。これは素晴らしい施設で、なかなか課題はあったのですが、実は私、商工労働部長の時にその担当になって、やや下火感があったのですが、驚く勿れ、東日本大震災の時に、関東方面の企業が仕事ができなくなったので助けてほしいという話がありました。その時にもう無償で良いから使ってねと言ったら、全国からIT関係の方々が来られて、その時に、忘れもしない、震災から確か3日目ぐらいの金曜日の夜に(そうした話が)あって「良いんじゃない。」と言ったら、一気に全国にそれがネットで流れて、関東の方が来られて、まさに余震で本当に大変だった時に、「大垣駅に着いたら片頭痛が消えました。」と。またネットで流していただいて、(ソフトピアが)満杯になりました。何が起きたかと言うと、せっかく集まっているので、週に1回ぐらい皆で議論しようということで、水曜日の夜に集まってサロンをやりました。実はその中で、今の「ポケモンGO」の心臓部になるような、仮想現実だとか、「フィンガーピアノ(アプリ)」だとか、それは少し前ですが、いろんなアプリがそこの場で出てきたりしました。だからまさに、スタートアップで大事なのは、集まって議論をする、そういう場を提供するということ、何が当たるかどうかというのは、予めはもちろん分かりません。ただ、今のまま企業さんお任せの新規事業ではなくて、やはりこの岐阜の地においても、若い人達がやってみようと思っていただけるような、その空間を、環境を作ることは大事で、愛知県のように立派な施設を作るアプローチもあれば、これから我々がやるように、まずはいろんな人が集まる、先輩やそういった方の話を聞きながら、何が必要かを議論すると、そんなことも大事かなと思っています。
記者
昨日の知事日程実績なのですが、予定が午後4時から始まっているのですか、午前中と午後の早い時間はどのようにして過ごされたのですか。
知事
一部報道もしていただきましたが、岐阜県の偉人である栄叡大師の顕彰法要がありまして、微妙ではあったのですが、一応法要なので、宗教的なことになるといけないということで、公務ではなくて、政務ということもないのですが、行ってきました。(美濃加茂市の)伊深にある正眼寺さんで、朝からずっと午後まで(参加していました)。あともう一つは、大学の授業をやっていたものですから、それで公務として報告させていただいたのは4時からということになります。
記者
「ぎふモーニングプロジェクト」なのですが、こちらの事業費はいくらぐらいなのかということと、ねんりんピック岐阜を契機とした県民運動だということですが、来年以降とか、長期的に続けていくご予定があるのかどうか、その辺りを教えてください。
観光文化スポーツ部
事業費は、精査中ですが、今のところ約2,300万円くらいです。
知事
実は医療関係のプロジェクトはもう一桁上の事業を国でやっているのですが、多分それを遥かに上回る効果があるかなと期待をしております。その流れで2つ目のご質問にお答えをすると、まずは今回広げるということで、プロジェクトをやります。実は昨年、既に社会政策課題研究所のやっていたプロジェクトがあって、その中では先ほど申し上げたように、明らかに栄養が足りないということが分かっていますので、今回はまず広げるという中で、改めて健康福祉部の方で検討を始めておりますが、ここでどういうデータを取っていくのかと、それによって次の施策に繋げていくような展開をしたいと思っておりますので、今回、まずは広げた上で、来年以降ももちろん、さらに医療的なというか、そうしたデータも加えながら、大学とも連携をしながら、前申し上げましたように、この間は名古屋大学とやりましたが、今度東京大学も含めてフレイルの国際標準を作っていくと、そうしたプロジェクトにも繋げていきたいと思っています。
記者
6月4日に、厚生労働省の人口動態統計で、岐阜県の昨年生まれた子どもの数が1万人を割り込んだということと、あと合計特殊出生率が岐阜県は1.27で、こちらも過去最低になったというデータがあります。こちらについてどう受け止められて、また県として新たに考えているような施策とかがございましたら教えてください。
知事
これは全国的な傾向ではあるのですが、以前も申し上げましたように、これは不可避なのかというと、多分そうではないだろうと。昨年、県であった調査で、今この岐阜県に住んでいる10代から20代の女性の7割以上は、子どもは2人から3人以上欲しいと答えていただいています。それが実現できていないということが、この数字で表れているということです。そうすると、産みたくない人に産んでくださいと言っているのではなくて、産みたい人が産めなくてこの数字になっているということは、政策の余地は必ずあるだろうと思っています。ただその中で、それが「働いてもらい方改革」なのか、子育てをしやすい環境なのか、お母さんにとっての安心が足りないのか、という問題が一つ。それから長期的に見れば、やはり出会いの場が少ないとか、晩婚化が進んでいるとかある中で、先ほどの交流が即意味があるかどうかは分かりませんが、やはり子どもの頃から多くの人と接している、共同作業をやるという中で、そうした出会いの場をベースから増やしていくと、こうしたものも必要かなと思っていますので、そうしたものも含めて、ちょうど日本の真ん中にある岐阜県ですから、交流人口を増やして、出会いの場を増やして、そして生活しやすい環境の中で、やはり子どもを産んでもらいやすい環境を作れば、少なくとも先ほどの2人から3人以上欲しいと思っている人に産んでいただけるような環境を作れば、この流れは多少変えられると思っています。
記者
「ぎふモーニングプロジェクト」について、江崎知事が知事選当時というか、選挙戦という意味では、その前からずっとおっしゃっていたことだと思うのですが、元々どういったきっかけでこれを発案されたのかをお聞かせください。
知事
私は元々、経済産業省のヘルスケア産業課長の後、厚生労働省の審議官、それから内閣官房の健康医療戦略室の次長をやる中で、やはり高齢社会における健康はどうあるべきかというのを、随分政策の対象としてきました。実際にこの国の高齢者を分析した時に、 100歳近くまで元気な方々の一群がいらっしゃいます。その方々の特徴を見ると、やはり美味しいものを食べて、運動をして、精神的に充実している、まさに免疫細胞を活性化する3条件、これをどう整えるかということに答えがあるだろうということは、もう国に居る頃からここだと確信を持っていました。これを今度は具体的に、こうした地域で実現するとすれば、どうしたら良いのかと。そこはまだ答えはなかったのですが、昨年まさに薬剤師会さんからのご相談の中で、こうしたことができるのではないかということで、喫茶組合さんと話をしたら、二つ返事で是非やりましょうと。今申し上げた3つの条件を整えるということは、全国的には難しいのかもしれませんが、たまたま喫茶店のモーニングというこの文化、これを活用することによって、今の、「美味しい」、「楽しい」、「ワクワク」という3条件を実現することができるのではないかということでした。実は喫茶組合さんに話を持っていた時は、少し半信半疑ではあったのですが、意外に評価が高くて、何でかと聞いたら、何年か前に振り込め詐欺が非常に広がった時に、警察の方から喫茶店に依頼があって、喫茶店に来ているおじいちゃん、おばあちゃん達に話をさせてほしいということがあったのだそうです。その時もまさに半信半疑だったそうですが、集まっているおじいちゃん、おばあちゃんには大変好評であったと。せっかく喫茶店に来ているこの時間に、そうしたことを教えてもらえるのだったらということで、その経験があったので、今回我々が話を持っていたら二つ返事で是非やりましょうということで、このプロジェクトに繋がったということです。
記者
特に健康増進のようなことですと、どちらかというと国単位とかの政策の方が多いのかなと思うのですが、岐阜県がこういうことを実施することのメリット、データを取れるというお話は今ほどありましたが、改めて岐阜県がやることの意義をお聞かせください。
知事
おっしゃる通り、これはもちろん、最終的には国全体のプロジェクトにすべきなのだろうと思うのですが、今申し上げました、「美味しい」、「楽しい」、「ワクワク」が、ほぼ毎日のように提供できる場所は意外に無いです。ですから、当初、薬剤師会さんがご相談に来られたように、お年寄りを何とか毎日か毎週、薬局に来てもらうような仕組みは作れないかというのが、元々の相談でした。それは多分、日本中でも同じことを考えながらほとんど成功してないと思います。逆にこの岐阜県、特に中部地域のモーニングという文化を使うことによって、結果的にではありますが、それが実現しそうだということ。そして岐阜県で成功することができれば、これを全国に広げていくということは可能だと。実は先立って石破総理と話をした時も、これが非常に受けておりまして、頑張って健康になるのではなくて、気が付かないうちに健康になってしまうという仕組みが大事で、それがやはりこのモーニングというもの、多分中部にアドバンテージがあるんだろうと思います。そして今回、ねんりんピックをこの岐阜県で開催することによって、全国のお年寄りがこれを体験するチャンスがあるということで、これは国の政策に展開していくための一つの布石として考えています。
記者
ガソリンの暫定税率について、野党各党が法案を提出して、本日紛糾して委員長の解任まで至ったのですが、改めて暫定税率について、江崎知事のお立場、廃止なのか、存続なのかお聞きできればと思います。
知事
もちろん今、物価高に対するいろんな対策の一つだということで、多分安ければ安いほうが良いというのは当たり前の話ですが、先立てから、10円引き下げるということで、瞬間風速的には少し楽になったというのがあるのですが、いろんな取組みがある中で、どの方法が、同じ税金を使うなら、ないしは税金をまけるなら意味があるのかということの議論だと思うのですが、個人的な意見としてあえて申し上げますが、まずは本当に今、物価高で困っている方にとってはそうした暫定税率の議論も一つあるでしょうと。ただ他方で、岐阜県自体が財政的に苦しいのもありますが、国自体もそんな潤沢ではないので、そうしたとりあえずという政策だけに頼っているのは結構厳しいかなと思っています。
逆に、以前、オイルショックの時に、田中角栄首相は逆の政策をやりまして、高いから下げるという単純な話ではなくて、高い原因となっている生産性というは、今のやり方だとコストが高いのでもっと安くガソリンを提供するような仕組みを考えるという方向に補助金を付けたんです。そうすると、要するに全体が上がっていても、コストを下げることによって、実質的に安くなるという方向を田中角栄さんはとりました。
今はどちらかというと高いから、とりあえずお金を足して下げるみたいになっているので、私も長く政策をやってきた者からすると、それだけで答えを探すと、多分財政的にはあまりにも負担が大きいまま、逆に言うと、産油国その他の餌食になってしまうというのは変ですが、どこまでお金があっても足りない政策になるので、それは一つの案としては分かるけれども、もう少しいろんな仕組みがあっても良いかなと思っています。
記者
先日、石破首相が、自民党の参院選の公約に全国民に2万円を給付して、子どもにはさらに追加でという公約を盛り込むと表明しました。この点について、知事の受け止めをお願いします。
知事
そういう意味では、今のご質問は前の質問とほぼ同じかなと思っています。今、本当に物価が高くて苦しんでおられる方にとっては、一つの救済かなと思うのですが、それは一律で良いかどうかというのに関しては、スピード感と手間暇を考えると、一律の方が、早くやるなら良いのかもしれませんが、今の話、お金の使い道として本当にそれで良いのかということについては一つの工夫があっても良いかなと思いますが、ある意味、一つのやり方かなと思います。
記者
各地の首長から、特に市町村ですが、事務作業が大変なことになるんだというような指摘も出ているかと思いますが、この点について知事はどのようにお考えでしょうか。
知事
それはその通りだと思います。ある意味、急げば急ぐほど事務作業が大変だし、多分、現場でやっている方からすると、この事務作業の手間をかけるんだったら、もうちょっと違う方法があっても良いかなという議論が出てくるのは、それはそれで分からないでもないです。ただ、逆に他に何がありますかと言った時の選択肢があれば、もう一つの議論になるかなと思います。
記者
先ほど来、交流人口、関係人口という言葉が出てきているかなと思います。先日、地方創生2.0の実現に向けた基本構想を政府が決定しました。その中で、関係人口延べ1億人というような数値目標も掲げられたところだと思いますが、この数値目標について、知事がどのように受け止められているか、教えてください。
知事
数値目標はメッセージなので、それは1億人でも良いかなと思いますが、岐阜県としてはもっと増やしても良いかなと思っています。特に何故かというと、国全体で1億人と言っても、何となく皆さんピンとこないと思いますが、岐阜県の場合は日本の真ん中にあるので、それが先ほどのように防災という前提で交流をしておくということ。それから飛騨高山もありますし、それから今すぐということではないですが、リニアができた時に、東京の方々にとって、関東の方々にとって1時間足らずで別世界に来れる。交流人口どころか、まさに2地点居住の場所としては最高の場所になってくる中で、1億人、全部岐阜というつもりはもちろんありませんが、押しなべて1億人というよりは、地域によってはもっと増えても良いかなと思っていますし、岐阜県はそれ以上のことをやりたいと思っています。
記者
そうなると、県としてどれぐらいの関係人口を作りたいという数値目標であったり、そういうものを決めるような構想があったりされますか。
知事
これはおっしゃるとおり、やりようによってはいくらでもできるかなと思っていて、先ほど発表しました、まさに防災という観点で、2つのふるさとを持つ。これは一つ大事な交流人口だと思いますが、そのために今回、(政策オリンピックの)第1.5弾として今から準備をする時に、じゃあこの地域は何人まで受け入れることができるのかということを自治体の方に考えていただく。子ども達が来た時に空き家がどれくらいあって、彼らを支えるためには地域のおじいちゃん、おばあちゃん達はどれくらい協力してくれるのかというのがあって、交流人口というのは弾かれると思いますが、そうしたことをまずしっかりやりたいというのが一つ。あと普通、交流人口というと観光が中心になるので、例えば飛騨高山だとか、今の観光地。それから関ケ原とか、下呂、郡上について、今まで来ておられる観光客をベースに弾くというのが一般的なやり方かもしれませんが、それは本当に一過性のものになるので、できればリピーターというか、そういう意味では二つのふるさとというのは大事かと思っていますが、その中である程度、安定的に滞在型でいらっしゃることは多分、交流人口としてはぴったりだと思いますので、そして、防災の面、交流の面、そして観光の面で、そう遠くない将来にそうした数字が出せると良いかなと思っています。
記者
米の価格高騰の問題に関して、今、政府が価格の引き下げに向けて、いろんな政策を打っているところであるのですが、米の流通の大半を担ってきたJAさんにも問題があるんじゃないかという、そういう指摘も中にはあります。JAさんは農家の方の農業経営を支えてこられた一方で、こうした指摘があるということで、江崎知事も農業に関する政策は力を入れたい分野の一つではあると思うのですが、このJAさんの組織としてのあり方というのを、全然米の問題と関係がなくても良いのですが、どうあるべきかということを教えていただけたらと思います。
知事
JAさんは、この国の農業を支える、いろんな農業技術の普及だとか、農家の方々が設備投資をする時のファイナンスとか、いろんな機能を担ってもらいましたので、まさにこれまでの努力が非常に大きかったなと思っています。
そんな中で今回起きた米の問題、不足すると(米価が)高くなる(こと)、ここは一つのJAさんにとっての新たな展開のきっかけになるかなと思っています。というのは、私は経済産業省におりましたので、こうしたことはあまり珍しいことではないです。要するに商品が足りなくなって、価格が高騰した時に何が起こるかというと、流通のあり方が見直される。つまり、このルートでしかいかないということが安定している時に、不足が起きると必ず価格が跳ね上がります。そうすると今回、小泉農林水産大臣がやったように、新たな流通ルートを作ることによって、今までの流通ルートが改まっていくというプロセスを必ず辿ります。ですから今、そのプロセスの途中だと思っていて、そうなると今度はJAさん自身が今までの役割の中で、今回起きたことに対してどういう対応していくのかというのは、私もしっかり見ていきたいと思っています。
特に今回の小泉さんがやられたことで分かったことは、とにかく消費者が米が足りないと言っている。そして生産者は一生懸命作りたいと言っている。この間にどういう価格帯であれば、お互いに納得できるかということがある中で、JAさんというのはどういう役割をそこで働かせていくのかというのが、これからの議論の中心になっていきます。
普通は逆で、作った人の生活を何とか維持しながら、流通で加工した結果として出てくる値段に対して消費者は買えますか、買えませんか、買えないのであったら、補助金をいくら付けますかという議論で、どちらかというと一方通行の流れの中で補助金で調整してくる、これがある意味、この国が長くやってきた、他の産業でも大体多いのですが、それが普通の市場になってくるプロセスの中で売りたい人、買いたい人の中の間をどう繋げていくかということなので、まさに、それがいよいよ始まったのかなと。その中でどんな機能を果たせるのかというのはこれからだと思います。
記者
減反政策と、それに続く事実上の減反政策と言われる、生産調整。そこの是非について伺ってもよろしいでしょうか。
知事
ある意味、今申し上げました需要と供給の量をどう見るかによって、それをある程度コントロールできるという前提の場合においては、減反政策が合ったと思います。ただ、通常の商品においては、そういうことはしないので、生産の効率化を徹底的に図った上で、それが生産者として納得できる価格になるかというのはマーケットが調整するということになります。
あともう一つ、今、世界的な紛争やエネルギー、食糧需給の問題を考えると、やはり今この国が持っている食糧生産のポテンシャルを、最大限に上げておくというのは大事だと思っています。特に、岐阜県の場合は食料自給率、カロリーベースで26%しかありませんから、その一方でこれだけ膨大な耕作放棄地があるということを考えると、やはり減反でコントロールしているよりも、しっかりとした生産をしていく。ただその時に、今までの生産だとおそらくコスト的に合わないということはもう明らかなので、生産の仕方、流通のさせ方、これまではどちらかというと海外というマーケットは多分考えていなかったと思うので、この国は。国内の消費者だけを見て生産を考えると、今までのやり方も一つの合理性があったかもしれませんが、最終的に日本の米を輸出していくということも考えた時に、まずは生産性をマックスにするというのは、ある意味経済の基本だと思っていますので、そちらの方向に舵が切られるのではないかと思っています。