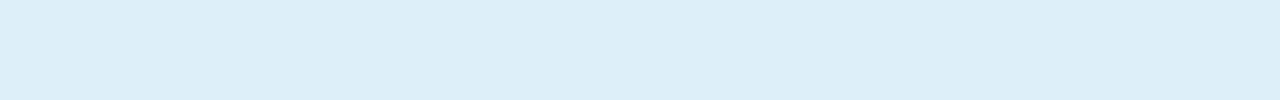本文
知事記者会見録(令和7年4月1日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年4月1日(火曜日)15時00分
司会
ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。
知事お願いいたします。
知事
年度が改まりまして、4月1日ということで、新しい体制が始まりました。今朝ほども、新しく入られる方、本当にフレッシュな方々の前でお話ができて大変光栄でございました。そんな中で、私の方からお手元に配らせていただきましたが、4月1日にもうスタートするということで、私もちょっと感動しながら、政策オリンピックの第1弾ということで、住民参加型の避難訓練と、ニホンザル対策のモデル事業を募集します。議論している中で、実際に今年度直ちに準備をしなければ、これから雨が降ったりとか、災害があったりする場合、それから本当に農作物の被害ということは待ったなしということで、各部が異動があるにも関わらず、一生懸命準備してくれまして、4月1日から募集ができる運びになったところでございます。
お手元の資料をご覧いただきながら説明させていただきます。まず季節に応じた住民参加型の訓練ということですが、特に自治会というものがなかなか成立しにくいという中で、やはり誰にとっても大事なものとして、避難訓練、防災ということをテーマとして挙げた上で、特に今回の目玉は「楽しい」ということです。皆が参加してみたいと思うようなアイデアを是非募集したいということで、お手元の資料の2枚目にカラーのチラシがありますが、直ちに今日から募集を開始して、5月の終わりまでということです。裏のページにありますように、実施要件の中で住民の皆様が楽しく参加できる防災訓練であるということ。そして季節の特色、夏だとか、雨が降る場合、場合によっては冬ということもあろうかと思いますが、それを踏まえた内容として、最初2回、3回以上実施しますかとなりましたが、1回以上ということで、加点ポイントにするかどうかは提案を見ながら考えたいと思っております。そして、やはり何と言っても子どもも参加してほしいということと、そして高齢者の方も参加していただく、本当に地域が互助の精神で助け合うという、その姿を是非お願いしたいなと思っております。それで、市町村と自治会が連携したものであること。そして、1番最後のところにですが、そうは言ってもイメージが湧かないかもしれないので、炊き出しや薪での火起こし、今は火を燃やせない子どもが多いということもあって、飯ごう炊さんをやってはどうかというアイデア。それから、実際に簡易トイレやダンボールベットを作ってみたことがない人も多いので、見たことはあるけど実際に作ってみると。あとは、暑さ対策、寒さ対策を勘案してのお泊り体験をしてみようとか、有り合わせのものでサバイバルクッキングをやってみたらどうかとか、いろんな防災ブースで、いろんな提案があるかもしれないですが、見て回ろうとか。あとは、火消しスピードコンテストとか、たんか作りとか、AEDの使い方も入れたりとか、訓練参加者にグッズをプレゼントしたりとか、魅力をまず感じていただくために、これは単なる例でしかなく、これをやってくださいということではなく、提案を見ながら考えたいと思っておりますし、その中でポイントとしては、これは誰が選ぶのですかという質問が後であろうと思いますが、先回りして言うとアイデアを選ぶ委員会を作って、中立的にやろうと思っていますし、特にその中に、小中高大学生の子どもたちを審査していただく方にも入ってもらおうかなと思っていまして、やはり子どもたちの目で見て、これは楽しいと感じるかどうかというのも審査のポイントになるということで、今回これをスタートしています。いろんなアイデアが出てくることを期待しながら、早速募集開始としたいと思っております。
もう1つがニホンザルですが、これは資料の冒頭にもありますが、イノシシやシカではないのかということですが、イノシシやシカはとりあえず柵で何とかなるという部分があるのですが、サルだけが集団で来たら全くお手上げだし、それこそ1つや2つの農家では対応できないという状況もありますので、皆さんの知恵を絞って考えていただけたらありがたいなということです。特に大事なのは、駆除することが目的なのではなく、一定期間作物を守り切ることが大事でして、たくさん捕りましたとか、そういうことではないということで、動物愛護の観点も踏まえながら、共生社会、まだ彼らの居場所が十分にあるわけではないので、まずは来ないでねということで、それをみんなで協力してやるにはどういう取組みが良いのだろうかということも考えて、知恵を絞っていただけるとありがたいなと思っております。同じく、手元の資料の1番最後のところにイメージとしてなのですが、サルの行動を把握して、集落の手前でちゃんと追い返すことがまず大事かなということと、サルの誘引用のエサをやってとか、大型の檻、これは結構一網打尽型というものがあるのですが、一度それを経験すると怖がってしばらく来ないとか、あとは効果があると言われてて、本当に効果があるかよく分からないのですが、山羊がいるとサルが来ないという説や、いろんなことがあると思うので、そういうことも考えてもらっても良いかなと思います。あとは、光る、動く、しゃべる、追いかける、何だと思うかもしれませんが、最初は効果があるかもしれませんが、学習するとサルは乗り越えてくるので、サルとの知恵比べも含めて、まずはアイデアだけが独り歩きするのではなくて、やってみるということを、どちらもそうなのですが、終わった後に検証してみて、どれくらい効果があったのかも含めて、対応していきたい思っております。
まさに4月1日にふさわしいスタートということで、準備をさせていただきまして、早速、県民の皆さんからのアイデアをいただきたいと思っているところです。なので、バックボードもすごいでしょう。私は何も言ってないですよ。早速、皆さんに(記事を)書いていただいて、発信していただきたいということですので、よろしくお願いいたします。ちなみに、ミナモ(県マスコットキャラクター)は健在ですので、「ミナモはどうなるのですか。」という問い合わせも多いのですが、健在です。この間広告で出させていただいたものも、私の隣にはミナモがいますから、安心してください。私からは以上でございます。
記者
知事がトップダウンで政策を考えていくこともできた中、この2つのことを政策オリンピックの対象にした理由を教えてください。
知事
私も4年間(県内を)回ってきましたので、多分これが答えではないかなというものがないわけではないのですが、誰かに言われたからやりましたということよりも、自分たちで工夫ができる、私も所詮人の話を聞いただけですから、実際にやってみてこうじゃないかというのと、先ほどの山羊の話ではないですが、やってみたいのだけれども、なかなか踏み切れないとか、いろんな話を聞いておりますので、それをまず自らやってみて、自ら改善していくと、そんな経験をしていただきたいということと、この2つを選んだのは今申し上げたように、待ったなしということで、一刻も早くやった方が良いということで、この2つから始めるということです。
記者
委員会を作って政策を選ぶということですが、ニホンザルの方も同じやり方でということでしょうか。
知事
一応、今のところのアイデアですが、サルの生態に詳しい専門家とか、動物愛護の(専門家の)方も入っていただこうと思っていまして、その中で選べたらと思います。
記者
委員会というのは県庁内と外部の方が一緒になったというイメージですか。
知事
そのような感じです。むしろ、外部の方が多いかもしれません。
記者
ニホンザルの方にも、(委員会に)子どもたちは入るのですか。
知事
今のところは入りません。
記者
避難訓練について、(委員会の)子どもたちをどのように選ぶのでしょうか。
知事
これから考えます。アイデアを募集するのにまだ時間がありますので、ゆっくり選びたいですし、場合によっては(訓練内容について)子どもたちが提案してくれるかもしれないです。
記者
「楽しく」ということが避難訓練についてはあるのだと思うのですが、楽しくすることのメリットとか意義とか、その辺りはどのようにお考えですか。
知事
それは大事なところで、何で防災訓練なのかという前に、共助であるためには、自治会が機能していることがすごく大事なことなので、能登半島地震もそうなのですが。ただ、残念ながら、この岐阜県内でも自治会が成立しないとか、ゴミ出しにルールが無くなって、自治会に入っている人ばかりに負担が起きているということはどこでも聞かれていることなのですが、ただそのような人たちであっても、防災という点においては皆が利害が一致するし、その時に、あえて時間を使って休みの日でも参加したくなることが大事だと思っていて、これをきっかけに自治会に参加することも悪くないなということで、「楽しく」ということでハードルを下げるということです。
記者
ある程度、避難訓練について、教育のところも考えていらっしゃるのか、その辺りの考えをお聞かせください。
知事
教育というか、実は子どもたちにも考えてもらいたいなと思っているのは、だいたいの防災訓練だと、どこどこと連絡が取れました、それで終わりということが多いのですが、実際には、どこどこに住んでいるおばあちゃんを連れて来るためにはとか、どこどこの橋が落ちたらどのルートで行かなければいけないということを考えてもらう。既成の防災訓練ではなくて、自分たちのアイデアだとか、特に教育という意味では、火を起こしたことのない子どもたちがすごく多い。実際に、飯ごう炊さんについては、聞いたことはあるけれどということになってしまうので、体験と教育、そして自分たちで考える、そんな防災訓練ができればと思います。
記者
それぞれ自治体からも募るということですが、基本的には選ばれた自治体で実施するということですか。
知事
自治体でも良いですし、自治会でも良いです。町を挙げてやりたいと思っても良いですし、自治体の中のこのチームでとしてやってもらっても、いろいろあっても良いかなと。
記者
ニホンザルのことなのですが、ニホンザルに限定してということも肝なのですか。
知事
サルの種類を限定してというよりは、イノシシやシカではないですということです。
記者
どうしてサルに限定したのですか。
知事
これも先ほど申し上げたように、私も実際に戦っている人間なので分かるのですが、イノシシは大体70cmくらいの柵で止まります。彼らは穴を掘ってくるので、そこさえ塞げばとりあえずは何とかなる。シカの場合は、広い所だと3mくらい飛びますが、ネットを張っておけば何とかなる。サルだけは残念ながら何をやってもダメで、私のところも電気柵をやりましたが、結局3年で全く意味は無くなりましたので、彼らは生活がかかっていますから、命に別状がないと思えば、間違いなく乗り越えてくるので、どうやって効果的に怖いなと思ってもらうか。逆にサルは賢いので、昔言われたのは、1頭を打つと、3年は来ないと、ボス猿が交代するまではあの地域が危ないんだと学習してくれるので、まさに知恵比べの形でやるということです。
記者
政策オリンピックについて、今後も随時と言うか、今年度中にどれくらいのケースを出したいとか、何か考えていることはありますか。
知事
ありがたいことに、こちらがまだ提案していないのに、これを政策オリンピックでやってということが続々と来ていますので、その中でオリンピックにふさわしいものもあったりとか、直接政策にした方が良いものもあったりとか、いくつか腹案はあるのですが、少しこなしたところで提案していきたいと思います。
記者
昨日、内閣府の作業部会の方が、南海トラフ(地震)の被害想定を出されました。岐阜県の場合は死者が100人増えて300人という想定が出ましたが、それについて知事の受け止めを伺います。
知事
こうした被害想定というのはいろんな前提条件があるのですが、より現実に合った形に直していくことが大事だと思っています。特に今回の推計の中で大事なのは、準備している場合としていない場合で、本当に大きな差が出るということです。防災訓練の関連ではありませんが、日頃から準備したことによって相当(結果が)変わるということが示されたことに非常に意義深いと思っています。
記者
今後準備をしていくという観点からも、今回の(政策オリンピックの)防災訓練というのは、その準備の1つという理解で良いですか。
知事
そのとおりです。訓練でできないことは本番では絶対できないと言われているように、いかに訓練をたくさんいろんな形でやっていくか。しかも、それを嫌々やるのではなく、先ほどの段ボールベットについても、いきなり目の前に置かれても、さてどうするんだとなるのが、作ったことがあるのだったら、僕がやっておくよと言ってやってくれたりとか。簡易式トイレについても、このビニールは何だとなる人もいれば、ぱっと作って向こうに置こうかっていうだけでも全く違ってきます。
記者
国会の方でも議論が進んでいる選択的夫婦別姓の件なのですが、先週岐阜市議会の方でも、意見書をめぐって、自民党が提出したものに自民の議員が会派を出てみたいな動きが出てきている中で、知事として、この選択的夫婦別姓制度の導入について、前向きに議論を求めていくのか、むしろ通称、旧姓使用の拡大を進めていくのか、いろんな立場がありますが、知事としてこの制度についてのお考えを伺えたらと思います。
知事
私はすごく大事なテーマだと思いますが、まだ議論が足りていないと思っています。何が足りていないかというと、大人にとってどちらが便利かという議論しかなくて、子どもの視点の議論が全くなされていないということが前から非常に気になっていまして、例えば大人はそれぞれが仕事をしやすいのだけれども、例えば兄弟で苗字が違うとか、その影響がほとんど議論されてないことがむしろ問題だと思っています。ですから、今はどちらかを選べという制度になっているがゆえに起きている話で、昔は、家族で統一(の苗字)だったところが今はどちらでも良いようになっていて、それでもまだ問題だという中で、何の議論をしなければいけないかというと、苗字がばらばらというのは、苗字は英語で言うとファミリーネームと言って、1番の影響を受けるのは多分子どもだと思います。そうすると、むしろそこまで議論するのだったら、例えば夫婦で結婚したら全く新しい苗字をファミリーネームとして決めるとか、むしろそこまでするのなら苗字は要らないのではないかとか、そういう議論はまだ聞いたことがないです。以前、どこかで子どもたちに聞くと、結構反対が多いです。子どもたちが自分のこととして考えた時に、お父さんとお母さんとで苗字が違ったり、兄弟で苗字が違ったらやはり大変だと思います。私もなぜこの点が足りないと思っているかと言うと、小学校の時に、英語の授業で、自分の親の名前を言いましょうという時に、お父さんとお母さんの苗字が違う子がいました。その時に、彼とやり取りをするとものすごく辛そうだなと。私はそれが忘れられなくて、だからこの議論では完全に子どもの視点が抜けているなと。しっかりと議論した上で何を選ぶのか、全く新しい苗字にするのか、それともそもそもファミリーネームでなくなるのだったら苗字なんか要らないのではないかとか、そんな議論をしっかりした上で、どちらかを決めていくにはまだまだ早いかなという気がします。
記者
知事としては、まずはもっと議論を尽くしてからということですか。
知事
特に子どもの視点を入れた議論をもっとしなければいけないと思ってます。
記者
政策オリンピックの件ですが、委員会の構成メンバーの中に知事は入られるのでしょうか。
知事
入らない予定です。
記者
採用されるアイデアの決め方というのは、どのようにされるのでしょうか。
知事
内々にはポイントも決めていて、例えば楽しさを何ポイントで、あとは効果とか、他への広がりやすさとか、参加人数というようなものを点数化した上で、各委員の先生方に採点してもらおうと思っています。
記者
もし採点が同点になった場合、決め方はどのようになるのでしょうか。
知事
その時は皆で決めるか、私が決めることは多分ないと思うので、その時は委員長に決めてもらうとかです。そこはまだやってみないと分からないところです。現時点で決まっていることとしては、しっかり採点基準は作ろうということです。
記者
ただ、同点になった場合の決め方はまだ未定ということでしょうか。
記者
そうです。同点だったら両方採択ということもあるかもしれません。
記者
政策オリンピックについて、選考委員のことですが、人数としてはどれぐらいの規模を考えられていますか。
知事
7,8名から10名弱ぐらいで、子どもたちを増やすとちょっと多いかなと思っていますが、だいたい議論がまとまることができる数ぐらいにしようかなと思っています。
記者
ニホンザル対策も、避難訓練の方も、いずれもということでしょうか。
知事
どちらかと言うと、ニホンザル対策の方が少ないかもしれません。専門家とか、そんなにたくさんにする必要はないのですが、防災訓練の方は、できる限り小中高大学生を入れたいなと思っています。
記者
避難訓練の方なのですが、先ほど知事は飯ごう炊さんが一つ良い(取組み)かもしれないとの話があったと思いますが、最近の事情を見てみると、アルファ化米であるとか、食べるということに関してはそちらの方がよく見かけるなという印象があるのですが、飯ごう炊さんをやることの意義について、知事はどのようにお考えなのでしょうか。
知事
アルファ化米も良いのですが、アルファ化米がなくなったら誰も食べられなくなったりとか、大災害を想定すると、多分1日か2日の話ではないと。そうなった時に、やはり温かいものを食べるとか、本当にいろんなことを考えて、特にこの岐阜県ですから、田舎の方だと普通の家には米があったりするわけです。そうしたものを使えることは結構大事で、例えば都会の方だと備蓄しているのがアルファ化米ということもあるかもしれませんが、多分県内にそれを均てんするよりは、これだけたくさん米とか野菜とか土地があるところなので、そういった今あるものを使うということが結構大事かなと思います。
記者
政策オリンピックの防災訓練の審査をする中に、小中高大学生の子どもたちを入れるということですが、どういう理由なのかというところで、現状、防災訓練をするにあたって、子どもたちの視点が欠けていることかなと思うのですが、具体的にどのような課題を知事として思われていて、だからこそ、子どもを(審査に)入れようという発想になったのかということをお聞かせいただければと思います。
知事
一つのイベント、地域の集まり、一種のお祭りみたいなものの時に、子どもたちが行きたいと思うかどうかは結構大事になりますし、大人の都合で、忙しいから行かないというよりは、子どもたちだけでも自分たちだけでも行きたいというのは、また次につながりますし、その子どもたちはいずれ大人になっていきますから、その時の経験はすごく大事かなと思っているので、あえて子どもと強調しているのはそういうところです。
記者
子どもをきっかけに、そのご両親として大人を巻き込んでいく、一つの歯車と言うか、エンジンとして子どもたちに参加してもらおうということでしょうか。
知事
その観点もあっても良いなと思っていて、夏祭りのように、子どもたちが行きたいから、親もやはり子どもたちだけでは行かせられないから行ってみるというのもあっても良いと思っています。それは、お子さんの年齢にもよるのだろうと思うのですが。あともう1つは、この写真の中にあるように、子どもが目の見えない方の手を引いているように、彼らがある意味非常に重要なプレイヤーであるということを理解してもらうというか、守られるだけの立場ではなくて、自分たちがそこで役に立つんだということも考えてもらえると、そんなことも期待しています。
記者
今回のそれぞれの政策オリンピックでの補助金の対象団体の数は、何団体を想定されていますか。
知事
防災訓練の方は、1件200万円を上限として、3~4団体あたりで、金額によって少し増えても良いかなと思っていますが、一応、補助率10分の10でやろうと思っています。ニホンザルの方も、もちろん金額次第ではありますが、こちらも1件300万円を上限にしながら、やはり3~4件のところかなと思っています。
記者
改めて、県民の皆さんには、どのように応募してほしいかとか、自治会であるとか、呼びかけがあったら教えていただきたいです。
知事
まず、今日この場がすごく大事な呼びかけかなと思っておりまして、まさに、そのためにアイデア募集のパンフレットまで作って参りました。この後は自治体を通じて、市町村から広報したり、これを市町村でも広げてもらうとより効果的かなと思っています。
記者
なかなかアイデアを競うというと、ためらう人、私のアイデアは本当に大丈夫なのかという感じで自信のない方もいらっしゃるかと思うのですが、そういう意味では結構気軽に応募してもらいたいという感じなのでしょうか。
知事
今回は、どちらかというと個人のアイデアというよりは、自治会だとか市町村がベースになっています。どちらかというと、こういうのを見るとやってみようかというのが、ある意味組織の基本だと思いますので、ただ、逆にこのチャンスがあるのにやらないというのはどうかなと。よく言われるのは、補助率があるからやりませんというのが多いのですが、(補助率は)10分の10ですから、お金が無いからできないですと言う人は、まず是非参加してもらえるとありがたいなと思います。
記者
以前、可児市のこども食堂を取材することがありまして、その団体の理事長が、運営するにあたって、資金や支援の面で、継続的に運用していくのは困難という話を聞いたのですが、具体的に知事として、今後こども食堂の存在意義や、どのような形で向き合っていきたいか、子どもとどのように付き合っていくのかについてご意見をお願いします。
知事
とても大事な視点で、本当に子ども食堂は、これからの子どもたちもそうなのですが、地域ぐるみで、子ども食堂はもともとはなかなか食事を十分に取れない子どもたちのために始まってはいるのですが、私は初期の頃に関わったのですが、家が貧しいからどうぞと言ったら誰も来ないんです。結局、誰でも良いから(来てください)でないと、子ども食堂は成り立たないということが経験でも分かりましたし、意外に来るのは生活が(苦しい)というよりは、孤食の子だったり、親と一緒に食事をしていない子が来たりとか、今そこからさらに発展して、地域食堂になったりしています。これは新しいコミュニティの形かなと思っていますので、ご指摘の点で確かに財政的に苦しいというのはあります。ある意味、食事を提供するという点においては、食材をどう調達するのか。今、JAさんも含めて、お米は寄付ということになっていますが、この米高の中で結構大変なことになってますが、そういう時に誰がサポートするのか。行政なのか地域なのか、いろんなやり方もありますし、先ほど申し上げたように、地域食堂になってくると、別に朝とは限らないので、地域のお年寄りの方々が料理をしたりとか、地域で穫れた野菜を持ってきたりとか、これからいろんなバリエーションができてくると思っていますし、そこで、中学生、高校生の子たちが小学生に宿題を教えてあげたりとか、特に経験で分かっているのは、シングルマザーというか、一人で子育て中のお母さんが実は一番助かると言われていて、それは子どもたちがご飯を食べてというよりは、そういうお母さん同士がコミュニケーションをする、同じ事情のあるお母さんたちが、子どもは誰かが面倒を見たり、食事をしている間に話ができるというように、どんどん進化しています。そうしたものを、これは地域によって特徴があると思いますが、それはしっかり行政としても応援していく一つのテーマにしたいと思っています。
記者
政策オリンピックで、委員会の方に知事は入らないということで、最終的に知事のところにその政策が上がってきた時に、知事の方で差し戻すことはあるのか無いのか、それも決めるのか確認したいです。
知事
オリンピックですから、選手を差し戻すことは普通しないと思っています。むしろ大事なのは、私が良いか悪いか決めるというよりは、最終的に効果がどうだったのか。特に今まで予算を付けっぱなしとか、やりっぱなしが多いのですが、大事なのはここにも書いてあるように、最後の3月にどうだったのかと。例えば、よくあるように、成功しなかったら金返せとかそんなことを言うつもりはないのですが、それがダメだったらダメだということをちゃんと伝えるということも大事な成果だと思っています。なので、私が良いとか悪いとか判断するよりは、皆さんが良いと思ったものをまずはやってみることが大事かなと思っています。
記者
効果検証というところで、ニホンザルの方は何となく分かる、例えば今まで食い荒らされていたところとか、目に見えて被害が分かるのですが、避難訓練の場合の効果検証は、例えば今までの訓練だと、参加人数が一定水準になったら、それは効果があったとみなすものなのか、どういうところにこの避難訓練の効果をもたらせるのかということをどう考えるか教えてください。
知事
考えているのは、まず参加者がもちろん多いこと。やる気のある人だけに来てもらっても多分訓練にならないので、できるだけ対象とするエリアの参加人数が多いということが一つ。あともう一つ、効果検証で、子どもたちも含めて、もう1回やりたいか、次やったら来ますかというのは必ずアンケートでやろうと思っていて、もういいやと思うのか、それとも先ほど季節に応じたと言いましたが、夏バージョンをやったら次は冬バージョンをやりたいとか、発展していく可能性があるかどうかというのが効果の一つのメルクマークになると思います。
記者
ニホンザルと防災訓練のそれぞれの問い合わせ先が、農政部と危機管理部の方になっていて、未来創成局が政策オリンピックなどを取りまとめるとご説明されていたので、問い合わせ先が未来創成局ではないのはどういうフローなのかということと、未来創成局はどう関わっていくのかを教えてください。
知事
基本的に、政策を実施するのはそれぞれの部局です。未来創成局は、政策オリンピックのやり方、例えば先ほどの審査員の決め方とか、あとはどんな分野が政策オリンピックに馴染むのか馴染まないのか。やり方、規模、支援の仕方というベースを未来創成局で作ってもらったら、例えば未来創成局の人がサル対策はできませんので、実際には農政部の方でそれを受けて、だったらこういうふうにやろうかとか、まさに防災訓練だったら、危機管理部の十八番ですから。ただ、どちらも今までやったことない取組みなので、そこは連携してやっていくと。逆に言うと、先程の評価の仕方を今度は逆に未来創成局で抽出して、次やる時に、こういう観点で政策オリンピックをやるとか、そういったことを考えていきたいと思っています。
記者
政策オリンピックは今後も10の目標の実現に向けてやっていくということで、次はこれをやりたいというのが既にあれば伺いたいです。
知事
あるのですが、それを言うとそればかりニュースになりそうなので。ちょっと面白いものをいくつか考えています。
記者
どこら辺の分野でというのがあれば教えてください。
知事
ちょっとヒントだけ言うと、教育の分野でやりたいなと。