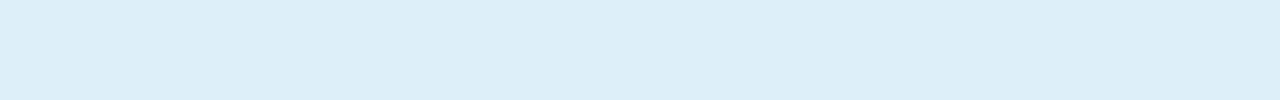本文
知事記者会見録(令和7年3月25日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年3月25日(火曜日)15時00分
司会
ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。
知事お願いいたします。
知事
まず私の方から、2点ご報告させていただきます。
お手元に準備されているかと思いますが、いよいよ間もなく始まります、来月23日からですが、「都市緑化ぎふフェア」のパンフレットでございます。私もパンフレットを見てワクワクするなというか、本当に岐阜って良いものがたくさんあるなという感じがしております。めくっていただきますと、ぎふワールド・ローズガーデンの素晴らしい写真から始まりまして、6つの県内の公園、ぎふ清流里山公園もそうですし、養老公園もあります。そして世界淡水魚園、おかげ様で非常に人気な所です。そして百年公園は今後いろんな使い方があるかなと思います。そして各務原公園、ここも本当に自然豊かな場所です。あと飛騨の方は特に公園ということではないのですが、飛騨地域の大自然ということで非常に素晴らしい所です。都市緑化ということで、都市なのかというのもあるかもしれませんが、人が住むところの中で自然と共生するというテーマの取組みとしては非常に素晴らしいものになっているのではと思っています。期間中にいろんなイベントを(開催し、)200を超えるプログラムがございます。そして70のイベントの中から注目されるべきものをピックアップした形で作っております。また、地域ごとにより詳しいものもこれから作ります。そして、デジタル版も用意しておりますので、本当に広く多くの方にこのフェアに参加していただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
もう1つですが、いよいよ年度が改まるにあたり、人事異動ということでございます。皆さん、お手元に人事異動の概要があろうかと思いますので、これに沿いまして紹介させていただきます。4月1日付けで、今回は2,202人の異動ということになります。全職員の44.8%ということで、半分近くの方に新しい場所で活躍していただくということでございます。ポイントとして書かせていただきましたが、「安心」と「ワクワク」、「人やモノが集まる岐阜県」を作るために、存分に力を発揮していただきたいと思っております。それからお手元の資料にもありますように、今回新しい部局に参加していただこうということで、まずは未来創成局、そして未来創成課ということで、これは国の制度に対して地方の方からいろんな政策提案をする、問題点を指摘するということで、制度や法律に長けた方々、更にその分野に強い方に参加をいただくということ、そして今回私の大きなテーマですが、子どもや女性の活躍ということで、子ども・女性局を部に昇格させて、そこで活躍していただくということ。更には観光文化スポーツ部ということで、文化、スポーツに加えて観光を発信するということで、当分野の経験者の方々に参加をしていただくということです。あともう1つは、まちづくりという観点で、今回理事というポストを新設いたします。特に岐阜県の場合は、中心市街地、ここをしっかりとしたものにしていくということ、当然それぞれの市町村の取組みがあるのですが、市町村を超えたより広い範囲でまちづくりの姿を描くということで、理事のポストを作り、そして特に関連の強い都市建築部長を兼務するという形で本格的にまちづくりの絵を描いていくと。市町村との関係もありますので、それと県庁内のいくつかの部を横断することもありますので、理事というポストを新たに新設した上で、そういった取組みをしていただきたいと思っています。
それから、次のページに被災地の復興支援のための派遣ということで、石川県、珠洲市、及び能登町に新たに増員をして、10名の方に活躍をしていただきたいと思っています。特に今回新たに、史学、歴史、文化といったもの、文化財についても知見のある方に行っていただいて、応援すると同時に我々も学ばせていただくということ。そして土木も当然ですが、インフラその他についても(派遣)させていただくということで考えております。
それから、県内市町村との人事交流ということで、それぞれいろんなテーマがある中で、今回3人増やして1人(派遣期間が)終わりとありますので、計2名増員になるのですが、教育という観点で山県市、瑞穂市の場合はまちづくりで、庁舎移転というテーマもあり、より広い観点からということで。池田町の場合は災害対応ということもあって、今回3名の方に新規で行っていただくことにしております。
あと、国との関係の人事交流でありますが、省庁では約20名ということで、それぞれテーマを持ちながら行っていただくということでございます。
それから、他県で災害派遣以外ということですが、お隣の富山県、愛知県、そして関係の深い鹿児島県ということで、ここは引き続き行っていただいております。
あと、独立行政法人等で県外へ7名ということで、資料に書いてあるとおりでございます。
そして、やはり大事なところでありますが、女性の活躍ということで、女性職員の登用ということですが、特にこれまで女性が配置されていなかったポストにも女性の活躍の場をということで、県土整備部次長に初めて女性職員を配置させていただくということ、そして西濃地域に初めて部長級の女性所属長ということで、全体を見るというポストについていただくと。東濃地域には、次長級で初めての所属長として県税事務所長という形でありますし、飛騨地域に初めて次長級の所属長として保健所長ということで、その組織のトップとして見ていただくことをお願いしているところでございます。参考に書いてありますが、女性の管理職登用率が過去最高の24%ということですし、以下課長補佐・係長級も29%で最高ということです。目標にあと1%ずつ足りないので、更にこれから力を入れていきたいと思っております。ただ、数さえ揃えれば良いというわけではありませんので、しっかりそれぞれに力を発揮していただく場所で活躍していただきたいと思っております。
私も着任して2か月でありますが、これまでの経験、それからいろんな方々の話を伺いながら、今回の人事をさせていただくところでございます。その後ろには、それぞれ個別の名前が入っているかと思いますが、私より皆さんの方がこの人かと分かるかもしれませんが、そういった方々の活躍を期待しているということです。私の方からこの2点をご報告申し上げました。
記者
人事異動の件を伺います。異動の規模が全職員の44.8%、 前年度が41.3%なので増えているなと思いますが、割合としても近年、ここ5年、10年で最多ということでしょうか。
知事
突出して(割合が)大きいわけではないですが、割と多いということになります。人数的には平成22年からでは最高になります。割合としては、平成24年に45%ということがありましたので、それに次ぐ規模です。令和5年に、同じく44.8%ということがありましたので、そういう意味では、今まで(近年)の中でも1番大きい規模ということです。
記者
新設部局の中では、未来創成局の中の未来創成課が新たにできる形なのですが、人員配置については以前も3つくらいのチームを設けてという話でしたが、具体的に何人体制で、人員配置とかその役割みたいなものを教えていただけたらと思います。
知事
未来創成局の局長が部長級ということで、局長に着任していただいた下に、全体総括として未来創成課長を置きます。その下に3つのチームを想定していまして、いわゆる働き方を担当するチーム、教育を担当するチーム、農業・林業ということで、地籍調査といったものを担当するのですが、そういった3つのチームに、それぞれの分野に今経験がある、ないしは関心のある方を配置しております。だいたい1チーム3、4名ということです。
記者
理事についてですが、理事というのは部長級でしょうか。
知事
部長級です。特別ミッションを与える時に付けるポストでもあると思います。
記者
位置付けとしては部長級と同じくということでしょうか。
知事
はい、部長と同じ並びです。ただ部を跨ることもありますし、特定の部の中で解決し切れないので、理事というのを加えた形です。
記者
過去に、今言われた理事というような名称はともかく、同様のポストは岐阜県としてありましたでしょうか。
知事
2回ありまして、その時、地域に対して付けたことが2例あります。
総務部
平成18年頃に付けた例があります。
記者
その時はどのような担当だったでしょうか。まちづくりということではなかったですか。
総務部
その当時は(地域の)振興局長に付けておりまして、理事兼振興局長ということで、平成18年4月に2名付けた事例があります。
記者
理事に新たに野崎県土整備部長を充てたというのは、知事としてどのような思いがあっての人選になったのでしょうか。
知事
野崎さんは県土整備部長の前は都市建築部長をやっておられて、今回まちづくりの中でも特に岐阜市、そして岐阜市というより県都である岐阜、加えて言うと、岐阜羽島駅から岐阜駅、更にはその周辺までとなると、一つの市ではないので、ある意味、都市建築プラス県土の両方を経験しておられるということで、彼にこのミッションを託そういうことです。都市建築部だけで閉じるには荷が重いかなということで、一旦(都市建築部へ)戻っていただいた上で理事を付けるということです。
記者
理事の話について、お伺いさせてください。理事というポストについて、最初に知事は新設という表現をされました。
知事
今現在はないのですが、全くの新規というよりは、理事というポストを今回の人事で新設をしてということになります。
記者
部長級は部長級なのですが、部長級の中での位置付け、序列としてはどのようになりますか。
知事
過去の例で言うと、中濃振興局とか岐阜振興局に局長プラス理事という形にしていて、その時も特別なミッションを与えるという形になりますので、上か下かというのはないですが、一つ明確に言えるのは、都市建築部だけでは閉じていない仕事もやらなければいけないので、理事という肩書きを付けたという形です。ミッションに応じてということです。
記者
単体の部長よりは領域が広いということでしょうか。
知事
守備範囲が少し広がるということで、従来の部長ポストでは賄い切れないので、理事という肩書きを付けましたということです。
記者
イメージ的には、知事がいらっしゃって、副知事が従来ですと2人で、所管を2つに分けてということでしたが、そういう意味で言うと、2つ以上の部に跨ってということでしょうか。
知事
今回は、単なる理事というかまちづくり担当なので、まさにまちづくりというミッションをしっかり都市建築部プラスでやってくれということです。ミッションオリエンテッド(目標を定め、その目標達成に向かうこと)だと思います。
記者
中心市街地活性化の検討ということですが、一丁目一番地のミッションとしては岐阜圏域でしょうか。
知事
そうです。
記者
一方で、もちろん岐阜県全県ですので、岐阜圏域について重点的に見ながらも、他のところも目配せするということでしょうか。
知事
どこまでできるか分かりませんが、まずはやっていただくということになるのは、リニア、東濃圏域です。東濃圏域については、今はどちらかというと(岐阜県)駅をどうするかという議論でやってきましたが、駅ではなくて、東京から見て58分で来ることができる別世界ということを言ってきましたが、まさにその別世界のイメージを作ってほしいということです。そこもある程度広がりを持った分野になろうと思います。
記者
東濃の方は、リニアの活用策についてということでしょうか。
知事
そうです。
記者
岐阜圏域については、県都を抱えるということなのか、新幹線、鉄道駅がある岐阜羽島駅を抱える岐阜圏域というニュアンスなのか、どちらのニュアンスでしょうか。
知事
岐阜羽島駅から、この県庁も通り、岐阜駅前、更には金華山、それから国際会議場、岐阜大学、そういった辺りも含めて、少し広いエリアになると思いますが、今回の高速道路の活用も含めた広範囲な視点でまちづくりの絵を描いていただきたいと。当然、岐阜市、羽島市、そしてその途中にある自治体も含めて、広い範囲で議論することになると思っています。
記者
人事は一つの戦略というか、知事としての思いみたいなものを出したいところだと思いますが、様々トピックはあるとは思いますが、知事として今回の人事を通してどういったメッセージを県民なり職員の方に出したいか教えてください。
知事
実は個別に見ていただくと、今回異動内示の仕方も古田前知事とは違ったかもしれませんが、お一人ひとりお呼びして、あなたにはこれをやっていただきたいということを明確に申し上げた上で、内示させていただきました。中でも、特別ミッションでより広く、今までやっていない仕事になると思うのですが、それをお願いした部分と、もう1つはよく見ていただくと、これまでやったことない人も付けている部分があります。今までのやり方ではないやり方、要するに違う視点でものを見てくださいと。前の議会で申し上げましたが、人は知識と常識で間違えるところがありますので、社会が変わらなければいけない時には、そういうしがらみに囚われずにものを見ることができることも結構大事かと思っておりますので、そういう点では今回人事の方々ともいろいろ相談させていただく中で、この人はこういう経験をしている、こういう特徴があると。私も知らない人ばかりではないので、十数年前に仕事した時に、こういうこともやられていたなというのも含めて、この人ならということで、まさに「安心」と「ワクワク」と「挑戦」をということで、その両方から適材適所で置かせていただいたということです。
記者
具体的な役職は言えない、言いにくいかもしれないですが、これまで技術職だった所に事務職を置いたということもありますか。
知事
そういうことです。
記者
まちづくりの関係で、ミッションとして、リニアと岐阜羽島駅から岐阜駅の周辺という2つを挙げられましたが、優先順位としてどちらの方に重きを置いているのでしょうか。
知事
岐阜周辺です。これがまず大事かなと思っています。あと、東濃の方は、今リニアの水の問題とかたくさんありますので、それにまず注力した上で、それと同時に(進めていきたい)ということです。ただ、まちづくりのやり方というのは、まず岐阜駅及び岐阜羽島駅の周辺のところから、ちょっと大きな絵を見ながら、そのノウハウも生かしながら考えていきたいと思っています。
記者
リニアの関係ですが、まちづくりを進める上で、今まさにおっしゃられたように、水位低下の問題からもうすぐ1年ということで、現状なかなか進んでいない中で、来月から新しい体制でまちづくりの計画を考えていくということは、何か月単位でどのようにまちづくりをしていこうみたいな、ある程度の目安などは考えられているのでしょうか。
知事
逆に言うと、リニアの場合は(工期が)少し延びてしまいましたので、その時間をしっかり使ってまちづくりをやっていくというのと、私も先立ってJRの幹部とお話をさせていただきましたし、今度リニアも見に行こうと思っていますが、その中でしっかりそちらはそちらで進めながら、それが終わってから考えたのでは間に合わないというのは、選挙期間にも言っておりましたが、同時に考えていくということ。それからJRの方々にとっても、ただ単にあそこに操車場があるから駅を送り込みましたということではなくて、リニアを作るにあたって、やはりあそこの岐阜県駅というのが一つ目玉になるなと思ってもらえるような、その絵姿が先にいるだろうということです。ただ、やはり何と言っても、住民の方々の不安を取り除くことが優先ですから、それに力を入れながら、ただそれと同時にやるという意味においては、まずは岐阜市の岐阜駅前のところを中心にやりながら、そちらも忘れていませんよということで進めたいと思っています。
記者
知事肝いりの未来創成局についてお伺いします。局長には、兼松商工労働部長を充てられたと思うのですが、選んだ理由と期待する役割を教えてください。
知事
皆さんご存知だと思いますが、彼は商工労働部長もやっておられて、新しい分野を切り開くというのもありますし、特に危機管理も非常に強い。コロナとか豚熱の時も、見事に立ち回りをしておられるというのと、私が申し上げるまでもなく、非常に前向きなキャラクターでありますし、職員の育成にもすごく力を入れておられて、やはり発信力と人を惹きつける力は要るかなと思っています。聞くところによると、彼の研修は立ち見が出るくらい人気があるということですので、もちろん特に大事なのは、これは全部楽な仕事ではないので、制度に対して物申すというのは、おそらく自治体の職員としては初めての経験になるだろうと思うのですが、その時に、それをまず恐れず、しっかり物を言えるという観点では、まさに衆目の一致するところかなということで彼を選ばせていただきました。
記者
就任初日に、職員の方に挨拶でおっしゃっていたのが、「県内どころか国の中で一番働きたい場所に県庁をしていきたい」ということで、働き方改革についても就任会見の時にお話がありました。一方で、2024年の県職員の自己都合退職も増えているという中で、人手不足の課題もあるのではないかと思います。今回の人事の中で、職場の魅力向上であったりとか、そういった部分で意識された部分があればお願いします。
知事
実は、奇しくも今日午前中、議会後初めてになりますが、幹部会議を行いまして、もちろん異動される方、退職される方もあるのですが、今回、ほとんどの方が別の部署で仕事をされるにあたって申し上げたのがまさにその点でありまして、今回初の議会になりましたが、通常の質問が23問くらいのところ、今回は59問の質問をいただきましたが、多分その準備に要した時間は(これまでの)4分の1以下ということです。ほとんど定時退庁になるということで、時間のところばかり皆さん気にされたと思いますが、答弁の作り方も変えました。最初に質問があった段階で、関係者みんな知事室に入ってくださいと、そしてみんなで議論して方針を決めた上で、ではこの方針で答弁の案を作りましょうという試みをしてみました。すると何が起こるかというと、若い人たちも知事や幹部が何を考えて、どんな議論をしているかというのと、若い人たちも意見が言える、特に今回、喫煙室を作るか作らないかという問題は、1時間以上に亘ってみんなで議論をして、少し喫煙者が少なかったので、後から喫煙者を追加して議論したりとか、そんなこともやらせていただいて、結果的に作らないという結論になったのですが、そういうふうに自分たちの意見が通るんだということ、そして知事を含め、幹部は何を考えて仕事をしているんだということが見える環境をしっかり作っていきたいと、これを今朝の幹部会議でもお伝えしましたし、せっかく社会のために働こうと思って県庁を目指していただいた方、若い人も本当にそれを作れる、そんな職場環境を作りましょうということを、まさに今日、幹部の皆さんにお願いしたところです。今回、人事は誰がどこに行くということばかりに注目されるのですが、それぞれの方々にミッションとして、本当に若い人たちの意見を取り入れるような仕事をしてくださいと。ですから、6月議会は更に楽しみにしてくださいということを申し上げましたが、本当にみんなで作り上げる県政を実現したいということを、この人事の中にも込めています。
記事
木曽川水系の連絡導水路事業の件ですが、長らく止まっていた事業ですが、去年の8月に国が事業の継続を決定されまして、新年度からいろいろ調査とか設計が始まるタイミングなので、このタイミングで伺いたいなと思ったのですが、事業継続は決まったのですが、関係の自治体からは、何せ地下40キロに亘るトンネルを掘るということで、地下水の問題であったり、結構環境面で心配の声が挙がっているということでありまして、古田前知事は環境面に対して、環境レポートをもっと細かく検討してくださいみたいな意見を付けてきたと承知しているのですが、江崎知事として、この事業についてどのように向き合っていくか。環境面という観点から、関係自治体から不安の声が挙がっていることを含めて、どのように向き合っていきたいかというお考えを伺いたいと思います。
知事
実はこの問題は、まさに徳山ダムを造った時からの問題で、日本一と言われる水をいかに生かしていくかという、その文脈の中で出てきた話ですし、このダムのために故郷を譲っていただいた方々にとっても、こうしたダムを本当に有効に使うということはすごく大事なことだということをまず最初に申し上げた上で、今回このダムができたおかげで、治水という意味においてはものすごく効果があって、やはり下流の洪水はかなり大きく減ったなというのはまずあります。その上で、今回の導水路は、治水と言うよりはむしろ利水で、特にご記憶にあるかと思いますが、平成6年の大渇水と言うか、私も覚えていますが、特に東濃とか、可茂地区では水が少ない。私は親戚が鵜沼にありましたが、本当に水がなくて、農業をやっていて、ほとんどもう全滅に近い状況であったと。あの時、160何日ぐらいの取水制限だとか、プールなんかも全部止める。そんな中で、どちらかと言うと、西の方で割と雨が降って東には降らないというこの県の状況を考えた時に、水をどこまで有効に使うかということの中で、もちろん渇水対策としていろいろあるのですが、一過性の対策をするよりも、それがあった方が、将来に亘って安心感があるだろうということで、この議論がされたと聞いております。その上でご質問にお答えすると、多分いろんな水系があるところを横に穴を掘っていきますから、いろんなことがあるのかもしれないと。それと、水系が違えば当然水質が違うので、それを入れても良いのかという議論は当然あろうかと思っています。ただ、その中で、おそらくこれをガンガン使う時というのは、先ほど申し上げたように、何十年に一度の大渇水の時なので、その時に水系云々という話ではないかもしれないし、まず水があることが結構大事かもしれないという文脈の中で、環境というものを考える必要があるのかなと思っています。また同時に、これはもう長年に亘る水利権の問題も絡んでいる話もあるので、そこも含めてもう一度、実はかなり時間をかけてこの間教えていただいたところでもあります。古田前知事の頃の意見書も全部読みましたが、まずは事業に関しては了解するとした上で、環境についてしっかり調べ直してくれというのが、毎回出している基本ラインだと思います。なので、まずは国の方がやることを決めた、それから名古屋市がやはり必要だということをおっしゃったという中で、あとは今度は、やると決まったのであれば、まさに今おっしゃった、環境影響はどれくらいのものなのかと、そして前の時は15年前なので、状況も変わっていますし、あと残念ながら地球温暖化と言うか、気候変動の中で、いろんなことが起きる可能性があり、そういうのを勘案しながら、もう1回しっかりそこは見直すと言うか、環境影響調査をやる必要があるかなということは、引き続き私も求めていきたいと思っています。
記者
今知事が言われたように、何十年に一度あるかないかの大渇水の時に効果を発揮されるだろうということですが、逆に言うと、コスト面が2,270億円に増えているのですが、何十年に一度あるかないかの渇水対策のためにこれだけのお金を費やすことが、果たして人口減少時代において、本当に妥当性があるのかと言われる声もあるのですが、そのコスト面については知事はどのようにお考えでしょうか。
知事
まさにその質問を私が職員に向かってしました。その時に、やはり渇水のレベルによって違うかなというのはありまして、農産物の被害というのは平成6年にありましたが、かなり長期に亘る取水制限の中で、健康への影響も考えた時に、おっしゃる通り2,000億円あったらペットボトルを買ったら何本になるかとか、そんな話も実はやりました。その時に先ほど申し上げたのは、一過性の対策として、それぐらいのお金があれば凌ぐことはできるかもしれませんが、逆にそれが継続的に供給できるのであれば、要するに何十年に一度ということは何十年に一度あるので、その度ごとに1,000億円近いお金を使ってペットボトルを買ってくるのか、それともこれ(導水路)があったら良いのかというのは、いろんな議論がある中で、一応これがコストパフォーマンス的に良いだろうということになっていると聞いています。ただ実際には、犬山の上のところに持って来ないと、そこから下の取水ができないとか、もっと下流で横に持ってたらどうかとか、私自身がいっぱい質問しましたので、とりあえずその中では何を想定するかによって、だいぶ違うみたいなのですが、とりあえずの選択肢としてはこれがあるのだろうということは、私も「そういうことですか」という理解はしました。その上で、ご質問にあった環境影響とか負荷の部分、コストパフォーマンスだけでない部分がどれくらい大きくなるのかというのと、あとは緊急性、そこをしっかり考えて進めていくようにしたいなと思っています。
記者
先日、石破首相が地方創生伴走支援制度を4月から始めるということを発表されたかと思います。地方創生の目的で国家公務員を自治体に派遣するものですが、岐阜県からは瑞浪市と美濃市の2つの市が選ばれたと承知していますが、この点について、県知事の立場として、この制度に対する評価と、これに期待することを教えてください。
知事
元々石破総理は地方創生大臣としてかなり活躍しておられて、その時、私もどこかのポストで一緒の会議に出ていたこともあるのですが、そういう意味では、地域の活性化に関しては、総理ご本人の意識として、先日官邸に行っていろいろ聞いてきたのですが、やはりそこは本当にご本人の思いとして強いなということは、まさに理解しているところであります。
その上で、地方に公務員を派遣するというのは、私自身がそういう立場で岐阜県に来ておりますので、これは自分の経験から言うと、すごく良いことだなと思っています。というのは、やはり自分の組織のことは分かるのですが、そうでない組織のことはやはり外から見たイメージしかないのですが、実際に国はどう動いているのかを知っている。それで今度、自治体に入ってみると、自治体はこういうふうに動くんだということが分かる。その中で、実は今回の未来創成局もその文脈ではあるのですが、逆に自治体の方から国の制度について意見を言うことはほとんど無かったんですよね。それで、私がまさに部長として仕事をさせていただいた時も、やはりどうしても法律がネックになりますという意見はたくさん聞きました。逆に、国から来ていると、その制度を直せば良いんじゃないのと。私の場合は、とにかくどうしても法律に引っかかる時は言ってくれと、法律を直してきてやると話をしてたのですが、それが単なる掛け声ではなくて、実際にそういう仕事をしてきた人たちが自治体の方に来るというのはお互いにすごく良いことですし、逆に法律案をかける立場からすると、現場の情報がすごく足りないんですよ。どうしてもあの霞が関の机の上で政策を考えることはしているのですが、本当のところどんな制度にすると地元が助かるのか。特に地方創生というのは、ほとんどの人が東京で考えてしまうので、東京の生活をしていながら地方創生を考えるというのは、結構無理があるかなというのは正直ありますので、そういう形で、しっかり伴走するということ、常にこういう制度があるから使ってくださいではなくて、制度そのものを作りに行く、ないしは、現場の情報を国の制度にフィードバックするという点においては非常に良いことだと思っています。
記者
福島の除染土の関連でお伺いします。国が福島第一原発事故の関連で発生した除染土を、2045年3月までに福島県外において最終処分をするという方針が決まっておりますが、これについて岐阜県において最終処分場を受け入れるということはあり得るか。また、その最終処分とまではいかずとも、公共工事による再利用を行っていくというものがあると思いますが、そちらについても岐阜県において、それを受け入れることがあり得るのかどうか、現時点での考えをお聞かせください。
知事
選挙の時に同じ質問をいただいたのですが、まず国としての方針しか決まっていないので、やはり自治体を預かる者としては、実はどういう手続きで、それをやった時に何が起こるのかというのが、情報が無さ過ぎるので、まずは国において、ルールやその他の対応の仕方というのが決まった上で、県としてそれをどうするかというのは判断すべきかなと。そういう意味では、今のところの情報では少し足りないかなという話です。
記者
国で新年度予算案の方で、高校の授業料無償化が議論されています。また、いろんな面で私立高校の方に流れるという話が出ている中で、江崎知事としては、この無償化というものが岐阜県にもたらす影響をどう考えるのかというのと、その公立と私立の教育の今後の(在り方)というのは、どのようにお考えになるか教えてください。
知事
大きく答えると、高校の無償化は悪いことではないと思っています。やはり自分の生まれた環境によって、どんな分野で勉強することができるかというのを制限されてしまうのは良くないかなと。特にこの国は、ある意味生まれた環境に関わらず、自分の進路を選べるというのは、世界でも実は稀有なことなのですが、それができてきた国だと言われているのですが、ここにきて、いろんな貧困問題がある中で、少なくとも子どもたちが自分の未来を考える時の選択肢を狭めないということでは非常に良いことだと思っています。
その上で、私立か公立か問題というのは、これは県によって状況が違っていて、岐阜県の場合はどちらかというと、いわゆる東京その他と違って、県立が優位というのは分かりませんが、そちらが先に決まってという流れがあったやに私は記憶しています。ただ、その中でどちらが優先ということよりも、特に今回教育に力を入れたいと思っていますが、多様な生徒が出ている中で、学び方にも多様性があっても良いのだろうと思っています。
その中でやはり公立と私立だと、教育方針でかなり柔軟性が変わってきますので、私立のところで実は柔軟性があって行きたいのだけれども、やはりお金が高いから行けなかったという人が行けるようになるという意味においては、これは良いことだと思ってます。
その上で全体の生徒さんたちが選ぶ公立か私立か問題というのを、客観的に捉えた上で、今度は公立は公立でしっかりと魅力のある学校にしていかないといけないと。一律だから良いんだということではないということが、いよいよこの制度によって迫られる問題に変わってきたのだろうと思っていますので、むしろそれがいきなり良いか悪いかというよりは、こういうことになった中で、イーブンになってくる中で、しっかりそれぞれ魅力を発揮していただきたいということが、私としての一番強い思いです。
記者
学校の魅力を作るということが大事になってくると思うのですが、今、現状で公立でいうと定員割れしている高校も数多くある中で、今後の定員の考えであるとか、統合であるとか、そのような方針はどのようにお考えでしょうか。
知事
実は定員の議論をする時は、皆さん、県内にいる人のことばかり考えていませんか。おそらく今回の私立問題で何が起こるかというと、岐阜県から県外の私立に行くという話も当然あるんですよね。それと今度はひっくり返してみると、県外から岐阜県に学びたいという人がいても良いはずなんです。だから、今までの議論は、どちらかというと減ることばかりを前提の議論にしているので、むしろ今回、いきなり異年齢(学級)がいけるかどうか分かりませんが、教育、子どもたちを育てるには岐阜県が良いとなった時に、逆に今度、県外から岐阜県に来ていただく環境としても悪くないと思っています。そういう点では、まさにこれから教育界の知恵の絞りどころ、腕の見せどころだと思いますが、生徒はこれだけ多様化している中で、35万人の不登校と言われている中で、どういう教育が今求められているのか。それができた時には、むしろ岐阜県に移住してでも子どもを学ばせたいという、そんな流れもあるのかなと、ちょっと夢物語と言われるかもしれませんけど、それがあっても良いかなと。とにかくこの日本の真ん中にあって、いろんな自然環境もあって、教育をもう1回見直すには最高の環境にあると思っていますので、直ちに合併するとか定員を削るというよりも、まずその議論をやった上で、そうした議論にいくのかなと思っています。
記者
石破首相の10万円の商品券の問題ですが、一政治家としてどうお考えになるか、所感を教えてください。
知事
これは石破さんというよりも、その後に出てきたニュースがそうであるように、今までそれが慣行だったということなのだろうと思います。だから、石破さんがやったとか石破さんだからやったということではなく、ただ、今大事なことは、今回、私がこの県に戻ってきたのもそうですが、今までの当たり前ということが見直される時期に来ているのだろうなと。
ですから、結果論で言うと、これからどうするのと。確かに前の総理たちもやってきた、それはそれで事実で、石破さんもやったのも事実なのだけれども、ではそれが社会的にこれだけ良いことではないという評価を受けている中で、じゃあ次やるのですかといったらやらないですよね。これがたまたま出てきたから止めるっていうのが、まず今まで当たり前だったと思うものを見直すという意味では、一つのきっかけになるのではないかなと思っておりますので、多分これを続けるという人はいないと思いますので、そういう点では本当に一般の国民の感覚に近い方向に今までの慣行が改まっていく一つの機会かなと思っています。