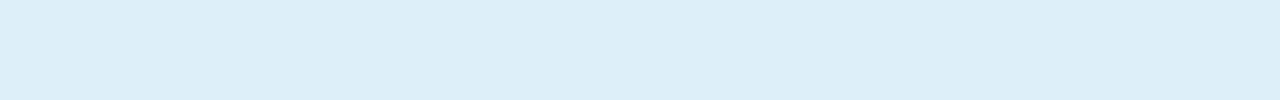本文
知事記者会見録(令和7年2月14日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年2月14日(金曜日)9時00分
司会
ただいまから令和7年度の当初予算案等につきまして、知事記者会見を始めさせていただきます。
知事よろしくお願いいたします。
知事
改めまして、皆様おはようございます。
令和7年度当初予算案についてのご説明をさせていただきます。
お手元に資料があろうかと思いますので、まず資料1、その後資料2と資料3を一緒に見ていただくと分かりやすいかと思いますので、よろしくお願いします。できるだけ分かりやすくご説明したいと思います。
【資料1】
まず、お手元の資料1で、ポイントだけ先にご説明をさせていただきます。おそらく着任して初めて(当初予算会見に参加する記者)の方もいらっしゃると思うので、1枚めくっていただいて2ページ目、そもそもの岐阜県の予算構造がどうなっているのかということをご覧いただくと分かりやすいかと思いますので、こちらから説明したいと思います。
岐阜県の予算規模として、9,020億円で今回予算を作りました。 9,000億円超えは初めてになります。以前をご存知の方もいらっしゃると思いますが、一度(岐阜県は)財政破綻をしていて、今は戻ってどうなっているのか、後で追加の資料が来ますので分かりやすく説明したいと思います。
まず、ざっくり申し上げると一般的な自治体もそうかもしれませんが、9,000億円の内訳を円グラフで見ていただくと、あまり自由度はなく、人件費、社会保障関係経費、税交付金、公債費、これらはほぼ自動的に決まってしまう予算なので、これらはあまり政策的に触る余地がないと。人数が何人いれば当然給料が決まってくる、また社会保障関係も多少の誤差はありますが、高齢者の数などでほぼ決まってくるというものです。
次に、これ以外のところで、投資的経費が、投資的経費と言いながら、建設事業や災害復旧に伴うものだったりするため、自由があるというより、その時の状況において決まってくるものです。
その次、その他というところ、1,443億円がそれ以外となりますが、その中にも施設の維持管理費や制度融資など、施設を持っている限りは発生してくるのであまり自由が効かないです。そうすると、その他の中のその他である276億円、これがある意味政策経費と言いますか、まさにいろんなことをやっていくためのお金になります。財政破綻の時も実はこれに近い数字でした。私が商工労働部長の時にはこの経費がゼロになりましたので、私もそれを経験していることからすると、まだ(財源が)あるかなという感じであります。
この後説明するのは、主にこの276億円をどう使っていくのかというのがまさに政策になるということをご理解いただいた上で、そういう構造の中で、まず本県の財政状況ということで、歳出面については社会保障関係費、今申し上げた高齢化の進展がありますから当然増えます。特に本県の場合は、公債費、前の前の梶原知事時代の話で、ご存知だと思いますが、いっぱい借金をしていて、特に国土強靱化、後でグラフを見ていただきますが、その後の古田知事の時代も大分これでお金を使っているので、この返済額が乗ってくるということでありまして、さらに最近、金利が上がっているので、利子返還がボディブローのように効いてくる、なかなか厳しい状況であります。そんな中でも先ほど見ていただいた276億円を有効に使うことが、ある意味政策の腕の見せ所ということかと思っています。その中で、県民の皆さんの安全・安心や未来づくりということで頑張るということであります。
歳入面ですが、どこの自治体もそうですが、増えています。これは、景気が良くなっているのではなく、いわゆる賃金の上昇や物価高で、価格が上がると消費税が増えてしまう、それに伴って税収が増えたのですが、こういうお金は当然あれこれに使うのではなく、県民生活の安定に優先的に使っているべきだろうと。(歳入が)増えたからもっとあれをやろうこれをやろうということをしっかり考えなければいけないということを思っています。
その下、予算編成の考え方ですが、私がずっと唱えてきた10の目指す目標ということで、これを念頭に編成する予算、骨格的(予算)、いわゆる骨格予算ではないですが、編成しました。ここで私から言っても良いのか分かりませんが、やはり県の職員は優秀で、この1週間で全部作り替えました。見事です。まさに、古田知事の時代にやっておられたこと、作っていただいたものを踏まえて、これを10の目標に再編できるものは全て再編しました。その上で、まさに当初から手を付けられるものはすぐに手を付けるということで、着任1週間でありながらほぼ予算は完成いたしました。
その中で10(の目標)をしっかりやるということと、目指すべき目標をやった上で、そうは言ったものの、義務的予算がいっぱいあるのと、再編内容の一番下にある普通建設事業費は当面の執行が円滑に行えるように8割で計算しました。8割の意味というのは、ちょうど今配られた表(追加配布資料(参考資料))でご説明すると分かると思います。
【追加配布資料(参考資料)】
今この県で何が起きているかというと、実は平成20年、私がちょうど(岐阜県庁に)いた頃ですが、いわゆる財政破綻、起債管理団体になってしまいました。この基準が、公債費率18%を超えると、勝手に予算を作るなということで、かなり国の管理が厳しくなるというものです。私は、平成20年から24年までいましたから、まさにそこにはまっていました。なので、商工労働部長の時に予算ゼロという経験をしたのですが、どう乗り越えたのかというと、実は乗り越えたというよりは、平成21~24年ぐらいを見ていただくと、(グラフの)緑と黄色になっていると思います。これは、本当はオレンジ色の金額を返していかなければならないのですが、20年債を30年債に借り換えるという、いわゆる金融上、財政上の必殺技を使っており、(返済を)先延ばししただけです。その結果として、(グラフの)黄色のところが減り、いわゆる(公債費率が)18%より減って、財政破綻を乗り越えたように見えているが、(グラフの)黄色の部分、緑とオレンジの差分の黄色ですが、令和6年で逆転しているのが分かると思いますが、要するにそれを返さないといけない、これから(返済額に)乗ってくることになります。返さないといけない分にプラスして、また新たに起債をしているというのがあり、このグラフをご覧いただくと(公債費率が)18%に向かってまっしぐらということになります。今、令和7年は太字で示しておりますが、先ほどの8割の意味は何かというと、これからいろんな道路や橋を直さないといけないのですが、今皆さんにお示した8割ぺースでいくと、この令和8年、9年は、黄色のペースになります。これがいわゆる財政破綻を免れて県政運営できる数字になるのですが、実は昨年度の8掛けにしています。昨年の額どおりに起債をすると、(グラフの)この赤が乗ってきます。赤になると、実は令和15年に財政破綻するのが見えている。これは累積ですから、ぴしっとはまるわけではないですが、例えば参考に起債そのものをやめたらどうかという乱暴な議論がありますが、(起債を)やめると(グラフの)この黒い点線のように下がるのですが、これはさすがに無理だということで、頭の体操ですね。ですから、やはり借金をしないといろいろできないのですが、今回8割、8掛けというのは、この(グラフの)黄色なので、(公債費率が)18%にいかずに、予算編成の自主性が維持できると。今後、何が起こるかと言うと(普通建設費を例年の)8割だけという訳にはいかないでしょうから、この(グラフの)赤の中のオレンジと、(公債費率)18%をどの辺に持っていくのかっていうのが、今後の6月補正予算、9月補正予算、12月補正予算、3月補正予算のポイントです。これがまさに知恵の使いどころであり、起債することで県が自由に使うお金だけで全部やるのではなく、国が災害の時に補助を出してくれるように、裏負担といって、自治体が一部出したら、例えば自治体が2(割)出したら、残りの8(割)を国が出してやると。災害だとかによって割合が違いますが、これは金融をやったことがあると、「レバレッジ効果」といって、自分の出したお金に対して何倍のお金が国から来るというのはものによって違うので、できるだけ戻り率が良いものにより政策的に使っていこうと。後で人事のところやその他で話をしますが、それを戦略的に考えることをやろうかなと思っています。まさに県のお金、いわゆる県単と言いますが、これを単純に使っていくよりは、国からの制度をうまく組み合わせることによって、例えば建設関係の事業費そのものは減らさない、むしろ増やす。でも、県で使うお金(県単)を減らしていくなど、知恵を使いながら事業規模は維持ないし拡大しながらこの(財政)破綻を免れる。この(グラフの)オレンジと赤の上の真ん中のどの辺りを狙いながら県の財政を運営していくかというところが、これからの課題になるということであります。
人によってはもうすぐ(財政)破綻すると言いますが、そんなことはない。ないですが、去年と同じベースで元気よく起債をしてくると令和15年にはダメになるし、去年を上回って起債するのであれば、もう2、3年後に破綻することがこの数字で見えてくるかと思います。ですから、これから記者の皆さん、いろいろと記事を書かれる時に、この県がどういう状況にあって、何をしようとしていて、そのお金に何の意味があるのかということをしっかり理解した上で記事を書いていただくと。県民の皆さんが分かりやすい、いたずらに不安を煽るのではなく、逆にいたずらに楽観視するものではないということ。これは財政課の知恵者の皆さんが昨日もいろいろ知恵を使いながら(資料を作成した)。分かりやすいでしょう、5枚ほどの資料をこの1枚にまとめていただいたのですが、これがまさにこの岐阜県の現状であります。借金がゼロであれば良いかというと、そういう問題でもなく、上手くやりながら、将来に対する資本を作っていくということがこの現状であるということでございます。非常に分かりやすい資料で、私も感動しながら、財政課はすごいと思いながら、(資料を)見ております。
【資料2、資料3】
ここまでが前提で、ここからいよいよ江崎県政の腕の見せ所、政策になります。資料2と資料3を同時に出してください。
まず資料2、これが10本の目指すべき政策、まさに「安心と挑戦の岐阜県」をやるために取り組んでいきたい、まさにこの4年間の集大成として申し上げたところですが、金額的にも本当に県職員の皆さんが大車輪でやっていただき、先ほどの276億円中約204億円、大半をこの10本に再整理しましたし、新しいものも立てました。金額も書いてありますが、柱ごとにぱっと見で金額のバランスもさすがだなと思いますが、やはり手厚くすべきところがきれいにバランスができております。その代表的な予算が項目で書いてあります。ちなみに(資料2の)左側(「安心」)を全部出すと118.3億円です。そして右側(「ワクワク」)を全部足すと85.7億円で、合計204億円です。正確には276億円全部と言いますか、外数、再掲もあるので、その辺の誤差はお許しいただくとして、政策で使うべき予算の大半をこの10本柱に整理したということでございます。
今度は、資料2を左側に置いていただき、資料3を右で開きながら、最初のページは同じですが、まさに若者や女性の流失が止まらず、人口減少にどう対応するのかというのと、「政策オリンピック」も早速2つほど入れていますのでお楽しみにということであります。資料3を1枚めくっていただいて、2ページ目(「若者や女性が持てる力を発揮できる働き方や職場をつくる」)から説明します。
<1.若者や女性が持てる力を発揮できる働き方や職場をつくる>
まずスタートアップです。これはもちろんスタートの補助ですが、特に女性のスタートアップに対して補助率を引き上げる。やはり女性が活躍するということに力を入れているのが「(1)スタートアップの創出・成長に向けた支援」です。
それから「(2)『稼ぐ力』の強化に取り組む小規模事業者への支援」は、人手不足、小規模事業者への支援をしつつ、女性の支援になるように、事業拡大や業態転換、特にマイクロワーク、働いてもらえる方、子育て中の女性の収入を増やすには、人手不足と合わせて、働きやすい場所、それから若者に対してもっと自由な働き方を可能にする、これを合わせて女性の力を発揮することで、企業の人材不足に対応する予算として大きく拡大しているということであります。
それから「(3)若者のUターン就転職・定着の促進」は、Uターン就転職のためのものです。これは昨年もやっておりましたが、高校生向け、学生向けに県内企業をアピールするいわゆる「高校生の日」などをやりながら、しっかり若者たちにチャンスを提供するということであります。これは従来からで、しっかりやっていくということです。
それから「(4)若年技能者等の産業人材の育成・確保」のところですが、若いうちから色々体験をする、特に児童生徒向けてロボットや通信技術に触れる機会や、高校生向けに宇宙航空産業の見学をしてもらい、発見してもらうということ。そして、保護者向けというものが何かというと、私も商工労働部長時代に経験しましたが、子どもや学生が「この会社で働きたい。」と言っても親が反対するという、いわゆる「親活」です。親にもしっかり理解してもらって、お子さんがこういう会社で働くことがいかに素晴らしいことかという理解をしてもらうということです。少しびっくりしますけど、これは結構大事なことで、これをしっかりやるということであります。
それから「(5)ワーク・ライフ・バランスの推進」は、女性だとか、働きやすい環境、エクセレント企業です。私は国で健康経営をずっと指導してきましたが、その中の項目として(国に)足してもらうような取組みをしたい。働き方改革より「働いてもらい方改革」に移行するための毎度のPR費も含めた予算でございます。
[今後検討を進める施策]
あと10項目の中で、(各項目の2ページ目には)今回は間に合わなかったですが、今後やっていくというものです。だいたい半分はできていますが、簡単に言うと、特定業務をしっかり切り出すという仕組みをしっかり作る。2つ目はマイクロワーク、まさに登録・紹介する仕組みを多様化するということ。それから真ん中の3つ目は、若い人の多様な働き方を推進するために、同時に複数就労することも可能にしていくと。これは社会保障の制度も変えなければいけないと思っています。それから4つ目は、少しびっくりするかもしれませんが、可能であれば、9時(から)5時(まで働くの)ではなく、9時3時というのを企業の将来的な働き方にして、子どもが帰るより先に親が家に帰ることができるという点、あと5時からまた別の人が働く、また同じ人も別のところで働くと世帯収入が増えるということ。前も言いましたが、皆さんいわゆる時給、最低賃金の話ばかりするのですが、そうではなく、最終的には世帯収入が増えれば良いので、9時3時でしっかり働いて稼いだうえで、子どもを迎えた後にオンライン等を使いながらまた5時から働くということによって収入が増える。これは企業からするとものすごく人手不足を解消するという形をもっと積極的にやると。あと、税制における「103万円等の壁」、こういうのは国でやっていますから、様子を見るというものです。
<2.子どもを産み育てやすい環境やサポートシステムをつくる>
2番目になります。「子どもを産み育てやすい環境」について、4ページ目です。まず不妊治療などの妊産婦への支援ということで、引き続きしっかりやっていきたいと思っております。特に今回は額と言うよりは、中身を触っています。不妊治療の保険適用後、10万円を上限に自己負担分を助成します。それから新生児マススクリーニング検査は、新生児を対象に先天性代謝異常などを早期発見し、適切な治療につなげることを目的とするものです。フェニルケトン尿症やメープルシロップ尿症など20疾患を対象としていますが、今回、国の実証事業に参加し、重症複合免疫不全症と脊髄性筋萎縮症の2疾患を追加することによって、より安心して、子どもを産めるような対応を手厚くやっていくということであります。
それから「(2)『ぎふっこまんなか社会』の推進」は、ずっとやっていただいているものを引き続きやりたいと思っています。保育所や認可外保育施設等に通う児童について、特に手厚くするのは、国の無償化対象とならない第3子以降の児童に係る保育料及び副食費の部分であり、無償化を実施する市町村への補助をしっかりとやっていきたいと思います。
そして、特に力入れたいのは「(3)子育て世帯等への経済的支援」であります。子育て世代ですが、やはり4年間回ってきた中で一番多かったのは多胎児です。双子、三つ子が本当に大変だということで、現行の県の制度では、第2子から10万円を支給していますが、双子の場合には、第1子から、それぞれに10万ずつ支給することによって、支援しようというものです。それともう1つ、4年間回ってきた中で大きな声であったのが、児童養護施設に入っている子たちが進学、社会に出る時に非常に困難を伴うと。特に高校、場合によっては芸術系(の学校)に行く時にその費用がかかるということもあるので、高校進学時には一般的には3万円ですが、さらに10万円加えて、合計13万円にするということ。あと、特に大学、専門学校に進学するときに、音楽であれば楽器、美術であれば画材道具ということにお金がかかりますが、施設にいる子はアルバイトで生活するだけで精一杯で(進学を)諦めている子が多いということを聞きましたので、今回、大学、専門学校へ進学する子に50万円を支援するということを新設していきたいと思います。就職する場合であっても、その準備ということで、一般の方であれば周りが面倒見てくれるところ、(そのような方が)ない子に対してしっかり応援していきたいと思っております。
「(4)困難な状況にあるこどもへの支援」になりますが、やはり里親です。残念ながら、親との関係が非常に難しい子どもたちがいるのですが、岐阜県は残念ながら里親の体制が少し弱いということで、しっかりやっていくということです。額を増やしてやっていくと。あと、こども食堂の補助とか、オンラインの学習支援とかもこの中でやっていきたいと思っています。
それから「(5)保育士など子育て人材の育成・確保」になりますが、育てる人を育てるということで、これは従来からやっていますが、放課後児童クラブの放課後児童支援員とかをセンターを作ることによって応援するということであります。
[今後検討を進める施策]
(資料の)右側の今後のものは、だいたいできていますが、もっと大事なのは、結婚時点から中学、高校ぐらいまでフルサポートする。そして、産後うつというのが一番大きな問題になっているので、そこを安心してお母さんを孤独にしないための取組み。それから2つ目が、子どもの数に応じて、いわゆるフランス型と言われていますが、子どもを産めば産むほど楽になる、そういったことを考えたいと思っています。それから3番目の男性育児。皆さんドキッとしてくださいね。男性の方がちゃんと育児に参加することを支援するのと、市町村の枠を越えて病児・病後児保育サービスが受けられるようにしていきたいと思います。これから将来的に是非やりたいと思っているのは、廃校舎などを使って、いわゆるイメージとしては林間学校です。海の子を山に、山の子、田舎の子を都会に、都会の子を田舎にということで、子どもたちに故郷を2つ持ってもらいたい、災害時には胸を張って逃げてこいということも含めた準備をしたいと思っています。これが、子どもの頃から出会いのチャンスを広げることによって、結婚につながるかどうかは(分からない)ですが、いろんな出会いのチャンスを子どもたちに広げるということをしたいと思っています。あとは、里親制度です。今回もやりましたが、さらに充実したいと思っています。
<3.お年寄りや障がいがある方が活躍できる場や居場所をつくる>
3番目はお年寄りです。これも大事にしたいと思っているところですが、高齢者の生きがいづくりということで、従来からやってきたこともしっかりやっていく。特に健康づくりのところに力を入れていきたいと思っております。今後のところで少し言いますが、喫茶店などを生かして健康にしていくという取組みです。
それから障がい者の文化芸術、パラスポーツということで、障がいのある方もない方も同じ表現の場でやる「ノーボーダーアート」、これを新規でやっていきます。やはり障がいがあるからちょっとかわいそうということではなく、やはり同じ社会のプレイヤーとして活躍する場所を作ろうというものです。
それから「(3)障がい者の就労・職場定着の支援」でありますが、やはり(障がいがある方の)社会で活躍、仕事ということです。特に農業分野の展開というのをしっかりやりたいなと思っております。農福連携で手厚くやっていく、できたものをちゃんと売ってお金が入るという仕組みをしっかり手厚くやっていきたいと思っています。
それから「(4)医療的ケア児等への支援の充実」、これも4年間回っている中で、医療的ケア児というのはすごく大変ですから、ここに対しても中身でより充実させていきたいと思っております。特に、医療的ケア児の子たちが宿泊学習とか修学旅行に行けない、こうしたことに付き添える看護師さんの派遣体制など、他の子と同じ体験ができるようにするということ。それから、親御さんが本当に大変なので、レスパイトサービスということで、親が休めるように一時預かりや短期入所などを支援することによって、本当に親御さんも追い込まれないようにすることに力を入れていきたいと思っております。金額はそんなに変わりませんが、中身を相当入れ替えています。
それから「(5)社会福祉施設の安全性・利便性の向上」、社会福祉施設の安全性、これも大事なことです。特に老朽化したトイレの洋式化やICTを使った見守りシステムを導入していくことによって、安心して施設に入っていただく。利便性の向上、いわゆるユニバーサルデザインです。そして、新しく直す時に、階段や段差をなくしていくようなことです。
[今後検討を進める施策]
あと、今後検討のところは(これまでに申し上げた内容と)少し被りますが、マイクロワークを進める。それから2番目にアグリパークです。ただ単に農業体験、今回は体験することの準備ですが、(高齢者や障がいのある方が)農業体験しやすい場所を作っていくというようなこと、それからマーケットも作っていく、それから高齢者の方が地域を支えるためのプレイヤーとして活躍していくための仕組みを今後手厚くしたいと思っています。そして4番目、喫茶店を使って、特に1人暮らしの(高齢の)方が、毎朝喫茶店のモーニングに行くことによって、運動と栄養といわゆるメンタルのケアをするということをしっかり取り組んでいきたいと思っております。あとは、是非やりたいと思っていますが、「親亡き後」も障がいのある子どもたちが社会のプレイヤーとしてしっかり活躍できるように、これは企業の方から歩み寄ってもらう、まさに仕事を括り出してもらう、これはまた後で出てきますが、そうしたことをやりながら、本当にいろんな人が多様な働き方をできるようにすると。1番下は岐阜ならではですが、やはり閉じ込め型になってしまってはいけないので、徘徊という言葉が良いかどうかわかりませんが、認知症のある方も、運動ができるような環境も作っていきたいなと思っております。
<4.災害などに強いインフラや医療・防災システムを整備する>
次が4番目です。ここは金額的にもちろん手厚くやっていくことになりますが、この外数にいわゆるインフラ系がありますから、あくまで276億円の中の話をしているということでよろしくお願いします。
地域防災力、実はこれを「政策オリンピック」でやりたいということです。南海トラフ地震があるので、この被害想定をした上で、それに見合った形で住民参加型の避難訓練というのをできれば施設に応じて10分の10の補助で、200万円位を上限に、今までのありきたりの防災訓練ではなくて、住民の方と自治会が一緒になりながら、例えば子どもたちにどこそこのおばあちゃんを連れてきてくださいとか、集まったところで飯盒炊爨(すいさん)をする、それから用意されているのではなくて、山に行って木を取ってきて火を燃やすとか、いろいろとこちらからの提案にはなりますが、より良い提案をしていただいたところに、10分の10で予算を付けて、それで特に良い取組みを今後来年度以降の補正予算になるか分かりませんが、展開するようなネタにしたいなと思っています。
それから、避難所そのものも、新規事業として国際基準で作りますが、やはり日本の避難所のレベルが低いと国際的にも言われているので、簡易ベッド、キッチンセットをしっかり準備をするということと、医療コンテナ、トイレコンテナについて、トイレは汚いものではなくて、洋式かどうかも含めてしっかりと。あとは障がい者、高齢者の方が安心して避難できるような体制も作ることに力を入れたいと思っています。
それから「(3)物資拠点の充実など災害時の孤立対策の強化」です。孤立対策について、今回の雪で孤立が出ましたが、岐阜県は孤立想定地域がとんでもない数としてありますので、それを訓練していくことと、特に今回分かったのが、雪が降り木が倒れて電線を切ると、逆に言うと、携帯(電話)が繋がっている限りいろんなことができると分かったので、まずは停電にならないようにするということ。それから、場合によってはモバイルバッテリーを飛ばすかというのもあって、そういったことも含めた効率化対策、岐阜県ならではの取組みもしっかりやっていきたいと思っております。
それから、「(4)災害に備えた防災対策の強化」ということで、これは建物そのものを直していくことに支援するので、額が大きいですが、あと道の駅を使ってバックアップをするような仕組み、やはり災害復旧で土が要るので、その備蓄拠点を置いておくと。必要なものは食料と医薬品だけではなくて、道を直すための土をどこから持ってくるんだということがありますが、そういうこともしっかり整備しておくということ。あとは埼玉で大変なことになっていますが、流域下水道とか県営水道の対策もしっかりとするということです。
それから、「(5)医師の勤務環境改善・医療提供体制の強化」なのですが、ご案内のとおり、医療資源の偏在化とか、色んな問題があります。他方で、これだけ大きい県なので、遠隔地には医療の世界では難しいと言われていたものが、そういったものを岐阜県ならではの仕組みとして、(医療資源が少ない)地域であっても比較的高度な対応ができるようにするということ。あとは、お医者さん自身の負担を軽減するためのいろんな仕組みを入れようとするものであります。
[今後検討を進める施策]
また、今後は特に自治会、今どんどん組織が弱くなっている自治会について、しっかり体制を取るために、やはりどうしても住民情報については、個人情報保護法上の制限がとても多いのですが、この法律は全ての条例に負けるように作ってありますので、むしろ県でこのようにすれば、元々災害時は適用除外なのですが、事前予防の時にはどういう情報であれば誰が持って良いかということを作っていきたいと思っていますし、その経過で法律改正まで迫っても良いかなと思ってます。防災訓練によって自治会を魅力あるものにしていくと、あと岐阜県の場合は住民だけではなくて、県外からの避難、南海トラフの場合は、愛知県や三重県の方々を受け入れるし、あと高山の方だと旅行者の避難ということも計画に入れないといけない。計画から外れていることが多いので、これも手厚くしっかりやっていかないといけないと。それから、移動型のコンテナ、上下水道、孤立集落、これも今回の内容にも入れましたが、さらに手厚くしたいと思っています。
<5.鳥獣害のない里山を作り多様な価値を生む農業を推進する>
それから、「安心」の関係の最後です。これは1番私がやりたかったもので、鳥獣害対策、里山作りということです。お猿さんを含めて、これを「政策オリンピック」でやりたいと思っています。定額補助で、上限300万円で、ただ単に殺処分をすれば良いということではなく、やはり彼らも生きている大事な仲間であるので、どうやったら被害が少なくなるか。どうやったらたくさん獲れるかではなく、最終的には被害さえなければ良いので、そのような仕組みをいろいろ考えてくださいということです。GPSを使って、個体、特にメスザルにGPSを付けてもらうことによって個体群の移動が分かるので、山ふたつ手前で撃退する仕組みとかドローンも使いながら、これはカワウもそうなのですが、まさに最先端の技術、今までは個々の農家が頑張ってやっていますということが多かったですが、エリアでしっかりやっていくと。それが将来的には農業とか、都会から来てみたいという人が入りやすくなる環境になるので、ここはしっかり力を入れていきたいと思います。
「(2)有機農業の推進など農業の高付加価値化への対応」についてです。今JA岐阜がやろうとしておられるように、有機にすることによって病害虫に強くなる。想定外に対応するために、品種改良についてもしっかりやっていきたいと思っていますし、その上で土から作り直すということで、これにもしっかり力を入れていきたいと思っています。
そして、「(3)農泊・ジビエなど中山間地域の魅力を生かした農村の活性化」について、先日に岐阜新聞に取り上げていただいた「農泊」、それからジビエ、やはり中山間地の魅力というのを、ただ寂れるのではなく、都会の人にとっては魅力があるということで、引き続き中身も入れ替えながらやっていきたいと。
それから、「(4)農業を支える多様な人材の育成・確保」で、やはり人材です。農業へ希望者、事業承継というよりはむしろやってみたい人にやりやすい環境、特に女性、外国人、若者ですが、その場合にはただ単に土といった昔のイメージではなくて、機械を使うこともありますから、そうしたものを体験する、この辺りもしっかりしたいと思います。そして、その上でできたものが売れなければ意味がないので、輸出拡大とか販売促進で海外そして都会に向けてプロモーションをやっていくということでございます。
[今後検討を進める施策]
今後は今言ったものをしっかり手厚くやっていきたいと思ってますし、特に2番目にある広域の狩猟チームについて、(害獣を)岐阜から追い出したら長野に行きましたということでは意味がないので、居場所もしっかり作っていくということも含めて。特に真ん中の項目について、山頂付近に居場所をしっかり作ってやるということを継続的やっていきたいと思っていますし、堆肥の活用、それから「アグリパーク」が出てきていますが、障がいのある方だけではなく、県外在住者も農業体験できるような場所をしっかり作っていくことによって、将来的な担い手を増やしていくということをしっかりやりたいと思っています。ここまでが「安心」の方です。
<6.山林や堆肥などを活用したクリーンなエネルギーを供給する>
ここから、「ワクワク」の方にいきます。12ページをご覧ください。
「(1)専門家を活用した森林経営改革の推進」について、専門家を活用した森林経営ということで、これは金額的にはそう大きいわけではないですが、技術というものをしっかり伝承すると、森林文化アカデミーを使いながらやっていくというものを少し手厚くします。
それから「(2)『脱炭素社会ぎふ』の実現に向けた森林の活用」の脱炭素社会、これはG-クレジットとして元々やっていますが、燃料材の生産目的として山の活用の方法を色々考えましょうというものです。
その次に、地産地消型の木質バイオマスの利用促進ということで、これは実際の作業が入るので金額は大きいのですが、間伐も同じことをやるのではなくて、しっかりその行き先も考えて、搬出の経路をしっかりやっていくということ。
それから「(4)脱炭素化に向けた再生可能エネルギー活用の促進」ということで、これは太陽光です。太陽光の導入促進ということですが、やれば良いというものではないので、昔商工労働部長の時にメガソーラーはやらせないと言っていましたが、やはり岐阜県の場合だと電圧が低いので、メガソーラーを作ってしまうと逆潮してしまうので、むしろ家庭サイズぐらいのところをしっかり応援していくということです。(メガソーラーを)やらせないとは言わないですが、あまり推奨しないという言い方ですが、そのようなことを考えているものです。
「(5)森林文化アカデミーを拠点とした技術者の確保・育成」について、森林文化アカデミーで技術者(を確保・育成していく)、これは大事なのでしっかりやりましょう。
[今後検討を進める施策]
この柱は、今後の方がちょっと面白いと思いますので、しっかり説明したいと思いますが、今のところこれまでの流れがあるので、従来予算の組替えぐらいで済んでいますが、むしろさらに手厚くしたいと思っているのは2つ目のバイオコークスです。経済林と言って、林業として使う部分以外を保水力を保つということと、先ほどの鳥獣の居場所にすると。そして、たくさんの木をどうするのかとなって、これを近畿大学の技術を使うと石炭と同じ状態にして保管ができるのと、石炭火力発電として使える、これもしっかり今後やっていきたいと思っています。それから先ほど太陽光(発電)しかなかったのですが、実は岐阜県は包蔵水力が全国1位です。小水力(発電)をしっかりやっていくことによって電気を安定的に確保し、山をしっかり安定させることによって、水の供給量が安定しますから、水力発電が有利になってきます。これから AIとかを使うととんでもない電気代がかかるので、やはり電気をしっかり作っていくところをやっていきたいと思っています。そして4番目、これが一つ目玉になると思いますが日本版ナショナルトラスト」です。これは何かというと、今は山が細かく細かく分割されてしまっているので、これによって道が作れない、所有者が分からないから木が降ろせないという大変なことになっています。ただ実際に所有権を確定しようと思うと、たった数万円の土地の所有権確定と登記をするのに下手をすると100万円位かかるということで、お分かりだと思いますが、今年の4月から相続に伴う不登記に対して10万円の過料がかかります。なのでびっくりするのですが、(所有権を確定して)やろうと思うと多分100万円位かかってしまうので、それではさすがに答えがないので、できればこれを財団か何かを作って一括してまとめることによって手続きを県でやると、その代わりいわゆる価値がない山は預けてくれと、場合によっては寄付してくれと、これによってイギリスのような自然を保安するナショナルトラストの岐阜県版というか日本版を作ることによって、山に林道を非常に作りやすい環境を作っていくと。そうすると林野庁の予算もうまく使えるようになるし、単なる作業道ではなくて、しっかりした林道を作ることによって搬出がすごく楽になるということで、これが多分この国の林業を妨げる最大の問題だと思いますので、そのモデルをこの岐阜県から作っていきたいなと。そして、このためのチームを作るというのは後で組織のところで申し上げますが、これは国の法制度にも関わる話なので、これをしっかり岐阜県発でやっていきたいと思っております。それから一番下に、岐阜県には大きくなった木を製材する機械がないので、それでも整備をすることによって、民間でやると多分ペイしないので持っていないですが、山の木を生かすためには要るかなということをしっかりやっていきたいと思っています。
<7.中堅中小企業の生産性を高め伝統産業の価値を発信する>
7番目は中小企業、ここからはベンチャー系なので私の1番得意分野ではあるのですが、まずはあるものをしっかり発信しようというのが「(1)本県が誇る地場産業の振興と伝統産業の未来への継承」です。これはいわゆる見本市といったブランディング、特に技法・伝統技能を承継できるようなアーカイブにもうちょっと力を入れたいと思います。
それから「(2)AI・ロボット技術等の活用による生産性向上の加速化支援」に、AI・ ロボットといった最先端のもの、特にAIをどこに使うかというと、今人が足りない時に、いわゆる製品の時にその人の動作をAIでと言いますかモーションキャプチャー(人体等の動きをデジタルで記録する技術)で確認することによって、不良品がどれぐらい出るかということを実は推定できるのです。この動きの時に不良品が出ると分かるので、そうしたものを使うことによって、熟練工でなくてもある程度(できる)。逆に言うと、不良品率を下げるとか、特に検品で画像処理技術を入れることによって、中小企業でも高い品質の維持ができる、省力ができるということです。
それから「(3)中小企業のイノベーション創出支援」ということで、特に研究機関との伴走です。今度また別の時に会見を開きますが、岐阜でいうとお酒、オリジナル酵母を使ってです。元バイオ課長(経済産業省生物化学産業課長)ということで申し上げると、杜氏さんがいろいろ手探りでやるのではなく、研究機関でやると。杜氏がやると一生かかって40回ぐらいしかできないのですが、研究所でやると2,000回できるとか、いろんな条件を変えることによって、新しいものを作ることができるということがあります。今度新酒を発表しますから楽しみにしてください。これは結構外国でいけるのではないかということで、そうしたものを応援するということです。
それから「(4)多様なニーズに対応した人材育成の促進」と「(5)『稼ぐ力』の強化に取り組む小規模事業者への支援」は実はセットになっていまして、これも先ほどの話に近いのですが、デジタル人材とかリスキリングです。今必要な仕事に対してリスキリング、要するに技能を研修することによって働きやすい人をつくると。(5)が受け手の方です。受け手の方では、先ほどの再掲になっているマイクロワーク、要するに9時5時を前提に1人の人が全部やるという働き方がこの国の基本になっていますが、そうではなくて、午前中だけとか、検査だけとか、それを切り分けることによって、今まで働けていなかった人、ないしは先ほどの9時3時で働いた後の時間帯も働けるとか、そうしたもので人を育てると同時に、企業の方から迎えに行く。(4)と(5)によって人材不足を減らしつつ生産性を上げる、そして世帯収入を増やしていくという、まさに中堅中小企業の大事なところであります。
[今後検討を進める施策]
(資料の)右側にはそれをもっと進めていこうと、特に伝統産業系のところでしっかりと手厚くやっていきたいということを今回やっていきたいと思っております。
<8.社会課題を解決し未来を拓く新たなビジネスや産業を生み出す>
それから8つ目。今度は今までは既存企業を強くするところだったのですが、やはり新しいものを見つけていかなければならないので、今度は地域課題、「課題があるところにビジネスチャンスあり」という世界をしっかりやっていきたいと思っております。例えば、さっきのお猿さん対策もそうですが、全国的なビジネスになり得るもの、そういったものを考えましょうと。ただ、その時にやはりDXを使うこともありますし、ここの部分はもう少し高度なところで、国家試験対策を応援するようなことも引き続きやっていきたいと思っています。
それから「(2)AI・ドローンなど先進技術等の活用による新たな価値創出」について、AI・ドローンを使いながら、岐阜県にはソフトピア(ジャパン)もありますし、テクノプラザもありますから、ここだけが高度な技術を持っていてももったいないので、それを実際にビジネス化するところを更に中身を充実させていこうと思っています。
そして「(3)インターンシップの活用等による高度外国人材等の就労促進」について、インターンシップということで、人材不足の中で今外国人労働者というのは注目されていますが、今回ご案内のとおり、研修技能実習生が特定技能に変わりましたので、そうすると転職ができてしまうわけです。そうすると選ばれない企業は本当に(実習生が)来ないということなってしまうので、したがって企業もただ安い人材を使おうなんていう発想をやめてくださいと。優秀な外国人材に来てもらえるように、選ばれる企業になるためにどうしたら良いのかということを、額は小さいのですが、すごく大事な予算としてやりたいと思います。
それから「(4)航空宇宙等次世代産業の成長に向けた支援」です。自動車産業自体も電気自動車に向けていろんな転換があったり、特に航空宇宙産業、1回残念なことがありましたが、やはりここで持っている技術というのは、将来に向かって宇宙産業も含めて、いろんなことがある中で、「ものづくり岐阜県」として参加できるようにしっかり応援していこうということです。
それから「(5)スタートアップの創出・成長に向けた支援」は再掲になるのですが、先ほどのスタートアップ、やはり小さなところであっても頑張ろうと、新しくやることをしっかり、特に先ほどの女性に手厚くやっていこうということも考えたいと思っております。
[今後検討を進める施策]
右側ほとんど再掲が多いのですが、特に先ほどの木を利用した石炭を作ることで一大産業になると思っていますし、下から2番目の空き家を活かしたいろんな体験、これも本当に資源として生かしていくといろいろできるかなと思っております。
<9.豊かな感性を育み多様な子どもが一緒に学ぶ教育を実現する>
9番目にいきます。今度はいよいよ子どもです。これも是非力を入れたいと思うのですが、産み育てるところまで行って彼らが成長していくところが大事かなと思っていまして、やはり故郷というのをいかに大事に思ってくれるかということを、演劇・ワークショップとかいろんなことをやりながら、高校だとか子どもの頃、小学校の頃から触れるということに力を入れるというのが「(1)ふるさと教育など豊かな人間性を育む教育の推進」です。
それから「(2)中高生等を対象にしたキャリア教育の充実」は、まさにキャリアとして専門性のところ、ここに対していろんな指導をしていく、体験することが結構大事なので、そのための実習設備を充実させるということ、それから先ほどの外国人について、今や美濃加茂の方でかなりの人数として来ている(外国人の)子どもたちをしっかり日本社会の中で活躍できるように応援をするというものであります。
それから「(3)デジタル人材育成に向けた教育環境の整備」、この時代はデジタルということがあるので、学校に(ICT機器等を)ばらまくということは文科省が何十億とくれるので良いのですが、これではなくて先生です。先生がしっかりそういう(デジタルの)ことを教えられるようにならないといけないということで、タブレットを更新したり、いかに教えていくのかということも大事になります。
そして今度は人で、「(4)教職員の働き方改革と優れた教職員の確保のための環境整備」です。そうは言っても、今いろんなことで先生方が大変になっている、校長先生、教頭先生も大変なことになっているので、こういうことをサポートする人材を供給していくために少し厚めにしています。あとは、まさに教員を確保するためということで、残念ながら岐阜県では先生がなかなか定着していないので、財政的な面で、奨学金の返還を楽にしてあげるとか、そういう形で定着を促そうというものです。
「(5)『ぎふ木育30年ビジョン』の実現に向けた木育の推進」について、やはり「木の国、山の国」としては木育ということが売りになりますので、木遊館のサテライトを郡上とか揖斐川に作ったりして少し増やしていくというものですが、今後更に展開していくことが基本になるかなと思っています。
[今後検討を進める施策]
(資料の)右側で触れておきたいのは、まず1番目で、やはり土や動物に触れるということで免疫力を高めるという体験をやりたいのと、特にやりたいのは2番目で、異年齢集団(による教育活動)です。1年生から3年生までを1つのクラス、4年生から6年生まで(を1つのクラス)で、同じ学年で切るからいろんないじめの問題が出てくるのですが、お兄ちゃんが小さい子の面倒を見る、お姉ちゃんが小さい子の面倒を見る、小さい子は今度自分が大きくなったら、また小さい子の面倒見るといういわゆるソーシャルスキルをしっかりやっていく。授業そのものも含めて、今後検討していきたいと思っております。そして1番下のインクルーシブ教育、不登校対応、フリースクールを分けるのではなくて、こういう子たちが一緒に学べるような環境を岐阜県がモデルになって作っていきたいと思っております。
<10.文化や芸術、スポーツなど人生を豊かにする活動を促進する>
そして最後になりますが、10番です。
特に、国民文化祭をやってきた、そして今年はねんりんピックもあるということで、本当に文化、芸術、スポーツを豊かにするということで、まずは何といっても世界に選ばれる観光地でなければいけないと。せっかく高地トレーニングもできるし、いろんな観光・文化もあるので、高付加価値な体験・コンテンツをやって、あともう一つオーバーツーリズム対策もここでしっかりやりたいなと思っております。
そして、「(2)文化を切り口とした地域の新たな魅力創出」です。文化を切り口とした新たな魅力の創造ということで、まだまだ良いものもたくさんあるのですが、発信できていないものもあるので、こうしたものをアートプロジェクトだとか、文化を切り口にして、まず地域の人たちが理解をして外に発信すると。どうしても文化は閉じてしまうことが多いので、発信する。後から組織図でその答えを出していきたいと思っていますが、(文化を)閉じずに、外に発信するということをしっかり力を入れていきたいと思っています。
それから「(3)文化活動への県民の参加促進」、やはり県民参加です。文化イヤーでやってきたこの流れを消してしまわないでということで、金額的にはそんなに多いわけではないのですが、(ぎふ)県民文化祭。あの「千人の第九」だとか、せっかく始まったものを消さないようにしていくことが大事です。
それから「(4)本県文化の魅力の国内外への発信」については、万博対応です。せっかく大阪・関西万博があって岐阜県も参加するので、しっかりと世界にアピールするということです。
それから「(5)スポーツ立県・ぎふづくりの推進」について、以前も言ったように日本の真ん中にあるということなので、いろんなフェスティバルやレクリエーションをやるには良い場所なので、そのためのいろんなアスリートの支援ということです。ねんりんピックは別(の予算)ですが、そういった価値あるものにしていくための取組みをしたいと思っています。
[今後検討を進める施策]
今後ということで、これだけたくさんの伝統文化がある県でありながら、何となく発信が少し弱いということがあるので、しっかりと(発信を)やっていくということです。それから3番目にある廃校となった校舎・公民館を使ってもっと安くいろんな活動ができる場所にしてあげたら良いのではないかということ。それから4番目の神社仏閣、特にお寺は昔は寺小屋だったんですよね。ある地域のコミュニティの場所としていろんな活躍の方法があるのではないかということ。それから5番目は、先程言った、せっかく日本の真ん中にあるので、いろんな大会を岐阜県でできるようにすると、そのためにまずある施設を開放するということです。できるだけ親しむことができる場所を作ることができたら良いなということでございます。
以上が、今回まさに江崎県政として10本の目標を直ちに進められるものとして、組替えも多いのですが、こういうことで、県民の皆様にお約束をした政策を実施していきたいと思っております。
その中で、せっかく記者の皆さんの前なので、目玉は何だと言うと、途中でも触れましたが、「政策オリンピック」と言ったものは、先ほどの鳥獣害対策、ニホンザル対策のモデルということで、1,500万円積んでいますが、ニホンザルにGPSを装着して、それをもとにやれることを考えようというのもありますし、優良事例として効果的なのは追い払いです。先程言ったように、殺処分すれば良いといったものではないので、動物愛護の観点もありますので、共存共栄できるような仕組みを考えて、とにかく農地、それから家庭への被害をなくすということで、良いアイデアを募集することを早速やりたいなと思っています。
それから、2つ目が県民参加型の防災訓練です。どうしても通り一辺倒の「点呼を取りました。」といったもので終わるのではなく、実際に他の模範となるような、子どもたちも参加をして実際に避難訓練をしてみるとか、その時に初めて条件が分かって、この橋が通れない時にどう回るかとか、あとは必ず飯盒炊爨だとか、実際に体験をするお祭りとは言いませんが、住民参加型のイベントを各地域でやる。非常に面白いということについては、一気に200万円ぐらい、そしてこれも10分の10でやってみてくださいということを3団体ぐらいを想定して600万円ぐらいですが、まずはやってみると。直ちにアイデアを活かして、いわゆるトップランナー方式と言うのですが、一番良いやり方を見つけて、それを他の地域に均霑(きんてん)していくと、こういうことをやりたいなと思っています。
それからこの4年間回ってきた中で、是非どうしてもすぐにやりたいということで、職員の皆さんにお願いして直ちに実現したいのが多胎児関係です。双子、三つ子さんです。本当に大変なのですが、第1子、第2子が双子であった場合、現行の県の祝金は、第1子には支給されず、第2子以降に支給されるという制度となっており、確かに私も子育てをやってみて、1人でも大変なのに同時に2人いたらとんでもなく大変だろうなと。まずは1人目からもちゃんとお金を出せるようにしましょうというのが1つ。それと先ほども言いましたが、児童養護施設の子というのは、施設にいる頃は良いのですが、そこから出た瞬間に本当にサポートがなくなってしまうと。特にあったのは芸術、アニメもそうですが、そういう分野に進みたいという子が次々と断念してしまう。やはり材料とか道具とか楽器が揃えられないということで本当に残念だったという話をたくさん聞きました。確かに、本当は家族とか応援してくれるべきものがないがゆえに諦めてしまうということがあまりにも(多い)ということなので、彼らに対しては、高校に行く時もそうなのですが、通常の3万円は(国から)来るのですが、それに10万円を上乗せして安心してまず高校に行きましょうということが一つ。それから高校から大学、これが一番(支援が)切れてしまうところなのですが、アルバイトで時間のほとんどを使ってしまって学業を諦めるということが非常に多いということを聞きましたので、そこに50万円ということで、まさに大学・専門学校に行く時の準備を安心してやってくださいということは直ちに始めたいと思っています。
当初はいろんな話もありましたが、子どもに関しては、こども家庭庁がこれからいろいろ手厚くやってくれると思っています。ただ、それが追いつくまでの間にも直ちにやれることをやると。したがって今後、こういった祝い金とか何とかというものを本当にありがたいと思っていない人も結構いるという話もあるのですが、今回は全部維持しますが、将来に向かってはこういったものを見直して、より意味のあるお金の使い方、本当に困っている人のところに制度としてやっていく。これは国だとある程度ざっくりとしかできないので、自治体ならではのきめ細かいやり方にして、県民や国民の皆さんの税金ですから、本当に意味ある使い方に次々と直していきたいと思っております。
【資料4】
そうしましたら、これを活かすために組織を直します。
いろんなものを全部ひっくるめて、これも1週間で見直しました。まず資料4の文章のあるページを左に置きながら、右手に赤と黄色の色がついている資料を見ると分かりやすいと思います。
まずは「総合企画部」、現在は「清流の国推進部」ですが、昔の「総合企画部」です。これは県内外に分かりやすい名前にするため、(名前を)「総合企画部」に戻します。その上で、その中に「未来創成局」、これが目玉の一つなのですが、先ほど申し上げました部局横断で政策を練り上げると言いますか、それこそ国とやらなければいけない仕事、先程の山の所有権、日本版ナショナルトラストを作るという、これは林政、農政全体に関わるようなところをここに人を集めてしっかりと法律問題も含めてやっていくようなチームを作りたいと思っております。それから働き方改革もそうです。国に対して、どちらかというとトップランナー方式をしっかりやった上でそれを広げていく。したがって、「政策オリンピック」の取りまとめをここにやってもらおうかと思っております。各部横断的であり、あとは女性の活躍のための仕組み作りだとか、あとは教育です。特に異年齢学級を作ったりとか、先程の故郷を2つ持つとか、空き家を活用して、これもやはり所有権、法制度に触れてくるものもあったりするので、そうしたものを各部横断的に考えて、まさに未来を創成する課というものを「未来創成局」に置きます。そしてこの中に、デジタル、今どうしても国全体がデジタルの進め方が、DXがふん詰まっているということで、こうしたものを新しい働き方の中で活かすという意味で、未来創成局の中に「デジタル戦略推進課」、「情報システム課」を持ってきて、まさに未来を創る局を新しく作ります。
それから、部として「子ども・女性部」。今回、10本の柱の大事なところで、やはり女性の活躍が重要ということで、これを部に昇格します。それでこの中に子どもたちということで、ここに私学振興課関係を持ってきます。なので、今回できたこども計画に基づく政策をしっかりやっていくということで、先ほど来申し上げたように、まず女性の就労支援、本当に多くの女性の方が活躍する場を与えられていない日本の国を変えていく、その1番大事なことをこのチームでしっかりやっていきたいと思っていますし、柔軟な勉強の仕方、やはり私学ということも結構ありますし、青少年健全育成もここに移管するということにします。
それから、3つ目は、「観光文化スポーツ部」です。元々「観光国際部」で観光しかやっていなかったですが、先程少し前振りをしましたが、文化はすごく良いものがあるのですが、閉じてしまっていることがあるので、そうしたものを外に発信するという意味において、やはり観光と一緒にすべきだろうということ。前の古田政権で一生懸命力を入れてやっていただいたものを、しっかり部として受け止めるということ。ただ文化スポーツだけでは同じことになっているので、ここに観光を付けることによって、世界に発信をしていく、県内外に発信していく。実はこれスポーツも然りで、健康ということも大事なブランドになっていますので、そうしたものをセットにするということで、「観光文化スポーツ部」として、ここにねんりんピックのチームも移して、この中でしっかりやっていくという体制を整えたいと思っています。
あとは、「環境エネルギー生活部」ということで、これも最近の温暖化、気候変動、災害の激甚化という中で、我々が何をしたら良いんだということで、特に省エネルギー、これはとても大事です。それから再生可能エネルギーの方に推進すると、一応整理としては「商工労働部」ではビジネスとして進める方に対して、「環境エネルギー生活部」は自分たちがどう取り組むかという整理です。したがって、脱炭素とあったものを、「省エネ・再エネ社会推進課」というように名称変更して、こちらに統合していくという形にしたいと思っております。まさに身の回りの問題です。
そして、これはもっぱら名称変更として1個足すぐらいでありますが、岐阜県のブランドである飛騨牛の銘柄のところに「食肉流通対策室」というものを設けて、しっかりブランド物を供給する体制も、これはどれぐらいニーズがあって、もう1回しっかり考えるということで、室を新たに設けてやってもらおうかと思っております。
(資料を)見ていただければ分かるという話ですが、今申し上げたように10の柱をしっかり推進して、県内外に発信する分かりやすい組織にと。これも人事課を中心に、1週間の大車輪で中の入替えも含めてやっていただきまして、これで予算組織も含めて江崎県政のスタートということにさせていただきたいと思っております。私からは以上です。
記者
先程からおっしゃっておりますように、すごく時間も少ない中でいろいろと自分のカラーをどう出していくかと言うところで、難しいところもあったと思うのですが、今回の予算、全体的に自己評価と言いますか、その辺はいかがでしょうか。
知事
一応、スタートとしては合格点に入れたのではないかと思っています。まずは、本当に県の職員の皆さんの力はすごいなと思ったのですが、もちろん既存の予算もちゃんとある中で、ほぼ前の体制のところで、もう9割方は組んであったものを、まさにこの10本に向けて柱を一瞬にして組み替えた上で、やはりその目玉になる予算というのを振るい出して、新規もしっかり作っていくことができたのは、偏に県職員の能力の高さだなと思いました。
記者
合格点というと、細かく言うと何点ぐらいでしょうか。
知事
何点ぐらいだと思いますか。それは、私が付けるのではなくて、聞いた人が付けるべきではないかと思いますが。
記者
大体70点とか80点ぐらいでしょうか。
知事
では80点にしておきます。先程の話、予算は8掛けでしたので。あと2割をこれから足していくということで。
記者
「政策オリンピック」も2つほど出してきましたが、その辺をモデルケースにしていくのかなと思っています。そこがある程度上手くいけば、国に提案していくということもおっしゃったと思いますが、その辺が先陣を切っていくようなものにしたいという気持ちがあるのでしょうか。
知事
まずは、「政策オリンピック」とは何だろうというのが多分あるのだと思っています。それから取り組みやすいもの、分かりやすいものでまず今回やってみて、ただ、これはまだ国に提案しなくても良いレベルの話なので、場合によっては先ほどの法制度を直していくようなものとか、そういったものも順次「政策オリンピック」のような形にしたいと思っていますし、今回の場合はお猿さんと防災訓練なので、大体聞く人はもう見えているのですが、できれば将来的には、子どもたち、小中学生も含めて、高校生も含めて、そういったことに参加しやすい仕組み、これは「未来創成局」の中でやり方も考えてもらいたいと思いますが、どのように括り出すと皆さんが参加できるかとか。抽象的なテーマを投げてもしょうがないので、ある程度分解して、予算も準備した上で、「さあ、何ができますか。」というぐらいのことがやれる、その一つの分かりやすいモデルとして今回2つ提示したところです。
記者
具体的に、どのように意見を募っていくことを考えていますか。
知事
今回の場合は、お猿さんの場合はチームでないと意味がないので、JAだったり自治体だったり。また、特に防災訓練はほとんど自治体です。もっと言うと町内会レベルでも良いです。ただあまり小さいとということもあるので、まずは市町村ですね。
記者
いろいろ見直した部分もあるのかなと想像はするのですが、これも言える範囲で良いのですが、削ったりとか見直した部分というのを差し支えない範囲でお願いします。
知事
先程、同じ予算の中でもパッと見の金額は同じに見えても、全部私が喋ってしまうと皆さんの出番がなくなってしまうのですが、特に女性のところを手厚くするだとか、子どものところでも割合を変えたりとか、出せる金額をちょっと増やしてみたりとか、そういったところの工夫はしてあります。
記者
組織改正のところで、「清流の国推進部」を「総合企画部」にすると紹介がありました。確かに、県内外にはこちらの方が分かりやすい部分もあるかなと思うのですが、一方でご自分のカラーというのを最初から出していくという気持ちも強かったのかなと思うのですが、その辺りいかがですか。
知事
どちらかというと、(バックボードに)ちゃんとミナモも入っているし、清流も入っていますが、やっぱり分かりやすさの方が大事かなと思っていて、特にこの「未来創成局」の人たちが国に行ったり他県に行って名刺を出した時に、(どのような部署か)分からないというのが良くないかなと。そこでワンクッション置いたらいけないということで、「総合企画部」と。別に「総合企画部」に私のカラーがあるとは思えないので、分かりやすさを重視しました。
記者
骨格的予算という言い方をしていて、骨格予算と何か明確に違いを設けられているのですか。
知事
骨格予算というのは、6割とか何とかということで必要経費の分だけを組むことが骨格予算で、「的」というのが、先程(もお話ししたとおり)公共事業の部分を8割にしたぐらいなので、「的」かなということです。満杯に積んでしまうと、前年と同額でどうのこうのとやるのですが、今回は増えていますが、基本的に義務的なところが増えているだけなので、全体としては縮んでいるので、そういう点では、後に少し残してありますというと「骨格的」。繰り返しますが、「骨格」と言ってしまうと6割とか何かを固めて、あと4割自由みたいなものなのですが、そうではないということで「的」が付いています。
記者
9,020億は、過去最大規模ということでよろしいですか。
知事
そうです。
記者
9,000億超えが岐阜県としては初めてということで、ただ一方で骨格的予算であるという今質問の中で、その骨格的の意味合いとしては、「資料1」の2ページ、3ページ目になりますが、普通建設事業費が前年度当初に比べて97億円ほど下がっていると。
知事
8掛けにしてあります。
記者
これが8掛けだということですね。その上で質問なのですが、2ページ目の先程ご説明いただいたその他の中のその他の276億円、これがいわゆる政策経費だと思うのですが、これは令和6年当初と比べると増えているのでしょうか、減っているのでしょうか。
財政課長
数字については調べて後ほど回答します。
記者
ここに骨格的は関わるのか、いわゆる義務的な経費の(投資的経費の)84億マイナスという部分が、これが本当に普通建設費、公共事業費の県単が減ったからという話なのか、6月補正予算でも更に政策経費を増やすみたいなニュアンスがあったのですが、この276億円の部分も8割というふうに考えた方が良いのか。
知事
別に骨格的でなくても良いのではないかと思っていたのですが、一応(投資的経費を)8掛けにしてあるから、色付けておくかというぐらいです。政策のところはほとんどフルにいけているのと、276億円について技術的な話をすると全部県費ではないです。もう少しマニアックなことを言うと、県費だともうちょっと小さくなります。ただ、それ(国からの予算)もうまく使って、こちらが動くことによって国の予算も使えます。この辺は6月でもまた増やしていこうと思っていますが、先程言ったように、8掛けにしないと令和15年に財政破綻をしてしまうので、その間ぐらいにする、それを全部建設(事業費)で戻すのか、それとも政策(経費)で戻すのか、これから更に議論を進めていくということになります。
記者
9,000億円超えで、過去最大規模と言っておきながら骨格的予算というと、意味合いが良く分からなくなるので、政策的な経費としてはもうフルで付けられたということで良いのでしょうか。
知事
もう少し分かりやすく言うと、(資料1の)2ページ目を見ていただくと、一番上の枠の中にあるように、9,000億円を超えたのは超えようと思って超えたのではなくて、義務的経費が(増えたことによって)159億円も増えてしまったので、出てしまったというだけで、これを除くと、80億円減っていますということなので、たまたま9,000億円を超えてしまったので、何となくすごい規模の予算を作ったように見えますが、借金返しとお年寄りが増えて交付税が増えたので、増えてしまっただけです。確かに、予算の見出し的には9,000億円超えと言っておきながら骨格ということは、まだブヨブヨなのかというと、一応もうちょっと増えると思います。9,000億超えというのは、(新聞等での)見出し的には使えますよね。あと、先程の80点満点を100点に変えてもらって、「本格予算を作成」みたいな(見出しも良いのではないか)。ただ、その中で8掛けしている部分というのは、建設(事業費)があるので、今後補正でちょっと増えるかもしれませんということがないわけではないかなというぐらいかな、正確に言うと。
記者
普通建設費用を抑えているので、全体として緊縮は緊縮なのですが、政策的にはいわゆる積極(予算)と言えるのでしょうか。
知事
一番分かりやすい言い方をすると、古田さんの時に作った予算案を組み替えることによって、江崎カラーを本当に見事に出してもらったということが一つと。その中で、額的には滅茶苦茶多くはないのですが、やるべきことを直ちにやれるようになったという意味では100点かもしれないですが、財政破綻しないために、まずは建設(事業費)、今すぐやらなければいけないものがあるので、それを見越して8掛けにしておいて、あとこれからどれぐらい必要なのかということ。また、さっき言ったみたいに、県費は少ないが、事業費規模を大きくできるいろんな術があるので、それをやることによって、(追加配布資料中の)この赤の真ん中のどの辺に持っていくか、中に建設事業費を増やす部分とうまくすれば、この政策経費も増やせるかもしれないというのが正確な説明なのですが、(細かい内容で)そんなこと記事に書けないでしょうから、まずは「9,000億超え」で「本格予算策定」ということで、10本の柱については再整理というぐらいが、多分見出し的には良いのではないかと。その上で、更に今後財政健全化も踏まえて、補正予算でこれに肉付けしていくというぐらいが一番正確なところです。増えるのかというとたぶん増えます。そういうことだと思います。
記者
何故(これらの質問をする)かと言いますと、予算にできたら名前を付けていただきたいという思いがあって。キャッチフレーズを。6月補正が終わった後でないとキャッチフレーズは付けられないということでしょうか。
知事
もう完全にできてしまったので、まさに「江崎県政予算始動」ということで、キャッチフレーズは皆さんが付けてください。正に「10本の柱」に(沿っていて)、ここまで見事にやっていただいて、私としても本当にありがたいなと思っています。
記者
南海トラフの被害想定の見直しというところですが、先程「政策オリンピック」の手法を用いて避難対策、県民参加、これをされるということでした。被害想定の見直しというのは、その素地として見直すというか、その知事の思いとして(いかがでしょうか)。
知事
あまり詳しく言ってはいけないのですが、今は割と岐阜大学の先生が昔やったものをそのまま借りてきているので、今のいろんな想定、気象庁も含めたいろんな条件が変わっているので、それに合わせる形でより最先端及び最新鋭の情報で想定し直した結果としてどれぐらい被害があるから、だからどこで何をしなければいけないかというのをやるということです。
記者
これは国の指示を受けてというよりは、知事の思いとして岐阜県独自で今回行うということでしょうか。
知事
防災チームの皆さんと話をしていたら、能登(半島地震)もあったので、しっかり見直ししておこうということです。
記者
南海トラフの被害想定の中で、今までは岐阜県の想定だけでしたが、例えば沿岸部、三重県、愛知県の沿岸部の避難想定というのも、今回初めて想定するということでよろしいですか。
知事
これから頼むので、そこまで頼んでも良いかなと思います。今まではやはり岐阜県の中だけで閉じるということで、自治体では当たり前の世界ですが、今回新しくお金をかけてしっかりやるので、そこも足しても良いかもしれません。今のところは、まず最新にしようと思っていますが、せっかく良いヒントをいただいたので、それもやった方が良いです。頼んでおきます。そうしないと岐阜県だけで計画すること自体多分意味がないと思うので。広域なので。
記者
予算資料にも、「他県からの避難者や」とあるので、将来的には沿岸の海の子どもたちにも避難しやすくするということですか。
知事
それも考えたいと思います。ここが私の政策の一番の目玉でございます。
記者
マイクロワークの話を各所でなされていまして、おそらくマイクロワークが大切なところは、企業側がいかに今ある仕事を細かく切って発注できるかというところにあると思います。ですから企業側にボールを投げられているような状況がありますが、実際問題、商工労働部としてもおそらく今走っていて、令和6年度も仕事の切り分けの支援みたいなことやっていらっしゃると思いますが、これを1歩も2歩も前に進められたいというのが江崎知事の思いだと思いますが、その手法というか、具体論はありますでしょうか。
知事
マイクロワークは中小企業の方にも出てくるのですが、こちらはどちらかというと企業の方で切り出すことになるのですが、マイクロワークというと、気が付いていないビジネスもあります。例えば、天気の良い日の観光地のレストランだと、天気が良いと200人ぐらい来て、天気が悪いと50人ぐらいしか来ないということで、そうすると何が起こるかというと、店員の数は50人(来客する)想定で作るので、天気が良いとみすみす150人見逃すので、マイクロワークというのは、今実際に行われているのは、朝9時に募集して、皿洗い3人、接客3人で、面接なしです。11時の15分前に来て、「あなたは今日は皿洗い。」、「あなたは今日は接客。」、そして3時まで終わると入金されるというのが典型的なサービス業系のマイクロワークで、それによって履歴が全部残るので、作業が上手かった人は次は優先的に取るという形にして、要するに新しく切り出すだけではなくて、新しくそういうことが使えるのだよということを教えていくことによって、特にサービス業系というのは、新しいチャンスがあります。そして、今度は企業として受け止めてもらって、そういう募集をするためには、ITシステムをちゃんと持っていなければいけないとか、そういうものを応援しますと。あともう一つは、伝統産業系のところがそうなのですが、全部1人で最初から最後までやってしまうのではなくて、例えば陶磁器の世界で言うと、シールを貼るだけ、これ実は子育て中のお母さんが1番良い仕事をするのですが、今までは誰かに丸々頼んでいた仕事を、おっしゃるとおり切り分けて、シールを貼るところだけを誰か別に募集しますというやり方を、企業さん方でやらなければいけないと。だから新しくマイクロワークとして、ビジネスとして作る部分と、従来企業が切り出す部分、それともう1つが先程のベンチャーとして、それ自体を仕事としてやっても良いという、だから3か所にあるというのはそういうことなのですが、それがうまく統合して発展すると良いかなと思います。
記者
今、「タイミー」とか全国規模でそういったものをビジネス的にやっていらっしゃるところがあって、そういうところと協定するのも、3本目はそうだと思うのですが、1番大切なところとしては、県内企業さん、県内事業者さんが、一歩踏み出すためのハードルが今のまま何とかやれば先細っていくのですが、かといって、一つ前に進めないというか、そこら辺のインセンティブを与えるというか、それかある意味動機付けをするということなのでしょうか。
知事
企業さんの方に支援する補助するというものが入っていて、例えば「坂口捺染」さんのように、元々出勤時間と退社時間のルールがない。それによっていろんな人が働けるというところを、むしろ健康経営として、県としても推奨して、逆に学生さんたちがそれにアプローチしやすいようなサイトを作るとか、国の方で表彰してもらうとか、あとエクセレント企業として県が応援するというところで、分かりやすく見せるということで、その時のやり方をまた括り出して、他の企業でもやってみませんかと広げる、そういったものがこの中に散りばめられていますので、全体としてはそのように進めていくということです。
記者
全体としてはトップランナーということですか。
知事
それもトップランナーですね。
記者
組織の見直しの点なのですが、まず「総合企画部」、「清流の国推進部」から改めたというところで、先日の就任会見で、「私になったから清流がなくなるわけではありません。」というお言葉もあったと思うのですが、この資料には、「分かりやすく示すため」というところがあると思うのですが、この辺りの思いについてもう少しお聞かせ願えたらなと思います。
知事
特に、岐阜県は他県からすると割とどこにあるか分からなくなりがちな都道府県ランキングで最下位だったりするので、やはり大事なことは、「清流の国」というのは岐阜県の人は分かっているのですが、県外の人が「清流の国」と言われて岐阜県を想定する人がどれぐらいいるだろうと考えた時に、これから他県との交流、それから国と仕事をする時に、例えば「未来創成局」の方は名刺を出した時に、「えっ。」って言われるよりかは、「そうなんですね。」と言われることの方がむしろ大事かなと。その上で「清流」は「清流」で大事にしたいと思っていますし、前申し上げたように、「清流」という言葉がイメージさせるものは人によってまだバラバラです。美山の私がイメージする「清流」と、都会の方が言う「清流」があるので、この「清流」という概念はもっともっと進化しても良いかなと。それは「観光国際」の中でもう1回ブラッシュアップしてもらって、「清流」というのがまさに岐阜県のシンボルになるのだったら、「『清流』といえば誰が考えたって岐阜だよね。」と、香川の「うどん県」がそうであるように、それが「清流」だったら「清流県」でも良いかなと思うのですが、今どちらかというと四万十川とかそっちを思う人がまだ多いので、だったらまずはこの政策をしっかり内外に発信するために、最も効果的な組織及びその名称にしたということに尽きます。
記者
この「未来創成局」についてなのですが、古田前知事も「清流の国づくり局」から、「清流の国推進部」というように部に昇格した経緯があったのですが、江崎知事の構想の中では、将来的に「未来創成部」であったりとか、そこに昇格していくような構想はあるのでしょうか。
知事
むしろ逆で、ここでまず一旦、部横断的なものをやったら、このメンバーは全員各部に併任しようと思っています。そちらに政策を持ち帰ってもらうというか、先程の不動産の登記が全然進まないが故に、実は農地の転用もできなければ、山の活用もできないということなので、このチームには「林政」、「農政」を中心に来てもらおうかなと。そうすると、ここで法改正ができたら、もうこのチームはいらないので(各部局に)帰ると。あともう1つ、教育でいうと、異年齢学級みたいなものを、教育基本法の関係だとかいろんな設置法の関係で整理をして、まずは私学からいこうと思っていますが、それがここに行ったら多分このチームはいらないので、むしろ部に昇格するというよりは、いつかは溶け込んでいくチームかなと。ただ、今それぞれのテーマを各部に投げてしまうと悶絶して終わってしまうと思うので、何故未来かというと、明日できるわけではないが、未来のために今仕込んでおく、場合によっては先ほどの日本版ナショナルトラストというのはおそらく税法との関係も出てくるでしょうし、場合によってはそのナショナルトラストができた時には、恐らくすごくいろんな問題を検討することになるでしょうから、しばらくはこれは残るし、部である必要は(ないかと思っています)。「総合企画部」というのはそういうことをやるところなので、その中でまさにスーパードリームチームを作るという、そんな感じです。
記者
今年は「農政」、「林政」であったりとか、来年は「教育」みたいなイメージで、こう一年毎に変わっていったりとか、そういうイメージでしょうか。
知事
同時並行的に、後でまた説明があるかもしれませんが、「未来創成課」の中に3チーム作ろうと思っていて、まさにその「働き方」のチームと、「農業・林業」、「ナショナルトラスト」チームと、あと「教育」チームぐらい。これを必要に応じて増やしていくということをまた今後考えていきたいと思います。
記者
組織の見直しのところなのですが、「環境エネルギー生活部」の関係なのですが、江崎知事も選挙前の政策集の発表のところで、バイオマス発電というところもすごく力を入れて、先程もお話があったと思うのですが、バイオマスとなってくれば「林政部」との関係も大きいかなと思うのですが、その辺りの考え方というのはいかがでしょうか。
知事
「林政」にいきなり投げてしまうと多分悶絶すると思うので、「林政」の方はどちらかというと今までどおりしっかり道路を作り、卸、林業としてやるというところにまずメインがあって、ただそれをやりやすくするための準備チームとして、ある意味「未来創成」の方で法制度のところ、まさに登記を簡単にするというのと、逆に言うとそこで出てくる木をどうするかということで、今まで林政は要するに材木になるところが基本、ないしせいぜいバイオマス発電のところに少し、これは商工労働部と一緒にやっていましたと。もっと本格的にバイオコークスまで作ってしまうという話を「未来創成」の方で議論しながら、ある意味やり方ですが、多分資源エネルギー庁と交渉しながら、それを作るための機械は結構お金がかかるので、多分県では無理なので、国からモデル的にやるので、国のお金を頂戴ということをやりに行く。それがこの「未来創成局」の仕事になって、その結果として、「林政」の方は切る方の作業をやってもらって、出た木をこちらで受け取る、多分ここはしばらくセットになってやっていくと。それがエネルギーとして売れるのなら、今度は「商工労働部」の世界になるので、エネルギーの販売のところに繋がっていく。多分各部完結型の仕事はこれからどんどん減っていくので、そういうのを「総合企画部」の「総合」は意外に良い名前だなと思っていて、その中にドリームチームを作ったということになりますから、多分今おっしゃっていただいた、「林政」の分野ではあるが、今までの仕事とは全く違う仕事になってくるので、そこをやり、ある程度「林政」の仕事としてそれも大事になってきたら、「未来創成局」のチームを解散して「林政」に戻すと、そういうことです。
記者
一般的な見地で、やはり縦割りというところが一般的なイメージとしてあると思うのですが、江崎知事のお話だと「未来創成局」が旗振り役になって各部を連携させていくようなイメージになってくるのでしょうか。
知事
私も国で働いてたので、逆に県にもいたのですが、県の方が縦割りでなく仕事ができます。国だと生涯その省だったりするので、全然他の文化を知らないのですが、県庁内だと顔も見ているし、同じ建物の中にいるし、どちらかというと縦割りじゃない仕事のしやすい中でも更にそれを進めるためにこの「総合企画部」の「未来創成局」を作ったという感じなので。元々経済産業省はあまり縦割り感がないのですが、更に県の方がもっと縦割り感がないし、私が県知事として戻ってきたのは、そういうスピード感のある仕事をやるためには、縦割りでは仕事はできないので、ただそれでも従来の仕事の中での整理がいるので、今回「未来創成局」を作ることによって加速したいという、そんな思いです。
記者
今回の予算について、金額的には最大ということで、捉え方としては、緊縮気味の本格予算みたいなところになるのでしょうか。
知事
そういう意味では緊縮はあまりしていないので、本格予算で良いのではないでしょうか。
記者
古田知事時代に予算の原案みたいなものが組まれていたと思うのですが、用意されていたものより、規模感としては増えているのか、減っているのかというところはどうでしょうか。
知事
ほぼ同じです。古田県政を引き継いだ上で、むしろそれを1番良い形で活かして、江崎県政に引き継いだという感じだと思います。予算も組織も全部、何一つ切り捨てることはしておりませんので。県職員の能力によってここまで見事に変えて、もちろんその中には表れてこない、同じ金額の中でも工夫がされているところも(あって)、後でまた各部から説明があると思いますが、そのようなすごく良い予算かなと思っています。
記者
用意されていた原案の中で、ほぼ同じところもあるという一方で、例えば、商工労働のヘルスケア産業のあたりとか、江崎知事がこの1週間で組み込まれた新規事業ではないかと思っているのですが、その一方で予算の規模感も同じとなると、廃止した部分、当初の原案より減らした部分もあると思うのですが、いかがでしょうか。
知事
あまりないです。廃止したのはほとんど、終了する予算ばかりのところです。場合によっては、私の時にもっと削ってしまって良いのではないかという議論があったのかもしれませんが、できるだけこれまで古田知事がやってこられたその結果として、こういうことはやりたい、やるべきではないかということで組まれた予算を原案としてもらっているので、ただ、私がこの4年間回ってきた結果としての「10本の柱」として、もちろん引き取れるものもありますから、引き取った上で足りない部分もあるので、そこを増やしつつ、もちろんその予算の枠の中でやりくりができますから、その中でもやり切ったという感じです。
記者
予算そのものを減らしたというよりかは、予定どおり終了したものの浮いた枠の中で、新たに例えば第二子以降の10万円の補助金の拡充とか、そういうところを進めたという認識でよろしいですか。
知事
それ自体もとんでもない額を積んでいるわけではないので、ただやはり、その同じお金をより良く活かすというか、従来やっていたものよりも、例えば先程の児童養護施設で育った子たちの苦しみというのは、元々55人しかいないので、それを活かすとそのお金でも多分助かるでしょうし、多胎児の方もそんなに無茶苦茶いるわけではないのですが、本当に苦しんでいた方に日が当てられないといった意味では、多少増えているのだと思いますが、その目立って何十億増えましたというわけではないのですが、よりきめ細かいというか、その現場にあった政策の課題に応えられるものは直ちに応えるという、そんな形です。
記者
(予算の)拡充等あると思うのですが、江崎知事がこの1週間で新規事業として組み込んだものがあればお伺いしたいです。
知事
鳥獣害対策で鹿対策しかなかったため、サル対策もやってくれと言いました。あと防災訓練もしっかりやってほしいというのと、先程の多胎児の話もそうですし、その辺りは目玉的に付けている部分があるかなという感じがしています。あと里親の話がそうですし、予算を手厚めにやったのですが、女性の稼ぐ力の辺りとか、この辺はしっかり積んでもらっています。ただ何かを犠牲にして何かをやったというよりは、予算の中を組み替えることによって、やるべきことをより丁寧にきめ細かくやったという、そんな感じかもしれません。あとは、元々国際基準に準拠した避難所とかをやらなければいけないこともあったので、その新規に組まれたものの中身をもう1回精査したりとか、パーテーションと簡易ベッドばかりではなく、医療コンテナとかそういった新しいものもちゃんと入れてよというように、予算の中で工夫をしています。
記者
元々の原案の中で、以前だと「清流の国づくり」と整理していたものを「10の目標」に合わせて整理したというのもあった上で、予算の増額とかはそんな大規模ではないということで、予算の積み方を変えたりということですが、鳥獣害対策といった「政策オリンピック」の2つのところは全くの新規と思ってよろしいのでしょうか。
知事
どのように予算費目を繰り出すかの説明のところで、予算技術上ちょっとマニアックになるのですが、「項」を立てるか「目」を立てるかとか、そういう意味では新規になるのですが、元々あったものから繰り出しているので、皆さんのイメージからすると、ボンボンと上に足しましたかとなるのですが、中で組み替えて、この分の予算の半分をもらってこっちにやってこれを新規にするという、そういう形でやってるので、トータルとして、すごく増えたり減ったりはしていないと。まさに予算技術の腕の見せ所です。
記者
国への政策提言を行っていくというお話がありましたが、こちらは例えば、現状は知事会から提言していくのがあると思いますが、県として国に提言というのは、どのようなプロセスを辿っていくのでしょうか。
知事
簡単に言うと法律改正を伴うものです。条例は自治体で作れますが、先ほどの山の所有権の問題だとか、いわゆる登記手続きのものというのは、法律に基づいていることなので、勝手に変えられません。ただ、こうした方が良いのではないかという前例を作った上で、国に提案していく。場合によっては、特区で抜いていくというのがありますので、特区申請をして、岐阜県だけこういうやり方をやらせてくれと。これでうまくいった暁には、国の方へ持って行って、法律改正も含めて制度そのものを見直してくれというのを、この岐阜県からバンバン発信していこうと思っています。
記者
「政策オリンピック」で良い例があればそれを前例としていくということですが、国にとっての岐阜県もそういう位置付けになっていけばという感じなのでしょうか。
知事
もちろんです。私がここに戻ってきたもう1つの最大の理由がそこで、この国全体がいろんな政策で行き詰っているので、それについて岐阜県からモデルを発信する。分かりやすく言うとまさに法律改正なのですが、そうではなくて、例えば農林水産省にしても他の役所にしても、補助金を付ける時に地域に対する補助金をこういう補助金にしてくれと。商工労働部長の時に、厚生労働省の緊急雇用の補助金があまりにも使いにくいからということで、審議会まで乗り込んで制度変えてくれということで274億円をもらってきたと。まさにあれをもうちょっと体系的にやりたいと思っています。
記者
国への提言に関連して「103万円の壁」の言及があったと思うのですが、「103万円の壁」をどうしていくべきかというご認識を伺えればと思います。
知事
元々は、ご案内のとおり、主に女性と言った方が良いかもしれませんが、本当は働けるのにそこのジャンプがあるが故にやめてしまうというのは、これだけ労働力が足りないと言っている時にこれがネックになっていると、これは国でやっている議論そのものです。「103万円」だけでなく、「106万円」、「130万円」の壁、それぞれあります。これは国がやってくれているので、その趣旨は良しだと思っています。ただ問題は、その結果として地方の財源が減るので、これはさすがに国の方もそのまま放っておくわけではないので、既にいろんな自治体がやっているように、そこの補填もちゃんとしてよねということさえできれば、女性を中心として今まで活躍したくてもできなかった人ができるようになるとか、それは結構なことだと思っているので、おそらくこれがいくらにするかという議論ばかり国がやっていますが、そうではなくて、そこはもっとグラデーションになっても良いのかなと。そもそもそういう制度自体がどうかというのは、国がやる議論なんですが、ただ逆に現場の方からすると、例えば「103万」が「120万」になったら良いのかどうかというのは、学者の議論ではなくて、現場の議論として、本当はもう10時間ぐらい働きたいということあるのか、それができたらまた発信していきたいなと思っています。
記者
「『政策オリンピック』は可能な限り実施します。」と言っていて、今まで「可能な限り」とはあまり入ってなかったと思うのですが。
知事
これは真面目な予算チームからすると、「実施します。」と言うと「今回の予算で全部やるのですか。」という質問が来そうなので、まずは可能な限り2個やりますと。これから補正でやるか来年度にやるかも含めて、可能な限り前倒してやりますというか、やれるところからどんどんやっていきたいと、そんな思いの言葉だという解釈をしていただければと思います。
記者
「10の目標」のうち、鳥獣害対策とかのところで、やれる項目をとりあえずやっていき、今後も「政策オリンピック」、それが市町村から募る形になるか自治会から募る形になるのか分からないですが、各項目と言うべきか、それとも各事業と言うべきかわかりませんが、続けていくということでよろしいですか。
知事
役人が「可能な限り」と書くとやらないということではないかと言うことですが、そんなことはないです。既に2つやるというのと、実は私のところには既に「政策オリンピック」の提案という紙が届いています。あと、世の中的にはこの10個の項目について「政策オリンピック」をやると思っている人が多いので、だからやり方も含めてというか、この抽象的なままオリンピックをやっても分からないと思います。あとできれば中高生、場合によっては小学生も含めて参加してもらいたいと思っているので、もう少し噛み砕いて、「ここの部分について皆さんのアイディアを募集します。」というオリンピックのやり方もあるかなと。これはテーマによってレベル感が違ってくるし、先程の自治体とか農協でないと提案できないというものもあるので、そういうものも含めて、まず今回は2つやってみて、先ほどの「未来創成局」の方の「政策オリンピック」チームの方で、やり方も考えてもらって発信していくということになって、それがいわゆるトップランナー方式のやり方だと思います。
記者
財政調整基金について、120億程度取り崩して一般会計の繰り入れが想定されていると思います。かなり大きな額で、このペースで行くと2、3年後にはなくなってしまうのかなという勢いですが、そこまで大きく踏み込んで財政調整基金を取り崩してでもやる事業というのは一体何を想定しているのかと。これをどこに当てたいという部分があるのかということと、このままでは当然いけないと思うので、例えば今後の積み立てについて、どのような考えをお持ちなのか。今後残高についてどういった見通しを立てられているのか教えてください。
知事
後で細かいところは財政課から説明がありますが、取り崩しているものは、例えば一発物で今回載せていませんが、でかいものがあったりします。「ねんりんピック」の予算とか。そういうもので、調整基金はまさに調整のための基金なので、削ってばかりではなくて結構積んだりもします。余裕がある時に積んで、そういう一過性のものの時に崩してということをやっていくので、何のためにと言うとまさにそういうものの調整として使っているのですが、財政課から更に詳しい説明をどうぞ。
財政課長
今、知事からあったように、そういう臨時的な歳出がある場合もございますし、最終的に予算全体をやりくりする中で足らないところをこういった基金を活用しながら予算を組んでいくという形になりますので、トータルの中でのこの取り崩しになっているということになります。
知事
1対1でやっているわけではなくて全体としてやってるので、それから前のやつを引き継いでいる部分もベースになっていますから、そして合わせたというぐらいです。また今後、ゼロから突っ込める時に今の問いにお答えできるようにしっかりしていきたいと思っています。
記者
今のところは、まだ今後どのように積み立てていくとかいうところまで考えていないということですか。
知事
そうです。グラフを見ていただいたとおり、こういう状況なので。
記者
基金の件なのですが、公立中学校等情報機器整備基金というのが、これもかなり大きく崩されて、残高も7年度末には2,700万ほどになると。これはおそらく使途にかなり縛りがある基金なので、今日のレクを聞いていると、高度なICT機器の整備とか、この辺に充てることを想定しているのかなと思ったのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
財政課長
まさに今おっしゃっていただいたように、その目的に使っている基金でございますので、学校でのICT機器であったりとか、パソコンとか、そういったものに活用しているということになります。
記者
普通建設事業費について、骨格予算だから8掛けだというご説明があったと思います。なかなか財政が厳しいので、この辺で積極財政というのは難しいと思いますが、敢えて優先順位を高めにして進めていくべき建設事業・公共事業は、どの辺の項目があるのかというような考えがあれば教えてください。先般の埼玉県で老朽化した下水道管の破損による大きな事故が起きたりもして、各自治体も非常に注目しているところかと思いますが、直接は基礎自治体かもしれませんが、県として何かできるようなこととかを考えていらっしゃるのでしょうか。
知事
実は、(普通建設事業費が)8掛けというのは、古田知事から引継ぎの時に「8掛けにしておいたよ。」と言われたから、「そうですか。」ということで、とりあえず8掛けなのですが、おっしゃるとおり、昨年と同じくにしてしまうと破綻してしまうので、むしろ県として大事にしたいのは、やはり防災関係です。特に、今既に半分指示はしているのですが、おそらくこれから起こる、今回の雪は想定外ではあったのですが、やはり雨です。雨によっては、河川が氾濫するとか堤防がおかしくなるとか、もっと言うと、河川敷に生えているものとかいろんなものがあるのですが、そういったものを計画的にやっていく中で、何にもない時にやると県費だけでやることになるので、何かあった時に国のお金を使えるだけ使えるように、あってから考えるのではなくて、ある前に考えておくようにという指示はしてあります。そうするとまずは県民の安全・安心が最優先ですから、防災的に危ないというところをリストアップして、何かあった時に、今回直すのであれば一気にここまでやってしまうと。そこにこの県単の予算を使うことによって、より防災の機関として、県土を強くしていくと。もちろん潤沢にあれば何もない時にやっておけば良いのですが、そうならないようにそういうことを直ちにできるように準備をするというのが、まさにこれからのポイントになります。
記者
2021年度以降に公債費が増加しているようなグラフになっているかと思います。これの原因としてはどのようなことが考えられるのか、ちょうどコロナ禍が激しかった時期とも繋がるような気もしますが、関係あるのでしょうか。
知事
基本的には国土強靱化です。災害対策です。「こんなに(予算を)積んで」と思っているかもしれませんが、やはりそれなりにニーズがあって積んでいるので、これはこれで必要な(ものです)。逆にコロナがあったが故に、そこに手が回ってなかったために頭が凹んでいるだけかもしれなくて、コロナはどちらかというと大半が国費でやったので、やはり県土整備系になるとどうしても県の支出が出てくるので、こうしたグラフになったと理解いただければと思います。
記者
古田知事が作られた当初1月時点の予算からの整理の方法で、もう一度確認なのですが、1月30日、31日辺りに、県のホームページでも予算編成過程ということで、どういう予算を今年度考えていますというものを県として出していらっしゃると思います。そこからこの「10の目標」に整理するというのは、この選挙前の公約について、この目標にはこういった予算というような割当てをしていったというイメージなのでしょうか。
知事
まず引き継いでから、私が着任するまでは一切それ(予算)を触っていないので、着任した後の(2月)7日の日に初めて予算を聞いて、そこから一気にここまで持ってきたということです。ですから、当初古田県政で組んでいた予算案がもう既にありましたので、その中で全部精査をして、どれがどの10項目に当てはまるかというのと、更にその中でこの政策に合うように、金額はあまり変えていませんが、中身を組み替えるということを、県職員の方がこれに基づいて一気にやっていただいたと、そういうことです。
記者
中身を組み替えるというところは、先ほどおっしゃったように、鳥獣害対策のサルの話であるとか、多胎児の方への補助ですとか、あと児童福祉施設、その辺りが中身を足したところでしょうか。
知事
先程の話で、鳥獣害対策で鹿対策しかなかったので、「何で鹿なんだ。」と思いながらでした。あと同じ予算を使うのであればこっちでも良いのではないかとか。あとは子どもの支援の中で、特に同じ支援をするベンチャーの中でも女性の方に手厚くするとか、その辺りは本当に職員の方がいろいろ知恵を絞ってやってくださったということです。
記者
この間の就任された直後の会見の時も、どういうことをやっていくのかということを予算で示していくということの大事さを語っていらっしゃったと思うのですが、改めて江崎知事になって予算を整理して、10の項目に揃えていくことの意義、そこで伝えたい思いはどのようなものなのか教えていただけますか。
知事
特にこの4年間回って、この県の課題というものは整理できているので、引き継いだ予算も県民の皆さんへのお答えとして、こういうふうにこの10の項目を進めていきますよと。これは1年でできるものではありませんが、まずは初年度として、よく言われたのが、「時間がないので前もって組んだ予算をとりあえずもらっておいて、執行の時に変えたら良いのではないか。」と言う人もいましたが、それでは県民の皆さんが分からないので、まずは大車輪でありましたが、この1週間でこの10項目に組み替えると。さらには、今回特に分かりやすいところで、先ほど申し上げました「政策オリンピック」にしたような、本当に困っておられるようなところには、直ちにそれ(予算)を乗せるということです。それができた結果として今日発表させていただいたということです。普通はこれ(予算編成)は2、3か月かけてやることですが、1週間でできたということです。
記者
スピード感というのはかなり意識されましたか。
知事
そうです。ですから、6月補正予算でやってはどうかという議論もいっぱい聞こえてきましたが、それでは遅いと。まさに防災は待ったなしですし、本当に困っておられる方はたくさんいらっしゃるので、直ちにやる、スピード感で変わるのだということを分かっていただけると良いかなと。「安心」と「ワクワク」を直ちに発信すると、そんな思いです。
記者
「資料3」の最初に、先ほどの質問で「(今回の予算に)名前を付けて」という話もあったとは思うのですが、今回の政策のテーマは「安心と挑戦」ということでよろしかったですか。
知事
「安心と挑戦の予算」ということでいかがですか。先ほど見ていただいた資料2の左側の方でちょっと「安心」の方が手厚くなっているというか、204億円の配分が「安心」の方が手厚めで、あとは本当に重点のところには重点(的に配分して)というところです。
記者
先ほど知事が、今回あえて中身を加えたところで防災訓練、それから鳥獣害の話ということがありました。資料3の冒頭でも人口減少というのが最大のテーマと書いてありますが、その人口減少対策については、いろんな政策が関連しているとは思いますが、今回特に力を入れているところはどんなところでしょうか。
知事
先程の説明でも(申し上げましたが)前半に力を入れたのは女性です。女性の方が持っている力を発揮するということと、ただ仕事があれば良いわけではなく、ワクワクしながら働ける、そのために新しい働き方、企業の方にも協力してもらって、1番能力を発揮できるところに送り出す。昔のように、一旦勤めたら徹夜残業も含めて気合と根性だみたいな、そういうことはやめようということで、強力に引っ張るし、女性の方がベンチャーをやる時には補助率も上げるし、とにかく頑張れというメッセージをしっかり出したいと思っています。
記者
超時短勤務であるとか、ダブルワークの話になってくると、やはりその労働者の安全をどう守るかと言いますか、長時間労働をどう防ぐかとか、時間管理をどうするかという議論になってくると思いますが、その辺りどのように対策をしていきたいと思っていますか。
知事
おっしゃる通りで、まず全体として増えれば良いと思っているのではなくて、以前もお話ししましたが、9時から5時の仕事を9時から3時で終われれば、企業としてみれば9時5時の分だけお金を払っても良いわけです。今は9時5時の仕事を8時まで引っ張って生産性が下がっているところに、最低賃金を上げろと議論しているから、企業が付いてこれないと。むしろ逆で、世帯収入とか可処分所得が増えれば良いわけなので、9時5時の仕事をまず3時までに終わるということを基本にできませんかというのが一つ。その上で、余った時間に働くなというわけではなくて、自分の趣味でも良いです、得意なことで(も良いです)。寝ずに頑張るというような働き方ではなくて、得意な分野を活かして、ちょっとICTを使いながらこういうサービスができる、いろんな経理もできる、デザインもできるということで働くようになれば、まさに長時間労働で苦しむとは別の働き方、その上で可処分所得が増えると。将来的にはこのチームで整理していくのですが、社会保障をどちらが払うのかという問題とかいろいろ出てくるので、ここは国の方に先んじて提案をしていくと。場合によっては、マイクロワークの方の収入が多くなった場合ということを、この国の制度はまだ想定していないので、それを先んじていろいろ課題整理をしていくこともあるかなと思っています。
記者
歳入が増加しているかと思いますが、その分について資料1では、「県民生活の安定や豊かさの確保のために有効に使っていく」とお書きになられているかと思います。一方で、その増えた分は義務的経費に消えてしまっているところがあるのかなと思うのですが、どのように県民の生活の安定や豊かさの確保のために使っていこうとお考えですか。
知事
この表現を入れたのは私なのですが、元々の原案は、「収入は増えているが、将来が心配だからいけない」と書いてあったものをあえてこう書いたのは、(収入が)増えたのは景気が良くなって増えているわけではなく、物価が上がっている、要するに県民や国民が苦しんでいる中で税金が上がってしまったことによるお金なので、今収入は増えているからあれをやりたい、これをやりたいといろいろ出てくるわけですが、その中でそのお金というのは県民の苦しみの中で出てきてしまったお金なので、やはり県民が楽になる方向により優先的に使うべきではないかという、ある意味メッセージとして書かせていただきました。お金に色は付いていないので、ぐるぐると回せばあるのですが、どうしてもパーツだけを見ると、県の収入が増えているから「あれもやってくれ、これもやってくれ。」という話になります。しかし、先程の本当に困っている方々、まさに多胎児(をお持ちのご家庭)だとか、施設で働いている子たちというのは、まともに(物価高騰などの影響を)食らってくるので、そういうところへはちゃんとすぐに発信できたら良いかなと、そういうことでやっています。
記者
お金が増えたからいろんなことをやるというよりは、むしろ優先順位を付けていく必要が高まっていることが言いたかったということでしょうか。
知事
そのとおりです。より生活に密着した方向に優先順位を高める方が良いのではないかというメッセージです。
記者
公債費の推移と今後の見込みの話なのですが、今回(普通建設事業費が)8掛けの骨格的予算ということで、今後6月補正(予算)以降にさらに積み増していくとなると、お示しいただいた黄色の発行ベースより増えると思うのですが、その見込みとして、令和6年度3月補正後の金額よりは減らしていこうというお考えでしょうか。
知事
減らさないと破綻してしまいます。
記者
この残りの部分の中で、少し増やすなりするということですか。
知事
正確に説明をすると、これは県費で返す部分の話をしています。ですから、これが減ったらその額だけ事業費が減ると考えるのが普通なのですが、そうではなくて、例えばこのお金を10使うことによって国のお金が100使えることがあります。一方で、県のお金を10使っても、国のお金が20しか使えない予算の使い方もあります。そうすると、県の皆さんとか事業者の皆さんにとっても、最終的な事業費が100あれば良い時に、その100をやるために県費を50使うのか、10で良いのかということは、まさにこれから知恵の使いどころになります。防災も含めて、(事が)起きてからではなくて、今から準備しておいてと指示をしましたが、公債費の黄色が少しだったら、去年よりも事業費が減るかというとそういうことではなく、黄色は減るが事業費を増やす方法はあります。そこにこそ知恵を使おうということなのです。単純に言うと、黄色が増えないと去年と同じ事業はできないのではないかと言う人がいるのですが、そんなことはないです。去年よりも予算が少なくても事業費全体を増やす方法はあるので、それでやりますという話です。
記者
先程、人口減少に関して、まずは女性の働き方に取り組みたいということをおっしゃっていましたが、他に取り組んでいる部分があればご説明いただきたいのと、今回は(予算編成までに)かなり短い期間だったと思うので、今後6月(補正予算)以降も含めて、プラスしていきたいものがあれば教えてください。
知事
まさに女性ということと、それと子どもです。女性の働き方がまず第一で、その次は子どもを産み育てやすい環境です。今産まれても活躍するのは20年後ではありますが、まずそのベースをしっかりやるということが、ある意味人口流出防止のために、女性が活躍できる場所を作ることが一つ。それから、県内で子どもを産もうと思ったら、産み育てやすい環境を作ることが2つ目、これが人口減少のための大事な話です。それをサポートするものとして、せっかく生まれた子どもたちが教育その他で苦しまないように、里親も含めていろんな支援をする、安心して将来を考えるようにすることが3つ目ということです。そういう段階にして、まさに人口減少をやりたいと思っています。それで、将来的には先ほど申し上げたように、県内で生まれるかどうかだけで議論していてはいけないので、「海の子を山に、山の子を海に」と言っているように、子どもたちに林間学校のような形で、子どもが少ないところに、例えば三重県、愛知県の海の子を1週間預かる、逆にこちらの子を1週間預かってもらう。さすがに今回はできないのですが、そうしたことで交流人口を増やしていくという形で、故郷を2つ持つ、向こうにとっても人口が増えるし、こちらも人口が増えると。そういうことをやりつつ、将来的にはリニアも活用して、東京とそういったことをやる、範囲を広げていくことを今後の取組みでやりたいと思っています。
記者
交流人口の話があったと思いますが、新年度かそれともこの4年間か、いつまでに取り組みたいという思いはありますか。
知事
できればすぐにやりたいなと思っています。しかし、さすがにこの1週間では無理だったので、まだやっていませんが例えば防災訓練だとか、そういったものにもいろんな外の人も入ってもらったりとか、最終的には観光客にも入ってもらうということでも良いかなと、例えば、三重県の子が岐阜に来ている時を狙って防災訓練をやってみるということも大事になってくると思っています。
記者
「未来創成局」について、今すぐやりたいこと、先程会見でおっしゃっていましたが、将来的な抱負と言いますか、「未来創成局」で今後こういうことをやっていきたいと期待することを教えてください。
知事
まずは先ほど申し上げた3つ、働き方の問題と、それから山のエネルギーがあって、土地の所有権について解除していくというか、日本版ナショナルトラストを作っていくという話、これが結構重たい話ではありますが、そういうのを考えてほしいと。それともう一つが、子どもの教育の中で順番をどうするかということもありますが、これからやりますが、異年齢学級だとか、先程の他の県の方と交流するといったものは一朝一夕にはできませんが、いろんな法制度も絡んだりということがありますが、そうした3つのチームを予定しているので、そこからまず取り組んでもらいたいと思っています。
記者
「未来創成局」があることで、岐阜県はこういう県なんだとか、国にどのように提言していきたいかという全体的な抱負、意気込みを教えてください。
知事
この言葉を使うとニュースになりますが、「政策独立国」になろうと思っています。それで、この日本で必要な政策の答えは全てこの岐阜県から発信することで、しかも県の中で閉じてしまうのではなく、国全体に均転すべき政策をこの岐阜県から発信することが「未来創成局」の役割だと思っています。
記者
予算のところですが、(予算額が)9,020億円となる大台の予算の中で、高齢化の進展に伴う社会保障費であったり、人件費が上がるというところで、自由に政策に使えるところが限られていると思うのですが、今日の会見でいろいろと独自性を出されて予算を組まれていた印象があります。今後、固定費でかかる部分は維持しながら、独自カラーを出していくためにやっていきたいこと、抱負を教えてください。
知事
私が(以前に県庁にいた時の)生き残りはいないのですが、商工労働部長であった時に政策予算がゼロだったところでやっていましたので、お金がなければ知恵を出そうということでやっていました。なので、(今回は政策経費が)276億円もあるので、これをいかにうまく使えるかだけでもいろいろできるかなと思っていますし、先ほども申し上げた「レバレッジ」と言って、県がお金を10出すことによって、国の予算を100もらうことができると、そういうものがありますし、もっと言うと、県の予算がゼロであったとしても、国に制度を作ってもらえれば、まさにそれで当時は270億円をもらってきていましたから、当時一緒に働いたメンバーがまだ残っていますので、お金がないから政策ができないなんてことは岐阜県ではありえないということで、まさに知恵の勝負をしていきたいと思っています。
記者
予算全体というか、公共事業についての考え方を伺いたいのですが、県が行う事業について、必要なものをやっていくのはもちろんだと思うのですが、梶原知事だと公共事業によって需要喚起していこうという公共投資的な意味合いのものを県がやって、需要を喚起して乗数効果を狙っていくという考え方もあると思います。一方で、そもそも県の予算が限られているから、そのようなことに投資する経費もないといった考え方もあります。県が行う事業について、そもそもどういう効果を期待してやるものなのかということについて、どういうお考えでいらっしゃるのか伺えればと思います。
知事
基本的には、経済対策で公共事業が多いというのは、今だいぶ変わったかもしれませんが、以前議論した時は、この国の労働者の10人に1人は建設関係です。なので、景気対策というと、公共事業にはそれなりの合理性がありました。その時は確か県の基金が2,600億円位ありました。ある意味国とかに頼らなくても十分やれたので、梶原知事はその基金を全部吸った上でまた借金しているので、その借金が古田県政の時にドカンと乗ってきて大変だったし、そして古田県政の時の借金の先送りがこれから私にドカンと乗ってくるということなので、おっしゃる通り、公共事業は間違ってはいないのですが、梶原知事の時のように先送りにしないで、そうすると知恵の使い方で、本当に少ない金額でありますが、今おっしゃったような公共事業による経済効果はありますので、なので先ほど申し上げたように県費は減ったとしても、相対としての事業が減らさずに、むしろ増やしたら良いでしょうということで、増やすための知恵を使うべく既に指示をしているところです。
記者
国の補助が得られる事業というものもあると思うのですが、乗数効果が大きいところで、15年位前の話になりますが、「コンクリートから人へ」と投資先を公共事業や箱物ではなくて、人への投資の方が良いのではないかという議論があったと思います。知事としては、特にどういう分野に対して投資をしていきたいみたいなものがあれば伺えると幸いです。
知事
右か左かという議論は私は正しくないと思っていて、やはり防災を考えたら、建設関係は絶対必要です。それからやはり日本の真ん中にある岐阜県にとって、人やモノが集まるためには、道路は絶対に必要です。道路があるから良いのではなくて、将来的にどれぐらいの物流とか人流を考えて、どんなインフラを考えなければいけないかということが必要なことです。ただ逆に景気さえ良ければということで、公共事業だけやっていたら良いということではもちろんなくて、人口減少にしっかり対応していくということと、やはり人から選ばれる岐阜県であるためには、ただ仕事があれば良いわけではなくて、そこで人が育つと、特に教育というのはすごく大事だと思っていて、やはり子どもを産み育てるのだったら岐阜県だよねということを考えると、人に対する投資はすごく大きいと思います。今日は予算の説明ですが、一番大きく抜けているのは、世の中には国のお金と県のお金だけではなくて、民間のお金というものもあります。むしろそのお金を呼び込むことによって経済が活性化するということは、元経済産業省出身の私からすると最も大事かなと思っているので、これから政策の中でその辺りを厚めにやっていきたいと思っています。
記者
経済産業省ご出身ということですが、経済産業省をイメージとした規則緩和、経済産業省は規制官庁ではなくて規制緩和をしていくイメージですが、県としても規制緩和という方向で、スタートアップなどがやりやすくなる環境を整えていく方向に今後進んでいくのでしょうか。
知事
規制を1つ緩和することと、100億円の予算を付けることとほぼ同じぐらいだという議論を以前にしたことがありまして、規制はもちろん意味があって存在しているので、ただ緩和すれば良いわけではなくて、要するに時代に合わなくなっている制度、先ほど申し上げたように、不動産の登記をする時には、全て過去に遡って登記をしなければいけない。それはなりすましだとかの防止のために必要なのですが、今は本人確認さえ出来ればこれを飛ばしても良い。しかし、放っておくとその制度は延々と残っているし、まさに食料安全保障の農地の問題だとか、いつも工場を建てる時に問題になるのですが、その手続きさえ合理化すれば、もっと迅速に対応できるかもしれないし、農業とかやりたい人がたくさんいるのに、手続きが大変すぎてできないということがあるのであれば、むしろそこを緩和していくということは充分あり得るかなと思っていますし、そういうことこそ、「未来創成局」の仕事でもあり、各部が積極的に、はじめに制度ありきではなく、制度も変えられるのだということで、「政策独立国」としてそのチャレンジを岐阜県からしていきたいと思っています。
記者
組織の見直しについてお伺いします。部が1つ増えることになっていますが、部が1つ増えるとかいろんな組織が発生する中で、人件費に対して、どういう影響があったかを教えていただきたいです。
知事
実は引継ぎの時に、古田知事に組織を増やそうと思うと言うと、「それは自由にできるよ」という話だったので、手続きは条例でできます。あと、今おっしゃったとおり、そこに配置する人、これから人繰りの問題で、部長の中でも、給料が高い人、低い人がいるので、そのあたりも勘案しながら配置していくと。新しく雇うわけではないので、やりくりの中で部ができたので、縦に全部人が増えるわけではないので、部長名が1名が増えるぐらいなので、その人の給与分が少し増えるかなと。新しい部長さんだとそんなに増えないので、予算的にはほぼ影響ないと思います。
記者
少し細かいのですが、課内室というところで、「増1」ということで、「食肉流通対策室」が挙げられていますが、これはどの部門からどう切り分けたのでしょうか。
知事
4年間回っている中で、やはり飛騨牛というのは県にとってもすごく大事なものですが、その処理場問題、私もいろいろ回ってきましたが、今県内で4つある中で3つが老朽化していて、今後どうするかという問題がなかなか進まないという話を聞きました。商工労働部長の時もこれに関わっていたのですが、ハラールの問題で、県内に作るかどうかは結構難しい問題であることは知ってました。ただ、実際回ってみるといろんな利害関係もあって難しいなということは聞いていたので、一旦しっかり室を作って、誰がやるのだろうではなくて、一度県として飛騨牛を将来どうするのかと。「銘柄推進室」がありますから、その知見を活かしながら、どこまで増やして、そのために県内でどれぐらい処理する必要があって、以前は群馬かどこかに持っていくという議論だったのですが、これだけエネルギーが高い中で持っていくのかという議論も含めて、そのコストも考えると、県内に置くべき処理場の規模と、それをどうするのか。この中におそらく誰が費用を持つのかという議論の中で、いろんな知恵があると思っていますので、それは県とか市町村とか、組合だけではなくて、PFIと言って民間のお金を入れる方法もあると思います。ただ、放っておくと誰もやらないので、しっかり担当を作って、議論をするために作りました。
記者
マイクロワークのことなのですが、知事は県庁内の働き方改革もいろいろおっしゃってると思うのですが、県庁内でマイクロワークを導入するとか、そういったお考えはありますでしょうか。
知事
そういったものがあっても良いかなと思っていて、私が内閣府にいる時に毎週会議をやっていましたが、一度も出勤していない人が結構いました。とある人も子育てを神奈川かどこかでしていたかと思いますが、そういうこともできるんだということで見ているので、おそらくそういったいろんな事情がある方も多いでしょうから、実験的にやってみたいなと思っています。まだ誰がどうなってということを聞いてないですが、柔軟に考えたいと思います。