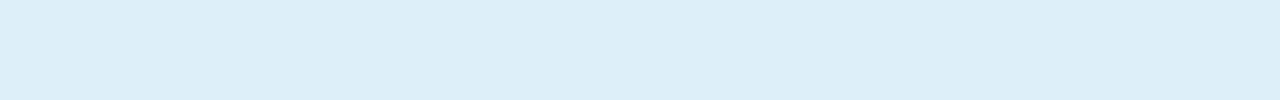本文
知事記者会見録(令和7年1月31日)
※知事及び記者の発言内容については、事実誤認や単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、発言の趣旨を損なわない程度に整理して作成しています。
令和7年1月31日(金曜日)14時30分
司会
ただいまから古田知事退任の記者会見を始めさせていただきます。
知事よろしくお願いいたします。
知事
まず、東京藝術大学との文化振興に関する連携協定でございますが、国民文化祭もそうですが、いろんな機会に藝大とは交流をしてきておりまして、この際、形のある協定関係ということにして、更に積極的にコラボを進めていこうということになりまして、今後、例えば積極的に本県のいろんな事業に、東京藝大の学生さんや、あるいは先生方に参加していただくとか、それから日比野学長のお得意の文化的処方に関する人材育成とか研究とか、そのようなことを積極的にやっていこうということで、連携協定を結ばせていただきました。署名はお互いに日程が合わなかったため、それぞれサインをして、郵送して交換するということで、今日付けの協定でございます。
それから配布はしておりませんが、今日時間を同じくして、観光庁の方から11月のインバウンドの数字の発表がございまして、これによりますと、11月は岐阜県のインバウンドが167,460人ということで、前年同月比35.4%増ということでございますが、これで昨年の1月から11月までを累計致しますと、11月末でございますが、我々が目標としておりました200万人を超えまして、2,013,580人でございます。11月でその前年と比較しますと2.1倍ということで、急速にインバウンドが増えてきております。それから、かつてピークにありました、コロナ直前の同時期と比べましても 32.1%増と、過去最高かつ目標の200万人を突破と、更にこれに12月の数字が加わりますので、1か月あたりどのぐらいになるのか、おそらく約20万人、(年間で)220万人から230万人の間にということで、引き続きインバウンドは大変好調であるということです。
それから、昨日ご連絡したと思いますが、埼玉の八潮市の道路陥没を受けた、県管理の下水道施設の点検でありますが、昨日報告したとおりでありまして、緊急点検が終わっておりますが、私どもとしては異常がないことは分かりましたが、この先更に口径2m以上の下水道管路について、管内部の異常があるかどうかということについて点検をする準備を進めておりまして、整い次第、来週には調査を開始しようという運びでございます。
それから、これも既に発表済みになりますが、一昨日1月29日に国交省から発表がございましたが、東海環状自動車道の山県ICから本巣IC間の開通が4月6日ということになりまして、私どもとしては、大変嬉しいニュースでございます。少し遅れておりましたが、最小限の遅れに留まったということで、NEXCO中日本をはじめ、関係者にご努力いただいた結果だろうと思っています。思い起こしますと、ちょうど私が知事に就任した直後の平成17年3月に東回り区間が開通いたしました。これは、いわば万博道路でもあるということで、愛知万博の開催に間に合うように、東回り区間を大変な勢いで作ったわけでありますが、その後、ちょうどこれで20年になるわけでして、この20年目の節目の年に、今度は西回り、この後養老山脈のところがまだ残っておりますが、県内については、あと本巣ICから大野神戸IC間が残すのみでして、これも夏までには開通予定と聞いておりますので、こうなりますと県内のICがすべて繋がるということで、名神高速道路と、東海北陸自動車道が繋がるということで、関西から中濃、飛騨地域へのアクセスが飛躍的に向上することが期待されております。もちろん、県境の養老山脈の中の水問題、これについても速やかに解決していただいて、三重県と繋ぐことも期待しておりますが、まずは岐阜県として、県都岐阜市に初めてICができると、三輪のスマートICもございましたが、本格的なICは初めてということで、岐阜ICの近辺は産学官連携によるライフサイエンスの拠点を作ろうという動きがございますので、そういった動きに拍車をかけるのではないかと思いますし、本巣市にとりましても、初めてのICということで、この地域の北の玄関ができるということで、大いに期待しているところでありますが、ちょうど20年目の節目の年にこのようなタイミングになったということで、ある意味で私自身としては感慨深いものがございます。
以上が、差し当たりの報告事項でございまして、その上で今日が最後の会見ということで、2月5日の退任前に、これまでの県政20年の歩みを振り返りさせていただくということで、お時間をいただいた次第でございます。
20年間7,305日、「5」いう数字がありますのは、閏年が5回ありますから、7,305日ということで、今日がちょうど7,300日目、あと残すところは明日以降5日間ということでございます。「光陰矢の如し」と言いますが、非常にこの時間の歩みの速さに驚くと同時に、それとは裏腹に年月の重さと言いますか、改めて振り返ってみますと、いろんなことがあったなということで、感慨無量でございます。
お手元の資料をざっと見ていただきますと、これは1期目から5期目までを時系列的に書いていますが、まず1期目は、一言で言いますと、この表題にありますように「はじめの一歩」ということで、県政の改革に取り組んだと、いわば基礎固めをした4年間でございました。内容的には、政策総点検ということで、全ての政策を拡充・継続・縮小・廃止といわゆる事業仕分けを一気にやりました。私自身も4万人を超えると言いますか、5万人近くの方々と2,500回を超える意見交換をずっと年間を通じてやらせていただきました。その上で結果報告を出したわけですが、政策の見直しと同時に行政組織の再編について見ていただきますと、本庁について、6部12局1総括監、これは総括対策監との名前だと思いますが、それに149の課・室、これらを合わせて168の管理職のポストがあったわけですが、これが9部2知事直轄73所属と言うことで、(合わせると)ちょうど84と、本庁の組織が半分になったということで、一気に大胆な改革をさせていただきました。この骨格は今も続いているということでございます。
それから、地域医療の問題に取り組みまして、まさに「オール岐阜」で地域医療対策協議会を現在に至るまで様々な医療問題について議論をし、行動計画を作って、実行していくという流れができましたし、特に次のページにあります周産期医療体制についても強化をし、また医師不足の問題も既にございましたので、修学資金貸付制度も設けました。これは、県内に定着すれば返還免除という、今はいろんなところでやっていますが、その先取り的な制度でございます。
それから、少子化も既にこの頃から意識をしておりまして、「子育て応援ステーション」、それから今もございますが「ぎふっこカード」、それから、「安心してこどもを生み育てることができる岐阜県づくり条例」を平成19年に作っておりまして、その上での基本計画ということでございます。
それから、持続可能な森林づくりということで、「森林づくり基本条例」もいち早く平成18年に作っており、「植樹祭」、「基本条例」、「基本計画」ということで、森林行政の体系ができたということでございます。
それから、今日の観光戦略に繋がりますが、「飛騨・美濃じまん運動」をスタートいたしまして、「みんなでつくろう観光王国飛騨・美濃条例」という条例を制定し、「岐阜の宝もの」制度をスタートさせたのもこの1期目でございます。
それから、十数年に亘って続いておりました御嵩町の産廃処分場の問題、これにつきまして、トップによる三者会談も含めて、約1年をかけて全面的な和解に到達したということでございます。
その他、東海北陸自動車道が(全線)開通いたしまして、これが東海地方と北陸地方の直結ということで、いろんな意味で、その後の様々な政策に大きな影響を与えてきております。
それから、「行財政改革大綱」を制定いたしまして、様々な見直しをすると同時に、県債残高がとにかく増え続けてきたわけですが、これをまず減らす方向に転換すると。当時ピークアウトと言っていましたが、県債残高をいつまでにピークアウトするのかということを最優先課題として見取り図を描く、ビジョンを描くということで大綱を策定いたしまして、それに沿って様々見直しをやってきたということでございます。
それから、ちょうどこの時期と合わせて起こりました不正資金問題、いわゆる裏金と称される問題ですが、これについても徹底した調査と検証をしまして、「岐阜県政再生プログラム」、それから「岐阜県職員倫理憲章」を制定しておりますが、この倫理憲章は、毎年新人研修で、私自身がこの憲章についてどういう思いでこの文言ができているか、どんなことがあったのかと、これは岐阜県庁という組織にとっては決して忘れてはいけない残念な出来事であるということで、丁寧にお話をしているところですが、そのような不正資金問題もございました。
それから、2期目は、「清流の国ぎふ」づくりの端緒と言いますか、政策展開が始まった時期でございますが、同時にこの時期は、いわゆる起債許可団体ということで、総務大臣の許可がなければ借金が一切できないと。これは全国で3団体、ワーストスリーになったわけですが、したがって「清流の国ぎふ」づくりのいわば端緒と、それから財政再建の戦いが続いた2期目でございました。
それに当たっては、「行財政改革指針」ということで、向こう10年間の指針を出し、また具体的なアクションプランを出しました。最終的には平成25年2月までが2期目でございますが、平成25年度の決算をもって、起債許可団体から脱却することができたということで、2期目の、いわば財政再建の戦いがようやく実を結んだということでございます。とはいえ一方で、やはり新しい政策展開として、今、観光国際部がございますが、その端緒となります観光交流推進局を創設しまして、海外戦略プロジェクトと言いますか、トップセールスも含めたキャンペーンを始めた時期でございましたし、その一つの典型が上海万博への参加ということで、ここで「清流」という言葉を使っております。
それから、もう1つは人口減少時代への挑戦ということで、長期構想をこの時期に策定しております。いわば長期構想と、それから財政再建の戦いと、表裏の関係になるわけですが、人口減少が不可避であるという観点から、もう1回県政の総点検をやろうということで出来上がったのが、「岐阜県長期構想」ということでございます。全国的に見ても、人口減少時代への挑戦という流れのはしりになったと思っております。
それから、「全国豊かな海づくり大会」を海なし県でもやらせていただき、「森は海の恋人、川はその仲人」ということで、「森・川・海が一体となった自然環境の保全」という岐阜らしいアピールをしたということであります。同時に、次の10ページにありますが、「清流の国ぎふ森林・環境税」を導入いたしまして、豊かな森林づくり、恵みの森林づくりを推し進めた時期でございました。
それから、国体、障がい者の大会、これに「清流」という名前を冠しまして、「清流国体・清流大会」ということで、100万人の大交流ということでございました。
それから、今度14回目になります「高橋尚子杯『ぎふ清流マラソン』」もこの時期にスタートしております。出発点は、東日本大震災による被災地へのチャリティ大会ということで、初開催をしたのが平成23年でございます。
それから、3期目はいよいよ「清流の国ぎふ」づくりの本格展開という時期でございますが、同時に安全・安心の問題も色々と意識し始めた頃でございます。
成長雇用戦略をまず策定いたしましたが、次にあります県土の強靭化計画を初めて策定いたしまして、岐阜大学と一緒に「防災・減災センター」を設置いたしました。ちょうどこの頃に御嶽山の噴火がございまして、戦後最悪の火山災害と言われておりますが、これに合わせて登山届の提出を義務化するということで、思い切った条例改正をいたしました。
それから、亜炭鉱対策ということで、御嵩の亜炭鉱の陥没問題が深刻化しましたので、予防対策をやろうということで、平成25年度以降、まだ今日も続いておりますが、着実に脆弱箇所から優先的に埋め戻しが続いておるということでございます。
それから、医療・福祉についても、最大のものは「ぎふ清流福祉エリア」ということで、岐阜市の鷺山一帯に、障がい者の医療・福祉、教育、文化、芸術、スポーツ、就労といった様々な面からの関連施設を一体的に整備するということで、こういうエリアを拠点として、障がい者に対する総合的な対策を展開した時期でもありましたし、それから子ども・女性局もこの時期に作っておりまして、「女性の活躍支援センター」等々で、子育て、そして女性の活躍と両面から応援していこうという体制が出来上がりました。
それから、「清流の国ぎふ」づくりもいよいよ本格的な展開ということで、清流の国づくり局を新たに作りました。これは、今日の清流の国推進部の前身になるわけですが、この時に「ミナモ」をマスコットキャラクターに委嘱しまして、考えてみればもう12年になるわけですが、着実に皆さんに理解していただけるようになってきたのではないかと思っております。また、この時期に「清流の国ぎふ憲章」を制定しまして、「清流の国ぎふ」づくりということの意義を明らかにしたということでございます。また、「清流の国ぎふ」というのは、岐阜県のものということで、商標登録もこの時にしております。
それから、ちょうど安倍内閣において地方創生ということが言われた時期でして、私自身も知事会のこのテーマの本部長を仰せつかりましたので、岐阜県としては「人口問題研究会」、先般再開をしてレポートを出していただきましたが、この「人口問題研究会」を設置し、ビジョンを作り、総合戦略をということで、まさにその第2期にやった人口減少時代への挑戦の発展形ということで「創生総合戦略」を策定し、実行してきたということでございます。
それから、この頃、海外戦略のもう1つの流れとして、世界遺産の登録を積極的にやってまいりまして、「本美濃紙」のユネスコ無形文化遺産と、それから関と美濃市に亘る「曽代用水」の世界かんがい施設遺産登録と、「清流長良川の鮎」の世界農業遺産、それから次のページにあります「山・鉾・屋台行事」(高山祭、古川祭、大垣祭)のユネスコ無形文化遺産登録ということで、観光キャンペーンを加速していく上でも、この世界遺産の登録推進が非常に効果的だったのではないかと思っております。
それから、4期目になりますが、この時期はまさに三大感染症との戦いが続いた時期でありますが、同時に人口減少対策にも繋がるわけでありますが、人づくり、魅力づくりといったことにも力を注いだ時期でして、そういったことを通じて「清流の国ぎふ」づくりのいわば発信を積極的にやってきた時期でもございます。
三大感染症は、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、それから次のページにあります新型コロナウイルス感染症ということでございます。こうした危機管理を通じて、今や「岐阜モデル」と言っておりますが、「オール岐阜」での推進体制、専門知の積極活用と、岐阜県独自の専門家会議を開催し、常設化し、当時で言えば、早期発見、隔離、自宅療養者ゼロという原則を頑なにぎりぎりまで堅持した時期でございます。それから、スピード感ある決断ということで、緊急事態宣言より先立って、常に岐阜県としては非常事態宣言を発出し、その際に単なる非常事態宣言ではなしに、医療・福祉対策、経済再生対策、教育対策ということを合わせた総合パッケージとして対策を打ち出しておりました。また、全国初でありますが、「感染症対策基本条例」もこの時期にいち早く制定・施行いたしましたし、それから国の「GoToトラベル」に先駆けて、県独自の「安心ステイ~ほっと一息ぎふの旅」というものを先に実行に移しております。それから、ワクチンもまさに「オール岐阜」で協力を得て、特に高齢者については全国トップの接種率で完了したということでございます。
それから、次のページが人づくりの関係ですが、各務原の「航空宇宙博物館」の全面リニューアル、「木遊館」、それから「morinos(モリノス)」と言っておりますが、森林文化アカデミーの中の「森林総合教育センター」、こういったものを通じて、人づくりを進めてまいりました。
魅力という意味では、「あゆパーク」、「関ケ原古戦場記念館」、それから「名鉄高架化事業」も半世紀の間いろいろと滞っていたわけでありますが、完全に関係者の合意ができ、今着々と進んできているということでございます。
それから、この時期はちょうどNHKの「半分、青い。」という朝ドラがあり、そしてまた「麒麟がくる」という大河ドラマがあり、ドラマロケーションといった面でも、あるいはアニメといった面でも、岐阜が非常に話題になった時期でございます。
それから、5期目は皆さんよくご存知でございますが、アフターコロナ、新型コロナの5類移行と合わせてアフターコロナ社会へということで、文化も含めて様々な対策をということで、サステイナブル・ツーリズム、国際交流、それから人と魅力づくりというようなことをやり、それから新たな日常ということで、次のページにありますが、人口減少、DX、GX、SDGs、スタートアップといったことをやってきましたし、次のページの、県庁舎の再整備も無事終わりました。そして、能登の大震災もありましたので、ちょうど今まとめに入っておりますが、「岐阜県強靭化計画」の改定ということで、能登に学んで更に強化していこうということでございます。
それから、次のページにありますが、世界遺産がまだ続いておりまして、「郡上踊」、「寒水の掛踊」がユネスコ無形文化遺産になりまして、また「伝統的酒造り」ということで、今海外で日本酒ブームでございますが、それに拍車をかけて、ユネスコ無形文化遺産登録ということで、更に積極的にキャンペーンをしていこうということです。
それから、「清流の国ぎふ総文2024」、それから「『清流の国ぎふ』文化祭2024」ということで、また最後に「清流の国ぎふ憲章」に「共生・共創社会」を念頭に、「共」にという言葉を入れさせていただいたということでございます。
ざっと時系列的に振り返ってみたわけですが、そういう中で、時代はどんどん変わり、社会が変わっていく中で、あえて整理をすると社会的な課題、県政にとっての課題として、3つ挙げられるのではないかと。
1つは、人口減少、少子高齢化社会にどう対応していくか。2つ目はグローバル社会への対応、これはまさに海外戦略であり、世界遺産であり、インバウンドということでありますが、もう1つはリスク社会で、様々なリスクがこの20年の間に、震災があり、火山災害があり、風水害があり、感染症がありということで、こうした様々なリスクにどう対応していくかと、3つの大きな社会的な変化、課題というものに、県政全体を流れる大きな底流と言ったことがあるのではないかと思っています。そういう中で、様々な政策を打ってきたわけで、今見ていただいたわけでありますが、20年経ったところで改めて振り返ってみますと、様々な政策をやって乗り越えていく中で、いくつか貴重な県政にとっての財産、レガシーと言って良いか分かりませんが、見えてきているのではないかと思います。
1つは、故郷岐阜のアイデンティティと、あるいは、魅力・誇りと言って良いのかもしれませんが、よく「岐阜には何もないですよ。」ということを言われたものでありますが、「清流の国ぎふ憲章」も作りましたし、清流文化を標榜した文化祭もやりましたが、岐阜県にとってのアイデンティティ、「清流」ということについての認識もかなり得られてきたのではないかと思いますし、それから次々と世界遺産登録が進んだということ、あるいは国民文化祭で実施しましたような草の根の「ちーオシ」や地歌舞伎を取り出して発信するというような、そのような地域の魅力の発見、発掘、再確認、そういったことを通じて認められる、あるいは高く評価される、あるいはどこに行かせても通用する岐阜の素晴らしいアイデンティティの魅力・誇りというものが、徐々に見えてきつつあるのかなとそんな感じがしております。
それから、もう1つは、しばしば私が言っておりますが、「オール岐阜」の取組みと言いますか、単なる合言葉ではなしに、まさに実体的に「オール岐阜」で協力をして、一緒に取り組んでいくという「共」にという精神であります。あるいは白川郷で言えば「結(ゆい)」の精神でありますが、スタートの政策総点検もそうでありましたし、危機管理への対策もそうでありますし、あるいは四大行幸啓を全部やらせていただきましたが、そうしたビッグプロジェクト、行事を通じての魅力発信とか、そういったことについて、「オール岐阜」でそれぞれが役割を分担し、苦労を分かち合いながら進めていくという、そういうスピリットが県、市町村、関係団体、県民に至るまで徐々に見えてきたのかなという感じがしております。
それから、3番目はやはりスピードです。物事を進めていくスピードということの大切さと言いますか、特に危機管理の場合、どう先手を打っていくかということで、例えば先程少し申し上げた、昨日の埼玉の陥没事故に合わせて、直ちに県内のチェックに入ると、これも先手を打つ一つの対応だと思いますが、そういったスピード感と言いますか、そういったこともずいぶん進んできたのかなと思っている次第でございます。
これまで、何とか進んで来れましたのも、県民の皆様、あるいは議会、市町村、県職員の皆さんのおかげでありまして、感謝の言葉しかないわけであります。本当に長い間ありがとうございました。特に県職員の皆さんは、県政改革の過程で給与カットもありましたし、それから危機管理、あるいは様々な行事に当たって、総動員という体制をとって対処して、本来業務と、それからそういった危機管理や大きなイベント業務とのバランスに大変苦労したのではないかと思います。そういう中で一つひとつしっかり乗り越えていただきました。私にとりましては、県の職員の皆さんは本当に誇りであり、感謝しかないと思っております。
ということで、ざっと振り返らせていただきましたが、そのような感想をお伝えして、私からの話はこのところでよろしくお願いします。
記者
5期20年の長い間お疲れ様でした。冒頭、「光陰矢の如し」というお話もありましたが、任期まであと数日残していますが、いよいよ節目を迎えるに当たり、今の心境をもう少し詳しくお願いします。
知事
心境というよりも、まだ日々いろんなことが起こっていますので、私としては最後の最後まで与えられた時間の中で、精一杯役目を果たしていきたいということで、全てが終わってからゆっくり考えにふけりたいということで、ただ、最後に申し上げましたように、今日こうして最後の記者会見になりますが、過去を振り返るという中では、先程申し上げましたが、感謝の思いで一杯でございます。
記者
5期20年を振り返ってと言いますか、ご自身の総括、例えば点数を付けるとすれば何点かということがありますでしょうか。
知事
私としては、自分なりに精一杯というつもりで、1日24時間掛ける7,300日ということでやってきたつもりですので、評価は自分でするものではなく、県民の皆さんや、またメディアの皆さんがされるものでありますので、自分で点数を付けるというのは、何を基準にどう点数を付けたら良いかよく分からないので、私なりに努力をしてきたということで、点数の付けようがないのですが、あとはお任せします。
記者
古田知事が知事として仕事をする上で、大切にされてきた考え方と言いますか、言葉などがあれば、教えていただけたらと思います。
知事
元々私の好きな言葉は「胆大心小」という、「胆」というのは腹、肝臓で、「大」は大きい、そして「心」を小さくと。「心」というのは気配りということで、「細かいことに気配りをしながら、決断は大胆に」と、こういう中国の言葉であります。そういう意味で一つひとつ目配りは丁寧に丁寧にやりながら、いざ決めるとなったら思い切って大胆に決めて進めていくと。このバランスをどのようにやっていくかというのが、これは別に知事としてというよりも、私自身がこれまでいろんな仕事をやらせていただく中で常に感じながらやってきたことであります。特定の言葉に集約するのはあまり好きではないのですが、あえて言えばそういう感じです。
記者
就任当初の1期目のところを振り返っていただきたいのですが、県庁の裏金問題をはじめ、県の財政も大変厳しい中で、岐阜県政の歴史を振り返っても困難な時代だったと思うのですが、当時のご苦労をどう振り返りますか。
知事
苦労というよりも、ある仕事を受け持った以上は、その関連で非常にスムーズに行くこともあれば、そうならないこともあるわけで、特にそうした課題に直面した時に、どういう形で乗り越えていくかと。乗り越えていく乗り越え方に、そこにリーダーシップの質とか、それから組織の体質とか、いろんなことが問われると思いますし、また乗り越えていく中で、より磨かれていくというか、より質の高い仕事と言いますか、行政ができるようになっていくということで、困難な課題が出てきた時には、そのように考えて取り組むと言いますか、真正面から取り組んでいくというのがまず基本だろうと思っております。そういう意味では、別にこの裏金問題だけではなしに、例えば御嵩の問題もそうですし、それから当時ほぼ破綻していたはずの笠松競馬も何とか盛り返しましたが、これも当事者の方々からすれば大変な問題でありますし、たくさんいろんなことがありましたが、真正面からきちっと向き合ってやっていくことが、困難を通じて鍛えられていくと。組織としても、職員としても鍛えられていくということで、そういう思いで取り組んできましたので、結果的にその乗り越え方についての評価は、皆さんにお任せするわけでありますが、そういうことで一歩一歩前に行くという、そんなことではないでしょうか。
記者
「清流の国ぎふ」の一連の事業についても、お伺いします。
まず、2010年の海づくり大会から始まって、ぎふ清流国体、そして昨年は総文祭と国文祭、一つ大団円を迎えられたわけでありますが、また今年6月に大阪万博で岐阜県催事を開催されるということで、こうした「清流の国ぎふ」のレガシー、改めてレガシーというのは具体的に何か、どうお考えになるかというのと、どのように受け継いでいってほしいかというのをお願いいたします。
知事
今いくつかの行事を挙げられましたが、それぞれ行幸啓の行事であれば、まさに天皇家の毎年の大きな行事で、国を挙げての行事でありますから、そういうものを岐阜県が開催するとなれば、まずは私どもこれまで言っているのは、この行事の意義は何かと、何を実現するのかと、何のためにやるのかという辺りで、やはり志というか思いをまず一つにして取り組んでいくということで、そういう志を持つということが一つ大きな出発点になりますし、それからそういう思い切った企画を進めていくことで、行政なり、あるいは岐阜県の在り様についての誇りと言いますか、自信といったものも生まれるでしょうし、そこから新しい政策の出発点になると。例えば国体をやりましたが、そこから「ねんりんピック」とか「レクリエーション大会」とか、あるいはアスリートのレベルの向上であるとか、あるいは「高橋尚子マラソン」のような市民マラソンとか、いろんなレガシーとして、一つの大きな行事がきっかけとなって、いろんなことが始まったと。そういうものを一つひとつ大切にしていくと言いますか、そういう意味でも、起爆剤としての行事の意義というのはあると思いますし、何と言ってもその行事を通じて岐阜をアピールできるというのも大きいのではないかと。いろんな意味で、おっしゃったようないろんな行事を、意義のあるものにしていけるかどうかもまた問われているのではないかと思っておりますので、意義のあるものにするような運びをする、企画をする、体制を作ると、そのようなことでやってきたつもりです。
記者
インバウンドが200万人を達成されたというお話だったと思うのですが、古田県政を代表するものとして海外の魅力発信事業というのはあったと思うのですが、この200万人を達成できた意義についてはどのようにお考えでしょうか。
知事
海外キャンペーンを始めた頃は、大体岐阜のインバウンドは10万人そこそこだったものですから、その時点から比べれば20倍ということで、コロナの直前が166万人でしたから、とにかく単なる元に戻るだけではなしに、一旦コロナ期は3万とか5万人とか一桁までいきましたので、ほぼ壊滅状態でしたので、単に元に戻るだけではなしに、もう一段上を目指そうという意味で200万人ということを申し上げたわけで、そういう目安として申し上げているだけなのですが、そういう海外キャンペーンも先程申し上げたのと同じで、岐阜のどういう魅力を、どのように磨いてどのように発信していくかと、その発信力が問われるわけですから、それを通じて急速に伸びてきたということはその発信力があったと、それから岐阜にそのような訴えかけるだけの地域資源があるということでもありますので、更に自信を持って進めていったら良いのではないかと。ただ、もちろんインバウンドの数字が高ければ高いだけ良いということではなしに、国内の観光もありますし、それから岐阜県の文化、あるいは岐阜県にとっての国際交流というか、いろんな多面的な国際交流の促進に、どのようにインバウンドが一つのきっかけになって広がっていくかとか、いろんなことをまた考えていく、そういう時期に来ているのではないかなという気がします。それと県内では、まだインバウンドと言っても、どこにインバウンドがいるのかとおっしゃる地域もありますし、あるいはもう見渡す限りインバウンドのお客さんがどこに行っても目に付くというところもありますし、それから最近では、アメリカで大ヒットした「SHOGUN 将軍」が、あれは関ケ原(の戦いの)前夜ですから、ここに来て、例えば関ケ原古戦場記念館をはじめとして、関ケ原にインバウンドの方々が今急速に増えてきたり、妻籠・馬籠というあの辺りもインバウンドが殊更に目立つようになってきておりますので、そのように地域ごとに違いがありますので、そういったところをどのように岐阜県全体としてバランス良くインバウンドということを捉えていくかと。それからおもてなしの仕方、それからホテル、サービス、それこそ人材育成、いろんなことを考えていく時期に来たのかなというのが200万人越えに当たっての感想というか、そのようなところです。
記者
最後に、先程県民への感謝という言葉があったと思うのですが、改めて古田県政と共に歩んでこられた県民へのメッセージをお願いします。
知事
私は着任した時から、県政の原点は「県民目線」、そして「現場主義」ということを申し上げて、1期目の県政総点検はまさにそういう精神で、徹底的に県内各地もお邪魔してご意見も伺い、県政の在り方を考えるスタートにしたのですが、そういう中で、岐阜県に対して厳しいご批判もありましたし、いろんな面で協力していただいたり、あるいはコロナとか豚熱とか、辛い時期もお互いに我慢をしながら、捲土重来を図るというようなことで一緒になって乗り越えてきたものでありますし、いろんな面でやはり県民あっての県政ということでございますので、もし今の県政が、皆さん方から見て一定のご評価をいただくとすれば、それは全て県民の皆さんのそうした県政に対する関わりというか、ご協力というか、参加というか、そういうことのおかげだと思っております。行政というのはやはり、ある種の方向を考えたり、方向付けと言いますか、目指すべき方向を考えたり、あるいはきっかけを作ったり、あるいはネットワークを作ったりとか、そういう行政は行政の役割があるのですが、しかしそういうものがあっても、そこに県民の皆さんが積極的に参加していただかなければ出来ないわけなので、何よりも私どもはそういう意味で、「県民目線」、「現場主義」ということで頑張らせていただきましたが、同時に、県民の皆さんもその輪の中に積極的に参加して、その魅力を発揮していただいたということで、何とか今日まで来れたのではないかなと思っております。特にコロナ禍でも、何かパニック的なこととか、地域の秩序に関わるような、そのようなことはほとんど私は聞いたことがないのですが、お互いに厳しい中で、逆に私どもはできるだけオープンにして、ガラス張りにして、例えばワクチンの配布にしても、あるいは病床をどのようにどこの病院をどう分担するかと、ベッドを分担するかということについても努力してきたつもりですが、一緒になって耐えるところは耐えていただきましたし、冷静に一つひとつ乗り越えていっていただいたのではないかと思いまして、そういう意味で感謝しております。
記者
20年ということで、この(配布資料の)ページを見ただけでもとても多くのことに携わられていらっしゃったと思うのですが、その中で一番印象に残っている出来事だったり、ご自身の中で1番思い出深いことを教えてください。
知事
なかなか1番というのは難しいんですよね。何か1つというのはちょっと至難の業ですね。非常に上手くいった場合もあれば、当初考えたことからすれば残念な結果に終わったこともあれば、あるいはとてつもなく困難な課題に直面したこともあれば、さっとスムーズに解決できたこととかいろいろあるのですが、それぞれに思い出はありますが、そういう様々なものをどれか1番というのはパッと浮かんでこない、いろんなものがバーッとモザイクのように炙り出てくるのですが、1つ選べというのはちょっと無理ですね。
記者
知事はいろいろな場所で、報道機関の取材の場などで、「自分は政治家というよりも役人なんだ、公務員なんだ。」というようなことの趣旨のお話をよくされたと思います。よく伺いました。これは真意としてどういったことを言いたかったのかということで、政治家論とか、役人論とか、何をもって政治家か、何をもって役人か、というところまで含めて、この長い政治家生活、公務員生活を振り返って、どのようにお考えになっているのかというのを教えてください。
知事
行政と政治というのは、常にある意味では不即不離の関係にありますから、どこまでが政治でどこまでが行政かというのは、完全に100対0に分かれるわけではないので、混じり合いながら物事が進んでいくと思います。ただ行政的なるものと、政治的なるものとのウエイト付けと言いますか、行政はどちらかというと安定というか、あるいは一定のルールの下で公平にというか、そのルールを適用して間違いなくやっていくということである意味極致だとすれば、政治的なものというのは、極言すれば決断です。決断の中には、行政としての適切さと、それから状況に応じた判断と、いろんなものが混じっていると思いますが、私にはどちらかというと、長いこと行政官をやってきたものですから、行政としての連続性とか、公平性とか、ルール適合性とか、そういうものをまずきちんと押さえながら決断をしていくと、決断に繋がってないといけないということを、そういう傾向があるのではないかというようなことを申し上げたのかもしれません。画線とはっきりとはなかなか現実には分けにくいですので、例えば、財政再建をやるといった時に、どこに対して厳しく、どこを継続し、どこを多くしていくかというのは、決断する部分もあれば、やはりルールに沿った部分もありますから、なかなかどちらかだけということではないので難しいとは思いますが、まずはとにかく、行政的な安定性をまず見据えた中で決断を考えていくということかなという感じがします。あまりそういう厳密な区分は難しいと思いますが。
記者
本当に大変な仕事を20年間務め上げられてきたなというのを、20年の歩み(の資料)を拝見させてもらって思いましたが、知事として20年間務められてきた原動力みたいなものというのは、どの辺が原動力として進められてきたのかというところを教えてください。
知事
知事という仕事は何と言っても、県民の皆さんに選んでいただいて、負託を受けているわけですから、その負託に応えるというのが基本ですから、混乱したことがあったり、難しい問題があったり、災害があったり、いろんなことがあるわけですが、県民からの負託に自分が果たして応えられているかどうかというところは原点ですし、もう1つ、私は高等学校までは岐阜におりましたが、それから東京に出て、海外生活も少しありましたが、ずっと東京暮らしなものですから、ざっと40年でして、高校卒業して40年経って故郷に戻ってきたものですから、元々県知事という仕事を自分の人生の中でやらせていただくなんてことは全く考えたこともなく、本当に選挙の直前のご要請と言いますか、お話をいただいた時に、「さて、どうしようかな。」というぐらいの感じでしたから。知事という仕事が自分の将来の選択肢に全くあったわけではないので、むしろ40年ぶりに故郷に帰ってきて、ある種自分を育てていただいた故郷に対する御恩返しと言いますか、自分が40年間、東京や海外で学んだり、経験したことが、故郷のために少しでもお役に立つなら、活かせるなら、それは一つの自分なりの役割なのではないかなという思いと、その2つですかね、原動力と言いますか、原点と言いますか、2つじゃないかと思います。
記者
そういった思いを抱えられて、20年間務められて、今感情としてあるのは、寂しさなのか、それとも充実感なのか、その辺りはいかがでしょう。
知事
ずっと続いてきていますから。突然ある時点で切って、「さあ、感情はどうですか。」とかと言われても、なかなかそのように途切れないものでして、大体朝起きて、今日のスケジュールをもう1回確認をして、自分なりに出番は何か、ポイントは何か、勝負どころは何かというようなことを考えながら、朝身支度をして、食事をして、出かけてきて、早速スタッフと話もし、いろんな方にお会いしたりしてやるわけで。全てが終わると、家に帰って、明日は何があって、どうしてこうしてということで、今晩中に確認しておかないといけないこととか、何だかんだとやりますから、それから寝てといったことの繰り返しです。それがそれこそ7,300日も続いてきているものですから、逆に5日後にそれが完全に終わるんだということ自身がどのようなことなんだろうかなという、別に心残りとかそういうことではないのですが、役割がそこで終わるということははっきりしているわけなので、ただ、終わった時におっしゃるような意味でのライフスタイルとか、生活感とか、周りに対する目線とか、そういうものは完全に、朝起きて、今日誰と会って、何をしてというようなことを、スケジュールから入るということは多分ないと思いますので、また違うライフスタイルが始まるので、それはそれで、自分がどのように変わっていくかというのは、興味はあるところでありますが、ご質問のような形で「今の感情を。」と言っても、それよりは最後まで、今日も朝出る時は「今日は記者会見があったな。」と、それから今日お目にかかる人はどのような人で、こういう話をしようか、というようなことをしながら出てきておりますし、今日帰ればこの週末はどういう行事があって、誰に会って、あと来週残った日は何があるか、というようなことを考えるのでしょうね。とにかく今のところは連続性の中にあるものですから。
記者
江崎新知事が就任するわけですが、古田さんはいろんなレガシーも残されていくわけですが、これだけは引き継いでいってほしいというようなポイントみたいなことはありますでしょうか。
知事
これとかあれとか言うよりは、今の岐阜県の在り様とか、それから県政の在り様とか、そのようなことについて、彼は彼の面で感じて考えてやっていくわけですから、あれとかこれとかということはありませんので、新知事として存分にやっていただいたら良いのではないでしょうか。
記者
退任後やりたいこと、またどういった生活を過ごしたいのかというところをお伺いできればと思います。
知事
今、申し上げたように、7,300日続いたライフスタイルがどう変わるのかっていうのが、自分で想像がつかないものですから、ある意味ではそこが楽しみというか、どう変化していくのかというのを楽しんで。今直ちにあれをやりたいとか、すぐこうしたいとか、そういうものはありません。それと、今、引越しも少しずつやっているのですが、無造作に20年間(のものを)押入とか、いろんな所に放り込んでいるわけで、いろんなものが溜まっているので、捨てるものとか、これから持っておくものとか、いろんな仕分けをしようと思うと、なかなか難しいですよね。まずはとにかく荷物を運んでいるので、一応、普通の生活ができるように整えて、それからというところです。どういう生活になるか、まだ想像がつきませんので、その時にお目に掛かったら、お話しします。
記者
懸案として、リニアの問題で地下水の低下、地盤沈下の問題があると思いますが、今後県としてはどのように取り組んでいってほしいという思いはありますでしょうか。
知事
地下水の問題は、発端は去年の2月下旬で、私のところに(報告が)上がってきたのは5月の連休明けです。直ちにこれを止めてくれということで、私がやったことはまず、工事を止めること、それからその次に起こっていることについて全面的に情報公開すること。それから、情報公開した上で、今、何が課題なのか、課題の整理をすること。その課題の整理というところから、専門家、行政、JR東海とオープンな形で議論を進めていくということで、課題が決まり、それぞれについて何をするかということが決まり、ということで進んできているのですが、進むにつれて、まず実態はかなり分かってきたと。もちろん、全面的かどうか、まだやることがあるかもしれませんが、かなり分かってきた。分かってくるにつれても、地盤沈下の問題とか、日々の湧水量がどれだけあるかとか、それに関連して、地下水の水位がどう変わっているかとか、地面の変化がどうなっているかとか、得られたデータは全部公開する。だから、その状況、議論、プロセス、全部公開するという中で、解決策を探っていくということで、とりあえずの対応もやっていますが、何と言っても、湧水対策、水を止めるということを、どのようにやっていったら良いかということで、所定の工法を念頭に置いて準備してきたわけですが、それが鹿児島での事故によって、ちょっと立ち止まって考えなければいけないということになって、今、立ち止まっているわけです。
だから、そのところについて、今まで念頭に置いた工法について、本当にこれで行くのか、ギブアップするのか、あるいは何か改良の余地があるのか、その辺がまさに今、焦点になっていて、まずJR東海の方で、事業者としてどうしたいのかということをまず出していただいて、それを専門家、行政、地元の皆さんが、それをどう評価するかというところで、みんなの納得、コンセンサスを得られたら、それに沿って次の作業になると、そういう所に来ているのですが、残念ながら、まだ前回の会合でもう少し具体的な方向性が出るかと思っていたのですが、私の居る間に一定の方向性をということで、1月下旬に日程を設定したのですが、まだまだ結論に至らないということで、そこは次の代に引き継がれるのですが、まずはそこをとにかく明らかにしないことには、進みようがない。そこを抜きにして、何か始めるということはありませんので、そういう意味では、非常に課題と焦点ははっきりしている。そこの問題を最後にどうやってスムーズに乗り越えて、皆さんが納得するかというそこについての提案をJR東海が出していただくと、そこから始まっていくと理解しています。
記者
先程、リニアの話のような継続的な課題もあれば、更に今後、日々進む中で、新たな課題も出てくるかと思います。先程、職員さんへの感謝の言葉もありましたが、職員に対して今後どのように仕事に取り組んで、どのように能力を発揮していってほしいか、メッセージなどがあれば教えてください。
知事
この20年間、多くの職員の皆さんと一緒にやってきましたが、いろんな課題を一緒になって解いていく中で、「オール岐阜」の前にまず「オール県庁」という体制を取るわけです。問題が大きければ大きいほどです。そういう中で、それぞれの皆さんが非常にテキパキと動いていただいてるのではないかと思いますので、これまでの様々な経験を踏まえて、新しい課題に積極的に取り組んでいただきたいです。
時代が変われば行政も変わりますので、どのように変えていくのか、新しい課題、テーマも次々と出てくるわけなので、まだ想定していないような課題が出るのが当たり前で、先程リスク社会と申し上げたのはそういうことなのですが、想定外のことでもたじろがずに、しっかりと真正面から、これまで通り「オール県庁」で乗り越えていってほしいと思います。
記者
「清流の国ぎふ」を掲げられたのは、2期目の頃からだと思うのですが、その前から、古田知事ご自身として、特に東京に出られた時、その時点から「清流」が、岐阜県の誇りと言えば「清流」だろうという思いがあったのか、それとも何も無いなと、全てはあるけどというぼんやりとしていたという感情があって、岐阜県知事になられて、その後、考えた上で「清流」というものが思い浮かんだのか、古田知事ご自身の感覚のところになるのですが、お伺いできますでしょうか。
知事
岐阜県といえば何かと言った時に、なかなか具体的なものが出てこないわけです。郡上と言えば「郡上踊」、高山と言えば「高山祭」、岐阜と言えば「金華山、岐阜城」とか、そういうものはあるのですが、岐阜県という枠組みの中で「岐阜」と言えば何か、あるいは何とかと言えば「岐阜、岐阜県」というものがあるのかないのかという意味で言えば、何か特別なアイデアが予めあって、それを進めたわけではないのですが、実際に、観光もそうですが、キャンペーンをしたり、いろんな方々と議論する中で、岐阜県とは何ぞやというところに常に戻っていくもので、かつ、皆さんも「岐阜には何でもあるよ。」と言う人もいれば、「何も無いよ。」と、そうやって一言言えるものは無いという人もいました。でも県政を進めていく上で、まさに「オール岐阜」で何かをやっていく上で、岐阜県民としての誇りや魅力、これぞというものはあって良いのではないかと。またそういうものを皆さんがそうだと思えば、そこが一つの新しい地域発展のエネルギーになるのではないかと。そのようなことを思いながら、しかしさあ何だろうかというのが、正直な仕事を始めた時の実感で、別にアイデアがあったわけではないです。最初に「水」ということを言い出したのが上海万博で、ものすごく反響が良かったのが岐阜のミネラルウォーターで、これを一番最初のキャンペーンで香港に持って行ったのですが、(ミネラルウォーターを)売り込みに行ったわけではなく、たまたまスタッフの人がバックに入れていただけで、持って行ったのは飛騨牛だったのですが、飛騨牛の試食会の時に、たまたま私の机の上に置いてあったのですが、前に座った香港の卸の総元締めの会長さんが「それ何。」と言うので、「岐阜の水ですよ。」と言って、ひとくち口にして、「これどこで売っているの。これはうまい。」と言うので、「これ、日本で売っている。」と言ったら「これが欲しい。」ということで、あっという間に万(単位)のオーダーの契約が成立して、香港のコンビニに並ぶようになったのです。ほんの(少しの)きっかけで、たまたま数本持って行っただけなのですが、やはり香港人にとっては、安全で美味しい水は誰もが求めている。その後、シンガポールに行ったら、シンガポールも水なんです。水を求めて、マレーシアと戦争をやって独立したわけですから。岐阜の水がそんなに評価されるというのを、その時感じたのですが、考えてみたら、和紙も水だし、木工も水だし、陶磁器も水だし、鵜飼も川でやっている。
それからもう1つは、岐阜県の人は一種の絆というか、自分たちは繋がっているという、絆めいたものを感じられるようなアイデンティティがあると尚、良いなと。そこにしかないもの、ここにしかないもので、どんな良いものであっても、やはりみんなで感じないといけない。岐阜は「木の国、山の国」と言っていますが、岐阜は平野部もあります。「森林税」と言ったら怒られまして、「森林環境税」ならオッケーと平野部の人は言うわけです。そういう意味で、絆みたいな、繋がりみたいなものが何となくないのかなというのは頭にあって、その漠然としたのが、先程の「全国豊かな海づくり大会」で、山、森、川、海が繋がって、「清流」というのを言ってみようかというあたりから、それで県民会議を開催し、議論したのですが、皆さん、「清流」が良いと言うことで、「清流の国ぎふ憲章」を練っていただいたという流れです。
個人的に言うと、よく東京で「岐阜はどういうところか。」と聞かれた時に、「私は川育ちですよ。」ということは、何となくごく普通に言っていました。「川で泳いで、町の真ん中に川が流れていて、川の周りを歩いたり、川で遊んだり、川育ちです。」と、周りには言っていた記憶があります。そういう意味では何となく川に惹かれたのかなという気はします。
私自身は自分の思いを優先してアイデンティティを決めるというのはあり得ないので、皆さんがどのように、あるいは、その言われた人がどう反応するかとか、そういうのを見ながら何となくここに収斂していったということです。
記者
やはり地元から出たときに一番アイデンティティというものを考える時があると思うのですが、古田知事は「川」というものを考えていたのかなという話がありましたが、東大を出られて、官僚をやられる中で、何か明確なものは思い当たらないけれども、川なのではないかなという、こういう感覚は今振り返ってみるとあったという感じになるのですか。
知事
物心ついた頃から、とにかく夏休みというのは、毎日、長良川で泳いでいました。それから、伊勢湾台風の時は、本荘の岐阜市民病院のところの堤防がほぼ決壊しかかって、消防隊員もあそこが切れたら岐阜市内が水浸しになるので、さあ大変だと言って、警戒の話が流れたところで突然水が引いていきました。それは愛知県の下流が先に決壊したので助かったのですが、秋になると台風が必ず来て、しかも超大型の台風が次々と子どもの頃は来ていまして、実際に水害もありましたし、だからそういう面でも川なのです。いろんな意味で川を意識したことは事実ですが、県の行政、県知事という立場で、「川」、「清流」というのがすっと出てきたかというと、そうではなく、むしろ皆さんの意見を聞こうということをずっとやってきた中で(出てきた)ということですね。
記者
就任された当初、5期20年、私は大変長くお務めになられたかなと思うのですが、当初は20年ぐらいはやりたいなとか、20年ぐらいはという思いがあったのでしょうか。
知事
何も考えてないです。というのは、県の行政そのものを直接担当したことがなかったので、例えば大規模小売店舗立地法の運用や個々の産業政策とか、そうしたことで各都道府県のいろんな方と話をすることはもちろんありましたし、政策を一緒にやることはありましたが、知事という仕事がどういうもので、どうなってというのが、全く手探りの状態、分からない状態で、先程の故郷への御恩返しというつもりで挑戦してみようかという気持ちになっただけなので、立候補したり、当選したところで、さて何年というよりも、これから何が始まるのだろうという好奇心だけでやってきました。その後も何年だからどう、何期だからどうという意識が一瞬も無いうちに、気が付いたらここまで来ていたと。ただ、4期目から5期目のところは、新型コロナが一つの、これは毎日のように死者何名、入院者何名と日本中がコロナ対策をどうするのかということで、誰もがこれに対する恐怖や関心がある中で、これは中断するわけにはいかないという意識はありました。それ以外の時は、何年ということなく、特段、何年という思いは無いです。
記者
歴史的に、誰よりも長く岐阜県の知事を務めたわけで、だからこそ、岐阜県の知事に必要な資質やこういうものは持っていてほしいとか、岐阜県の知事はこう言った視点、要件がということがあったら教えてください。
知事
これまでやってこられた人も、存じ上げている人もいますし、存じ上げない人もいますが、それぞれの個性でやってこられたと思いますし、連続とそれから発展の繰り返しかと思うのですが、「資質がこうだ。」とおこがましいことを言えるようなことはないのですが、鴨長明の方丈記の冒頭のセリフにあるように「ゆく川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず」ということがありますが、清流、川の流れが絶え間なく流れている、県政も絶え間なく続いているわけで、そこに元の水にあらずということで、水そのものは入れ替わっている。入れ替わるからこそ、続いている。入れ替わるからこそ、発展していく、変化がある。だから、継続と変化というものがまさに、この言葉に象徴されているのですが、このように引き継がれていって、それぞれが素晴らしい岐阜県を創ろうということで頑張ってきておられるわけですし、これからおやりになる方もそうでしょうし、ということで繋がっていくというか、そんなことではないかなと。こういう資質が大事というような偉そうなことは言えません。
記者
20年、ありがとうございました。
知事
こちらこそ、ありがとうございました。皆さん方にはいろんな面でお世話になりました。相当、日程やいろんな面でご無理を申し上げたこともあったのではないかと思いますが、お陰様で何とか今日まで来れたということで、あとまだ5日ありますので、何か起こって取材のご要望があれば、また何か緊急ということでこの場に立つこともあるかもしれませんが、そういう事も無く、穏やかに終わっていく事を祈っております。
皆さま方の目線が、県政の重要な一角を成していると思っています。皆さん方(メディア)の立場で県政をどのように受け止めて、どのように県民の皆さんに伝えていただけるか、これは県政にとって欠くことのできない大事な要素だと思いますので、引き続き、岐阜県政をよろしくお願いしますというお願いを申し上げて終わりたいと思います。どうも長い間、ありがとうございました。