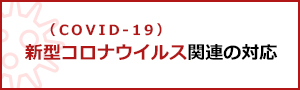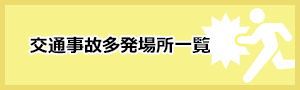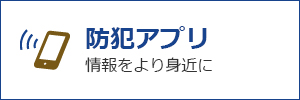本文
令和6年度第4回海津警察署協議会
警察署協議会の概要
警察署長が警察署の業務運営に対する住民の皆さんの意見、要望等を伺い、これに誠実に対応して、警察署の業務運営に反映させるとともに、警察業務への理解と協力を求めるため、各警察署に設置されるものです。
令和6年度 第4回海津警察署協議会開催結果
開催日時
令和7年2月21日 金曜日 午後1時30分から午後3時00分までの間
開催場所
海津警察署 会議室
出席者
協議会委員 5名
海津警察署 署長以下 7名
概要
1 海津警察署長 あいさつ
2 令和7年岐阜県警察基本指針並びに重点目標及び令和6年中の海津警察署管内における事件・事故の発生状況等
3 意見交換
海津警察署に対する意見・要望等
質問
侵入窃盗事件に対する防犯対策について
関東圏において、侵入窃盗事件が多発していることで防犯対策への関心が高まってきています。
市報かいづ2月号では、各家庭での戸締りや狙われにくい環境整備を行うようチラシが配布されたところです。
同種事件を踏まえて、海津警察署として、特別な活動は行っていますか。
回答
生活安全課では、地域課などと連携して、市民の防犯意識を高めてもらうため、スーパー等の協力を得て、店先でチラシ等を配るなどして、防犯広報を実施しています。
また、交番、駐在所の警察官が実施している巡回連絡という活動を通じて、個別に防犯指導を行ったり、広報誌を作成・活用して防犯広報を実施しています。
さらに、万が一、事件が発生した際には、認知後すぐに犯人の追跡捜査ができるよう、日頃から防犯カメラの位置等の情報を把握し、情報共有を図っています。
質問
ゾーン30について
海津市内に「ゾーン30」は、何か所あるのですか。
回答
現在、当署管内には
・ 令和元年12月に「海津小学校を中心としたエリア」
・ 令和3年11月に「今尾小学校を中心としたエリア」
の2か所に「ゾーン30」を設置して運用しております。
「ゾーン30」とは、学校や病院などの歩行者が多い生活道路において、安全・安心な歩行区間を確保するため、最高速度30キロ規制を路線ではなく区域(エリア)全体に指定する対策のことです。
現在では、「ゾーン30プラス」という対策も広まっており、通常の「ゾーン30」としてのエリアの速度規制のほか、エリア内に物理的なデバイス(ハンプ、狭さく、カラー舗装等)を設けることによって、車が速度を出しにくくする対策を講じています。
車にとっては、走りにくいエリアとなるため、そもそもエリア内へ車が入って来なくするという狙いもあります。
要望
チャイルドシート非着用の車両について
チャイルドシートをせず登降園される保護者がいます。
保護者の中からも“危険”という声が出ています。
定期的に巡回をお願いします。
回答
チャイルドシート非着用につきましては、四季に実施される交通安全運動期間などを通じて、タイミングを見ながら取締りや街頭活動を実施して参りたいと考えております。
なお、本協議会後の早い段階で、一度街頭活動等を実施したいと考えております。
質問
外国人の自転車利用に対する指導について
夜道、外国人の方の自転車が気にかかります。
街灯がないところでは、見にくく危険だと思うことがあります。
外国人の方への指導等は、どのようにされているのでしょうか。
回答
外国人の自転車利用者に対する指導につきましては、雇用している会社での研修会や、外国人の派遣団体等の集会の際に、交番員や駐在所員だけでなく、交通課員も出向くなどして、交通安全講話を実施しています。
講話では、
・ 日本と母国との交通ルールの違い
・ 岐阜県や海津市内の交通事故の特徴
・ 交通事故になりやすいパターン(事故態様)
・ 反射材の有効活用
などの内容に加えて、
・ 自転車は車両の仲間であること
・ ヘルメット着用等の自転車利用時の交通ルールについて
・ 免許が必要な電気自転車(モペット)について
・ 自転車の飲酒運転禁止について
などを説明し、指導しております。
普段のパトロール時には、外国人に限らず、自転車であっても交通違反等を見かけた際には、声掛けをして指導・警告していますし、場合によっては、検挙することもあります。
なお、自転車乗車時のヘルメット着用に関しましては、会社での指導が徹底されている効果なのか、通勤等で自転車を利用する日本人よりも外国人の方が多く着用されているように感じています。
質問
露天商と反社会的勢力とのつながりについて
露天商と反社会的勢力とは、深い関係があるとされているようですが、どのような関係なのでしょうか。
回答
露天商と反社会的勢力との関係については、的屋がそのまま暴力団になった組もありますので、暴力団と露天商とは関係がないとは言えない現状にあります。
元々露天商は、屋外での商売であるため、嫌がらせや商売に適した場所の取り合い等に関し、いわゆる用心棒代としてみかじめ料を支払っていた者もおり、暴力団の資金源となっていました。
しかし、平成3年に暴力団対策法が制定され、暴力団排除の機運が高まったことにより、露天商の中でも暴力団を排除する動きが強まっています。
現在でも露天商等に暴力団の介入が全くないとは言い切れない状況のため、当署管内で行われる祭事に露天商が出店する際には、暴力団排除条例等を根拠に出店者に関する情報提供を受け、暴力団排除のために警察から主催者に情報提供するなどして社会全体で暴力団排除に努めています。
質問
闇バイトや薬物事犯への対応について
闇バイトや薬物など市民生活に迫る危険について、巻き込まれないことはもちろんのこと、少しでも早い段階での相談が大切だと思いますが、通報や相談に対しては、どのような対応をされていますか。
回答
闇バイト対策は、闇バイトへ応募してしまった者の保護対策として、そのような相談を受けた際の取扱いに関する要綱が制定され、昨年10月から全国警察を挙げて保護することとなっております。
また、それら相談者から求人側の突き上げ捜査ができるよう、情報提供を依頼しています。
次に、「闇バイトと思われるサイトを見つけた」旨の相談では、そのサイトを調査し、書込者の特定や削除依頼を行っています。
最後に、闇バイトに応募しやすい若者世代に焦点を当て、検索サイトの「Google」や「Yahoo!」、SNSの「LINE」や「Instagram」など計8社に対し、闇バイトを検索した際に、警察庁による犯罪実行者募集に応じないよう注意を促すポップやバナーが出現するようになりました。
このように、闇バイトに応募をする側の対策を講じることで、同様の募集が機能しなくなることを目的としております。
薬物事犯につきましては、薬物使用者に関する情報提供があれば、その情報を基に捜査を開始します。
また、自身が違法薬物を使用している旨の相談であれば、その相談者を逮捕することとなりますので、同様の相談は極めて少ないのが現状です。
よって、SNS等で広告を出して違法薬物を販売するなどしている「あおり」、「唆し」と呼ばれる行為を取り締まるべく、インターネット上の情報をもとに捜査を行い検挙するなど地道な対策により、薬物の撲滅を目指しています。
質問
自転車の飲酒運転取締りについて
自転車の飲酒運転の取締りについて教えてください。
回答
自転車利用者に対する「飲酒運転」や「ながら運転」についての罰則が新設され、昨年11月から施行されています。
普段のパトロールなどで、自転車によるマナー違反や交通違反を発見した際には、停止を求めて指導、警告を実施していますが、その際に酒の臭いがすれば、自動車の飲酒運転の取締りと同様に、水でうがいをさせた上で、呼気中のアルコール濃度を計測します。
基準値を超えれば、酒気帯び運転で検挙となりますが、基準値に満たない場合であっても、運転手の言動、歩行動作の確認等を総合的に判断して、酒酔いと認められた場合には、酒酔い運転として取り締まることとなります。
酒気帯び運転の運転者に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転の運転者に対する罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
質問
カスタマーハラスメントに対する警察の対応について
過日、カスタマーハラスメントへの対応についての講話を聴く機会がありましたが、警察ではカスタマーハラスメントに関する通報や相談があった場合、どのような措置をとりますか。
回答
現時点では、明らかなカスタマーハラスメントを受けている旨の相談は確認できませんが、相談があった場合、警察安全相談として受理し、その後の対応については、署長指揮のもと処理していきます。ただし、相談の内容に、刑事事件の対象となるような脅迫・強要に当たる言動、行為がある場合には捜査の対象となっていきます。
過去に市役所に対して、何度も不当な要求を繰り返したことで、検挙に至った事案も聞いているところですので、相談があった場合は、適切な対応に努めてまいります。
要望
信号無視等に対する更なる取締り要望について
本日、警察署に向かうまでの間で、大型車両の信号無視を何回も見ました。現在も、警ら活動や交通違反取締りを実施していることと思いますが、今後も、パトカーによる警ら活動を継続的に行ってほしいと思います。
回答
署員には、パトカーはもちろんのこと、捜査用車両にも警光灯を載せ、点灯させながら走行するよう指示をしています。警光灯を点灯させると、警察車両が目立ちますので、交通事故や交通違反の防止にもなりますし、犯罪企図者にとって、海津市内で犯行を思い止まらせることにもつながりますので、引き続き、警光灯を点灯させた警ら活動を指示していきたいと思います。
開催風景