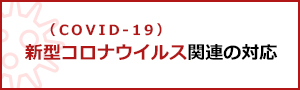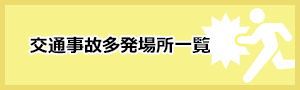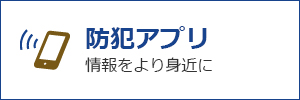本文
令和6年度第3回海津警察署協議会
警察署協議会の概要
警察署長が警察署の業務運営に対する住民の皆さんの意見、要望等を伺い、これに誠実に対応して、警察署の業務運営に反映させるとともに、警察業務への理解と協力を求めるため、各警察署に設置されるものです。
令和6年度 第3回海津警察署協議会開催結果
開催日時
令和6年12月9日 月曜日 午後1時15分から午後4時00分までの間
開催場所
海津警察署 署長室
出席者
協議会委員 4名
海津警察署 署長以下 7名
概要
1 令和6年年末年始特別警戒出発式等の視察
2 海津警察署長 あいさつ
3 令和7年海津警察署速度取締り指針の説明
4 意見交換(海津警察署において)
海津警察署に対する意見・要望等
質問
自転車を使用する中高生に対する広報・指導について
道路交通法の改正により、自転車運転時の「ながらスマホ」や酒気帯び運転に係る罰則規定が整備されましたが、通学時に自転車を使用する中高生に対して、どのような広報及び指導を行っていますか。また、今後、どのような計画がありますか。
回答
自転車は運転免許が不要な上、子供からお年寄りまで、幅広い年代で利用されており、自転車を趣味とする方も増え、自転車利用者のルール違反やマナー違反が社会問題となっています。
また、人身交通事故発生件数のうち自転車が関係する割合が増加傾向にあることから、自転車に関する道路交通法の一部が改正されたところであります。
このため、本年11月1日からは自転車運転時の「スマホ利用」や「酒気帯び運転」の罰則が整備されたことで、通学等で自転車を利用する中高生もその対象となっています。
【中学校・高校に対する呼び掛け】
そこで、海津署としては、管内の各学校の生徒指導の先生を通じて生徒や保護者への広報を依頼するとともに、海津明誠高校では、警察官と先生が協働して自転車通学する生徒にチラシを配布しながら自転車の交通ルール遵守に対する呼び掛けを実施しました。
このほか海津署管内の3つの中学校に対してポスターを配布し、校内での掲示をお願いするとともに、全ての教員にチラシを配布して生徒への指導をお願いしました。
【街頭における交通安全指導】
これまでにも、毎月15日の交通安全の日には、街頭にて交通監視をしながら交通安全指導を行い、日ごろのパトロールではルール違反やマナーの悪い自転車を見かけた際には、その都度、警察官が声掛けをして指導を実施しています。
【ヘル着サミットの開催】
このほかにも、西濃地域の高校生と警察がヘルメット着用に関して意見交換する討論会「ヘル着サミット」を開催するなど、自転車のヘルメット着用率の向上への取組も実施しています。
今後も、地道な活動になりますが、地元の皆さんや先生方と一緒になって、自転車利用に関する交通ルール遵守の意識向上を図っていきたいと考えています。
追加の質問
ヘルメットの着用について、中学生は着用していると思われるが、高校生の着用率の向上が懸念されるところです。
その回答
「ヘル着サミット」は、先日、西濃ブロックの警察署(大垣、揖斐、養老、垂井、海津署)管内の高校生が集まり、「なぜ、高校生はヘルメットの着用者数が伸びないのか」を議論し、また、各地区の代表者が県警本部に集まり、県内討論会を行っています。意見集約、情報共有、着用率の高い他県での取組の紹介や取り入れをして、高校生自らの意識を変えていき、着用者数の向上に努めていきます。
質問
横断歩道通過時の自動車運転者及び歩行者に対する広報啓発について
横断歩道を渡ろうとしたときに片方からの車は、横断歩道手前で停止し、もう一方からの車は、停止している車を見ているにもかかわらず、停止することなく横断歩道を通過していくということがありました。
通り過ぎて行った運転者は、高齢の方で、停止してくれた運転者は、若い方でした。
このような場面に直面することが多いため、何か啓発するような機会が、よりたくさんあればと思っています。
回答
今年のJAFの調査の結果によりますと、岐阜県の横断歩道停止率が全国3位になったとのことでした。これはとても素晴らしいことであり、日ごろの活動の成果であると考えております。
これを踏まえて、ドライバーに対しては取締りを通じて、横断歩道を通過する際の危機意識を高めていただき、さらなる横断歩道の停止率の向上を目指してまいりたいと考えます。
現在、海津町西江地区におきまして、高齢者交通安全大学校を実施しておりますが、このような場において、横断歩道は絶対優先で、横断歩道に人がいれば車両は必ず停止しなければならないことを改めて教育していくとともに、参加者から地元の方々へ広めていただいているところです。
さらに、地域で行われる集まり等の場で、交番員や駐在所員が講話等する際には、車両を運転される方に対しては同種の内容を、一方、歩行者に対しては、
「横断歩道を渡るときは、手を挙げて横断する意思を車に知らせること。」
「横断歩道を横断するときは、左右の車が止まったことをしっかり確認してから渡ること。」
を指導することで 「一方の車が止まったからと言って決して油断してはいけない」という交通安全教育をいろいろな場を通じて実施してまいりたいと考えています。
質問
報道発表による弊害及び報道時のポイントや表現方法について
特殊詐欺発生に伴い、広報があったと記憶しています。発生直後のこととなると、被害者の詮索などが心配されます。
事件・事故について、知り得た情報などを共有することは、大切だと思いますが、差別や偏見につながらないように気を付けるべきポイントや表現方法などを教えてください。
回答
警察による報道発表の可否の判断については、個々の事案ごとに検討をしております。
検討する主な要素としては、1つ目が当事者のプライバシー保護、2つ目が捜査への支障、3つ目が発表することの公益性があります。
「被害者の詮索」に関しましては、報道発表の際には、第一に被害者のプライバシー保護を考慮し、被害者に関する個人情報を必要最小限とすることで、被害者の特定に至らないよう注意をしております。
10月26日の特殊詐欺被害を報じる新聞を例としてみますと、被害者は、海津市、無職、80代、女性と報じられているように、できる限り、被害者が誰であるかが分からないような報道発表に努めております。
他方で、捜査への支障を考慮しつつ、被害状況は、より具体的に発表することで、同種事案による連続被害の防止につながるよう、対応しております。
また、発表のタイミングにつきましては、発生直後に発表することを基本としておりますが、これは、特殊詐欺のような事件報道につきましては、同種事案の連続被害の防止を目的として、タイムリーな発表に心掛けております。
さらに、幅広い注意喚起を可能とするため、新聞報道のみならず、当署のホームページ、交番・駐在所が発行する広報誌、県警本部から発信されるメール等の広報媒体を利用し、より多くの人の目に触れることができるよう努めております。
このほか、表現方法については、近年のSNSの普及により、さまざまな意見を容易に発信することが可能となったことを考慮し、被害者に対する差別や偏見につながることがないよう注意を払い、警察本部の広報担当課及び事件・事故等の主管課と協議を経て、適正な報道発表となるよう努めております。
例えば、ひとつの言葉でも、受け手によって、異なる意味として理解できるようなあいまいな表現を避け、客観的な状態をお伝えするよう心掛けております。
質問
駐在所の警察官と地域の方々との連携や取組について
回答
地域警察官の活動は、国家公安委員会が定める地域警察運営規則に定められており、地域の実態を把握して、その実態に即した住民の意見要望に応えた活動を行うとともに、常時警戒態勢を保持し、全ての警察事象に即応する活動を行いながら、市民の日常生活の安全と平穏を確保することを目的として活動しています。
これらの任務を達成するために、交番、駐在所勤務員は、日ごろから、警ら活動等を通じて、交通の状況、住民の居住実態、意見要望、事件事故等の発生状況を的確に把握して、市民のみなさんにとって身近で切実な事案を誠実に処理し、犯罪や交通事故防止の指導、犯罪の予防検挙などに取り組んでいます。
なかでも、交番、駐在所の勤務員が、個々に担当する区域を巡回して、一般家庭、事業所等を訪問する「巡回連絡」という取組を強化し、市民のみなさんの意見要望の聴取に当たっているほか、地域のみなさんの意見要望を反映した活動を推進するため、交番や駐在所に「連絡協議会」を設置するなどして最新の情報を提供するなど、交番、駐在所の警察官と、地域の方々との連携強化を図っています。
なお、東江駐在所では、日原(ひわら)、長久保地区の防災訓練に参加して防犯講話等を実施しているほか、日頃から独居高齢世帯への訪問を強化しています。
また、海西駐在所では、朝夕の登下校時における見守り活動を頻繁に実施しているほか、大江駐在所では、地元祭礼行事等に参加することで、より身近な存在として、顔の見える関係を心掛け、地域の方々との連携を図っています。
質問
独居老人の方々への警察としての取組について
回答
独居の方に限った話しではありませんが、警察では、各部門が横断的に連携し、高齢者に対する各種対策に取り組んでおります。
●生活安全課では、特殊詐欺の被害者の多くが高齢者であること及び固定電話を入口とした被害が被害全体の約半数を占めることなどを踏まえて、65歳以上の高齢者に対して、次のように、さまざまな取組を行っております。
〇自動通話録音警告機や防犯機能付き電話機の貸出
〇固定電話対策として、NTT西日本の特殊詐欺被害を防止するための取組の御案内
〇金融機関において高齢者による高額引出があった場合に、金融機関の職員が警察へ通報し、臨場した警察官が直接顧客に特殊詐欺被害に遭っていないか確認することで被害を水際で防止する全件通報
〇今夏には、岐阜県警察が岐阜ヤクルト販売株式会社と協定を締結し、ヤクルト販売員による顧客への声掛けやチラシの配布により特殊詐欺被害等を未然に防止する活動に御協力いただいております。この取組に関しては、12月17日にヤクルト販売員に海津警察署員が同行し、訪問先の高齢者に対して、特殊詐欺などの被害に遭わないよう指導することを予定しております。
●地域課では、高齢者宅への巡回連絡を強化し、高齢者の生活や行動の実態を踏まえた困りごと、悩みごとの解消、犯罪防止、交通事故の防止、緊急時の対処方法などについて指導するなど高齢者を事件、事故から守ることを目的とした活動を行っております。
●交通課では、交通安全に関する取組としまして、
〇地区を選定し年間を通じて交通安全教室を実施する「高齢者交通安全大学校」
〇老人クラブ、地区集会や社会福祉協議会の会議などへ出向いて交通安全講話や反射材の配布活動
〇何度も交通事故を起こす高齢運転者への家庭訪問指導
〇家族や包括支援センターからの情報提供をもとに運転免許の自主返納に関する相談受理
などを行っております。
開催風景