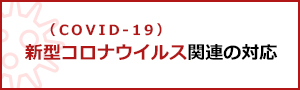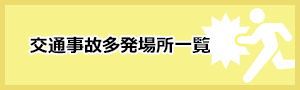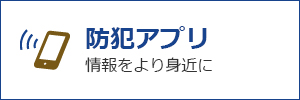本文
令和6年度第2回海津警察署協議会
警察署協議会の概要
警察署長が警察署の業務運営に対する住民の皆さんの意見、要望等を伺い、これに誠実に対応して、警察署の業務運営に反映させるとともに、警察業務への理解と協力を求めるため、各警察署に設置されるものです。
令和6年度 第2回海津警察署協議会開催結果
開催日時
令和6年9月6日(金曜日)午後1時00分から午後4時00分までの間
開催場所
岐阜県警察本部 科学捜査研究所
海津警察署 会議室
出席者
協議会委員 5名(うち1名は本部視察のみ)
海津警察署 署長以下 7名
概要
1 岐阜県警察本部科学捜査研究所視察
2 意見交換(海津警察署において)
海津警察署に対する意見・要望等
質問
安全・安心の体制維持について
予定されている海西駐在所の廃止は、人口減少による組織の見直しによるものと思いますが、今後、更に海津市の警察組織が縮小されていくのであれば、どのような体制で海津市の安全・安心を担保していくのか。
回答
岐阜県警察では、令和5年10月に「岐阜県警察交番・駐在所整備指針」を策定し、現在226か所ある交番・駐在所を、令和15年度を目途に170か所程度に統廃合することとしています。
これは、当県も長期的に人口減少が続くことで、将来的には警察官定数の削減が予想され、今までどおりの警察活動を維持することが困難な状況になりかねないことから、県警察として、県民の皆様に対し、できるだけ公平で手厚い警察サービス等を提供するため、将来予測を踏まえ、警察力の配分の最適化を行うための取組であります。
当署管内においては、警察本部から令和8年度末までに海西駐在所を廃止し、平田交番に統合する方針が示されています。
海西駐在所を廃止し、平田交番に統合するに至った理由につきましては、警察本部において、管内の治安情勢や人口動態、隣接交番等との距離等を総合的に検討し、決定されるに至ったものです。
今後、海西駐在所は廃止されますが、その反面平田交番の体制が強化されることにより、結果的には、平田町全域を24時間警戒するための体制が強化されることになります。
このため、平田交番のパトカーが常に町内を巡回しているため、これまでどおり警察官の姿やパトカーが警戒している姿を見せることが可能ですが、駐在所廃止直後は、しばらくの間、海西地区に移動交番車を導入するなどして、地域住民の方の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
なお、そのほかの大江駐在所や東江駐在所の統廃合の話題は、今のところ出ていませんが、現在の海津市内の治安情勢等が平穏に推移しているため、将来的には統廃合される可能性は否定できないところです。
このため、仮に大江駐在所等が統廃合になった場合においても、「見せる活動」のほか、移動交番車の運用等により、地域住民の方の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
質問
チャイルドシート、ジュニアシート着用に係る広報について
チャイルドシート、ジュニアシートの着用について、どのように広報しているか。
回答
道路交通法では、チャイルドシート等の着用義務や罰則については、6歳未満の幼児が対象となります。
しかし、シートベルトの着用の目安は、一般的に身長140cm以上とされており、身長140cmに満たない6歳以上の児童等に関しても、子供の安全を確保するため、子供の体型に合った乗車用補助装置の使用を推奨しています。
また、チャイルドシートやジュニアシートは、「乳児用」「幼児用」「児童用」と子供の発育状況に応じて分かれています。
それぞれのシートの規格を確認していただき、使用する子供の発育状況(年齢、身長、体重等)に対応した乗車用補助装置を使用していただくようお願いしているところです。
今後の対策として、交通取締りを通じて、厳しく目を光らせていくとともに、会議や集会などで行う交通講話においても、事故等の事例を紹介しつつ、チャイルドシート等の安全性について広報していきたいと考えています。
特に、こども園などでの保護者が集まる集会や新入学児童の保護者が集まる機会があれば、チャイルドシート等の着用・使用について広報してまいります。
質問
横断歩道通過時の自動車運転者及び歩行者に対する広報啓発について
先日、信号のない横断歩道を渡ろうとしていた方がいたため、横断歩道の手前で止まったにもかかわらず、対向車線から走行してきた車両が、スピードを緩めることなく横断歩道を通り過ぎていき、あわや事故になることがあったが、何か対策できないか。
回答
対策としまして、ドライバーと歩行者それぞれに応じた対応をしていきたいと考えています。
ドライバーに対しては、指導取締りを通じて横断歩道を通過する時の警戒心や危機意識を醸成することで、更なる横断歩道での停止率の向上を目指していきたいと考えています。
歩行者に対しては、交通安全講話などの場を通じて、
「横断歩道を渡る時は、手を挙げて横断する意思を車に知らせること。」
「横断歩道を渡る時は、左右の車が止まったことをしっかりと確認してから渡ること。」
を指導することで
一方の車が止まったからと言って決して油断してはいけない
という交通安全教育を実施していきたいと考えています。
質問
交通施設の視認性について
国道258号上の横断歩道のペイントが消えかかっているところがある。
また、同道路では、ところどころ樹木の繁茂により信号機が見えにくくなっていたり、路側帯が減少したりしている。
施設管理者としての対策について教示願いたい。
回答
横断歩道や信号機を始めとする道路施設は、公安委員会、すなわち警察が管理するものとなっており、その補修は優先順位をつけつつ実施しています。
横断歩道の舗装は、警察で定期的に行っているところですが、消えかかっている横断歩道があることが分かれば、現場確認を行い、必要なら補修の申請を行っています。
街路樹などの剪定は、道路管理者が定期的に行います。しかしながら、標識や信号の視認性が確保されていない場合は、警察から道路管理者に対して、改善を求めています。
また、民地からの樹木による場合は、警察官が現場確認の上、その土地の管理者に対して改善を求めています。土地の管理者の多くは一個人であるため、費用や能力的な問題から時間がかかるのは否めませんが、一つ一つ丁寧に対応することとしています。
開催風景
科学捜査研究所視察状況
科学捜査研究所視察状況
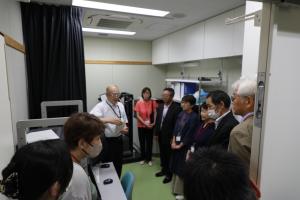
科学捜査研究所視察状況
意見交換等の状況